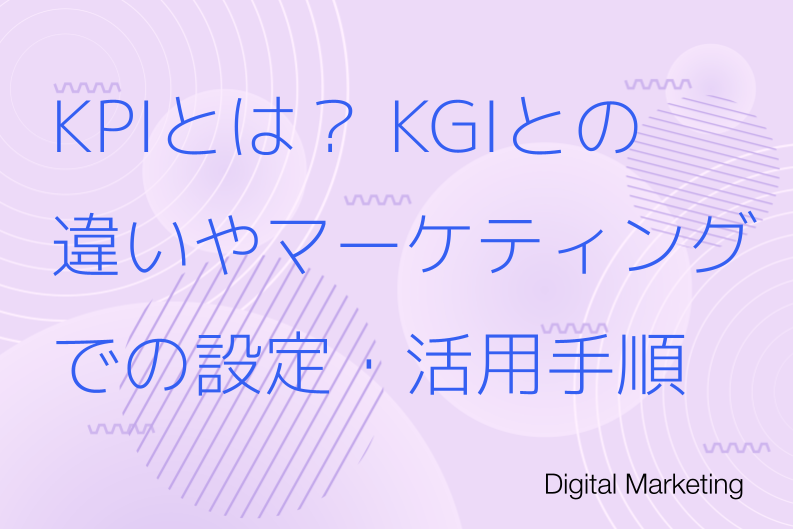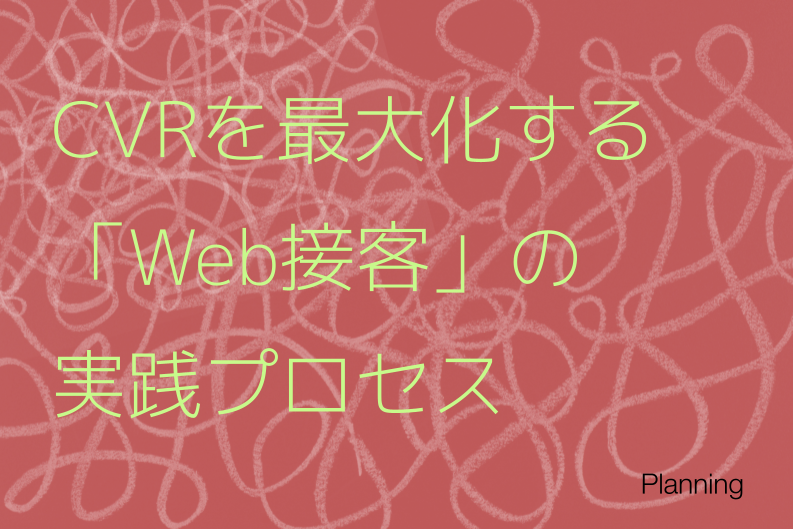■ 能書き
本件、自分も審査員として参加している関係上、盛り上がってほしい。
というか、やっぱり審査していてテンションが上がるのはいい企画書に出会ったときなので、みんなにいい企画書を書いてエントリーしてほしい。
そのために何か、ためになることを書くのがいいのではないか。
という気がしてきたんですけど。
とはいえ僕が書くまでもなく、受賞常連の手練れの方々が既にノウハウなど発信していると思うので、どちらかと言うと、今から企画を始めたい方、企画職じゃないけどアイデア提案したい方などが「あ、企画ってこんな感じか」って思えるような記事を書いておこうと思います。
せっかく間口が広いしね。
■ 審査員コメントについて
販促コンペは年々応募数が増えていて、かなりの量の企画書を審査するために結構な人数の審査員が参加しています。
皆さん業界の第一線で活躍されている方々で、ありがたいことに毎年アドバイスを載せてくれています。これ、読むのがいいと思いますよ。
エントリーするなら特に。
審査員が大事にしていることがなんとなくわかりますしね。
で、自分もその末席を汚す身として、今年は下記のようなコメントを書きました。
クライアントや商材のファンになること。そして自分が良い、好きだと感じる要因を分析し、「好きの構造」を導き出すこと。その構造を誰かに伝えたいと考えると、それが企画になったりします。またその構造を別の物やシーンに置き換えたり、与える変数を変えたりして検証してみるのもいいかもしれません。見つけた構造が強固なほど、強いコンセプトになっていくと思います。
あのー、ちょっとこれ勢いに任せて書いてしまったんですが、
抽象的でよくわかんないとこもあると思うので補足させてください。
■ 企画 =「好きの構造」
「好きの構造」はよく使うんです。
例えば、自分が大好きな物の事を、それを知らない誰かに説明する。
うまく説明できて、その人も好きになってくれたら嬉しいじゃないですか。
だから、なんで自分はこれが好きだと感じるのかをよく考えてみる。
で、それをまだ知らない相手にも分かるように、相手が知っている事に置き換えて説明する。
自分が良いと感じているのと同じような構造を、相手が持っている材料を使って構築する試み。
言ったら、これが企画です。
企画を考える最初の一歩って、およそこういうことなんじゃないかと思っています。
その構造が見えたら、いろんなものに置き換えられるようになるので、様々な検証ができるようになります。
そしたらより多くの人の中に、同じ構造を見いだせるようになってくる。
ターゲット像が見えてくる。
で、そういう構造のことをできるだけ短い言葉で言い表すと、それがアイデアと呼ばれるものになったりします。
感覚として、アイデアって勝手に空から降ってくるものみたいなイメージがありますが、実際には手元で材料を組み合わせて構築するもの。という捉え方のほうがしっくり来ます。
まあ、ぼーっと材料いじってたらいつの間にか思いもよらぬ形が見えてくることもありますけど。
■ アイデアは馬鹿みたいにシンプルに説明する
企画書に書くアイデアは、できるだけ短く、平易な言葉で説明したほうがいいです。なんかコンセプトー!とかいってカッコいい横文字使いたくなったりするんですけど。
いや敢えてそういう言葉使うこともあるんですけど。
企画コンペはこの一言が勝負と言っても過言ではないし、特に販促は人が動くことが求められるので。
「〇〇(誰)を、〇〇(どう)させるアイデア」
と一言で言いきったほうがいいです。
だって全然知らない人に、そうか。って思わせるわけだから。
これがいまいち言い切れないときは、構造が複雑すぎたり、アイデアが2つ3つ混在してたりするときで、もうちょっと分解してあげたほうがいいです。
結構、複数のアイデアを一緒くたに語っちゃってることってあるもんで。
そうするとよくわからない。
いいこと言ってそうなのに、結局どうしたいのかよくわからない企画書って結構あるんです。これは読み解きに苦労する。
だから無理にひとつにせず、別の企画に分離するといいと思います。販促コンペはひとり何個でもエントリーできますしね。
受賞者はたいてい1人(1チーム)で複数案出していることが多いです。
・コンペのコツとして
「あとで思い出せる強い言葉を置いておく」ということがめちゃくちゃ大事です。
特にコンペではたくさんの企画書がいっぺんに審査されるので、読み飛ばされて何も残らなかったら終わりです。
審査員によっては、まずざっと流し読みしてから、後で気になったものに戻って来る。
みたいな審査方法をとっている人もいるんじゃないかと思います。
お題によってはアイデア被りが多くなることがあって、そういうケースでは自分もこれをします。
順番に見ていくとアイデアが被ったとき先に見た方の企画書を良く感じてしまいがちなので、そういうバイアスを振り払う意味でも。
そのときに、あとで「〇〇を〇〇させるアイデア」ってあったな。って頭に浮かぶような言葉にしておくといいと思います。
オシャレな横文字でかっこよく決めても頭に残らないと戻ってこれません。
審査側が数百という単位で企画書読んでるとしたら・・・と考えられたし。
アイデアが見えたら、それが誰にでも伝わるように企画書にしていくターンですね。
よし、書こう、企画書。
といって、何から手を付けていいやら・・・ってなるかとので思うので、
次に必要なのは「台割り」かな。
しかし、いいかげん長くなってしまったので、それはまた別の記事にしようかな。
やろう!販促コンペ!