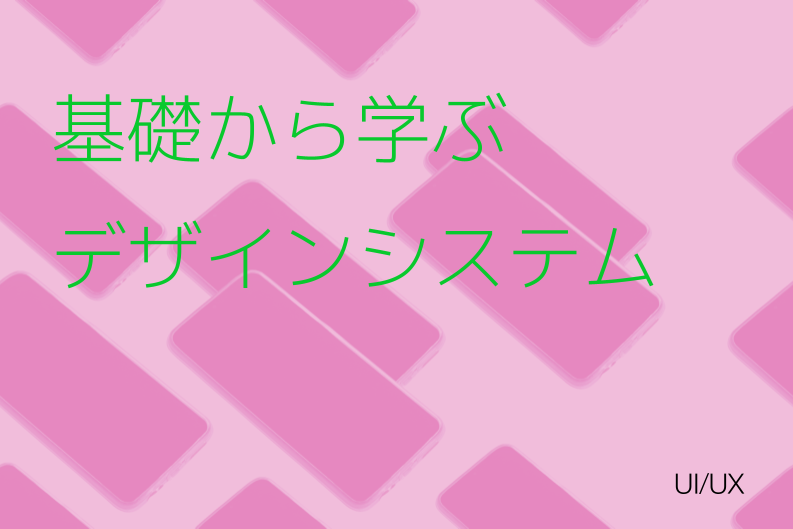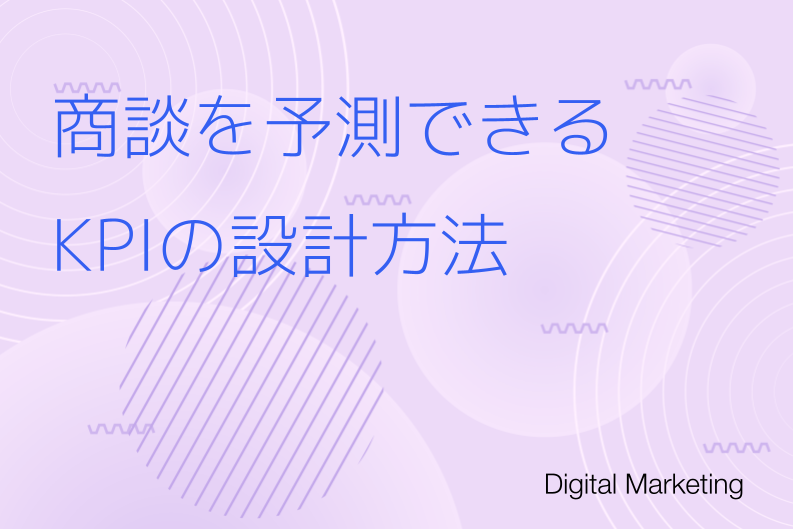2024年にアプリ版がスタートした「切り抜きジャンプ+」。本サービスを開発した博報堂アイ・スタジオ(以下、アイスタ)のチームは、今も「少年ジャンプ+」と併走しながらマンガのミライを切り開いている。
今回は「少年ジャンプ+」籾山悠太編集長と、アイスタの原一弘と池田朋矢が集い、「切り抜きジャンプ+」の成果と反響、そして漫画の未来に寄与すべく今後実現したい企画について、語り合った。
「切り抜きジャンプ+」で自由に遊んでほしい

──2024年にアプリ版がスタートした「切り抜きジャンプ+」ですが、反響はいかがでしたか。
籾山編集長:アプリ版に対応して3カ月強で切り抜き画像が2万7千枚以上シェアされました。一日300回くらい切り抜かれてましたね。その後は少し落ち着きましたが、1カ月に5,000〜1万回で推移しています。アイスタさんと苦労して作ったので、多くの人に使ってもらえてよかったですね。
原:「切り抜きジャンプ+」では、選んだマンガのコマに、図形のスタンプを押せたり、色を変更できたり、文字を入力できたりと、いろいろなデコレーション機能をつけました。その編集機能を読者さんが駆使しまくって、ものすごい加工をしてくださっています。

池田:うちのデザイナーチームもノリノリで編集機能のアイデアを出してくれて、楽しく作れました。
そうやって楽しんでデザインができたのは、マンガの持つ力だけではなく、そもそも「少年ジャンプ+」の仕事に関われるというモチベーションに引っ張られたからだと思います。
籾山編集長:いろいろなアレンジのおかげでX(旧Twitter)のタイムラインでも目立ちますよね。大変ありがたいです。あと想定外だったのは、作家さんへのファンレター的に使ってもらったことですね。コマのなかに作家さんへのメッセージを書き込んでるんです。本当にみなさん自由に楽しんで使ってくれてます。

池田:我々としてもユーザーさんには自由に利用してほしかったので、使い方のサンプルも積極的には提示しなかったんです。機能だけ置いて自由に遊んでほしかった。それが功を奏してるのかなと。
きめ細やかな設計で作者の権利を守る

──「切り抜きジャンプ+」が、作家と読者をつなぐ大事なサービスになっているんですね。
原:当初は「マンガで稼ぐ」というコンセプトで、切り抜きをシェアしたユーザーが収益を得られるような仕組みを考えていました。
ところが「マンガを応援する」というかたちにコンセプトを変えても、読者の方々は積極的に利用してくださった。
池田:切り抜きのユーザーランキングがあるんですが、ランキング上位のXアカウントでも、フォロワー数が2、300人ということがあるんですよ。それはフォロワー数が少なくても、切り取りがうまくハマれば読者を呼び込むことができることを示していますね。事実、8,000以上のマンガ閲覧数を記録したものもあります。
──読者に歓迎された一方で、マンガ家さんたちの反応はいかがでしたか?
籾山編集長:当初は過度なネタバレや、作品の価値を貶める切り抜きが出るんじゃないかと懸念をしていましたが杞憂でしたね。みなさん、ポジティブに使ってくれています。
また、そういう懸念をどうしても払拭できない場合でも、切り抜きを許可するかどうかは作品ごとに作家さんが判断できるんですよ。これも、アイスタさんに相談して技術的に解決した部分が大きくて。
池田:管理側の機能として、作品ごとに切り抜きの範囲やスケジュールを決められるような機能をアプリ開発会社さんが搭載してくれました。切り抜き可能範囲を作品ごとに「全ページか、もしくは冒頭の数ページか」と細かく指定できるようにしたり、公開日から数日経ったら切り抜き範囲を広げたり。
籾山編集長:結果的に、最初は不安がっていた編集部と作家さんもだんだん受け入れてくれました。今ではほとんどの作品が切り抜きに対応しています。
原:不適切なテキストを書いた場合に弾く仕組みも一応つけてますが、そういったケースはほとんどないですね。
そもそも開発前にデータ分析している時点で、作品を冒涜するような形での切り抜きはあまり見受けられなかったので大きな心配はしていませんでした。性善説っぽくなってしまいますが、わざわざシェアしてくれる人はポジティブな投稿をする人がほとんどです。
籾山編集長:一応、通報機能もつけてますよね。報告件数としてはどれくらいですか?
原:幸い、その機能はまだ使われていないですね、通報ゼロです!
籾山編集長:本当ですか? 機能が壊れてるとか……。
原:そこは大丈夫です(笑)。
“切り抜き”文化を世界へ広げる

──「切り抜きジャンプ+」を周知するための施策にはどんなものがありましたか?
池田:コミックスの発売記念やプロモーションの一環で、「切り抜きジャンプ+」を織り交ぜた企画をやってきました。籾山さんとやらせていただいた案件で言うと、天野明先生の『鴨乃橋ロンの禁断推理』がありますね。犯人を推理して的中させた方のなかから抽選でプレゼントをするというものでした。
https://kirinuki.shonenjumpplus.com/cp/2310/kamonohashiron/
籾山編集長:公式推理クイズをSNS上でできるのが新鮮でしたね。『株式会社マジルミエ』(原作:岩田雪花、作画:青木裕)でもキャンペーンをやりましたよね。

原:あれは株式会社の話だったので、宣伝部員を募集する企画にしました。あとこれは施策じゃないですけど、今では『ふつうの軽音部』の原作者であるクワハリさんをはじめ、作家さんも切り抜きに参加してくださっていて、すごくうれしく思っています。
籾山編集長:アイスタさんはサービスを提供してお終いじゃなくて、その後の使い方を一緒に考えてくれたり、サービスのその後の運用も見てくれるのでありがたいです。
──籾山編集長は、この先の「切り抜きジャンプ+」の展開をどう考えていますか?
籾山編集長:「MANGA Plus by SHUEISHA」という海外展開用のプラットフォームがあるのですが、そこでも「切り抜きジャンプ+」的なことがいつかできたらいいなと思っていますね。
原:海外でミームになっている日本のマンガもありますもんね。
籾山編集長:今だと「週刊少年ジャンプ」で連載中の『カグラバチ』がアツいですね。そういうミームになったコマも、「切り抜きジャンプ+」経由でシェアされていくようになったらいいなと思います。また、他のSNSへの展開も含めて、いろいろできたら面白そうだなと。
「少年ジャンプ+」の一番の目的は、新しくて面白いマンガを作り届けることです。私たちが子どものころって、発行部数以上の潜在読者がたくさんいたと言われているんですよ。
原:学校で回し読みとかしてましたもんね。
籾山編集長:回読率っていうんですけど、昔先輩に聞いたところでは「週刊少年ジャンプ」の回読率は「3」だったと言われていて。つまり、1冊を3人が読んでいた。ということは、発行部数が600万部超だった最盛期は、約2,000万人が毎週「ジャンプ」に触れていたわけです。
池田:実感としてはもっと多い気すらします(笑)。
籾山編集長:そうですよね。あのころのクラスメイト全員が読んでるっていう状況を、スマートフォン、インターネットでも再現したい。そのために「切り抜きジャンプ+」は不可欠なツールですね。
池田:これからもよろしくお願いします。小学生のころから親しんでいる媒体ですから、こうやって関われて、本当に光栄です。
原:あのころの自分に「お前、ジャンプの仕事してるよ」って伝えたいですね。定例も続いてますし、切り抜きに限らず、いろいろやっていけたらうれしいです。引き続きよろしくお願いします!