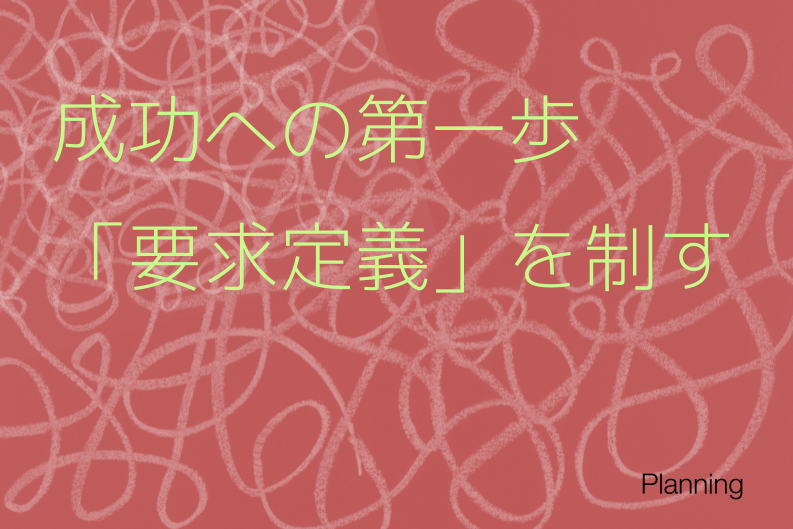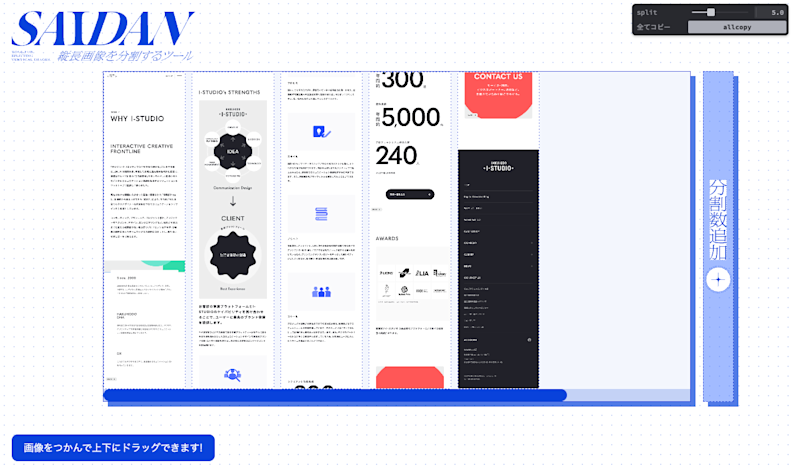■ 台割りについて
さて、いいこと思いついたし企画書にするぞ。
となってまず必要なのが「台割り」です。
台割りと言うのは、ざっと全体の流れを並べた下書きみたいなもので、このページでこれを書くぞ!という意気込みだけで作ったほとんど白紙の紙芝居みたいなやつです。
これだけ聞くとどうかしてますけど。でも大丈夫。やります。
一旦シートの中身は書かなくていいので、最初から最後まで必要なページを並べてみる作業です。
映像でいうとコンテ、漫画でいうとコマ割りみたいな作業です。
たたき台と言ったりもしますね。
■ ストーリーを作る
自分が考えた企画・アイデアについて、どういう順番で説明したら伝わるのか、ストーリーとして考えます。
まあ、まず基本の要素を並べると下記のような感じ。
・与件/問題 |
あー、ここでよく問題と課題とアイデアがごっちゃになることがあるんですけど。
まあ、ちょっと、一旦、それ細かく説明すると長くなるので端折りますが。
与件/問題
「与件/問題」は、依頼主から提示されている既知の問題の再確認。
問題というのはこの場合、理想と現状のギャップのことです。
課題
「課題」は、問題を解消するために排除すべき障壁です。
これはあなたの導き出した着眼点の提示になります。
依頼主も気づいていない何か。です。
ここに発見がないといけない。
アイデア
「アイデア」は、まあ、抽象度の高い言葉なのでアレなんですが、
ここでは課題を裏返したもの、と考えてもいいです。
課題を排除するためにやること。ですね。
〇〇を〇〇する!と一言で説明できるといいやつです。
施策内容・期待できる効果
で、「施策内容」は実際に実行する具体的な内容。
そのあとに「期待できる効果」を書いて納得させます。
まずはこの形で白紙にでっかく見出しだけ置いて、一旦、最少5ページのスカスカの企画書ができます。
これを埋めていってもいいんですけど。
■ 伝わるストーリーの基本
ただ、これをストーリーだと考えると、どうでしょう。
いまいち面白くないな。と感じるかもしれません。
人は、ものごとの因果関係をつなぎながら、ストーリーとして理解します。
なので、読みたいストーリーにしてあげたほうが伝わります。
では、ストーリーの基本ってなんでしょうか?
起承転結
最も一般的で分かりやすいのは「起承転結」ですかね。
企画書でもこの展開を作ってあげるのが正攻法です。
アイデアにたどり着くまでにこれを作っておくと読んでもらえる確率が上がります。
台割りに当てはめるなら
起 → 与件:依頼内容 |
かな。
ただこれ、中身書き始めちゃうと、途中でいろいろ言いたいことがでてくるもんで、ごちゃごちゃするんですよね。
あれも言いたいこれも言いたいってなって。でもそれって結局あんまり伝わりません。
1ページの中にたくさん言いたいことが埋め込まれるとまず読み取られないので、
1シート1メッセージが基本です。
ほんと、1ページ使っても結局頭に残せるのって一言くらいしかない。
こちらが言いたいことを言うのではなくて、
聞き手が聞きやすい物語を語ってあげることが大事です。
■ 親に話すように作る
つって、そんなん言われても難しいじゃないですか。
作家じゃないし。
なので、台割りを作るときには、親と話してみてください。
いや、実際に話さなくてもいいんですけど。
親に説明するつもりで喋ってみるんです。
台割りで書こうとしている順番どおりに説明してみる。
・与件「あの、〇〇の話なんだけど」(起) |
ということを、台割り読みながら声に出して言ってみる。
どうです?親を説得できそうですか?
声に出してみて、ちょっと苦しいなと思うところには、なにか論理の飛躍があったり、
前後の因果関係がつながってなかったりするので見直しが必要です。
もしセリフひとつを1ページで言えなければ、メッセージが複雑になっているのでページを分けたほうが良いかもしれない。
と、このように、何をどの順番で伝えるかを
親と話すように整理するのが台割りを作るときのコツです。
台割りができたら、もう企画書はできたようなもんです。
あとは中身詰めていけば良いから。
いや、まあ、それも頑張るんだけど。
これをたたき台にして複数人で作業分担もできるしね。
1ページに割り当てられた言いたいことがブレないように、
できるだけ少ない言葉で表現していくのがいいです。
親、そんな聞いてくれないでしょ?
食器洗ってる親に、後ろから声かけてこの説明するの。
親が手を止めて聞いてくれるイメージが湧いたなら、結構いいかもしれない。
■ 参考スライド
台割りは、ほとんど白紙の紙芝居。と言われてもイメージつきにくいかもしれないので、
一応こういうことだよっていうのを下記に置いておきますね。
まあ、見るまでもないっちゃないんですけど。イメージの共有まで。
迷ったら、一旦こういうことを書けば良いんだなー。と、立ち返ったりできるといいと思います。
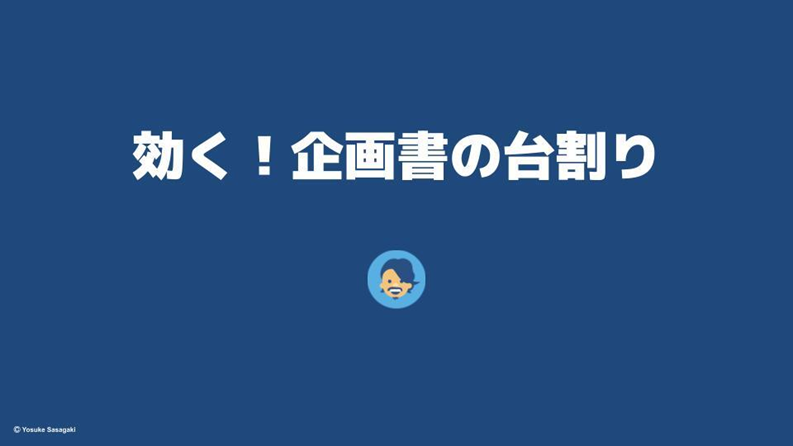
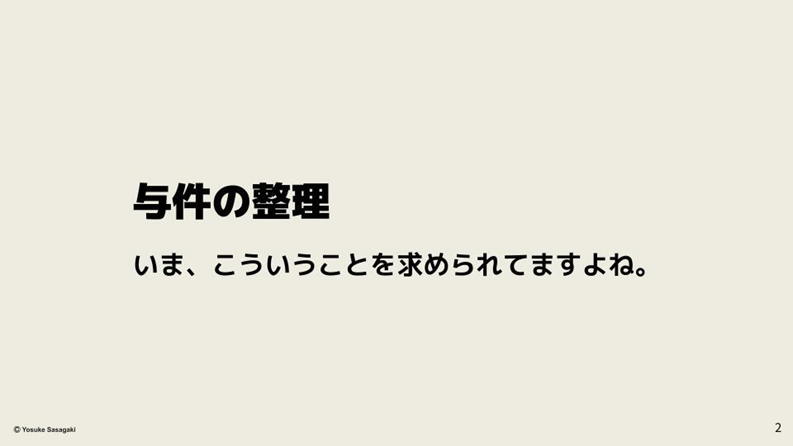
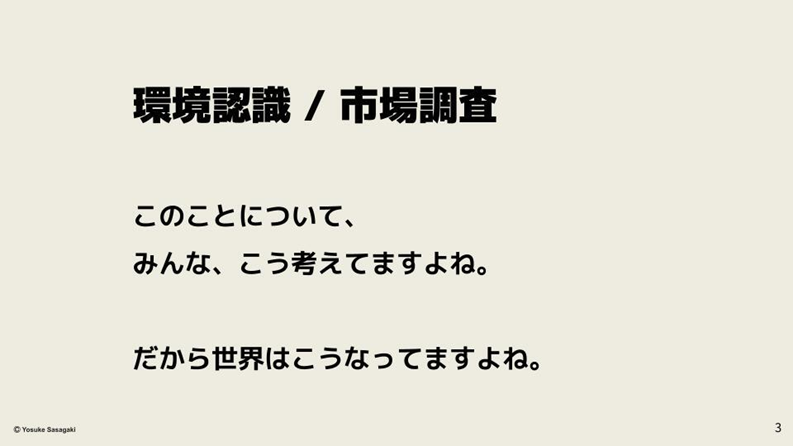
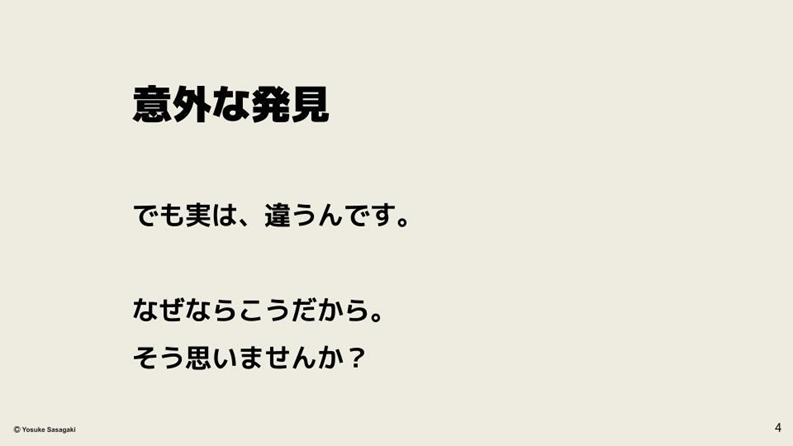
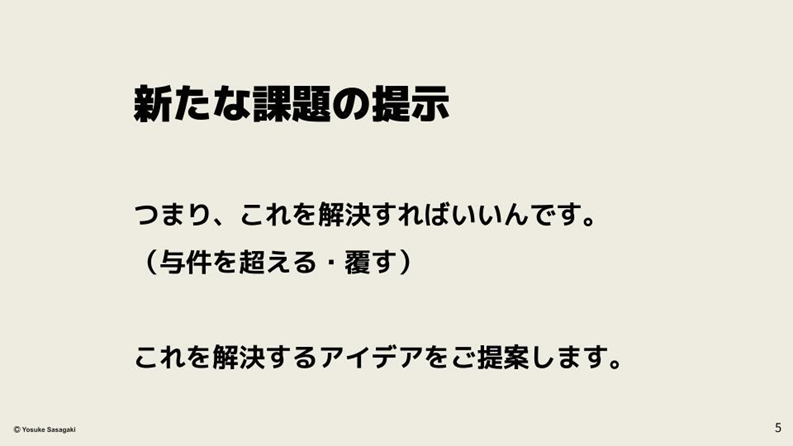
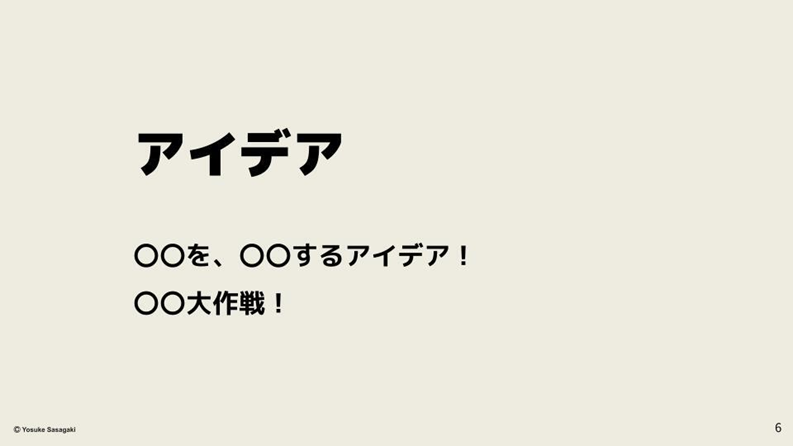
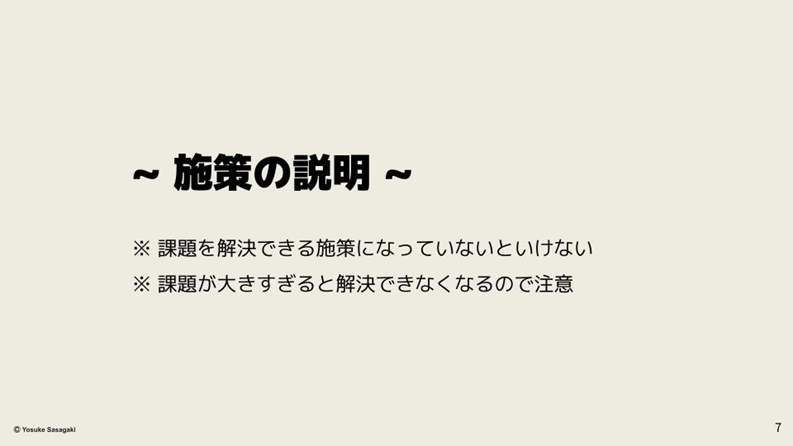
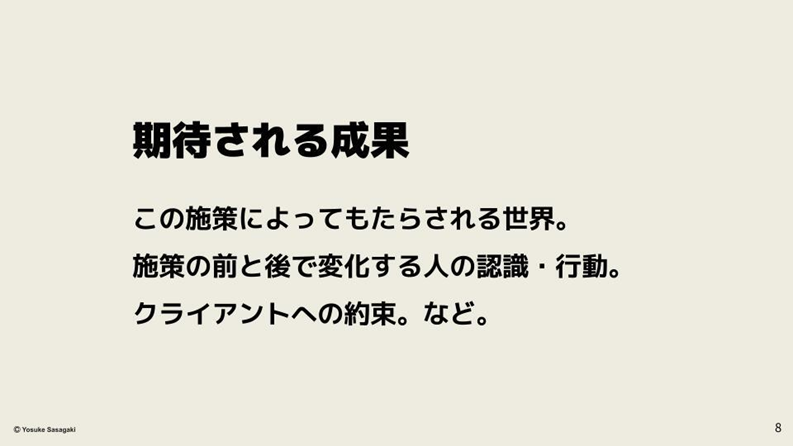
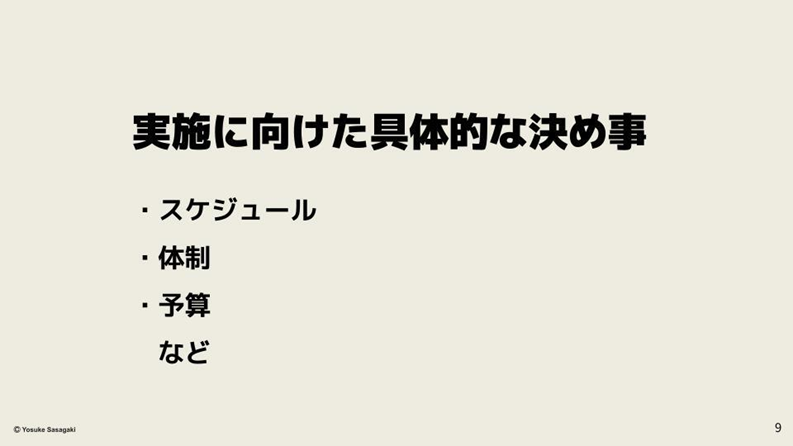
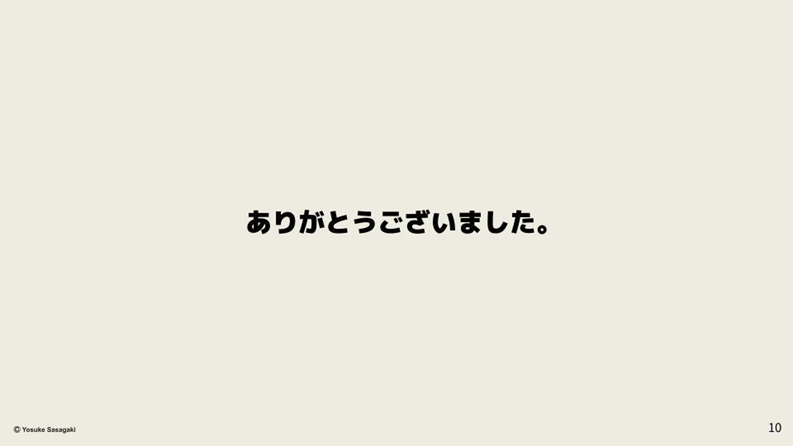
もちろん、他にも効く企画書を書くためのメソッドはいっぱいあるので調べてみるのも良いですし、
なんと販促コンペのサイトには過去の受賞者の企画書がそのまま載ってるので、
これを見ない手はありません。助かるー。(ページ下の方)
■ その他考えること
今回端折りましたが、中身を詰めていくにあたって考えることは他にもいろいろあります。
・環境認識 / 市場調査 / 競合調査
・実効可能性 / フィジビリティ
・人を動かす方法 / 認知から態度変容までのプロセス
・ベネフィットとインサイト
などなど。
そもそも、自分が思いついたアイデアが果たしてユニークなのか、他の人も序盤で思いつくようなものなのかは、コンペでは結構気にしたほうが良いでしょう。
最初に思いついたアイデアは、他の人も考えついている前提でいたほうがいい。
そしてそのアイデアは、このクライアント、この商材でなければ実現できないことになっているか?
という視点をもってブラッシュアップ。
どこかで見た汎用的なフレームの焼き直しになってはいないか?
冷静に見ると結構ここで引っかかったりします。もうあるじゃん。と。
汎用的なフレームを持ったアイデアが悪いわけじゃないし、実際仕事では重宝したりすることもあるんですが。しかしコンペでは通りにくいと考えたほうがいいですね。
被るし、強い優位性が見いだせないと他の案に負ける。
販促コンペのコツ的な話
もうちょっとコツっぽいこと言うと、販促コンペには審査員が選出するグランプリ・ゴールド・シルバーの他に、クライアントが選ぶ協賛企業賞というものがあります。ガチ勢ともなるとこれのどっちを狙いに行くかも定めてたりする。クライアントの願いを最速で叶えに行くか、あるいはクライアントを含めた社会全体に何かを巻き起こしていくか。とか。
いずれにせよ、企画書一発で勝負できるのは面白いですよ。
自分のアイデアが誰かに見てもらえて、うまくすると社会実装されるかもしれない。
これってちょっと他には代えがたい体験だったりします。
まあ仕事では提案で負けると自分の全部を否定されたみたいな気分になって
落ち込むことも多々あるんですが。
仕事というのは多かれ少なかれ、その繰り返しかもしれませんね。