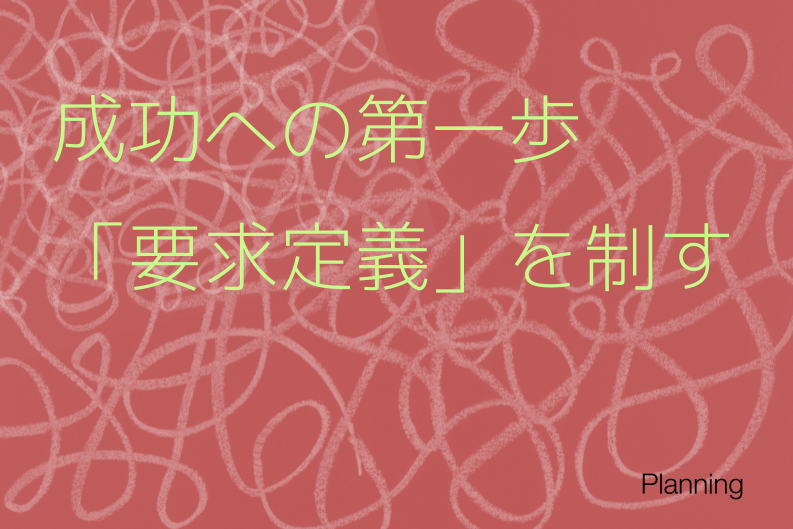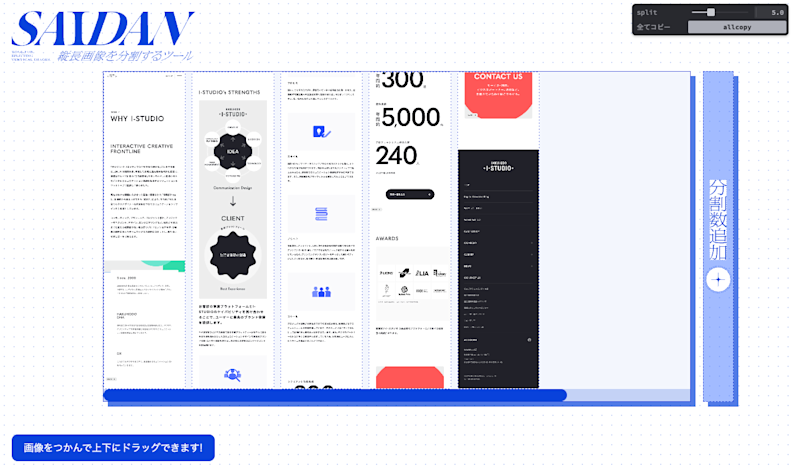ROI(投資利益率)とは?
ROI(Return on Investment)は、費用対効果や投資利益率など、投資額に対する利益率を示す指標です。M&Aなどの評価基準であり、現在ではマーケティングにおける設備投資の事前チェックや、施策の効果分析手法としても重要視されています。
ROIの計算式
ROIを算出するための基本的な計算式は以下のとおりです。
ROI(%)=利益÷投資額×100
ここで言う「利益」は、施策によって得られた売上から、売上原価と投資額(施策コスト)を差し引いたものです。そのため、計算式は以下のように分解できます。
ROI(%) = (売上 - 売上原価 - 投資額) ÷ 投資額 × 100
マーケティング施策における「投資額」には、広告費、ツールの利用料、コンテンツ制作の外注費、関連する人件費(社内リソースの工数)などが含まれます。どこまでを投資額に含めるかは、ROIを算出する目的や組織のルールによって定義する必要があります。
具体例でシミュレーション
【前提条件】
あるマーケティング施策(例:Web広告)に100万円を投資した。
その施策経由で500万円の売上が発生した。
売上500万円に対する売上原価(商品原価、サービス提供コストなど)が100万円だった。
【計算ステップ】
利益を算出する
利益 = 売上 - 売上原価 - 投資額
利益 = 500万円 - 100万円 - 100万円 = 300万円
ROIを算出する
ROI(%) = 利益 ÷ 投資額 × 100
ROI(%) = 300万円 ÷ 100万円 × 100 = 300%
この結果は、「投資した100万円に対して、3倍の利益(300万円)を生み出した」、つまり投資効率が300%であったことを示します。
ROIがマイナスになる場合
ROIがマイナスになるのは、施策によって得られた利益(売上 - 売上原価)が、その施策にかけた投資額を下回った場合です。
例えば、上記のシミュレーションで、投資額が100万円、売上原価が100万円だったのに対し、売上が200万円に満たなかったケースを考えます。
【前提条件】
投資額:100万円
売上:180万円
売上原価:100万円
【計算ステップ】
利益を算出する
利益 = 180万円 - 100万円 - 100万円 = -20万円ROIを算出する
ROI(%) = -20万円 ÷ 100万円 × 100 = -20%
ROIがマイナス(0%未満)になるということは、その施策が投資額を回収できておらず、会計上「赤字」であることを明確に示しています。
ROAS(広告費用対効果)との違い
ROIとROASは混同されやすいのですが、ROIは投資費用に対する「利益」の割合で、ROASは「売上」の割合を指すという違いがあります。マーケティング戦略では「ROASで成果をスピーディーに判断し、ROIで正確な投資効果を判定する」など、両方をうまく使い分けることが大切です。
ROAS(Return On Advertising Spend)は、広告の費用対効果・広告費用回収率を算出する指標です。
ROAS(%)=広告経由の売上÷広告費×100
最大の違いは、ROIが最終的な「利益」を見ているのに対し、ROASは「売上」を見ている点です。 ROASは、広告がどれだけ効率よく売上を生み出しているかを測るための指標であり、ROIのように利益率(儲け)までを反映するものではありません。
どちらの指標をいつ使うべきか?
比較項目 | ROI(投資利益率) | ROAS(広告費用対効果) |
見る対象 | 利益 | 売上 |
計算式 | (利益 ÷ 投資額) × 100 | (売上 ÷ 広告費) × 100 |
分子のコスト | 売上原価、投資額(広告費、制作費、人件費など全て) | (計算上考慮しない) |
分母のコスト | 投資額(広告費、制作費、人件費など全て) | 広告費(媒体費)のみ |
判断基準 | 0%以上(黒字) | 100%以上(広告費を売上が上回る) |
ROI分析を活用する際の注意点と限界
ROIは万能な指標ではなく、その特性を理解せずに使うと、かえって判断を誤る可能性があります。ROIを活用する際は、以下の点に注意し、その「限界」を理解しておくことが重要です。
長期的な施策の評価には適さない
ROIは、比較的短期間で投資と利益の関係性を測るのには適していますが、長期的な視点が必要な施策の評価には適していません。
例えば、オウンドメディアのSEO対策、企業ブランディング、SNSでのファンコミュニティ育成などは、目に見える利益(売上)につながるまでに数ヶ月から数年単位の時間がかかります。 これらの施策を短期的なROIで測定すると、初期段階ではROIが極端に低く(あるいはマイナスに)算出され、「効果のない施策」として誤って停止されてしまうリスクがあります。
数値化できない「無形の価値」は測定できない
ROIはあくまで「利益(金額)」という定量的な数値に基づいて算出されます。そのため、施策によって生み出された「数値化しにくい価値」は、計算からこぼれ落ちてしまいます。
例えば、施策による「ブランドイメージの向上」「顧客満足度(CX)やロイヤリティの向上」「SNSでの好意的な口コミ(UGC)」などは、すぐには利益に結びつかなくても、中長期的に見れば確実にビジネスに貢献する重要な資産です。 ROIの数値だけを絶対的な判断基準にすると、こうした目に見えない価値を生み出す重要な施策が過小評価される危険性があります。
ROI分析はどのような場面で活用すべきか
ROI分析は、マーケティング活動を「利益」という最終成果に結びつけるための強力な羅針盤となります。データに基づいた戦略的な意思決定を行うために、特に以下のような場面で活用されます。
施策が本当に「儲かっているか」を客観的に評価する
マーケティング施策の成果は、「PV数」「リード獲得数」といった中間指標(KPI)で語られがちです。しかし、ROIはそれらの活動が最終的に「どれだけ儲けにつながったか」を客観的な数値(利益率)で可視化します。 これにより、感覚的な評価(例:「あの施策は盛り上がった」)を排し、どの施策が本当に事業の利益に貢献しているかを冷静に評価できます。
投資規模が異なる施策の「効率性」を公平に比較する
ROIは「利益率」で成果を算出するため、投資した金額(規模)が異なる施策同士でも、その「投資効率」を公平に比較できます。 例えば、以下2つの施策があったとします。
施策A: 投資100万円 → 利益300万円(ROI 300%)
施策B: 投資5,000万円 → 利益1億円(ROI 200%)
利益の「絶対額」では施策Bが圧勝ですが、「投資効率」の観点では施策Aの方が優れていたと判断できます。ROIは、予算規模の大小に惑わされず、どの活動が最も効率的に利益を生み出しているかを特定するために役立ちます。
参考記事:メールマーケティングの費用対効果とは?コスパを高めるツールと4つの手法を徹底解説
データに基づき「リソース配分(選択と集中)」を判断する
各施策のROI(投資効率)が明らかになれば、「選択と集中」という戦略的な判断が可能になります。 ROIが高い(効率が良い)施策には追加の予算(ヒト・モノ・カネ)を投下し、逆にROIが低い(効率が悪い)施策は、その原因を分析して改善するか、場合によっては停止する、といった判断を下せます。 これにより、限られたマーケティング予算を最も効率的な場所(=利益を生む場所)に再配分し、企業全体の利益最大化に貢献できます。
マーケティングROI分析の具体例
ROIは「費用に対して、最終的にいくら利益を生んだか」を同じ物差しで比べられる指標です。ここからは、実務で出会いやすい5つの場面を取り上げ、どのように使うと判断がぶれないかを整理します。
1. チャネル横断の予算配分を決めるとき
検索広告、SNS広告、記事広告などに同じ期間投資し、チャネルごとの利益を並べて翌月の配分を見直します。下記の計算式で算出し、数値が高いチャネルは増額、低いチャネルは改善か縮小に回します。
チャネル別ROI(%)=(売上 − 売上原価 − チャネル別投下費用)÷ チャネル別投下費用 × 100
注意点は、評価期間をそろえることと、制作・運用の手間も費用に含めること。やりがちな誤りは、クリック数や表示回数だけで判断してしまうことです。
2. リードの入口(流入経路)を“受注まで”比べたいとき
資料DL、ウェビナー申込み、比較サイト経由などの入口ごとに、商談・受注まで追い、利益で比較します。問い合わせ数だけでなく、最終の利益で投資先を選びます。
ソース別ROI(%)=(受注売上 − 売上原価 − ソース別投下費用)÷ ソース別投下費用 × 100
注意点は、問い合わせ→商談→受注の段階名をそろえ、入口を必ず記録すること。やりがちな誤りは、ダウンロード数だけを見て「良い施策」と判断してしまうことです。
3. ナーチャリングやリターゲティングの回数と内容を調整したいとき
初回の問い合わせに対して事例→導入手順→個別相談の順でメールを送り、再訪者には広告を一定回数だけ表示します。接触が増えるほど成果が下がる地点を見つけ、回数や内容を調整します。
回数帯別ROI(%)=(当該回数帯の受注売上 − 売上原価 − 配信費用)÷ 配信費用 × 100
注意点は、対象を大まかに分け(初回/比較中/検討中)、連絡の上限回数を決めること。やりがちな誤りは、開封率だけを追って接触を増やし過ぎ、逆効果になることです。
4. イベント/展示会・ウェビナーの実施可否を決めるとき
展示会ではデモ体験から個別相談へつなぎ、ウェビナーでは最後に相談フォームへ誘導します。名刺・登録数ではなく、商談・受注につながった利益で判断します。
イベントROI(%)=(受注売上 − 売上原価 − 総投下費用)÷ 総投下費用 × 100
注意点は、会場費だけでなく準備や事後フォローの手間も費用に含め、続ける条件(黒字など)を事前に決めること。やりがちな誤りは、名刺や参加者数のみで成功と見なすことです。
5. ツール導入や外注の見直しをするとき
配信やスコア付けの自動化で生まれた時間をABテストに回す、LP制作を外注から自社テンプレに切り替えるなど、増えた成果と費用を比べます。
(ツール/外注)ROI(%)=(増分粗利益 − 費用)÷ 費用 × 100
注意点は、導入前に「何時間減る/何本増える」を目安化し、見直し時期を決めること。やりがちな誤りは、月額の金額だけで高い・安いを判断し、増えた成果を確認しないことです。
参考記事:HubSpotでマーケティングROIを測定・改善する方法
マーケティングROIを向上させる・改善するための具体的な方法
ROIの計算式(利益 ÷ 投資額)に基づけば、ROIを向上させる方法は「利益を増やす」か「投資コストを減らす(最適化する)」の2択に集約されます。
利益を最大化する
利益(売上 - 売上原価 - 投資額)を増やすためには、売上を伸ばすことが最も直接的なアプローチです。マーケティング施策においては、以下のような取り組みが該当します。
コンバージョン率(CVR)の改善: LPやWebサイトのUI/UXを改善し、より少ない訪問者で多くの成果(eBookダウンロード、問い合わせ)を生み出す。
リードの「質」の向上: 施策のターゲティング精度を上げ、より受注確度の高いリード(MQL)を獲得し、商談化率・受注率を引き上げる。
顧客単価(LTV)の向上: 既存顧客へのアップセル・クロスセルを促進し、長期的な関係性を構築してLTV(顧客生涯価値)を高める。
投資コストを最適化する
ROIの分母である「投資コスト」を見直すことも重要です。ただし、闇雲にコストを削減すると、それに伴って売上(利益)も減少し、結果的にROIが改善しない可能性もあります。 目指すべきは「投資コスト削減」ではなく「投資コストの最適化」です。
効果の低い施策の停止・見直し
ROIを測定し、効果の出ていない広告配信や施策への投資を停止・縮小する。
リソースの再配分
停止した施策の予算を、ROIの高い(効果実証済みの)別の施策に振り分ける。
業務効率化・自動化
MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用し、これまで人手で行っていた定型業務(メール配信、リード管理など)を自動化する。これにより、実質的な人件費(投資コスト)を削減し、担当者はより戦略的な業務に集中できます。
正確なROI測定が、マーケティング成果を最大化する鍵
本記事では、ROIの計算方法、ROASとの違い、活用シーン、注意点など、マーケティングROIの基礎知識を解説しました。
ROIを正確に測定し、データに基づいて改善活動を行うことは、BtoBマーケティングの成果を最大化する第一歩です。しかし、BtoB特有のデータの分断により、施策と最終的な売上を紐付け、ROIを可視化するのは容易ではありません。
ROIの測定・改善や、MA/CRMを活用した具体的な実践方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。