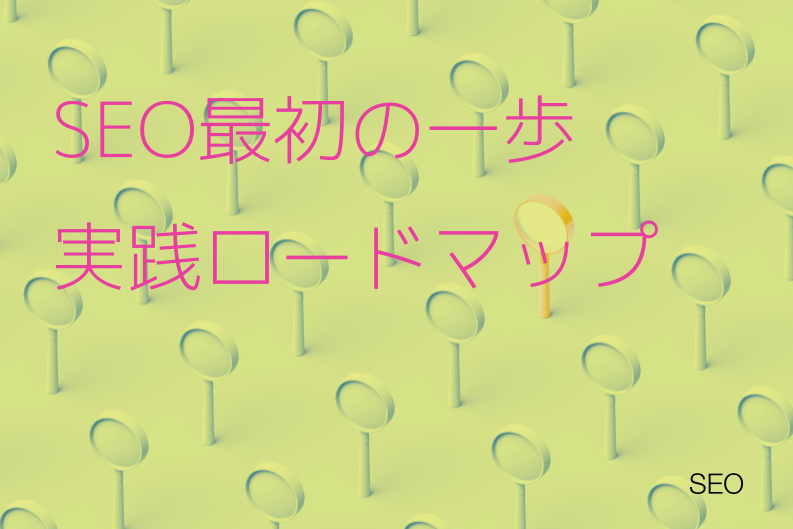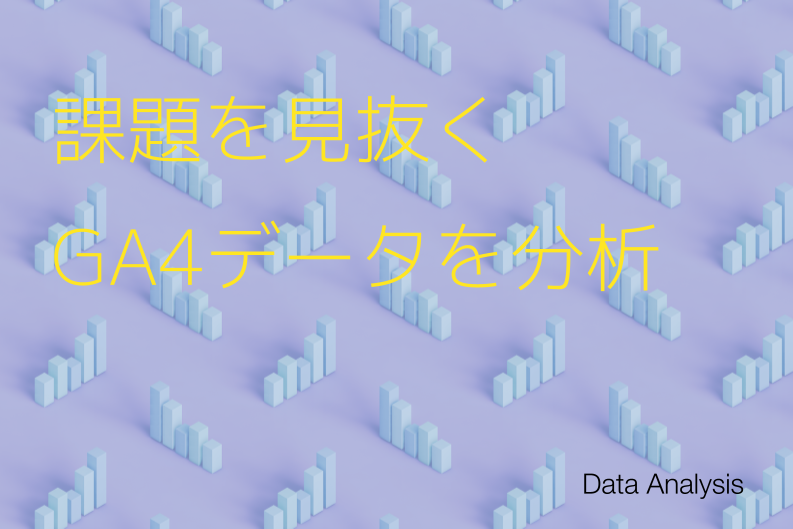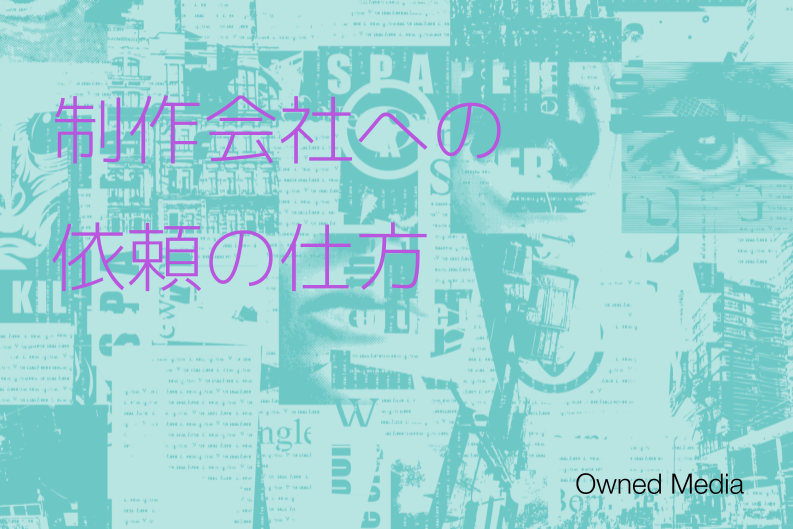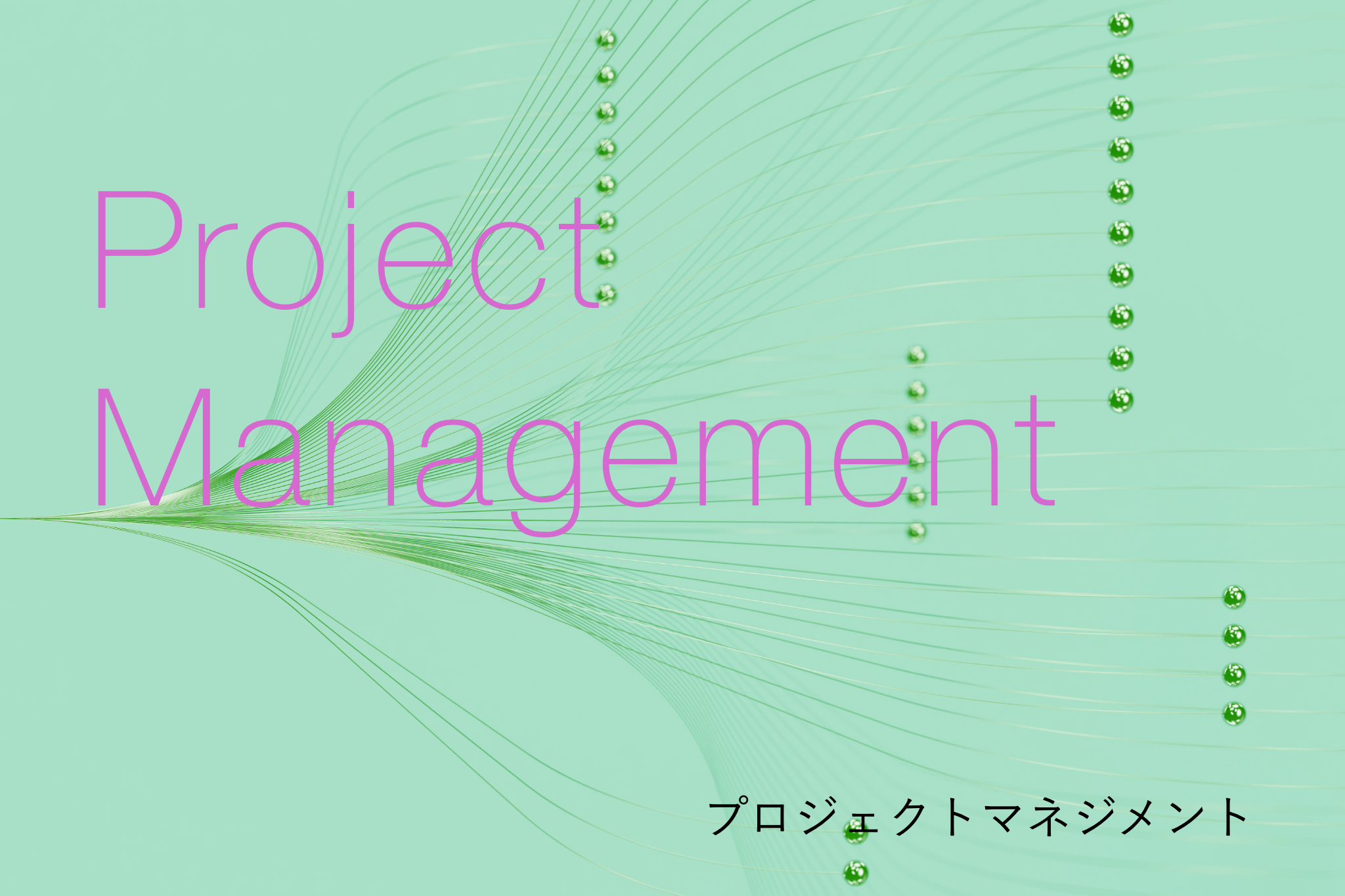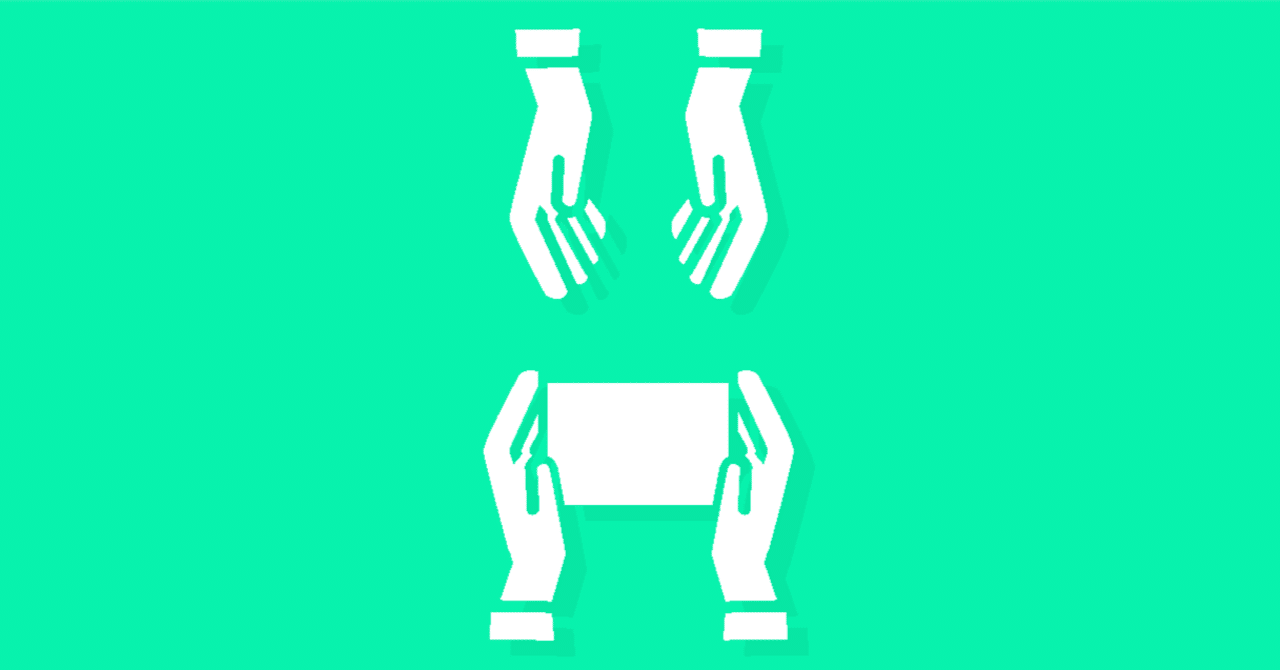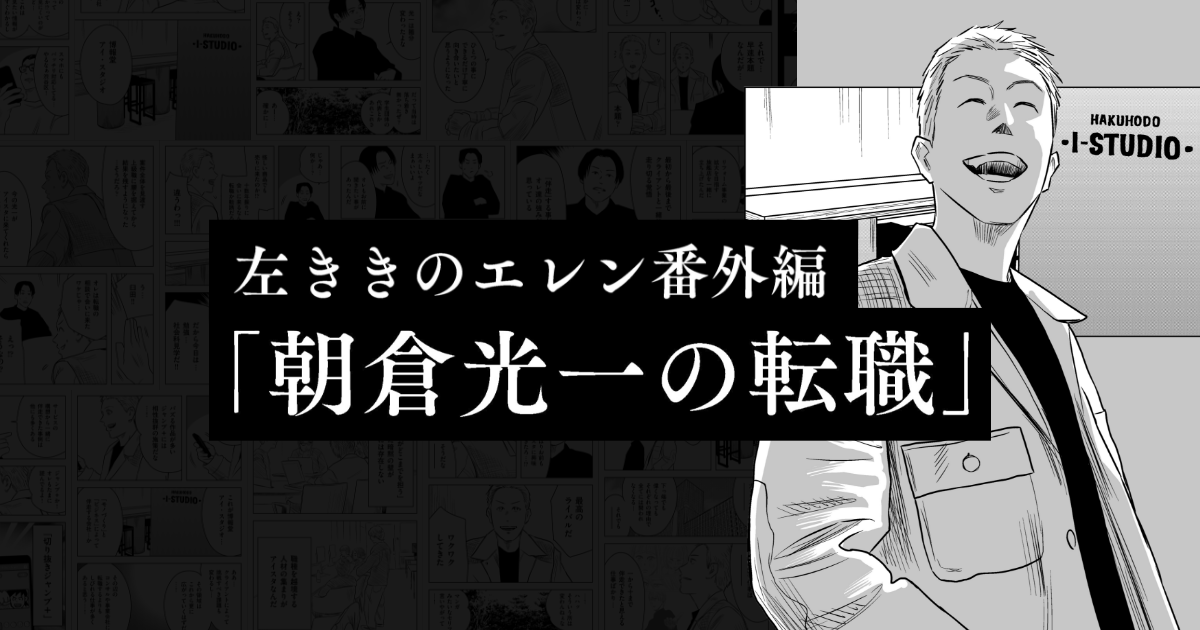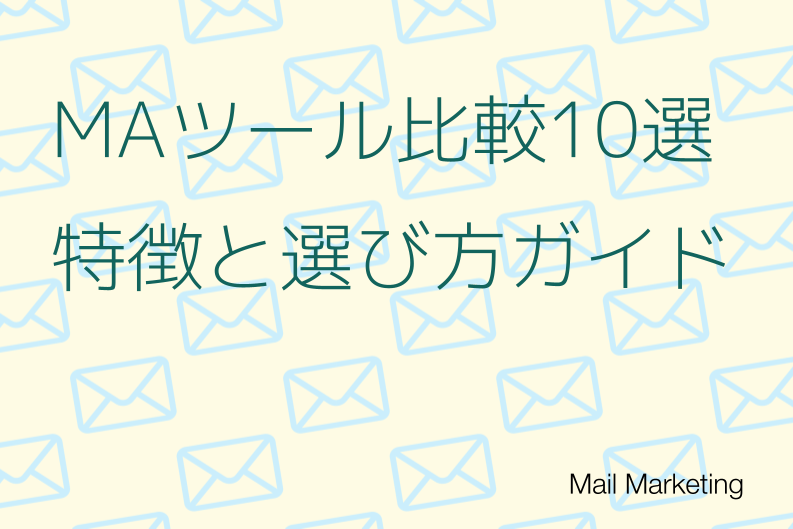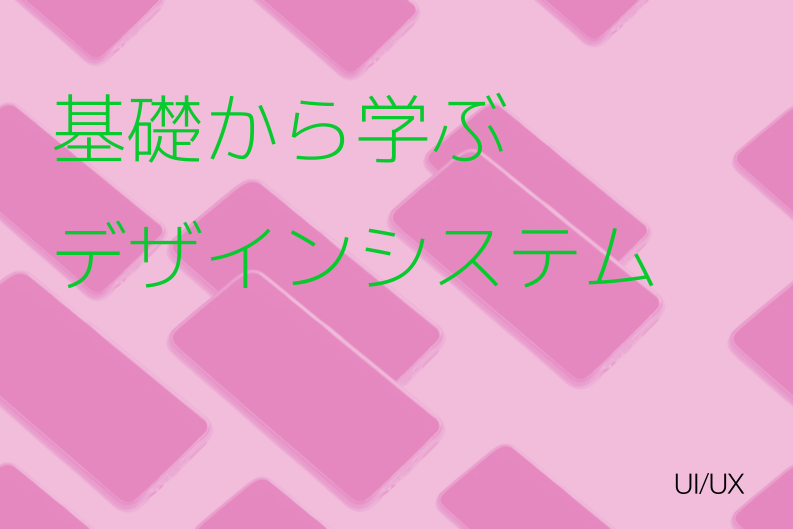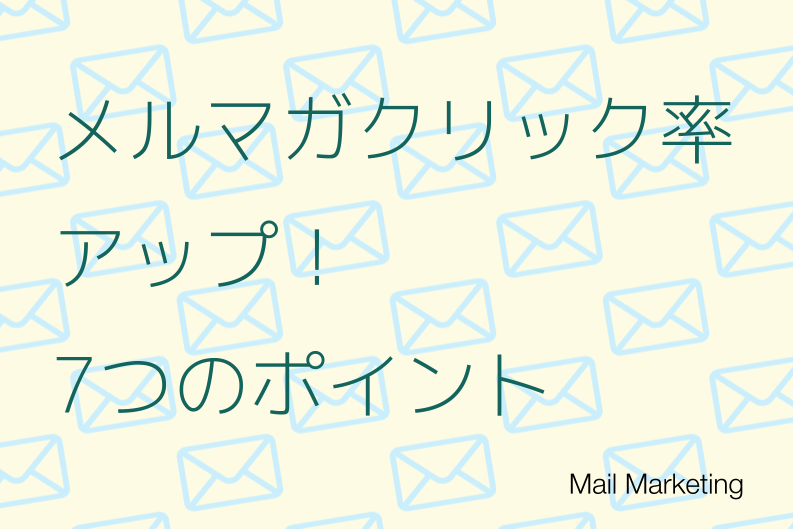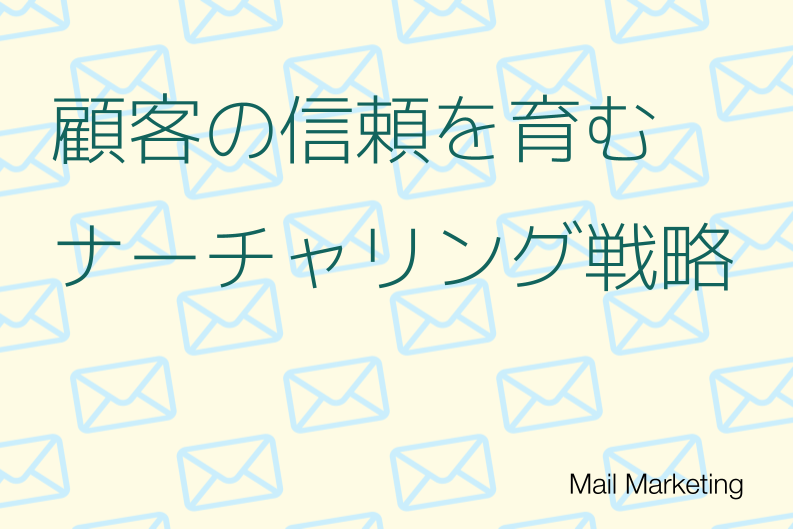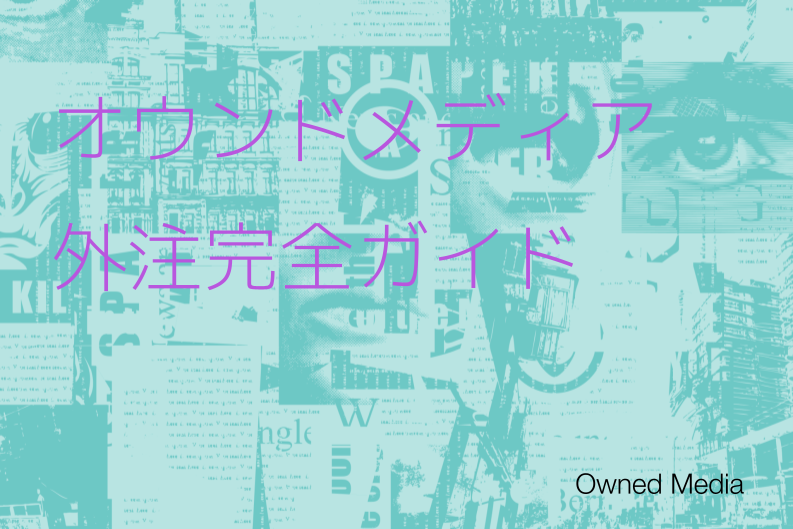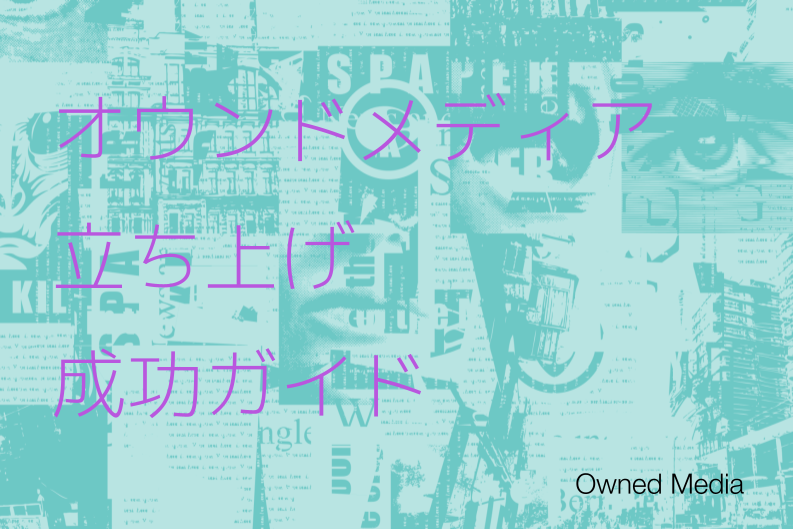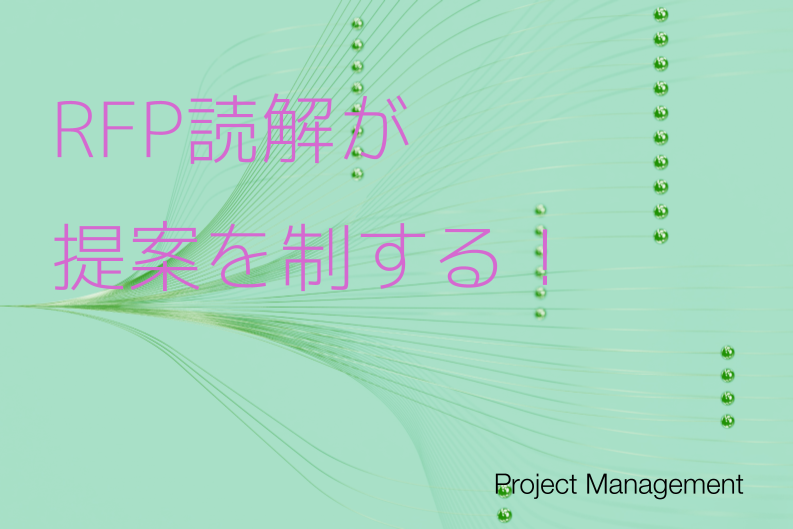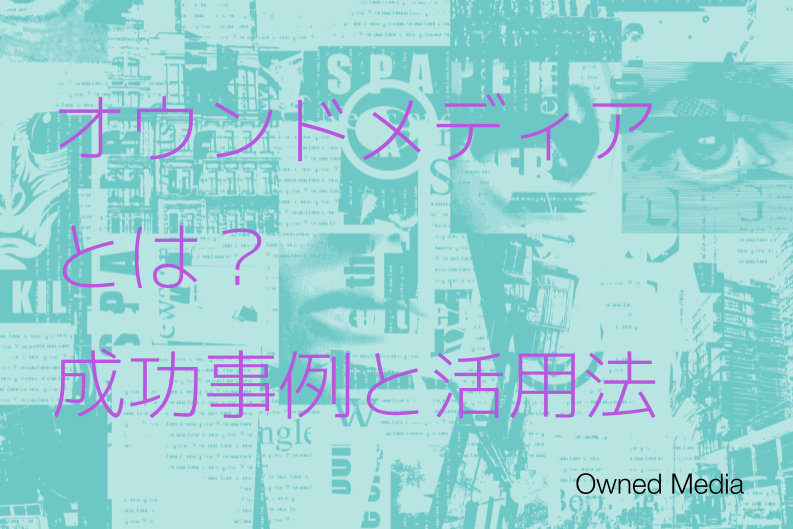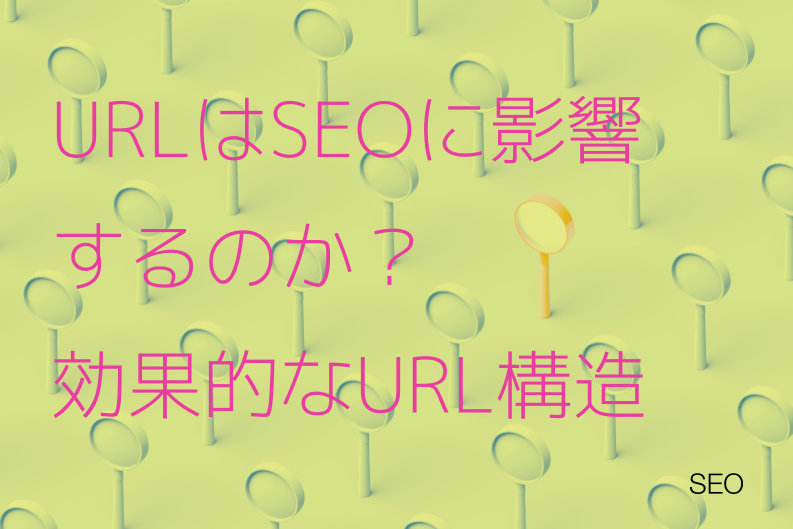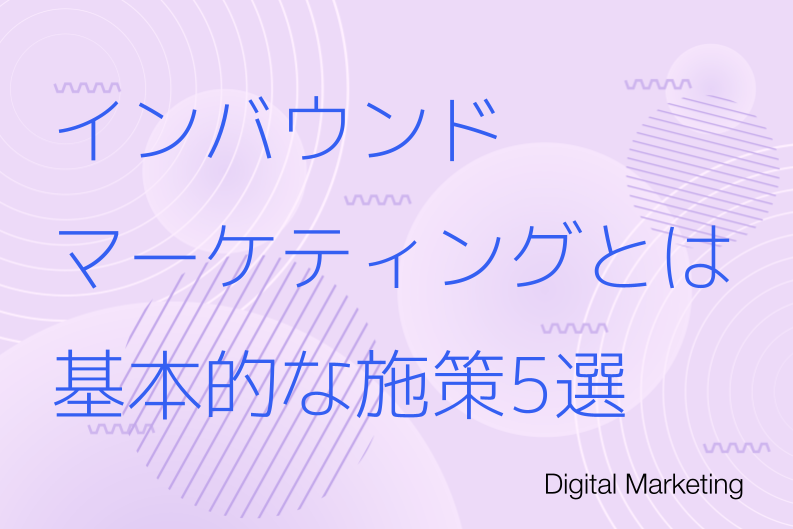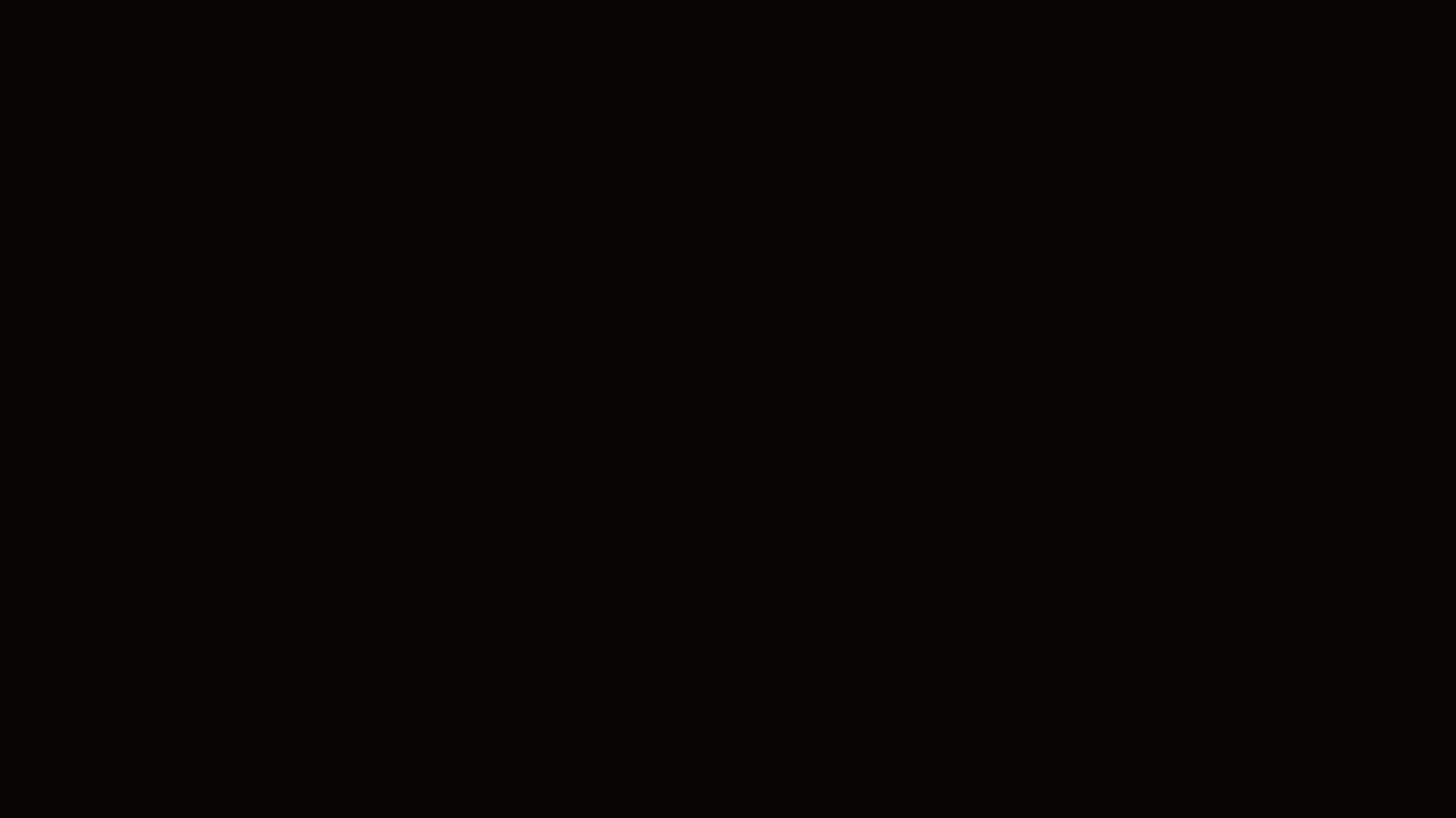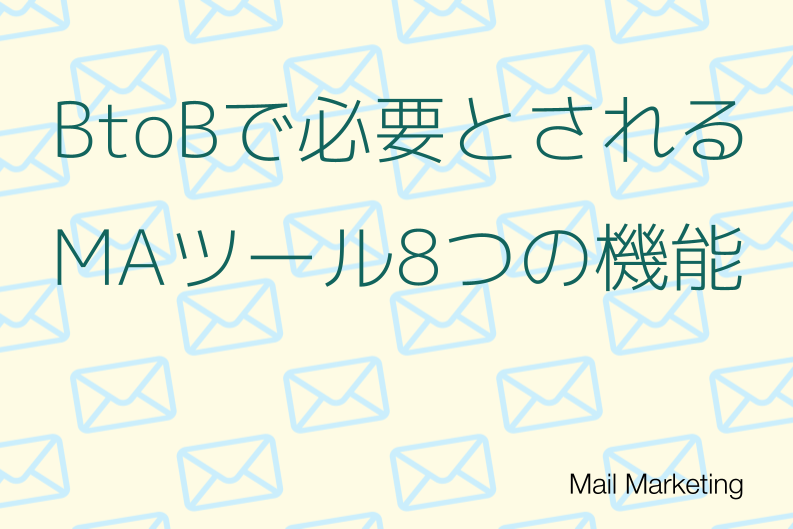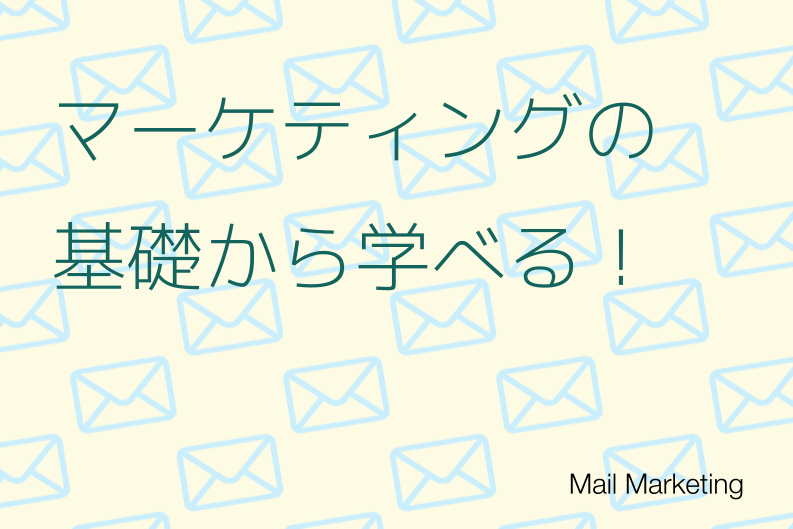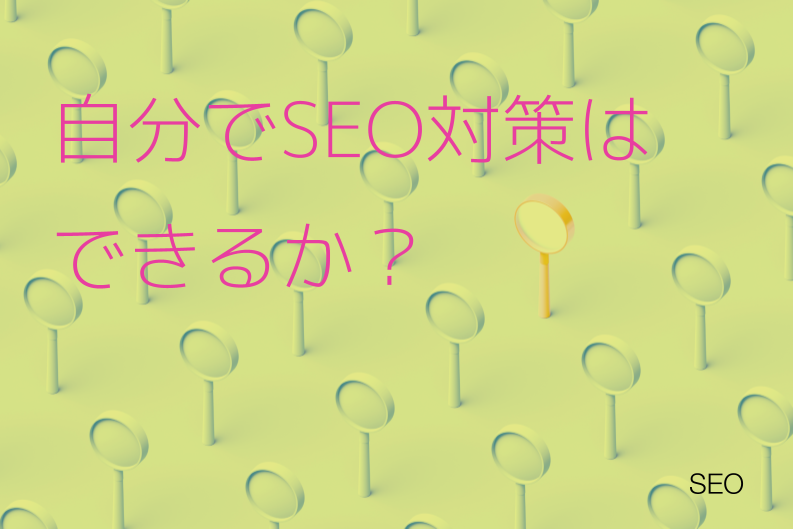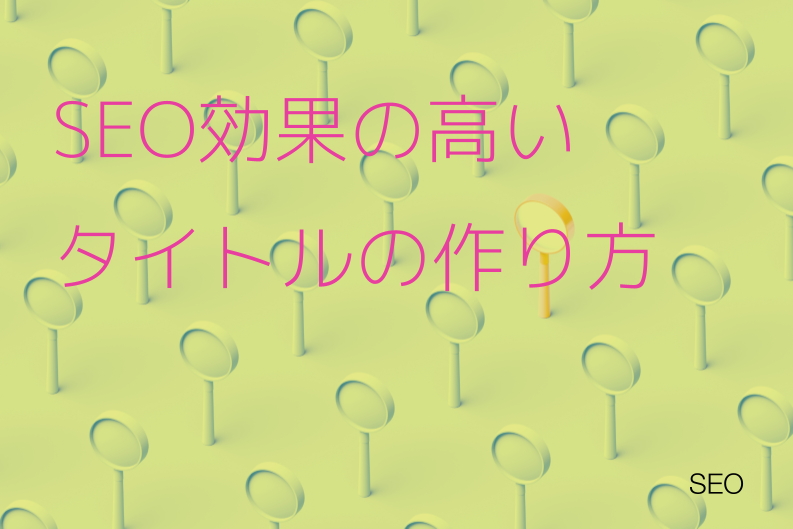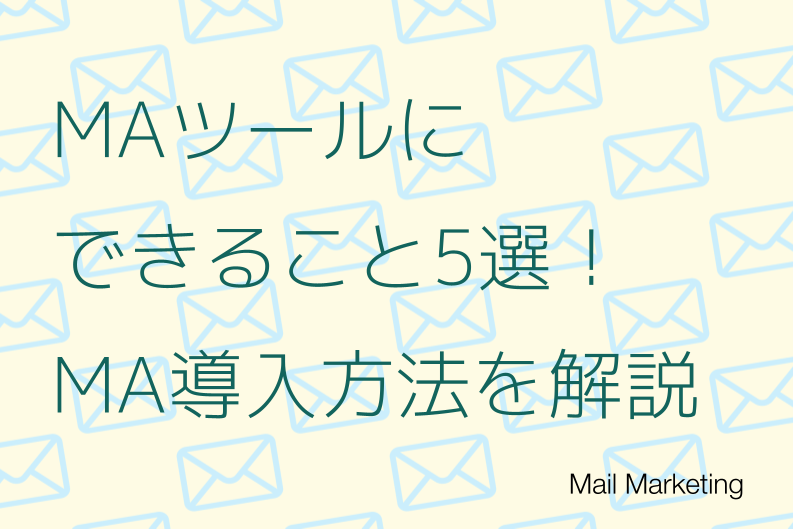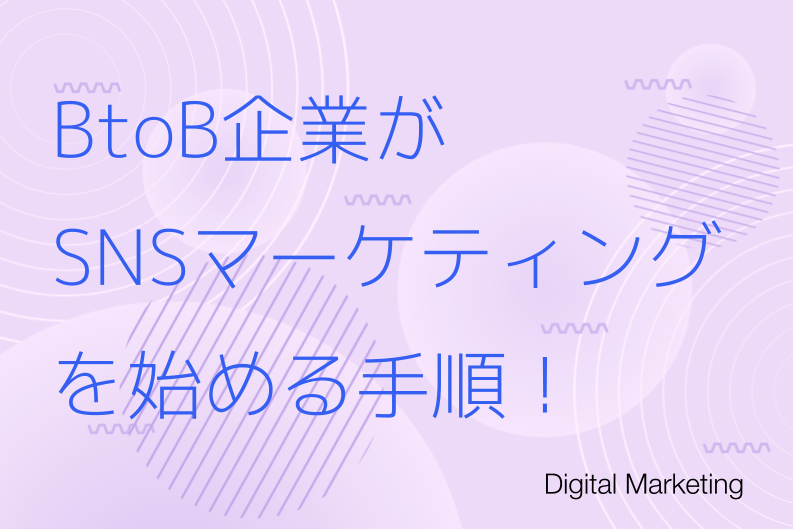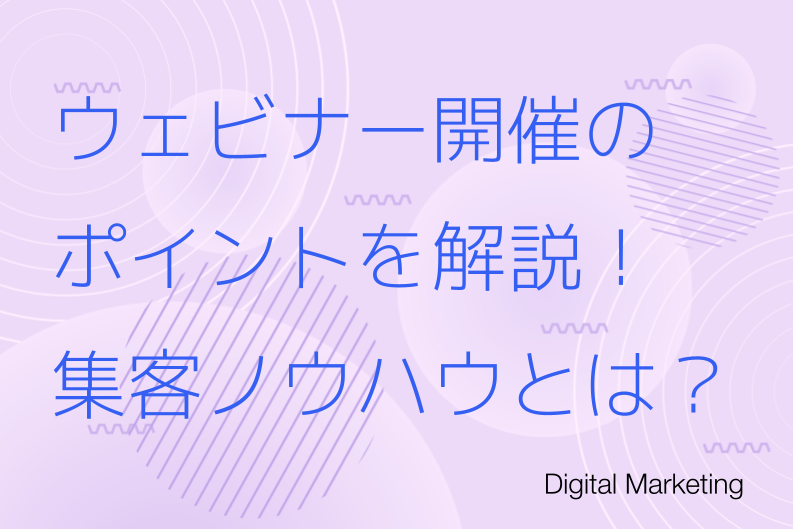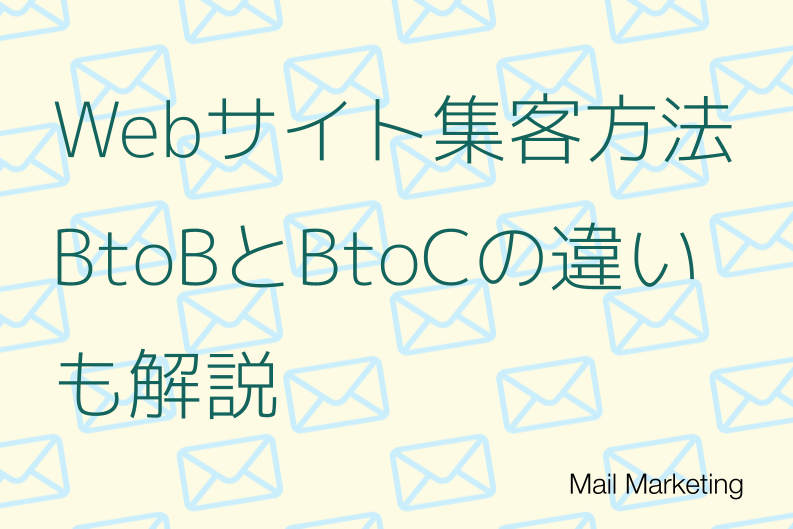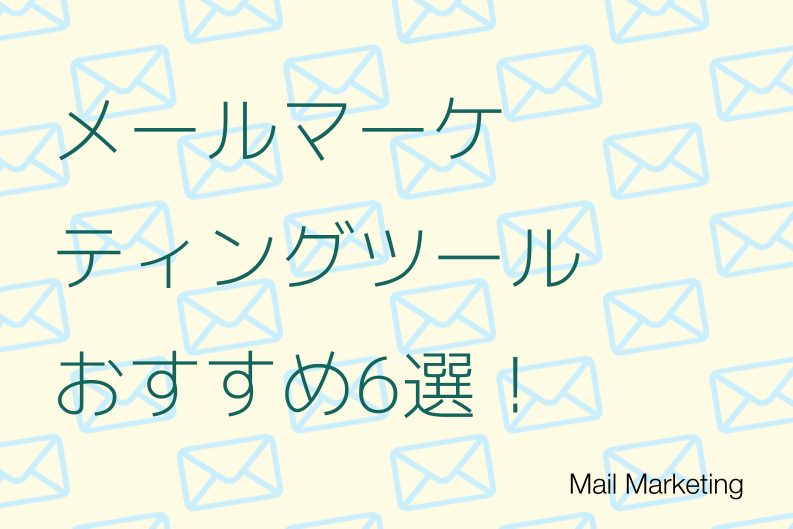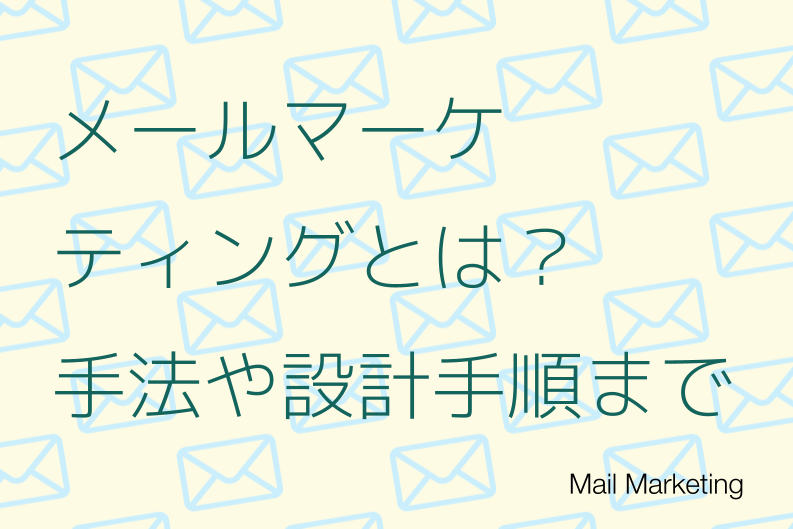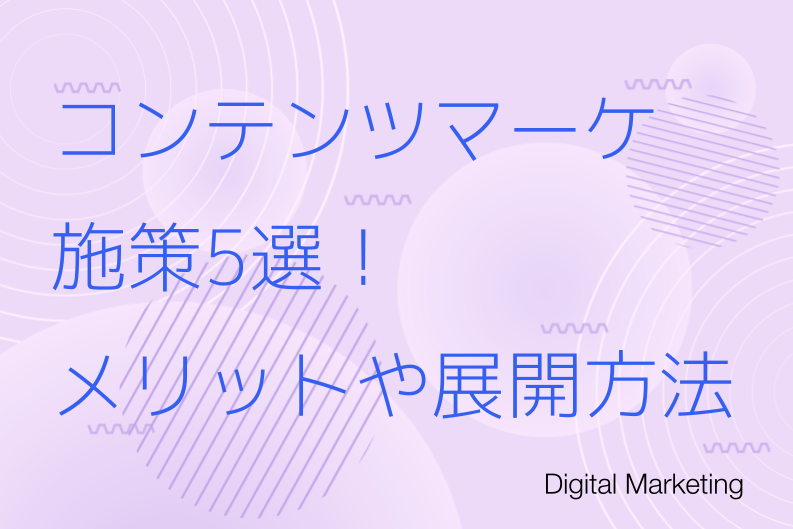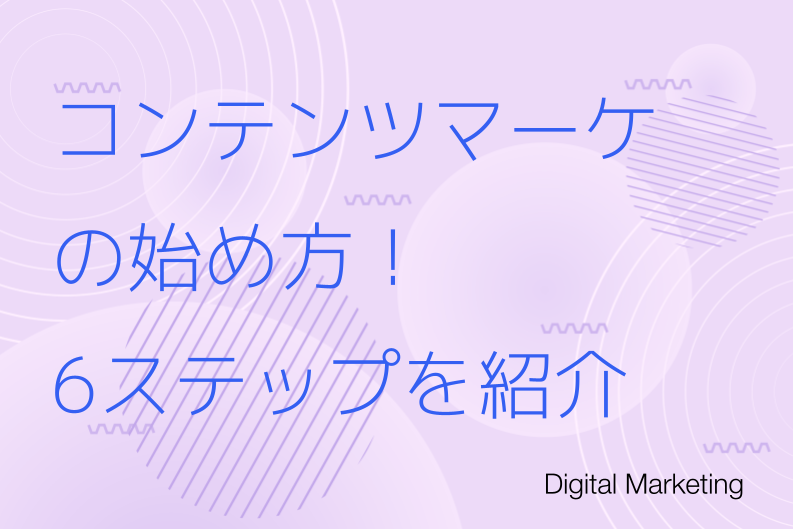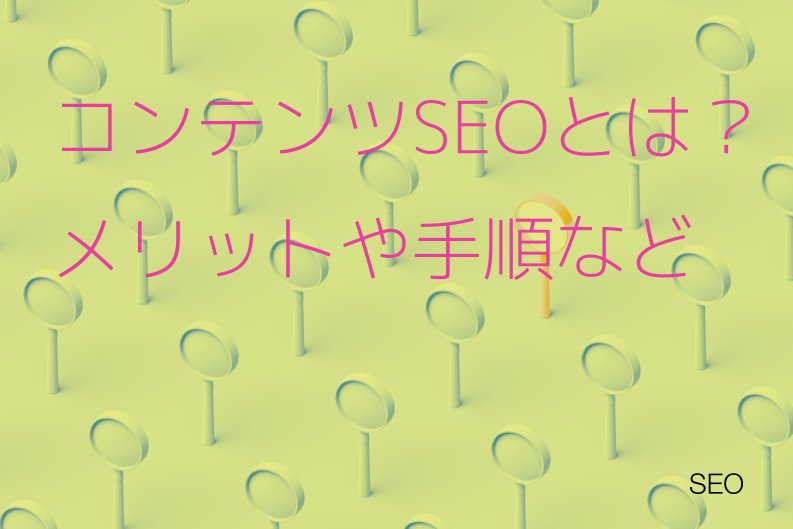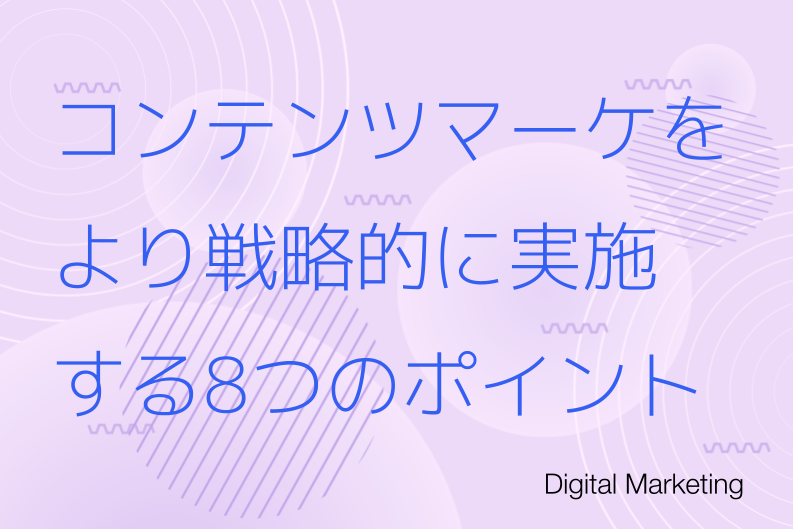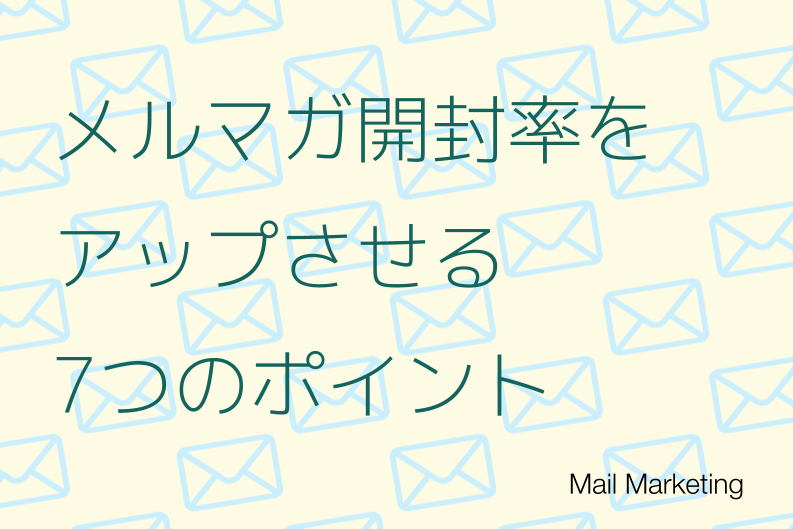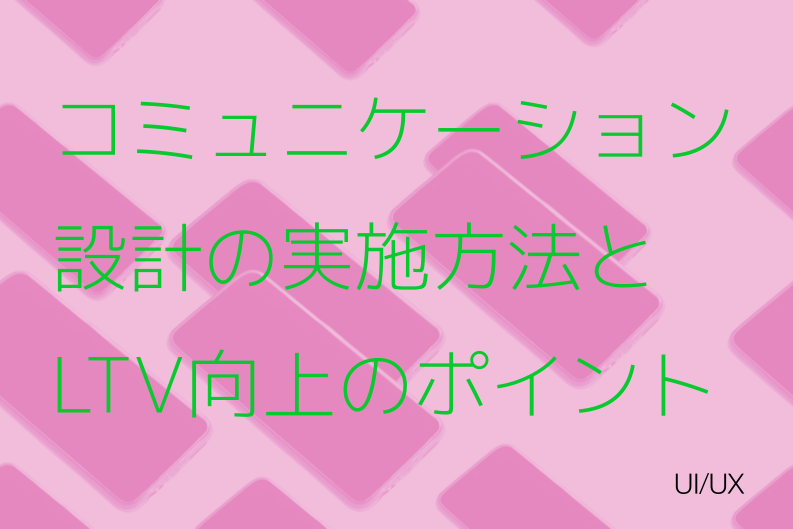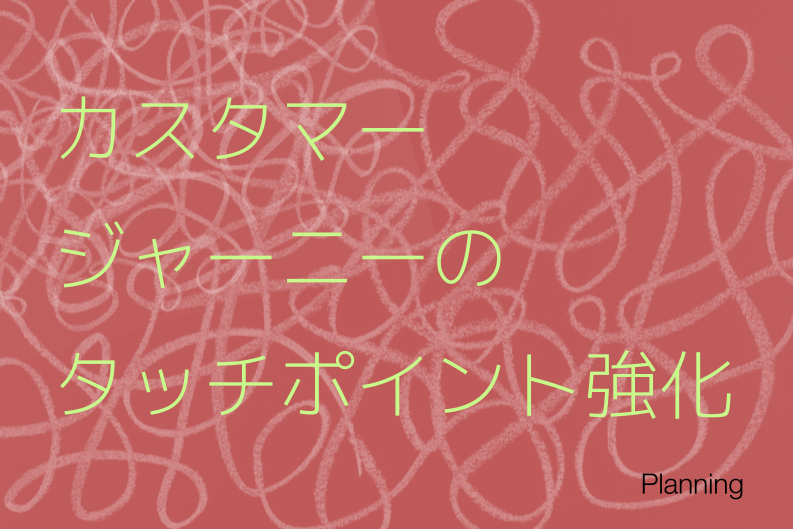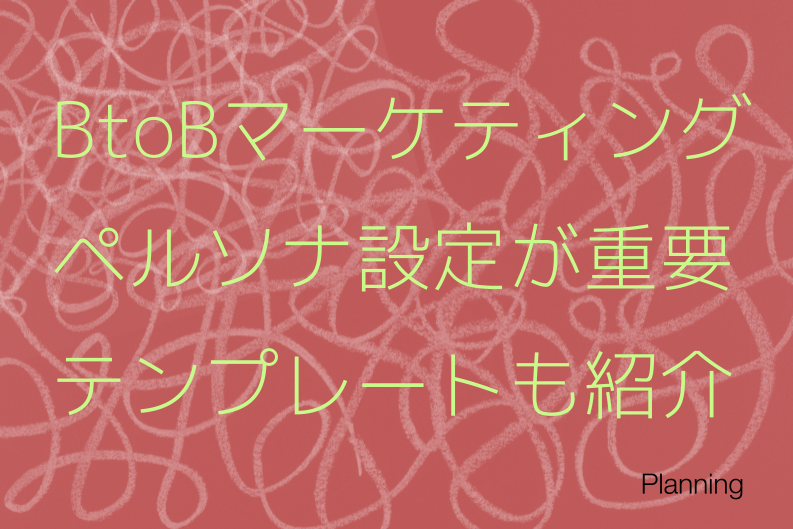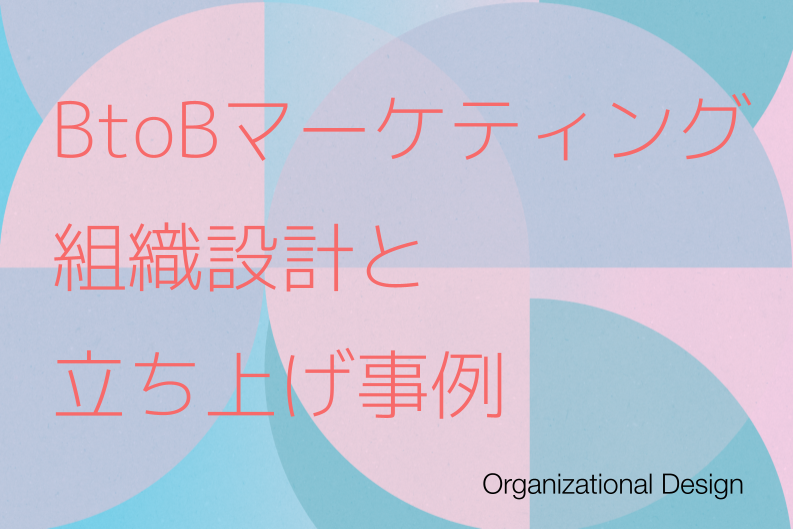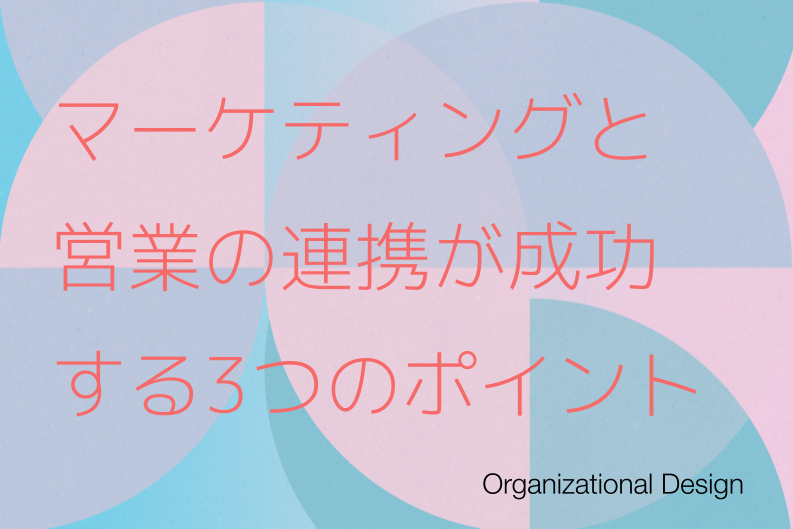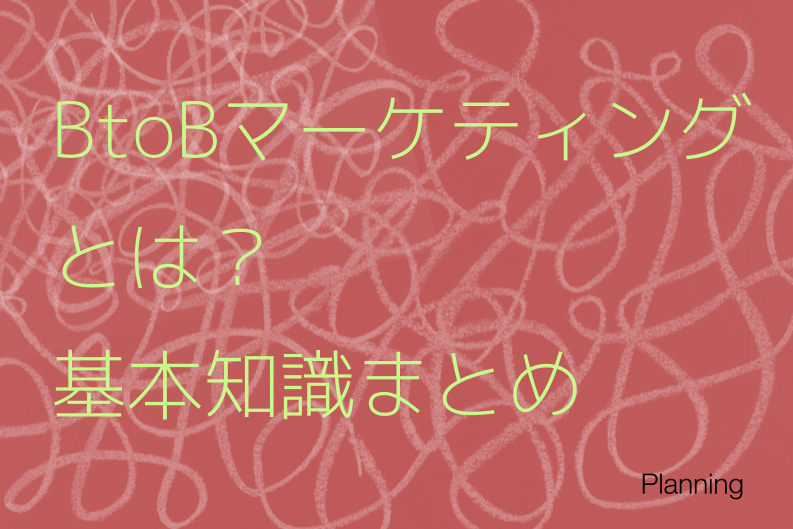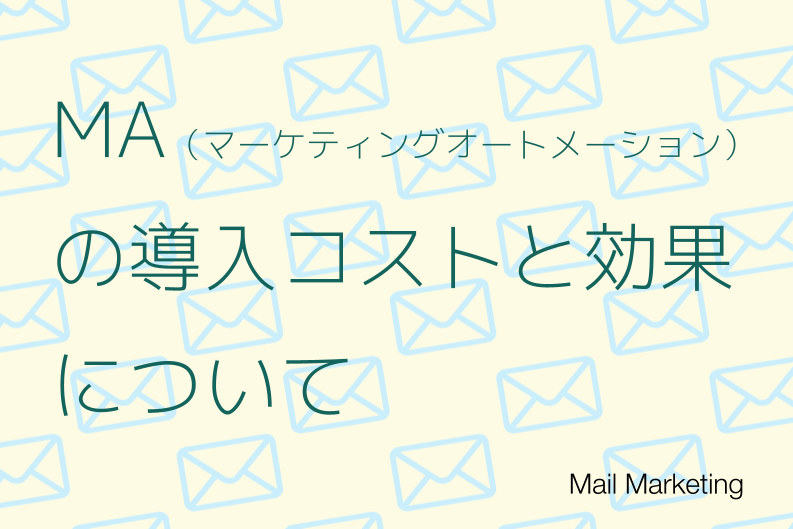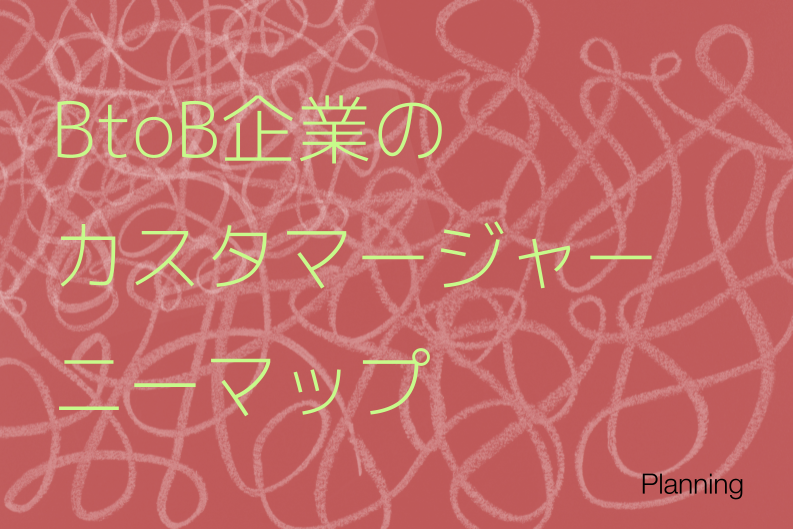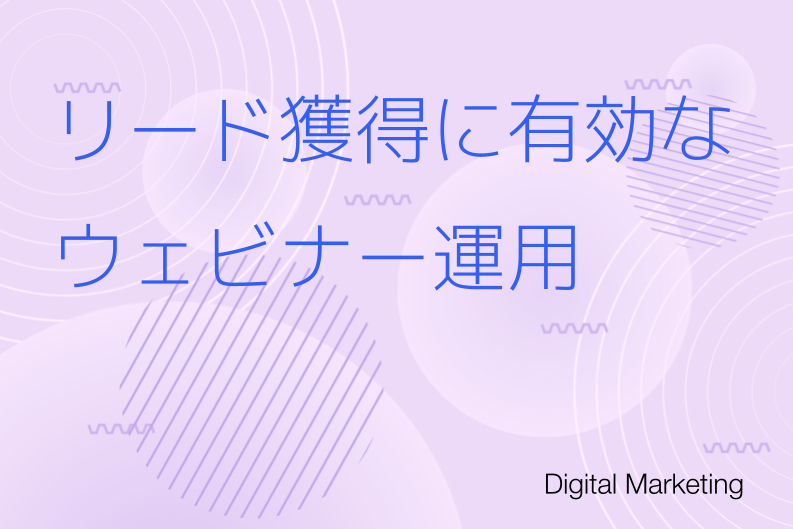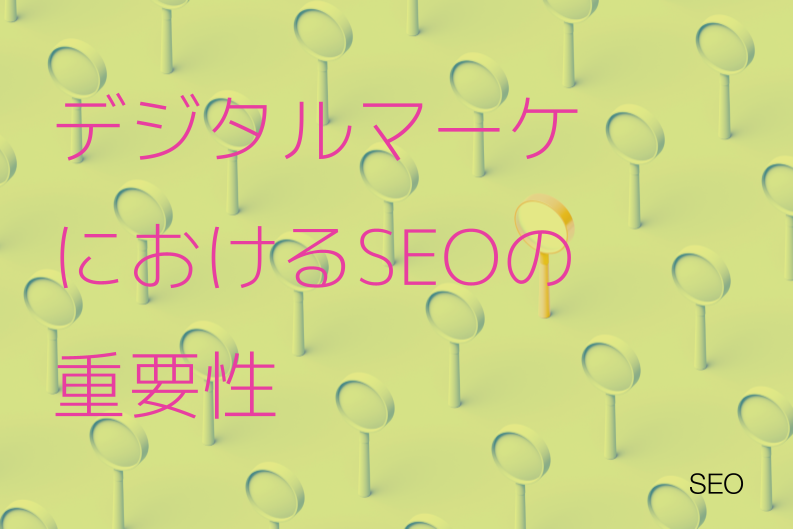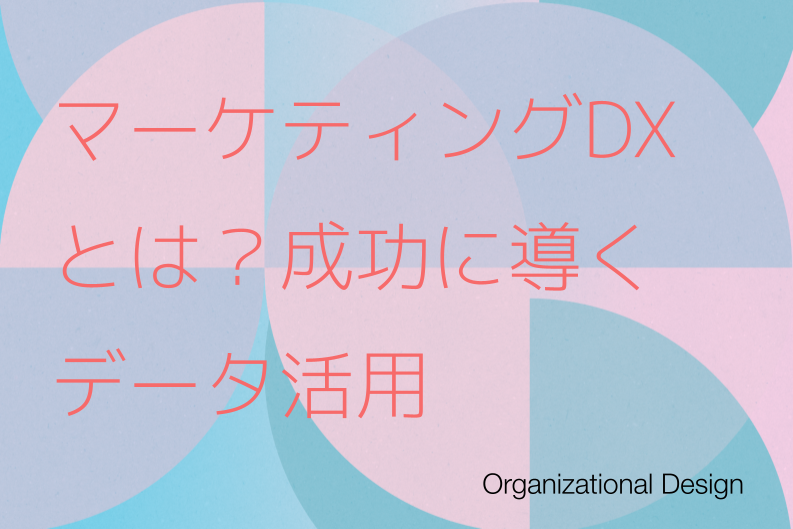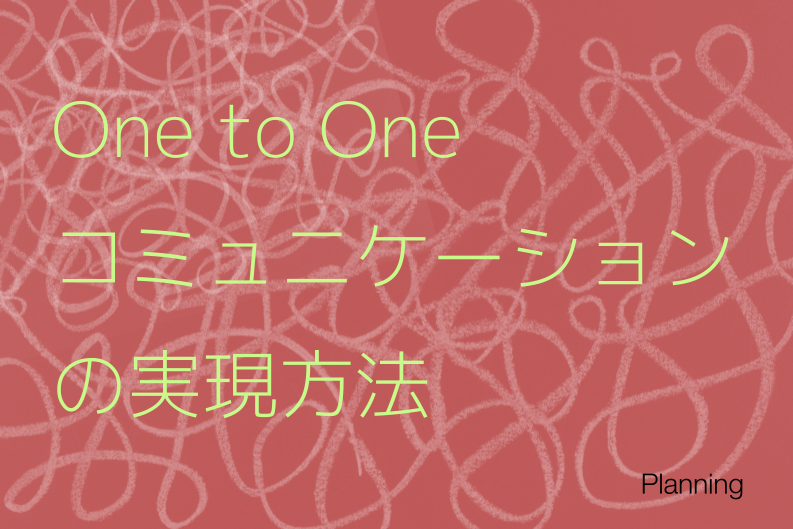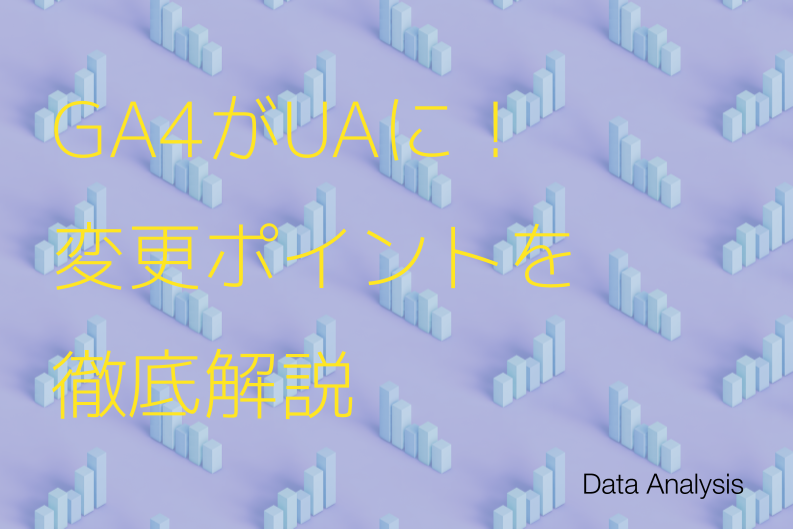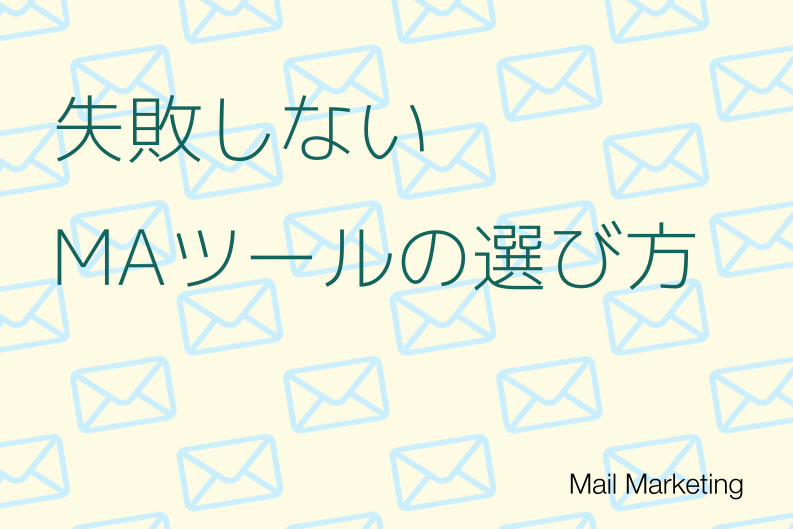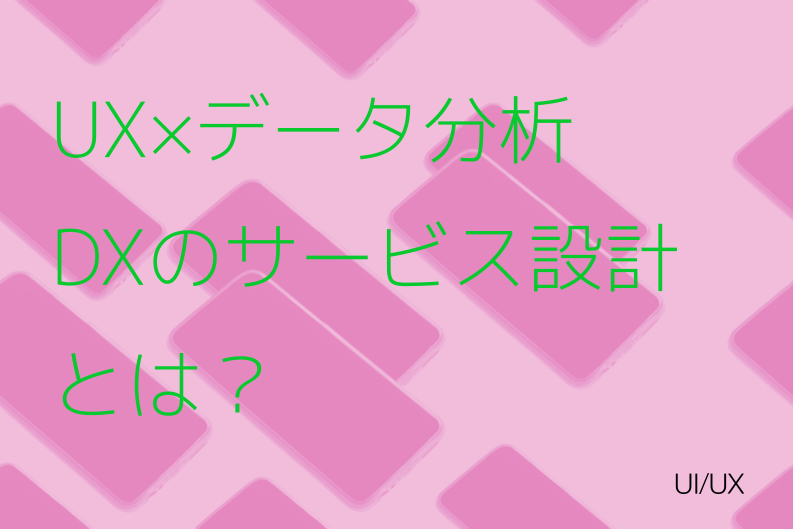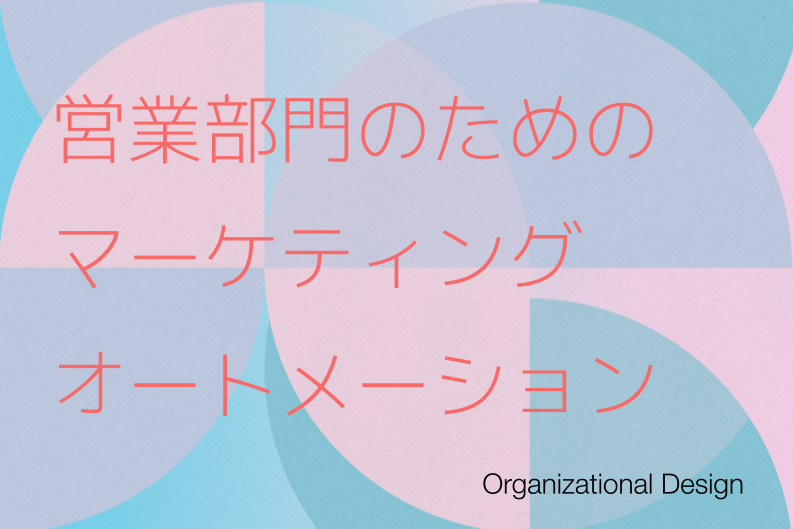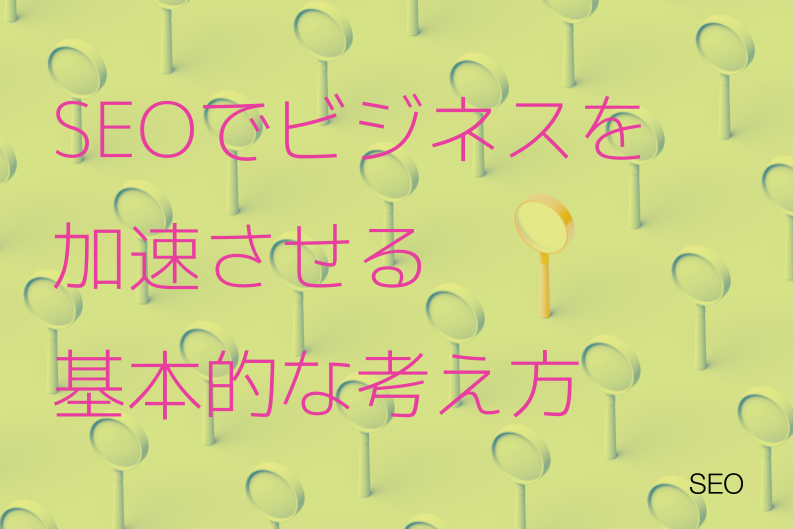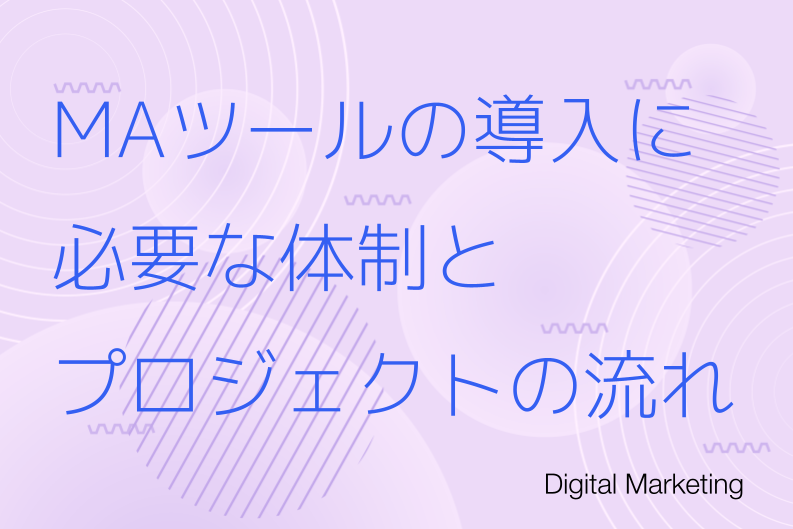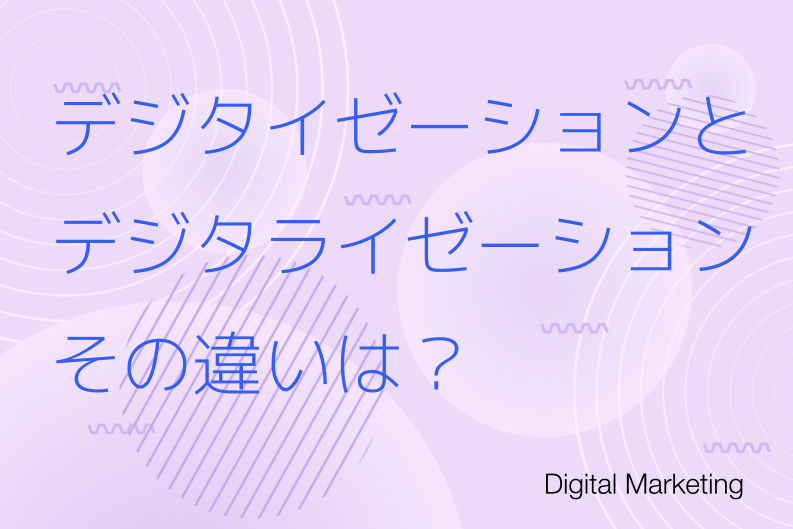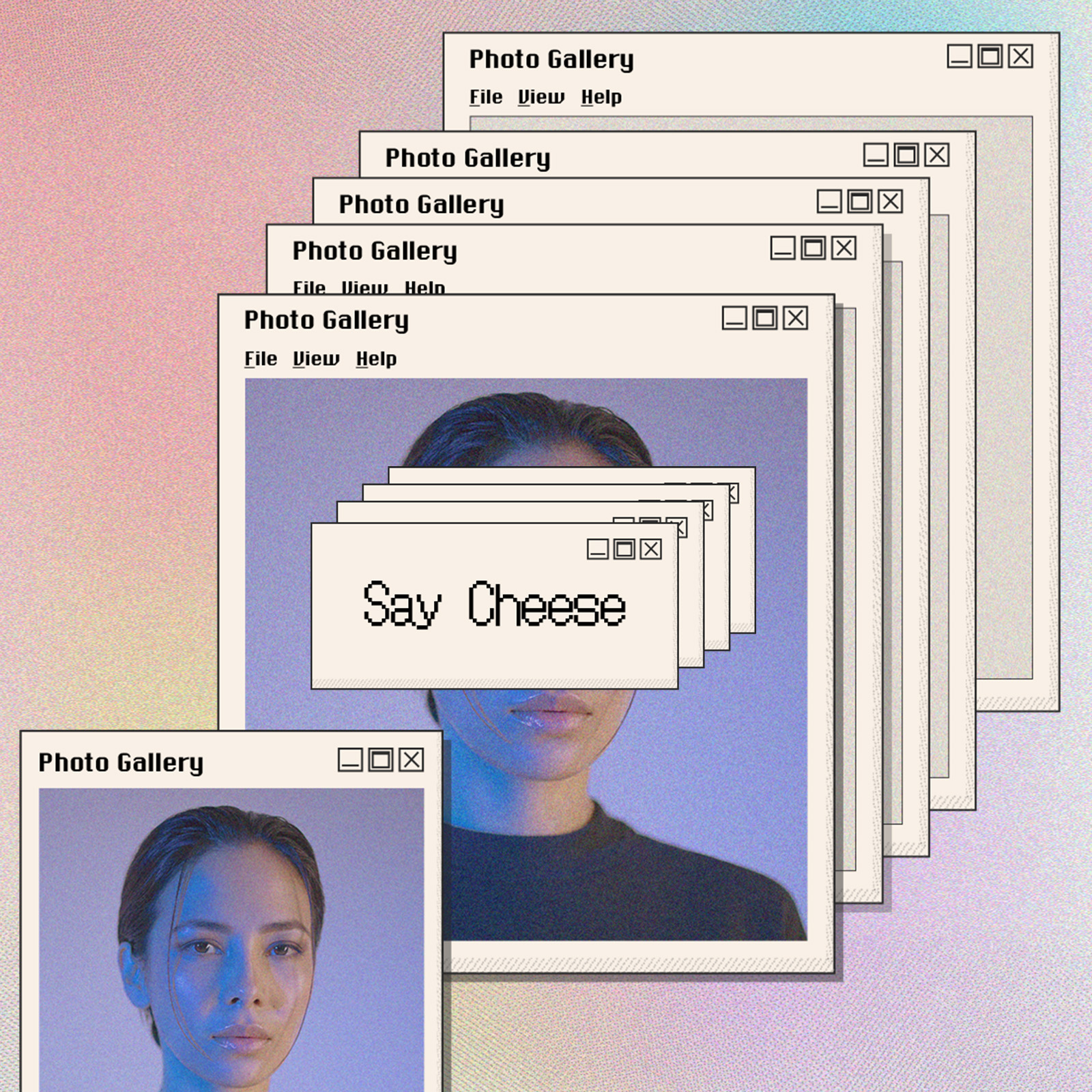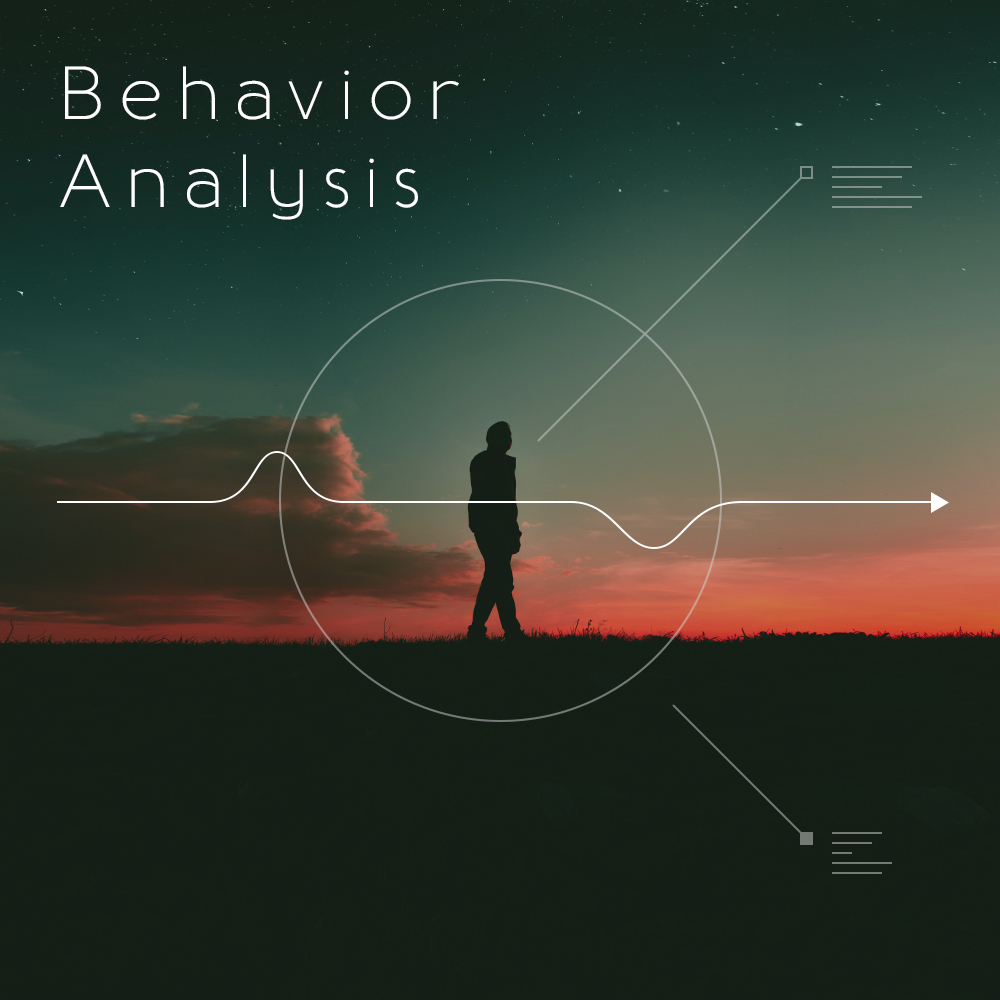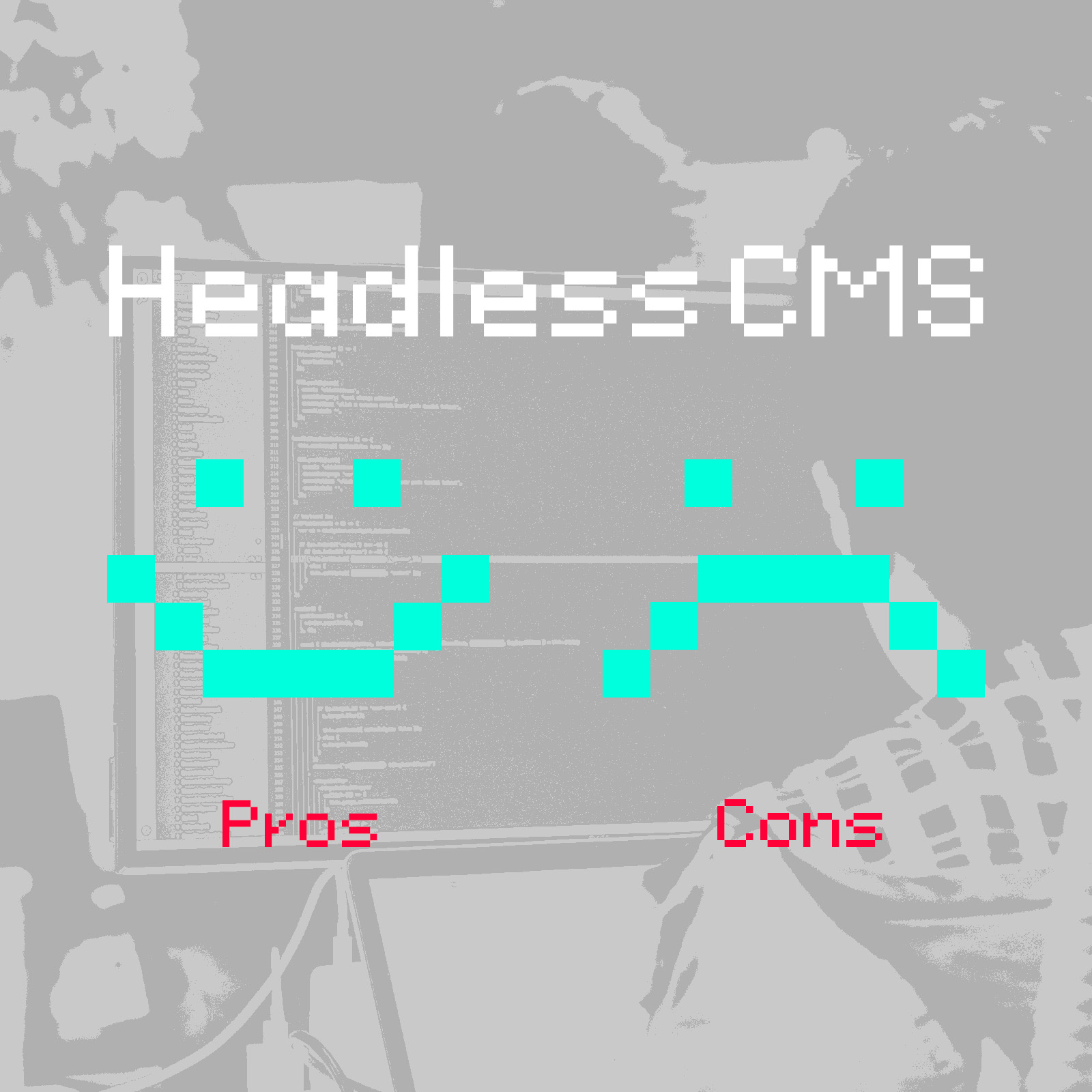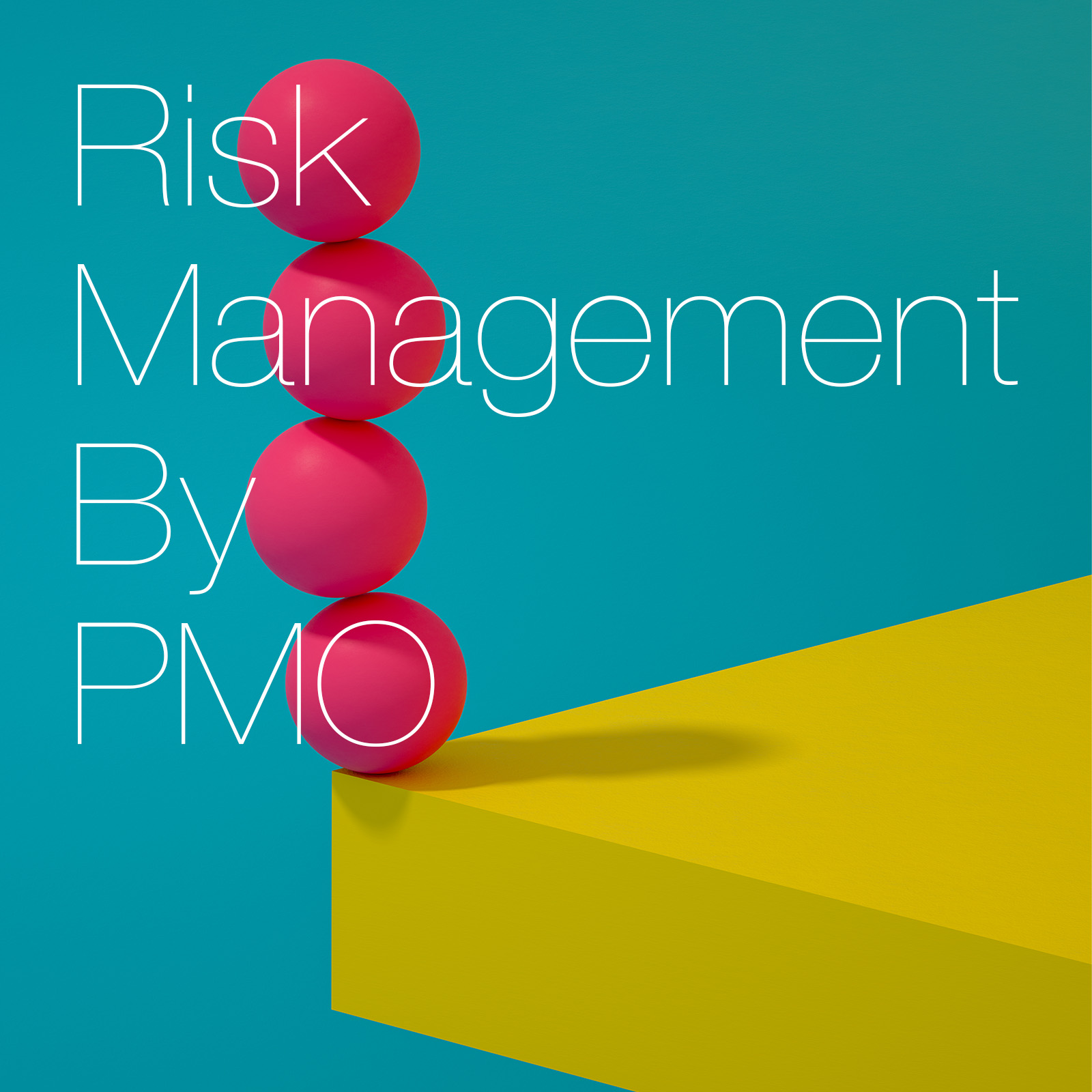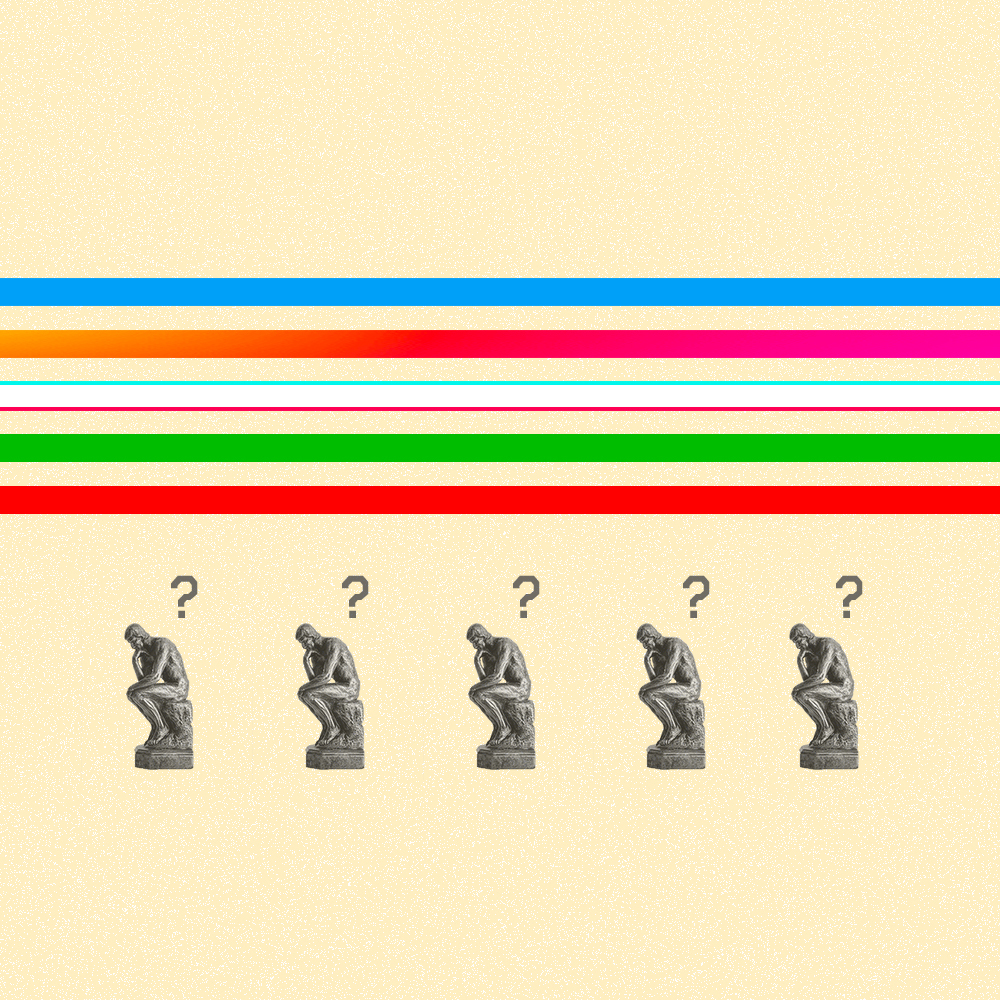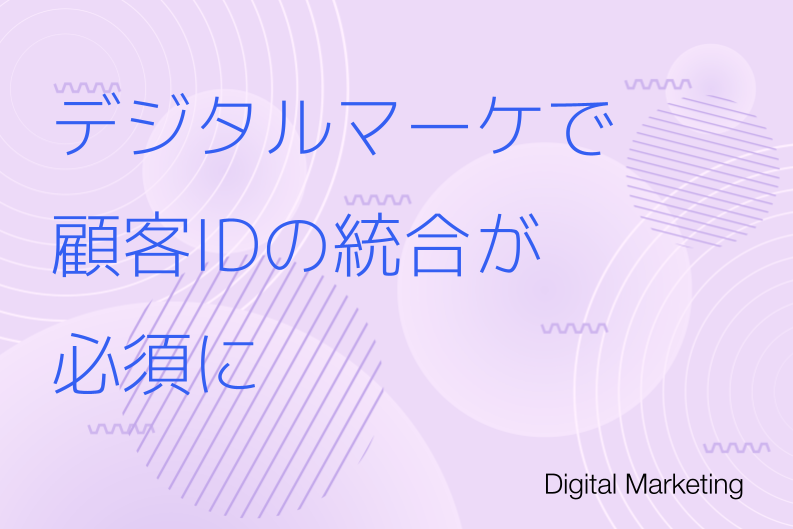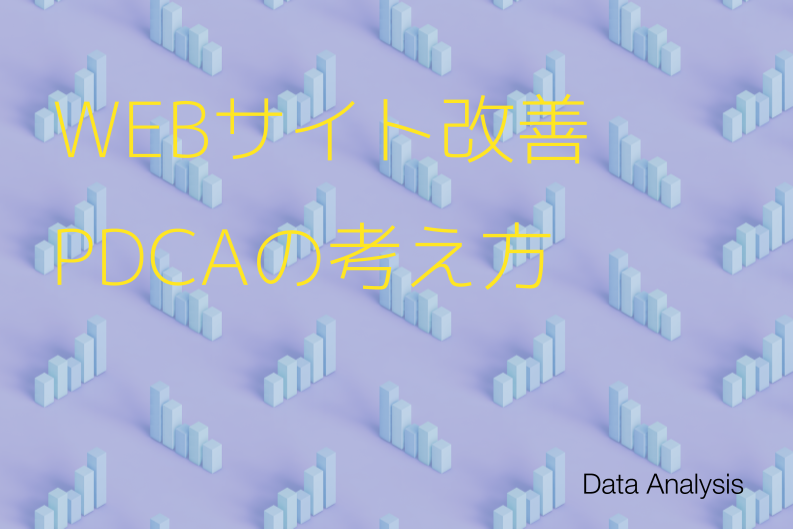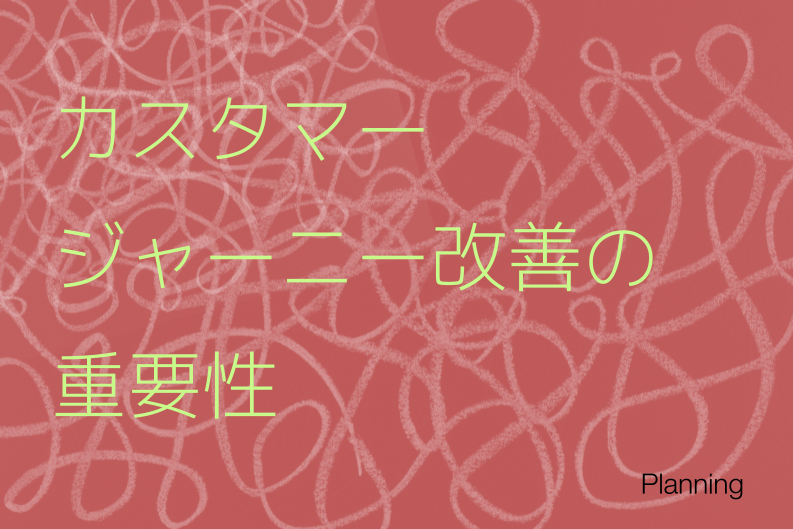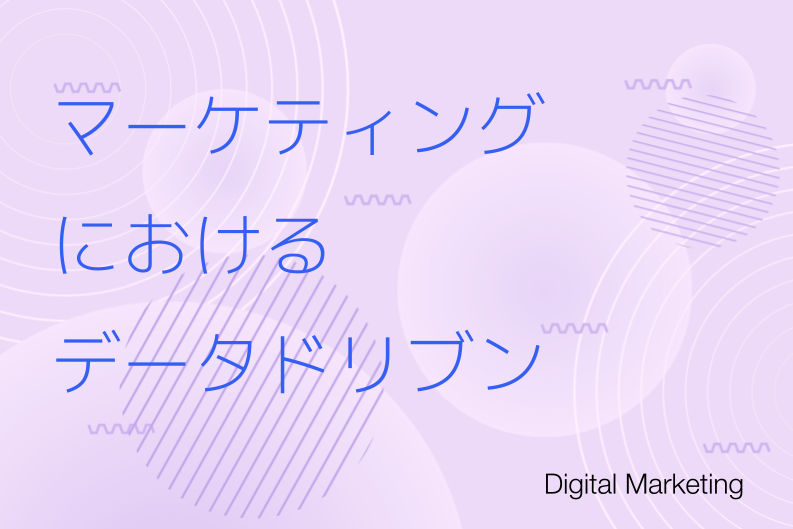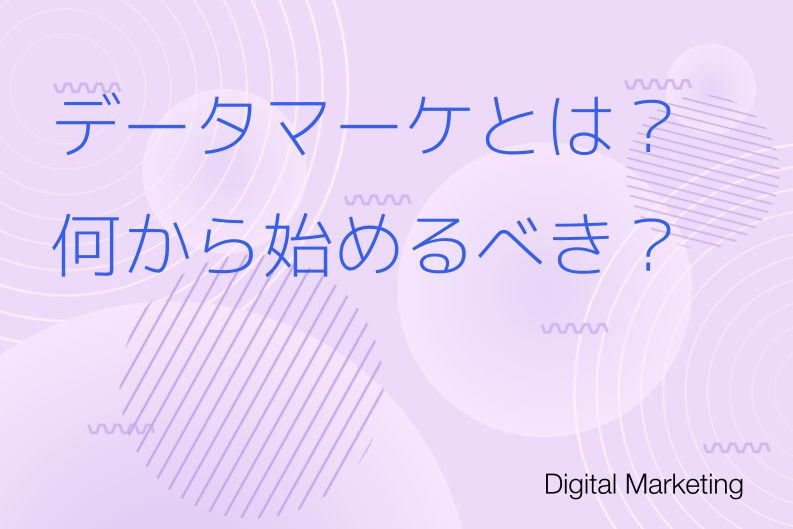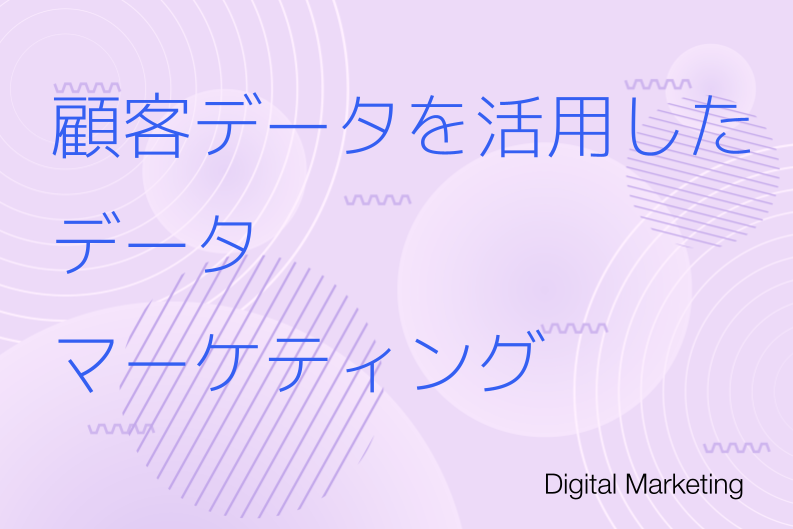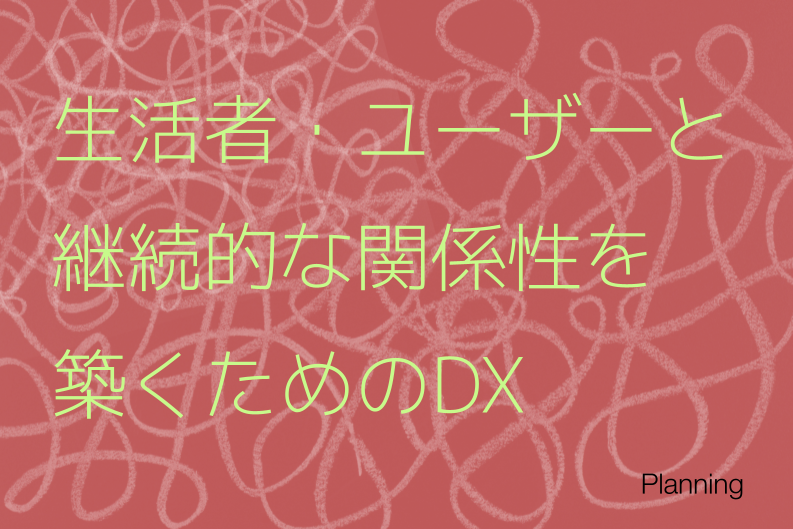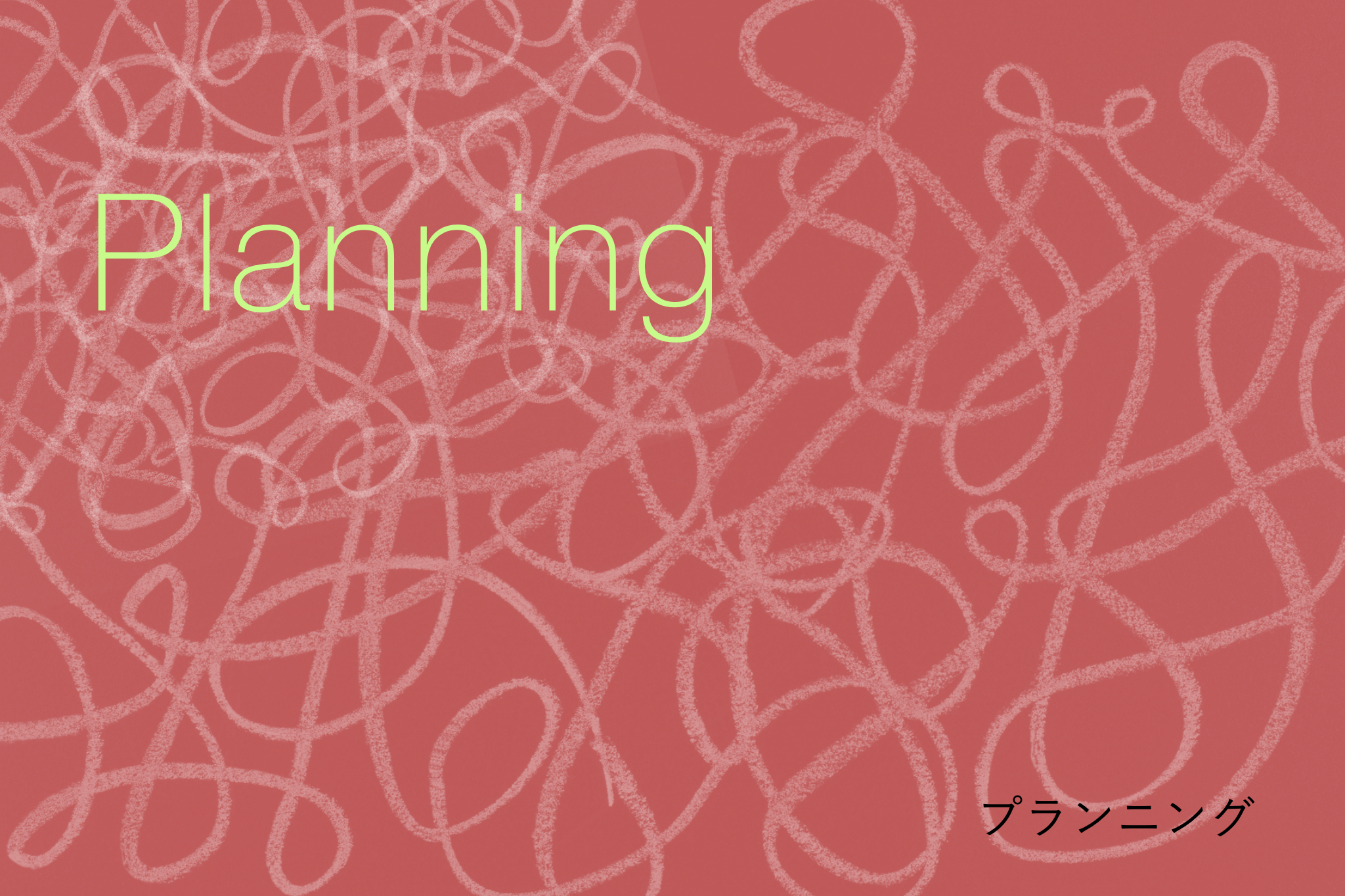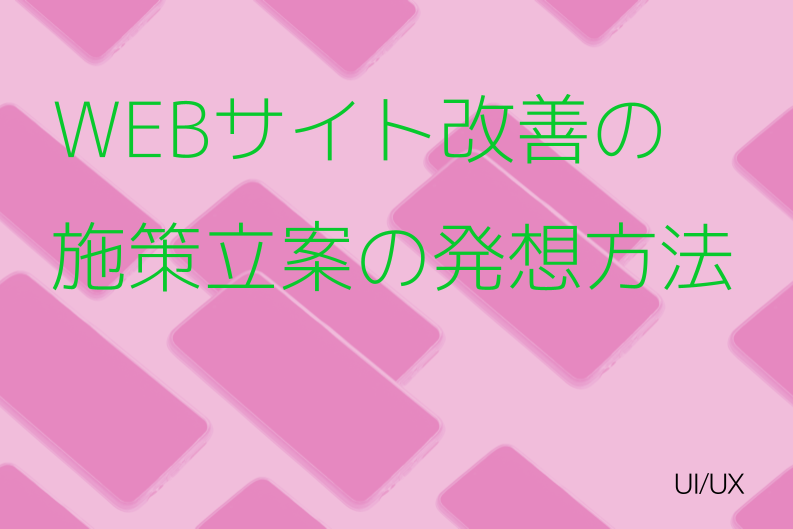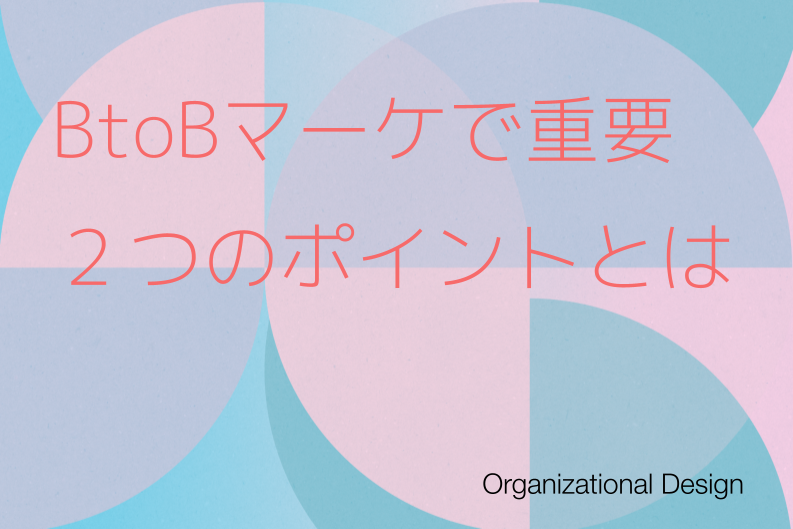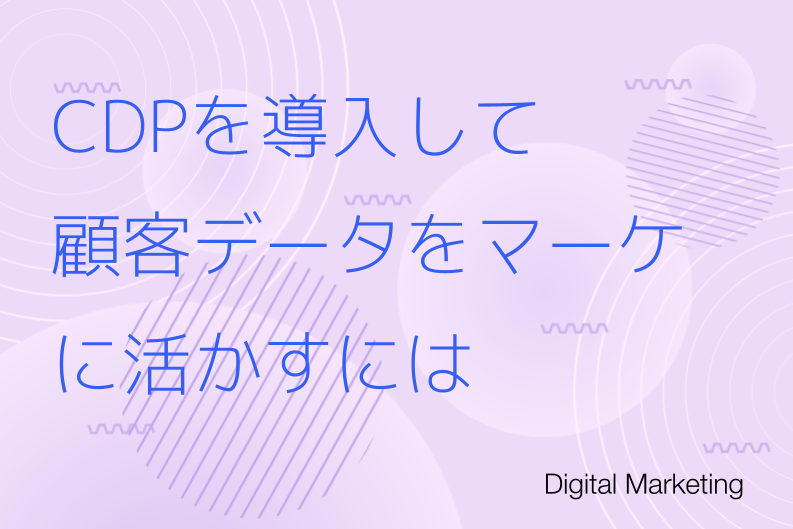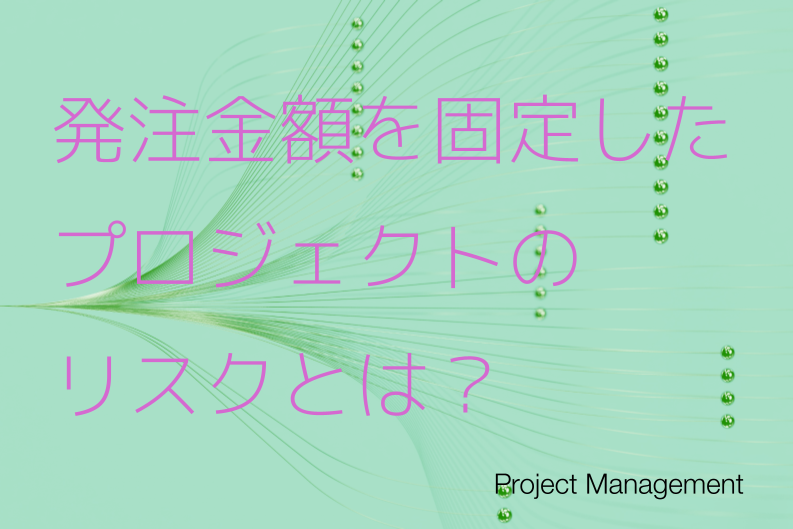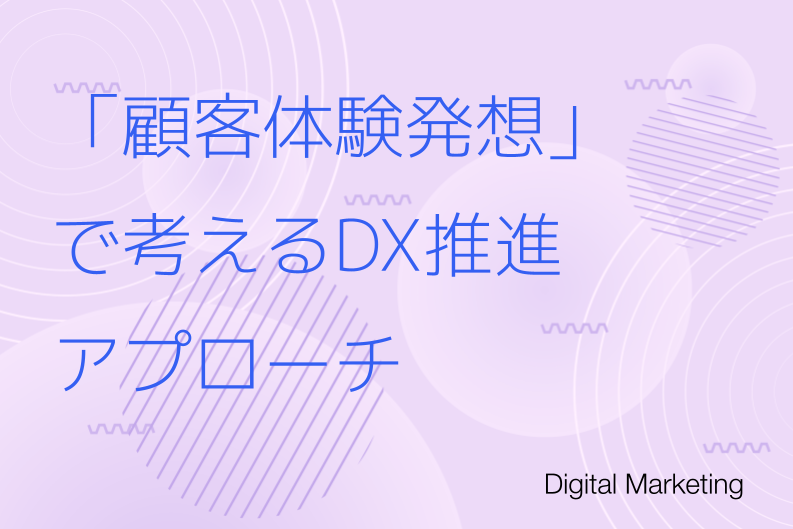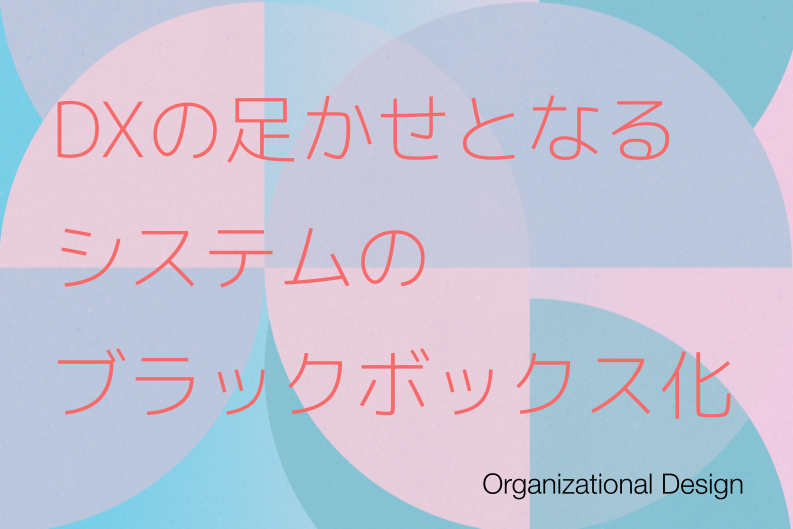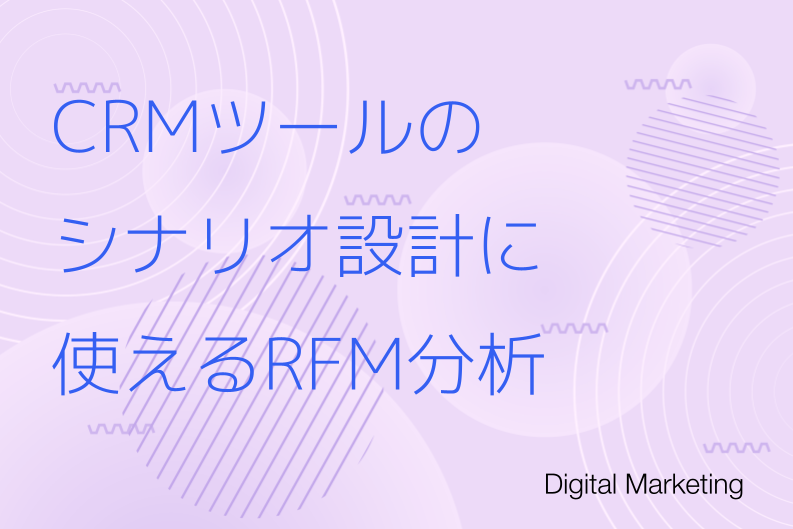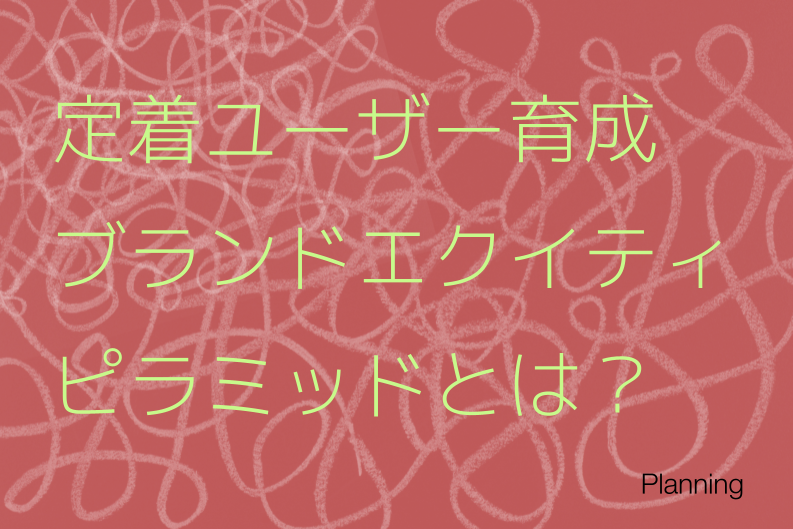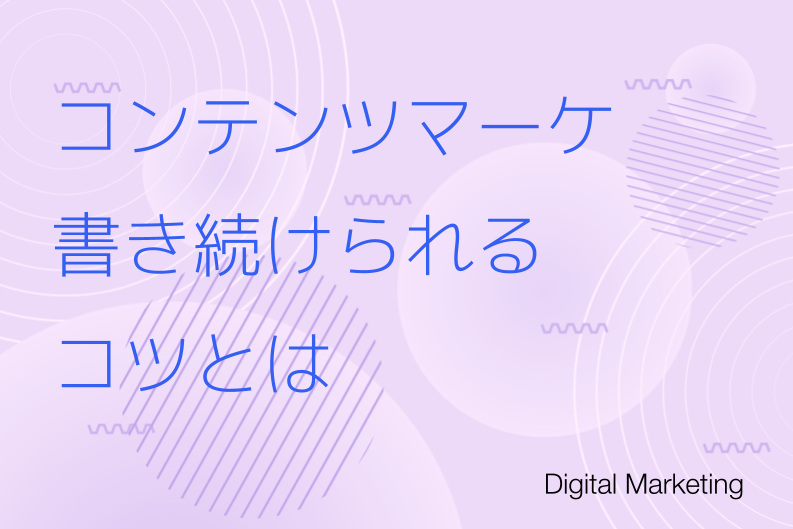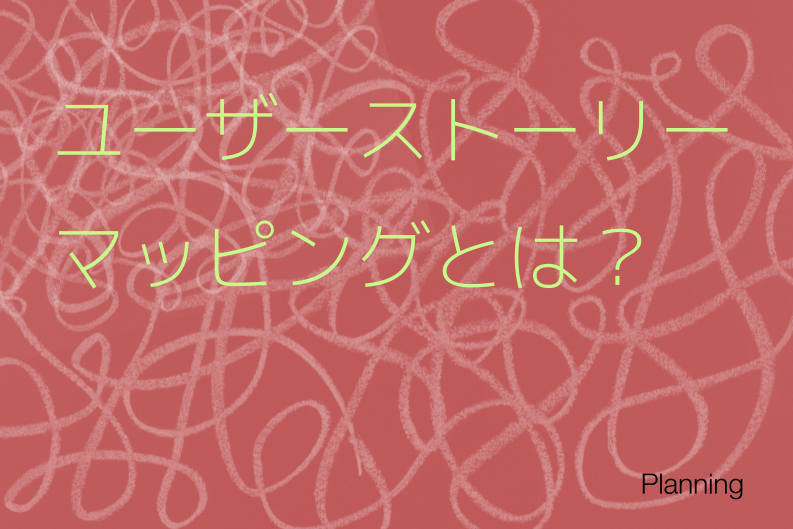躊躇なく楽しんでくれた!実証実験で気づいたこと
ー 初めて、エールがイベントで使われたのはどこですか?

満永「エール初の実証実験の場って、実は3年前に、<サーモを設置するはずだった音楽イベントONE MUSIC CAMPさん(前編参照)>なんです。
エールの開発目処がたって、1番最初に『ご無沙汰です!』ってメッセージを送って、実証実験の試みを快く受け入れてくれて。おかげで、実際のフェスユーザーに楽しんでもらえた。もう、ほんと感謝しています。」
吉澤「色々なご縁が、繋がっているんですよね。」
ー 実際にユーザーに使ってもらって、気づいたことはありましたか?

猪塚「社内テストを繰り返していたから、だいたいこうなるだろうと。ある程度想定していたんですけど、想像以上だったのは、本番でみんなの叫ぶ声が…めちゃくちゃデカい!会社でやったときとの違いを感じました。
吉澤さんみたいに、ふだんから叫ぶ人はいいんですけど(笑)、私…がんばってもあんまり叫べないほうで。実証実験をしたONE MUSIC CAMPって、山の中のイベントだったんですけど、天気も良くて、開放的になって。私も、めっちゃ叫べました。そのロケーションの違いで、こんなに変わるんだって驚きました。」
星野「声が想定よりデカいのはもちろんですが、みんな声を出すのって楽しいんだな。って改めて感じられたっていうか。複数回来てくれた人が、前回の自分の記録を越えようと大声を出してくれたり、子どもが楽しんでくれたりとか、みんな躊躇なく楽しんでくれて。それはよかったというか、いい気づきでした。」
満永「声を出すことがモチベーションになるって…実は声を出すまで気づかないんですよ。カラオケのカロリー表示に近いかもしれないんだけど、なんとなく100カロリー消費したのか、うれしい。このインサイトは、日常に感じないし。」
吉澤「そう、声を出させるってすっごいチャレンジだったので、みんな現地で上手くいくのかドキドキしてたんじゃないかな。声が中心のガイドだし、プリンタ筐体は離れたところにあるし、出てくる写真は叫んだ瞬間の顔だし。…でもそこがキモだった。カードを受け取った瞬間に体験してくれた人たちがみんなで爆笑してる姿は、想像を上回る結果で。心の中でガッツポーズしました!」

次の“ギルド”かも?プロジェクトを通じて感じた、新しいチームづくりの可能性
ー どうしてこのチームは、こんなにチームワークがいいのでしょう?

満永「基本、関わってくれる人みんながいい人だと思いますよ。行動することをいとわない人たちが集まってるって、すごく稀有な気がします。」
吉澤「たぶん、このプロジェクトって学びの場になってて。チーム内外含めて領域が違う人が集まると、自分では想像していなかったようなアイディアも出てくる。あのカードに電子マネーをつけたらイベント中の決済で使えるよね、とか。思いついてもやらないだろうなって思うことも、とりあえず、議題にあげてみるといろいろ動き出す。それが結果的に好転してる。」
満永「行動が正義なのは大前提なんですけど、アイディア側とか、エンジニア実装チームでいきなり紙でメガホンつくって叫んでみる、っていう人って多くないんじゃないかな。これ、量産想定で小型化しましょう。ってプロデューサー側から提案が出たり。それぞれの立場から、自分ごとにしながら、動けてる。奇跡的な状態かもしれないですね。」

猪塚「メンバーみんなが、イベントの現場に行くから、一緒にいる時間が多いのも大きいかもしれないです。イベントに行くと現地で使っている人の生の姿や声を、エンジニアも含めてみんなが見ている。直接聞いてるし。」
満永「そうですよね、数千人もさばいて、対応いただいてますもんね。」
猪塚「はい。あとエンジニアとしてはコロナ明けの『ここぞ、という公開タイミングに合わせなきゃ』という気持ちもあって、特にスピード感を持ってやってました。
クライアントがいるわけじゃないから本当は締切もないんだけど、そのタイミングに実装を間に合わせなきゃって。期限やスピード感に対する意識は強かった気がします。」

満永「急に、勝手にイベント決めてきて、すいません!」
猪塚「いやー 動き早っ!て思いました(笑)」
星野「でも、これが絶対無理っていうタイミングでもないんですよね(笑)」
道堂「無理なことは無理って言ってもらえましたよね。それって大切なことだったかなと。」
星野「イベントで1回だけ動けばいいってものじゃなくて。その先の展開も考えて、運用しやすくないといけない。誰でも簡単に動かせるとか、マニュアル化するとか。それを意識しながら設計することは、難しいけど楽しいです。」
吉村「そういえば、議事録の概念整理のメモに 【 カードや筐体よりも、応援する人を立たせる 】って書いてあって、エモくなりました…。振り返ると、その整理は大事だったなと思いました。皆さん、サーモ歴長いでしょう?僕は途中参加だったからもう、絶対1番必死なメンバーだったと思います!」
星野「サーモ歴(笑)」
吉澤「吉村くんはエールのプロジェクトから、途中で加わったもんね。前日の輸送段階から届かなかったらどうしようって、ピリピリしてたよね。」

吉村「このチームで何か残さなきゃ!って強い気持ちがあったんで、もう頭おかしくなりそうでした。届いて、あ〜〜!よかったぁ!って。」
満永「サーモ歴が浅い、今回新しくメンバーに加わっていただいた吉村さんがチームの共通課題認識を持ってくれていることも嬉しいです。これ、結構すごいことだと思って。
だって僕らに社訓が、あるわけじゃないじゃないですか(笑)明言してもないし法人格でもない。週1以外Slackでしか繋がってるものがないのに、共通認識が合ってるって、超うれしい。新しい組織の形、ギルドの次のような感じがする。」
吉村「そうなんですかね、そう言ってもらえると僕もうれしいです。」
満永「このチーム、何でもゼロからつくれちゃう。ってのがそもそもすごいんですよね。」
吉村「振り返ると、なんか…このチームのメンバーって各々の中に目標があるタイプが多くて。それぞれのタスクとして終わらせる、ってことをしない。今回、先輩たちが僕ら若手を育ててくれてるんだろうなって意識もあるし、もっといいものを作りたいとか、それぞれ目標を持ってるから自然と動くし、フラットな…いいディスカッションができてたと思います。
空気を読んで迎合するとか、人の意見を潰す、潰されるってことは1度もなかったです。」
チーム/メンバーのこれからの展望は?エンタメ・発見・展示会
ー プロジェクトの今後の発展や、可能性について聞かせてください。
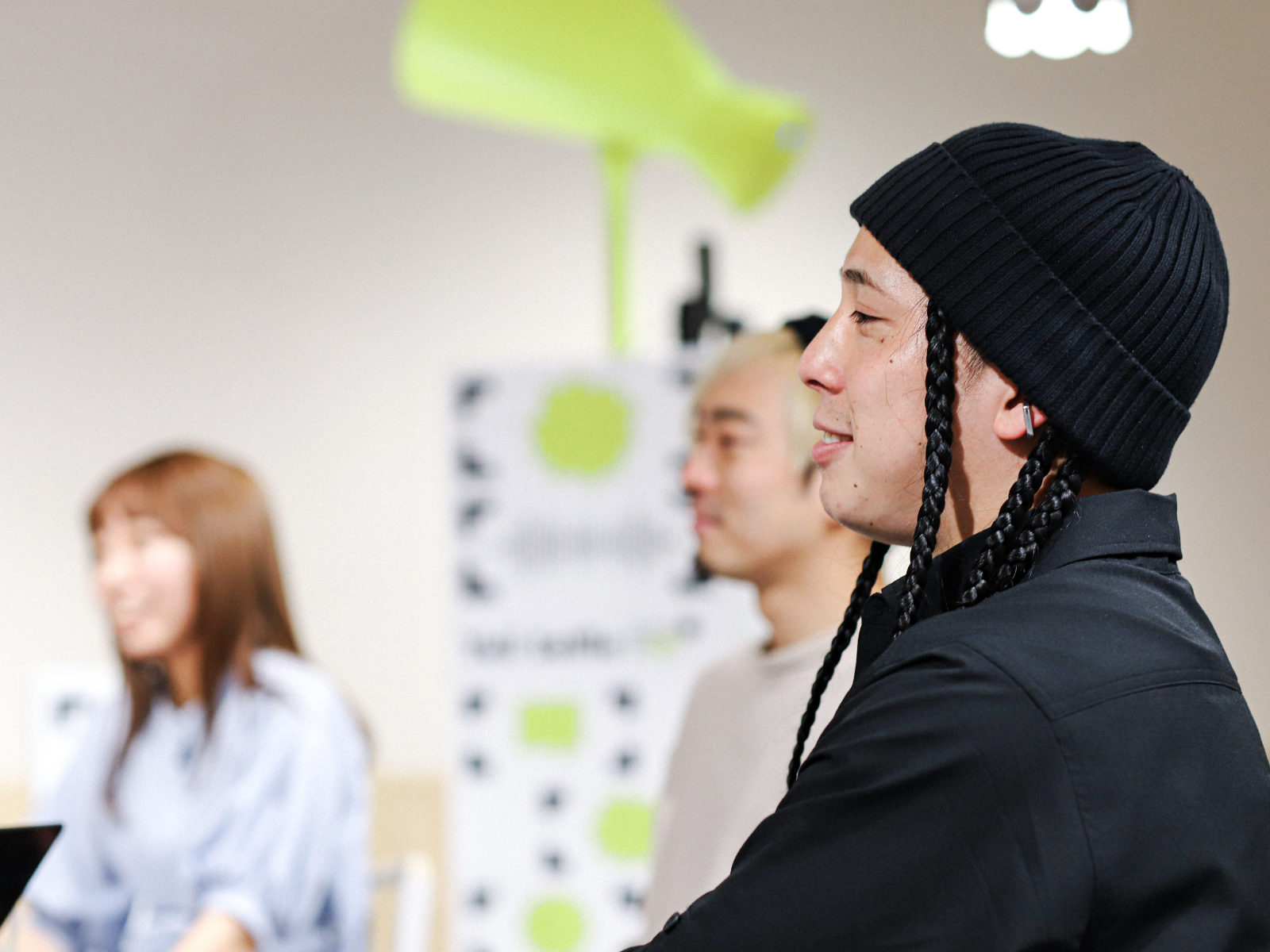
満永「僕らHYTEKって、これまでずっとデジタルとフィジカルの間のものづくりをやってきたことが、今の形に結びついています。
道堂がデジタルの研究開発を担当していて、僕はアナログな場所でパフィーマンスやイベントの仕事をしていた。ふたりの興味の延長上、交差点にあるものが、ライブやイベントといったもので、それが今につながってます。ものづくりを通じて、グローバルに発信していくことを続けたい。
サーモはもう既に海外を渡っていて。テキサスで、めちゃくちゃ検温してるんですよ。これからも人種やモーメントを選ばず展開していきたい。検温って、あの時期…世界中の人が、同じような“負”を感じていたからか…当時、海外から反応は多かったです。」
星野「反応ってどんなかんじでした?」
満永「『日本人はやっぱクレイジーだな』『プリクラ作っちゃう国ってやっぱヤバいね』『あれ自体がディストピアじゃん』『あの個人情報はどのような扱いになるんだ?』といった、そこまで幅広い議論を生んだのは“検温体験”だったからでしょうね。
エールに関しては…おそらく体験して『いいな』と思ってくれた人が伝えてくれるものになっていくかなと。ゆっくり、ゆっくり広がっていけばいいなって思っています。」

吉澤「ビジネスの出発点って、たくさんの人が使いたいとか、やりたいと思ってもらえるかどうか。人を動かすものって結果的に利益も生み出すと思うんです。そういう意味では、サーモもエールもそういうものが作れた。
あとは、どれだけ収益に繋げられるか。輸送方法を工夫したり、複数台製造するためにコストを検討するような細かいことから、いろんな企業さんが使いたいと思ってもらうための集客視点、広告視点とか、収益モデルは何が最適なのかとか、都度考えてますね。
ちょっと話が逸れるかもしれないけど、サーモの次を作る前に道堂さんと話してたのは、いろんな技術を取り入れてビジネスチャンスを作るアイデアのベース...サーモセルフィーの系譜を受け継いだ“サービス”が、必要なんじゃないかって。
サーモセルフィーで、強いブランドが作れたと思うので、これをセルフィーシリーズというコンセプトでコンテンツを増やして拡げていく。これがチームにおけるベースのビジネスモデルになるんじゃないかなって思ってました。道堂さん的には、そのあたりどう思っていましたか?」
道堂「そうですね。一時期はこのチームのブランディングをどうするかって考えたので。最終的にクライアントからこのチームに対して依頼がくるような形ができたらいい。
感覚的には…このエールを1万台売って稼ぐ、ってのは現実的じゃないんです。そもそも運用できる体制がない。そういう意味でも、デジタルで広げていくのが現実的ですよね。
フィジカルでインパクトを与えて、人が体験しているのを誰かに見てもらえる。ってのはPRの視点でも大事で、ものづくり段階でそこを意識してやろうって話をしてました。」

満永「よくする議論で好きだったのは、これはリースで薄利多売だけだとキツイから、売り切りで常設モノでチャージさせる手もあるよなとか。
以前、サーモの問い合わせの中で、海外からソフトウェアの権利を買えないか?売ってくれって!相談の連絡があって。その問い合わせは、特殊だなって思ったけどいいヒントをもらえました。
つまり、フィジカルなものは、ショーケースとしてあるけど、実際の売り物はもっとソフト的な概念的なもの。アイスタさんに実装いただいた、アプリケーションかもしれない。
サーモセルフィーの商標とか。ライセンスとか。ほにゃららセルフィーシリーズの概念が売れていくってなれば、可能性あると思う。吉澤さんが、いろんなタイミングで『とはいえビジネスにしなきゃ!』って話題を繰り返しするんですよ(笑)。だからチームの議論の中で、アイデアやクリエイティブと並行して考えるきっかけにもなりました。」
吉澤「まだ試行錯誤中なんですが、イベント会社さんに売ってマージンをいただく仕組みとか、チーム自体にフィーをもらって研究開発を進めるとか、そんなアイデアも出しながら、シミュレーションしてみたり。
サーモを触って使ってくれた人が、『これ“ヴィッセル神戸”に提案しよう』って動いてくれたりね。お世話になった川島印刷さんと吉村くんとで新しくビジネスに繋がったり。ここに関わってくれた人のご縁で仕事をつくるような、いいきっかけも生まれてます。」
満永「ですよね。実際に、これまでクライアントやスポンサーがしっかり付いてきているので。そこは、僕ら自信持っていいんじゃないかなって思ってます。」
ー 最後に、このプロジェクトに限らず、今後どんなことに取り組みたいですか?

吉村「目下はエールセルフィーを広めたい、が1番です。ただ、HYTEKさんと関わって“エンタメをつくる”を初めて意識したこともあって…身近な生活のエンタメ化。身の回りのものが、生活が便利に、楽しくなることに取り組んでみたいかな。」

猪塚「私は普段エンジニアとして実装することも、テクニカルディレクターとしてディレクションもやるんですが…誰も体験したことがないものをつくりたいと思ってます。私は結構UX(ユーザーエクスペリエンス/ユーザー体験)にこだわりたいタイプだから、新しい体験をつくるのは難しいけど楽しい。」
星野「僕は便利よりも、楽しい体験が好き。便利は便利でもちろんいいんだけど、ひとつ面倒くさいことがあるけど、それでちょっとした体験でも楽しくなる、みたいなことが好きで。そういうものを作っていきたいです。このチームの仕事は、楽しい体験が社会課題につながっている。HYTEKさんとは、これからもそんなものづくりをしたい。」

満永「ぜひ。うん、離さないから(笑)。僕は…個人的には、AIとの共生よりも、これから『人の生き方がどう変わるか』が気になってて。今後エンタメをつくる人は、ものづくりに集中できる、いい社会になりそうな予感がしてます。
例えばブロックチェーンって…勝手に“徳を積む”ってことになるんじゃないかとか思ってて。そういう仮説研究を、プライベートワークで2年位やってます。こういった試行錯誤ができる場所やチームが、もっと出てきたらいいなって。
いろんなチームの方と、国際的イベントやフェスティバルのタイミングに何かできないかなと考えています。」

道堂「これまで通り、新しい技術をつかったモノを発信していきたいです。ただ、テクノロジーはアップデートされていくけど、最先端って鮮度がいずれ落ちると思っていて。だから、ずっとやり続けたいし、発信し続けたいです。
一方で、このチームで発信するものは、技術的にめちゃくちゃ最先端ではないけど、その時代や社会背景を捉えたコンセプトを組み合わせることで、別の視点で新しいものになっていると思います。今後も、その両方の視点からものづくりを考えていきたいなと思います。」
満永「直近だと、ほにゃらら“セルフィー展”くらいの展示はできそうな気がしてて。
“〜セルフィー”って、時代を映しているって思うから、それがまた一個上のレイヤーの活動になれたらなって。広告で経験したことをもっと、別領域につなげてチームの仕事を広げたいです。いつも、みんなが気持ちいいと思うようなものを設計したいですね。」