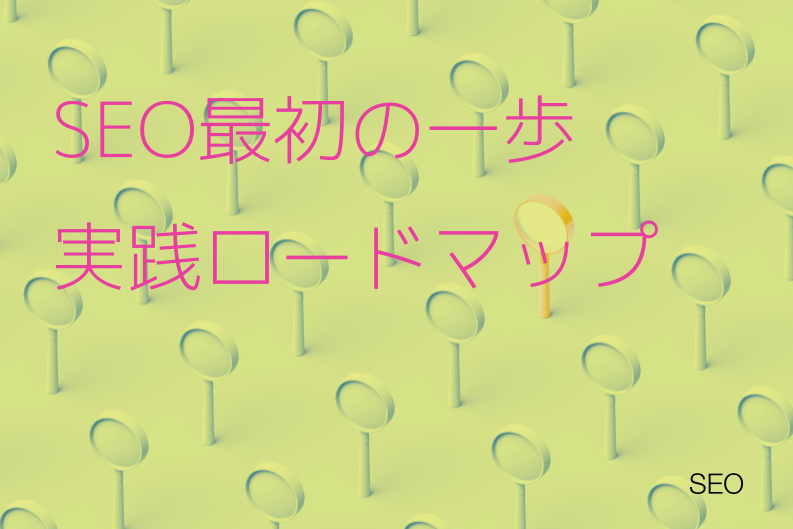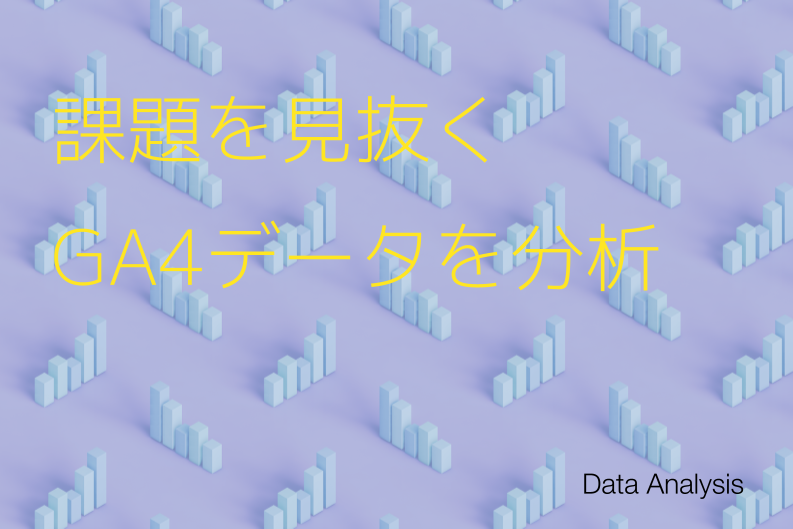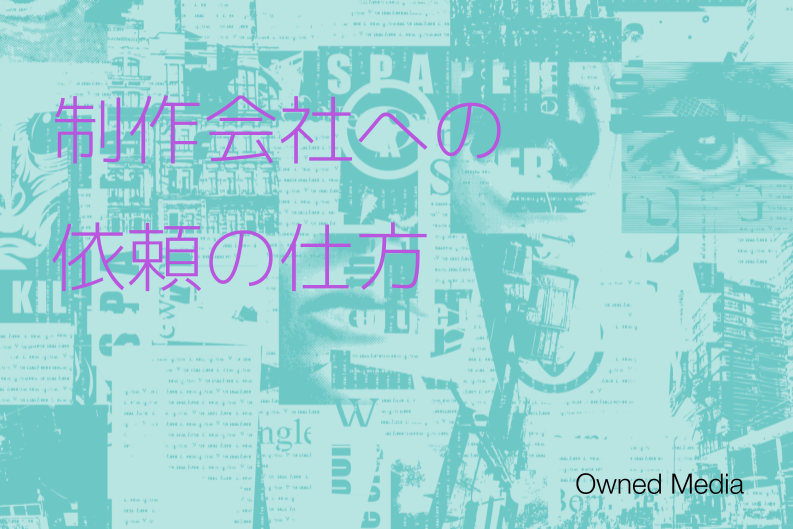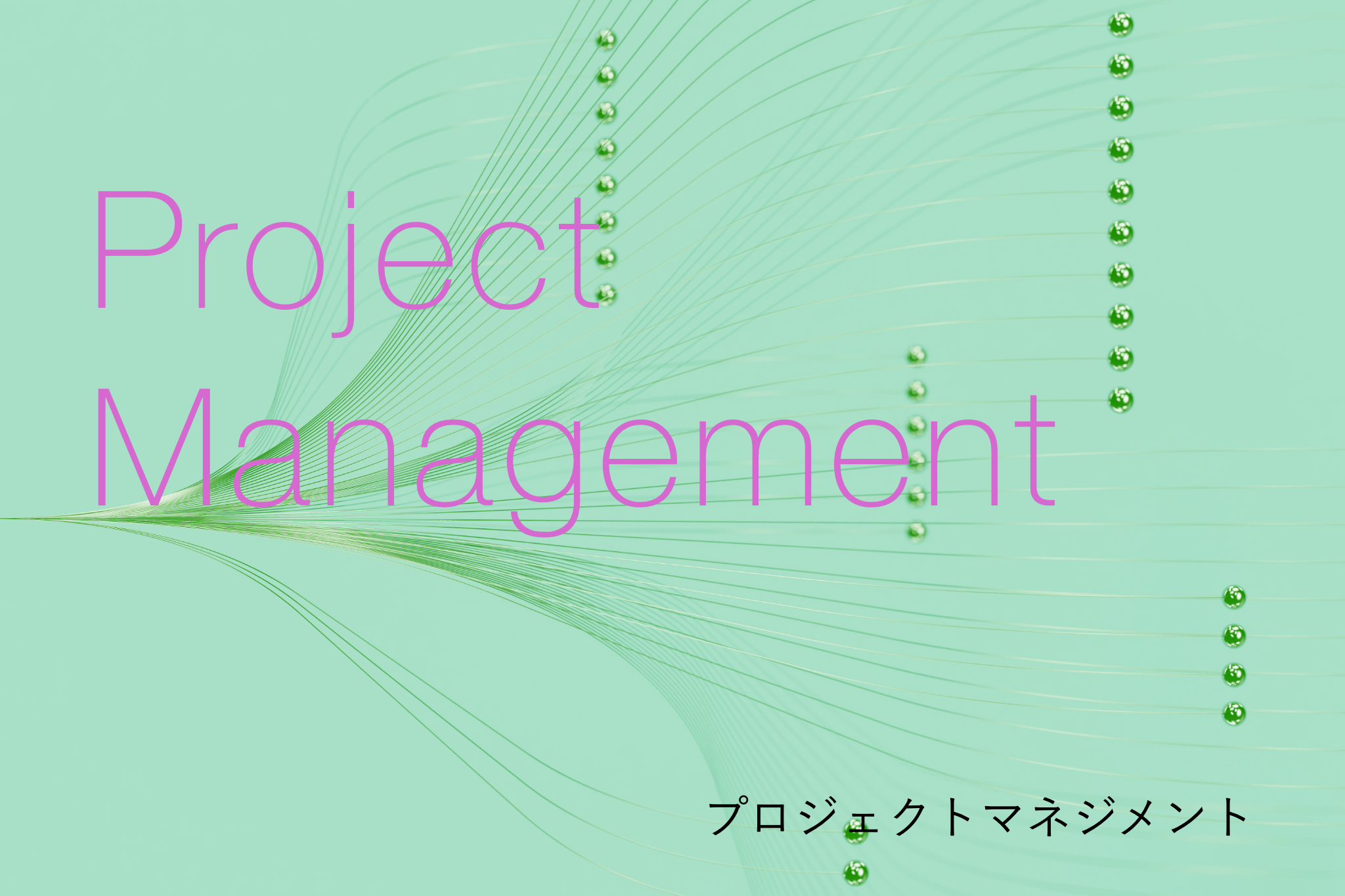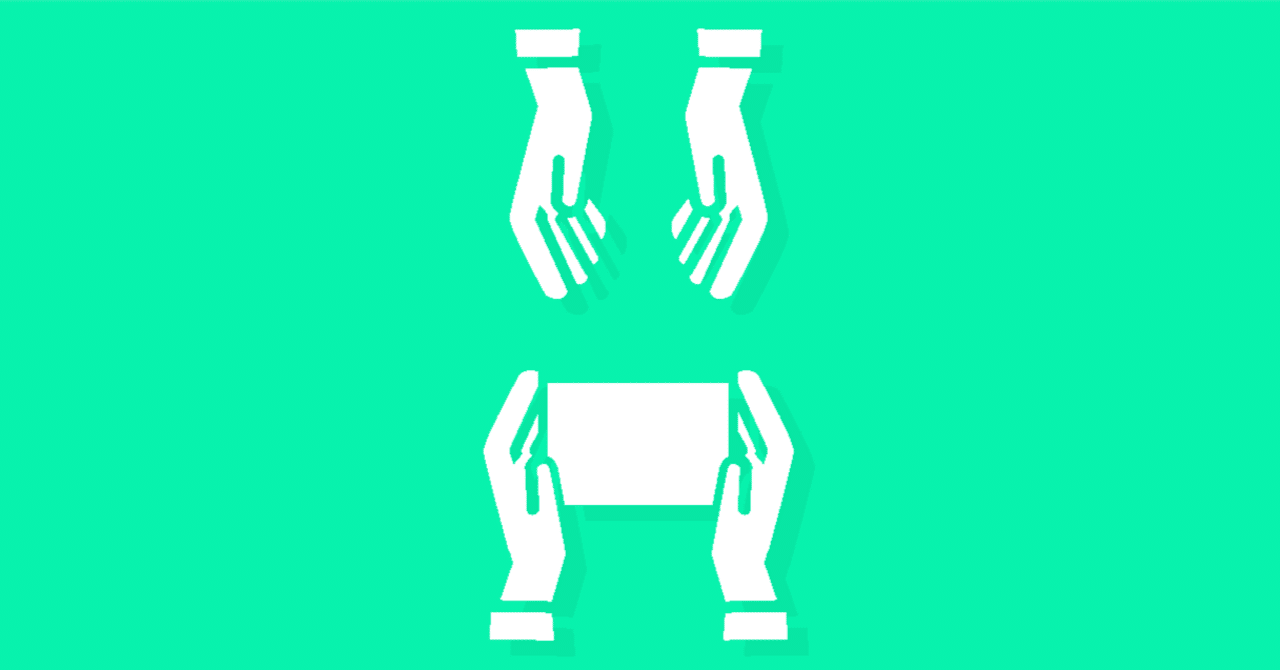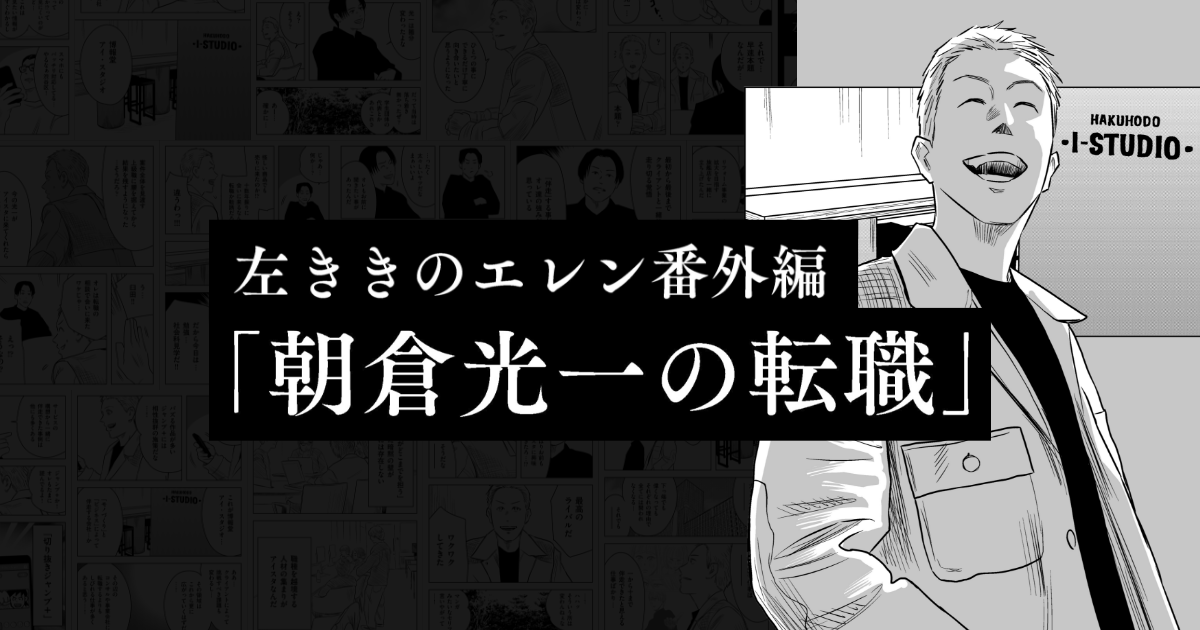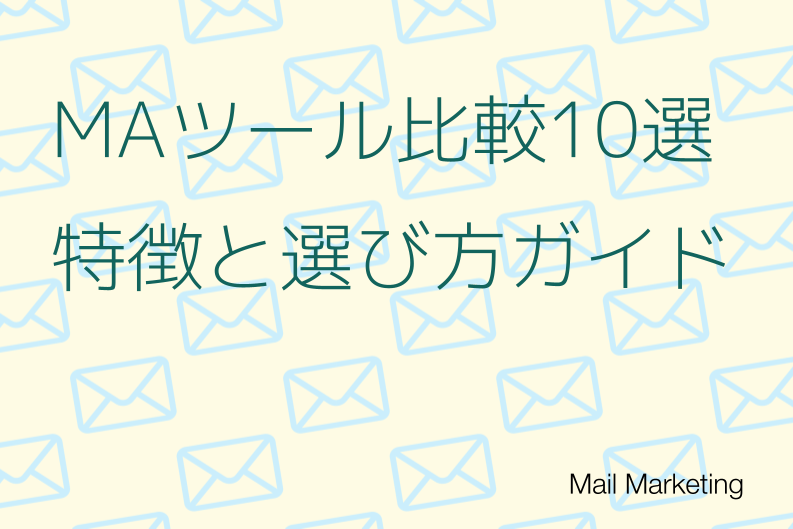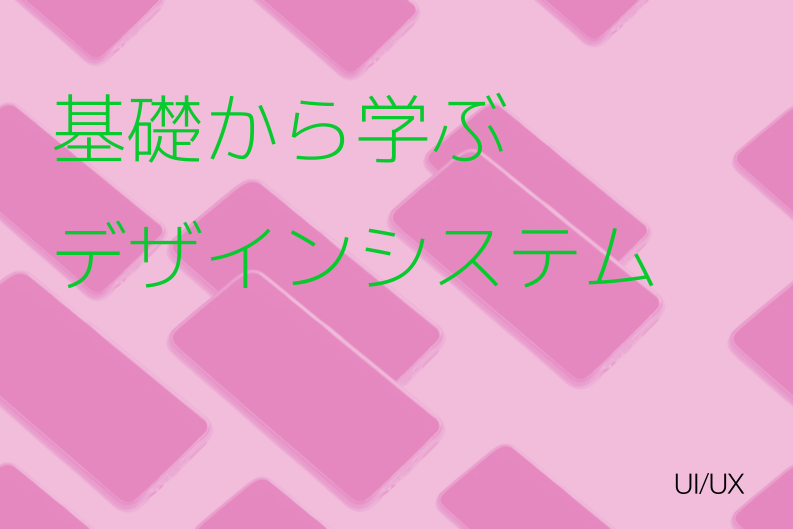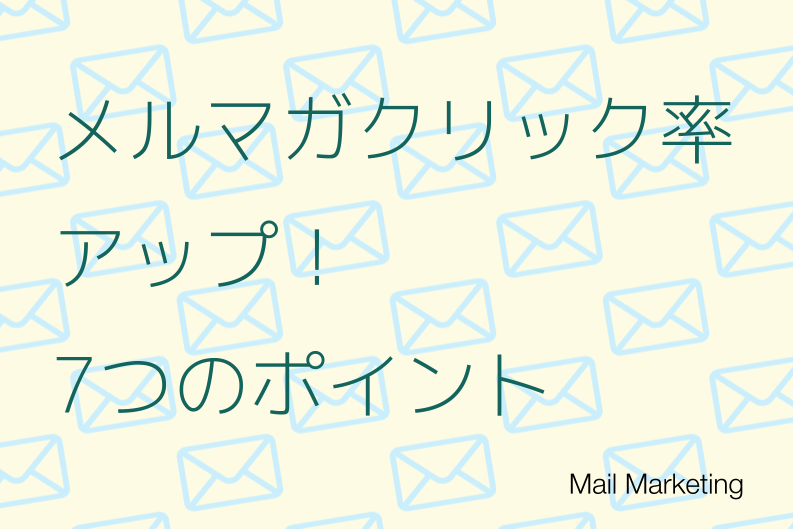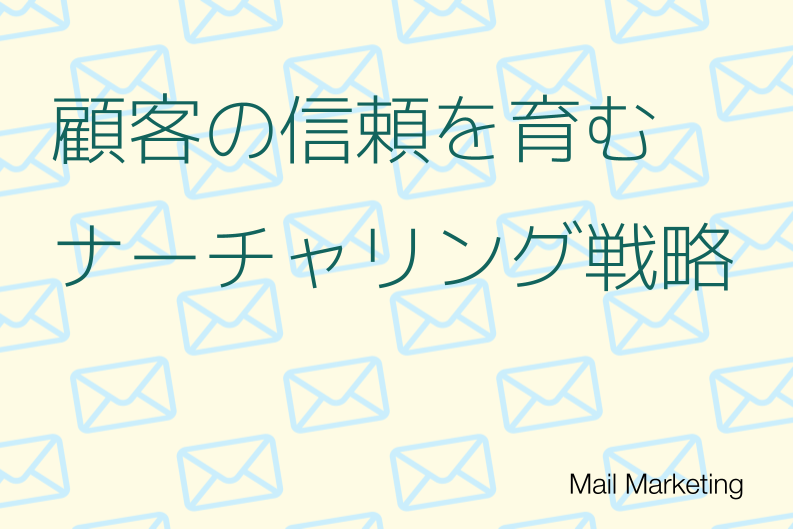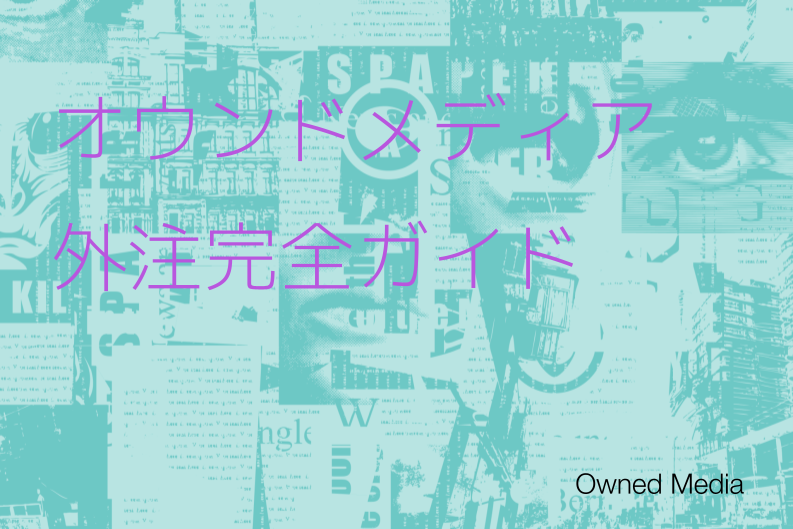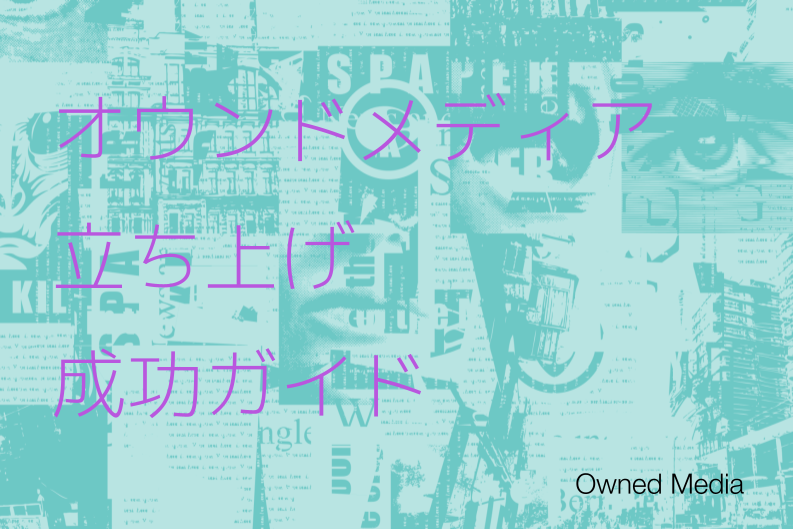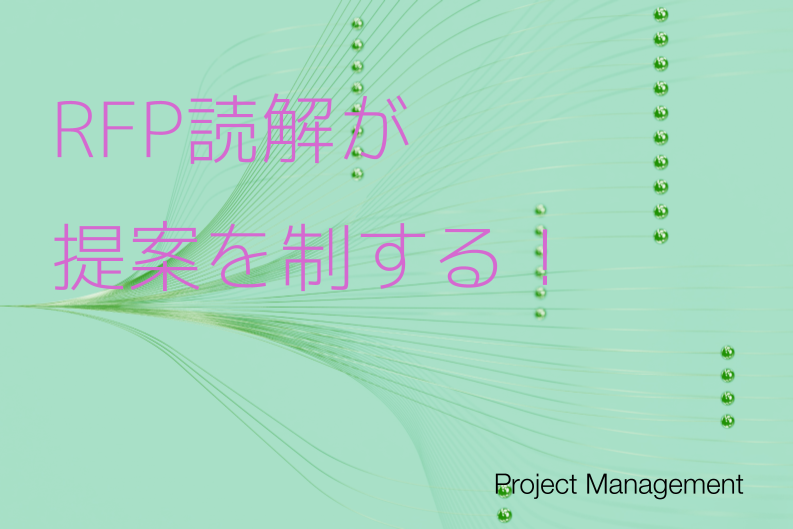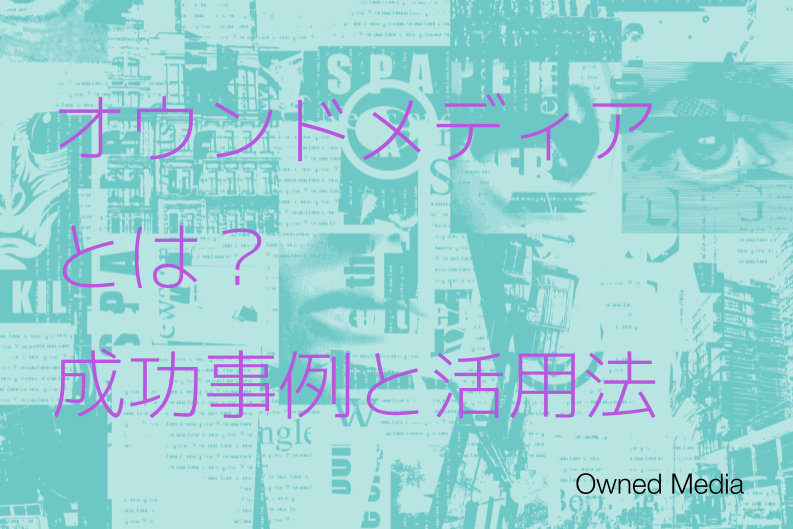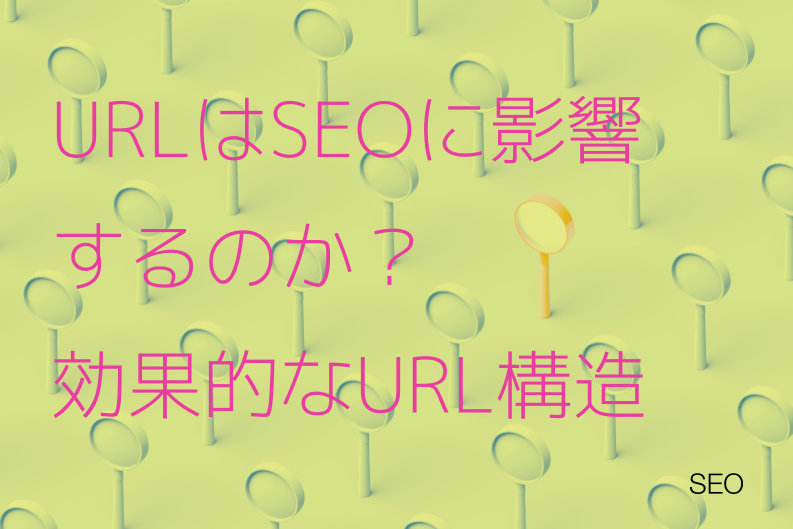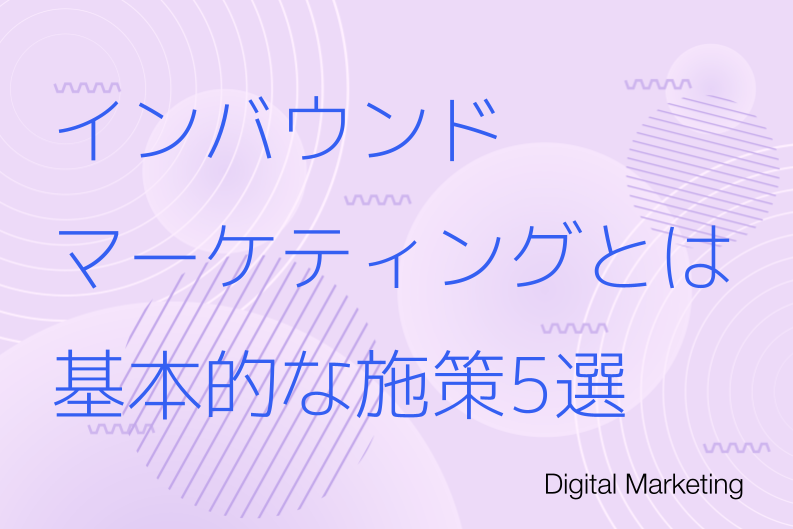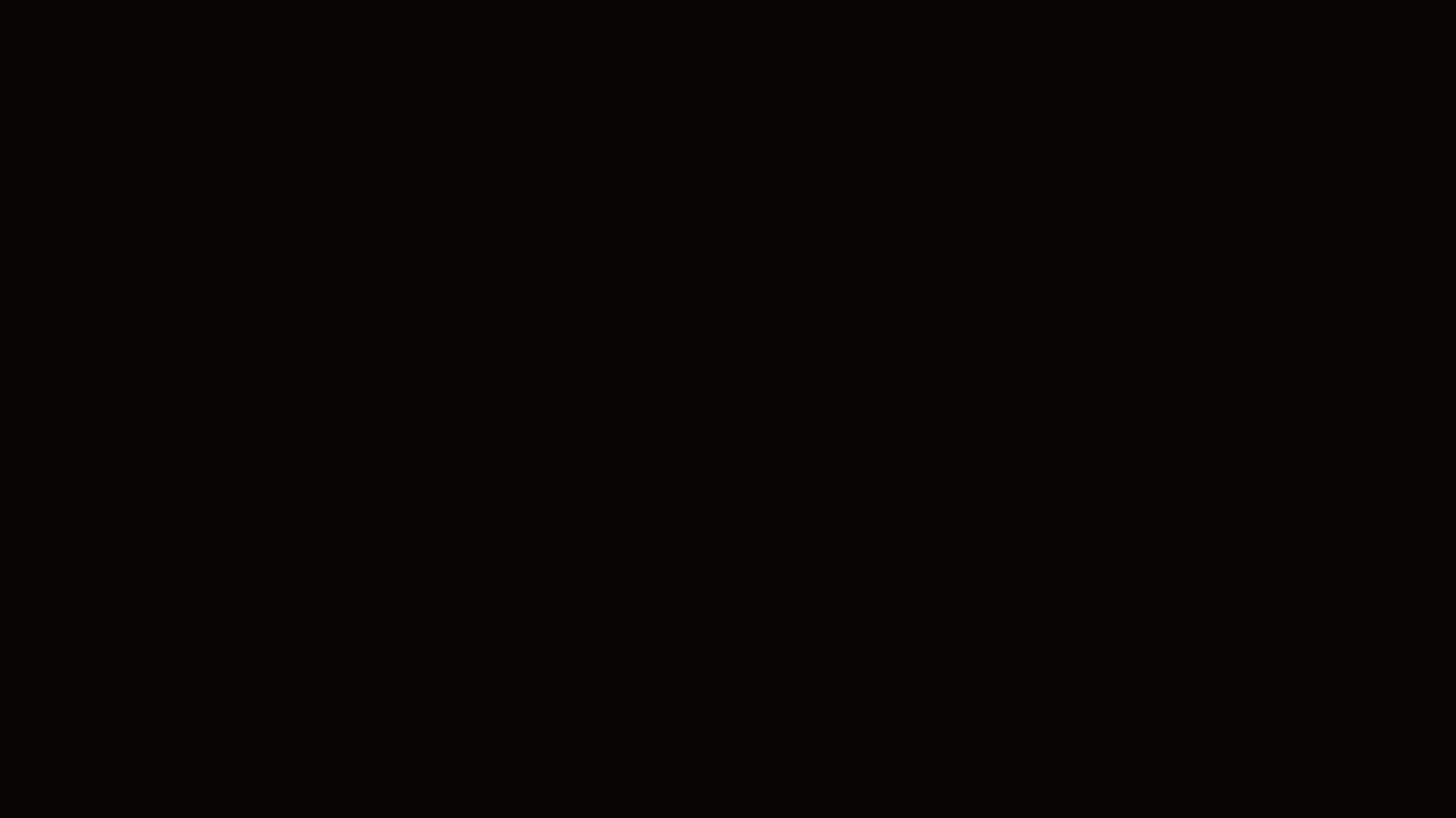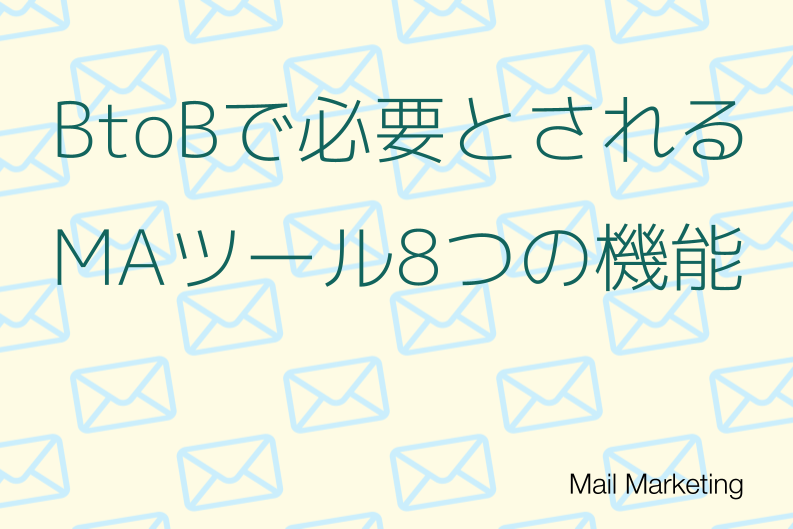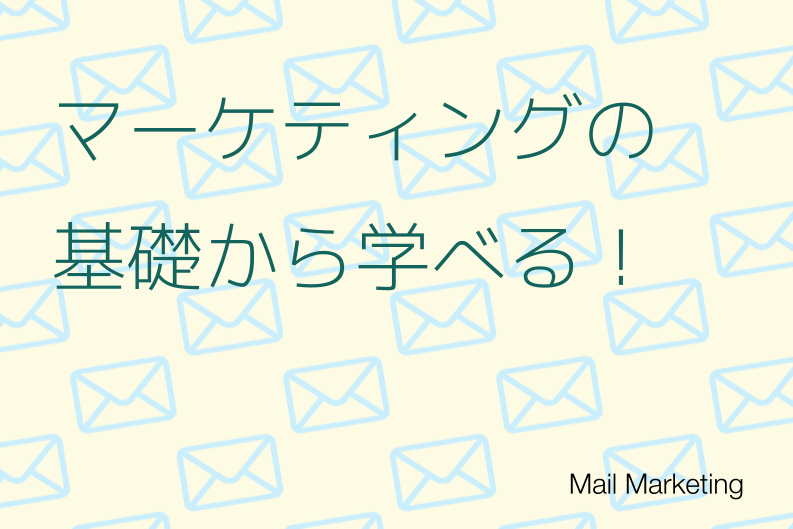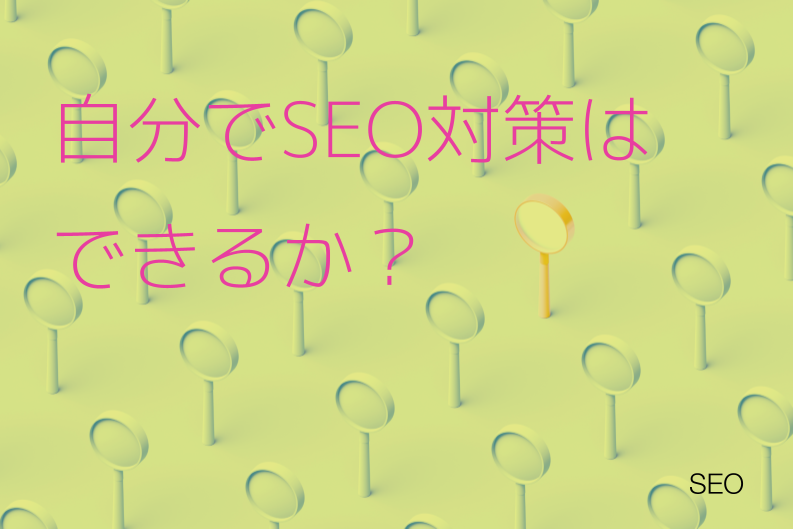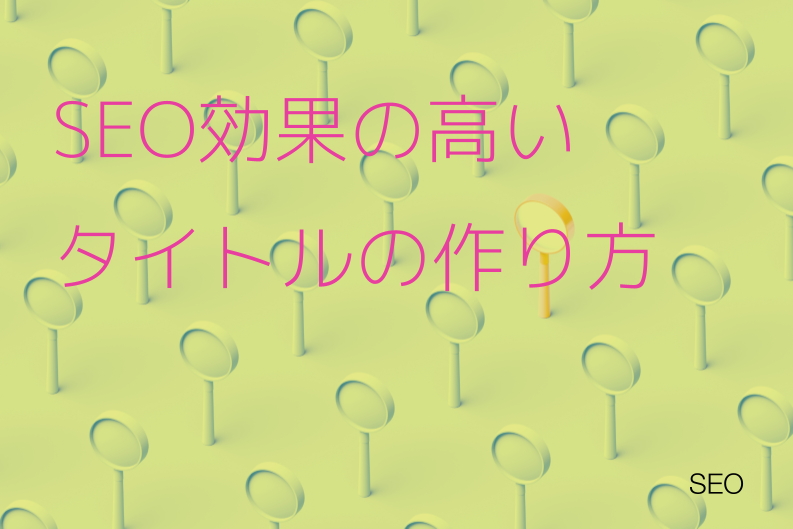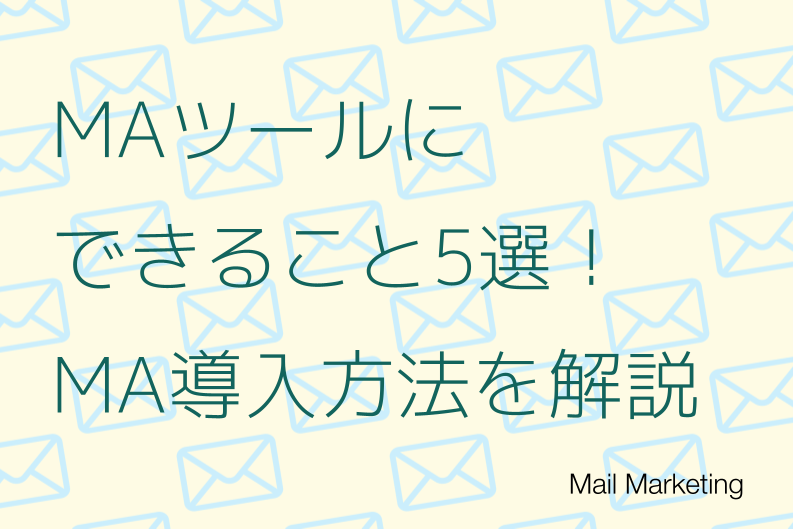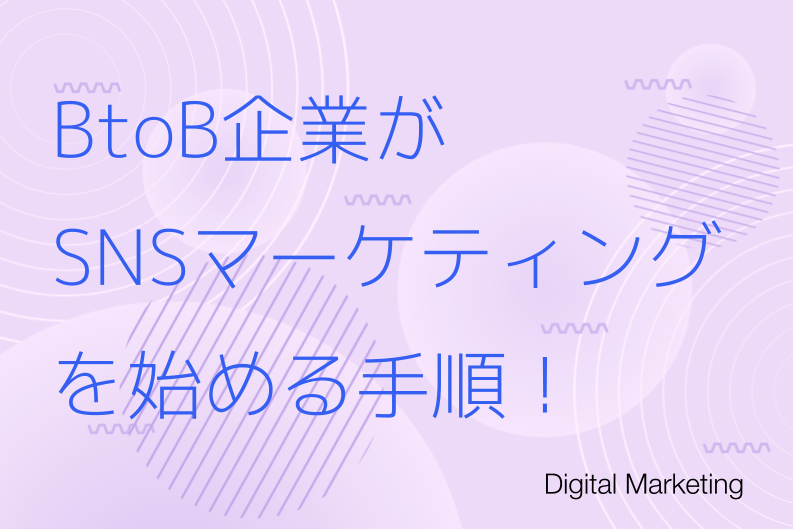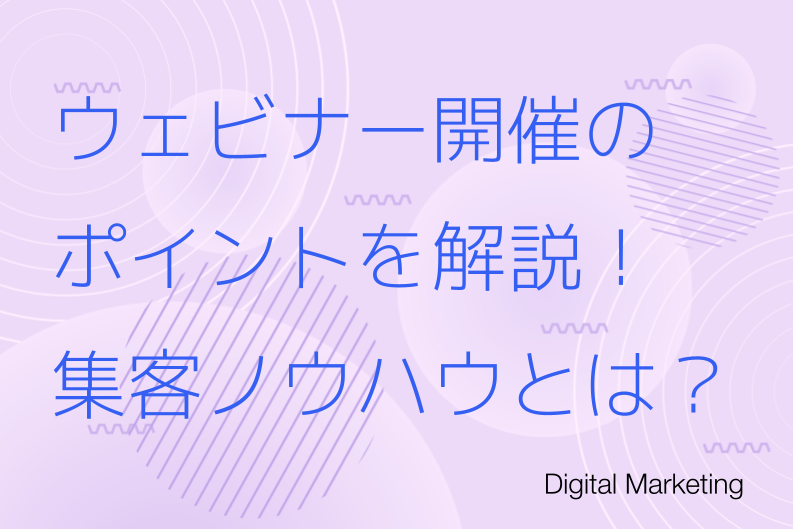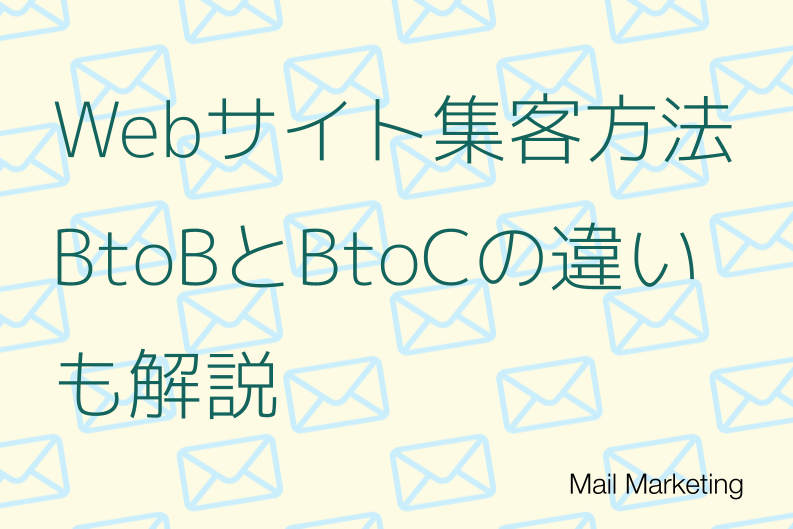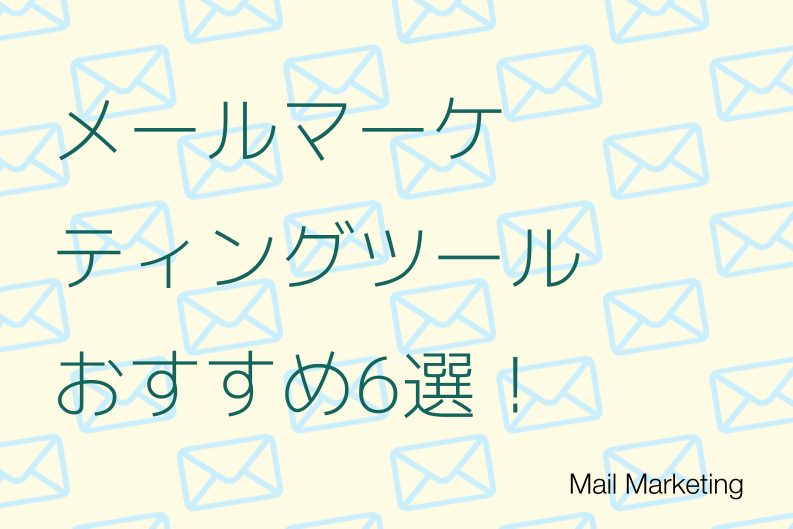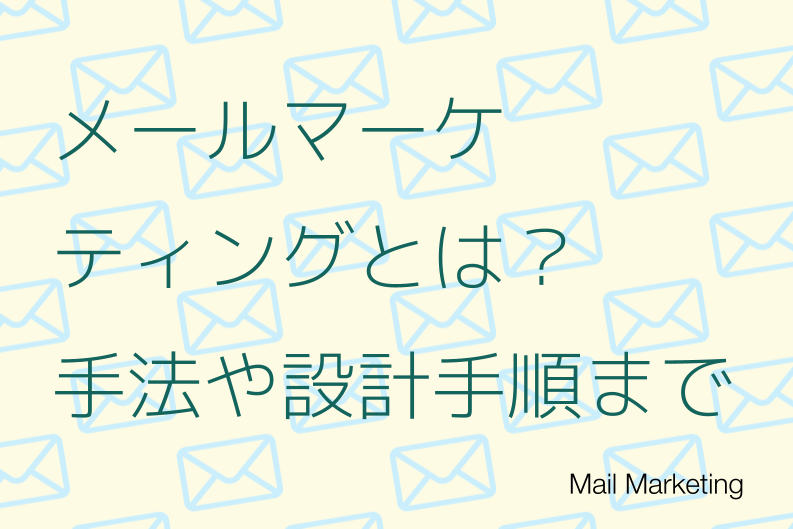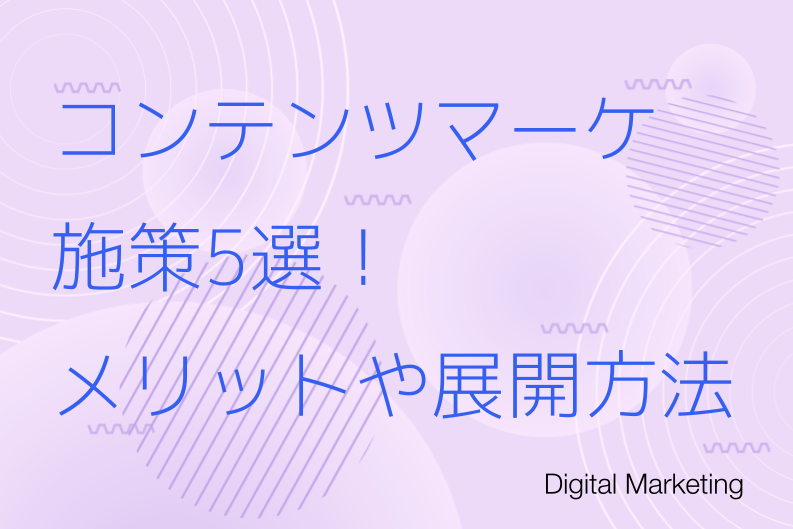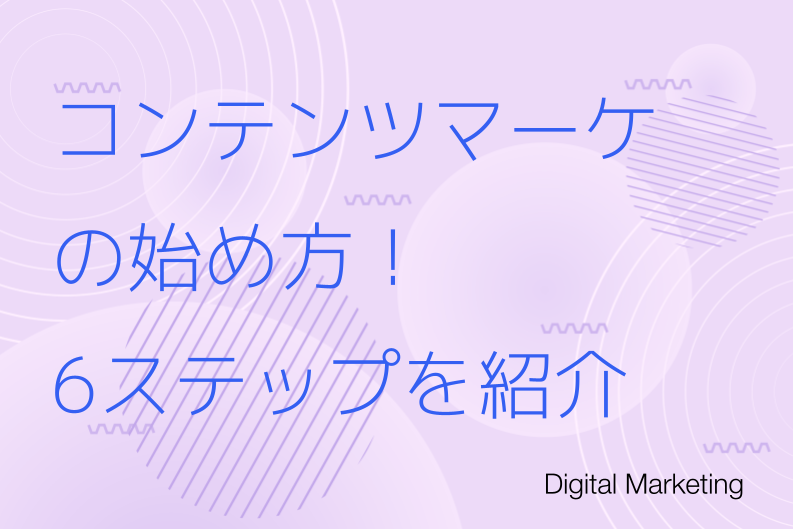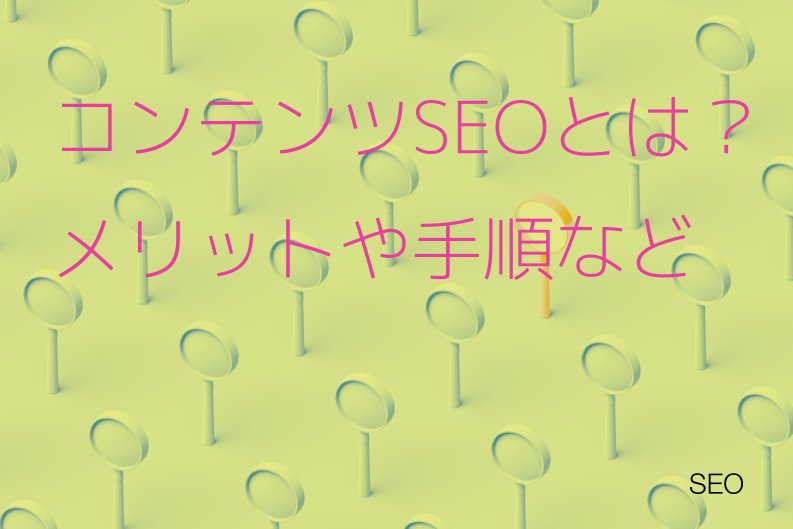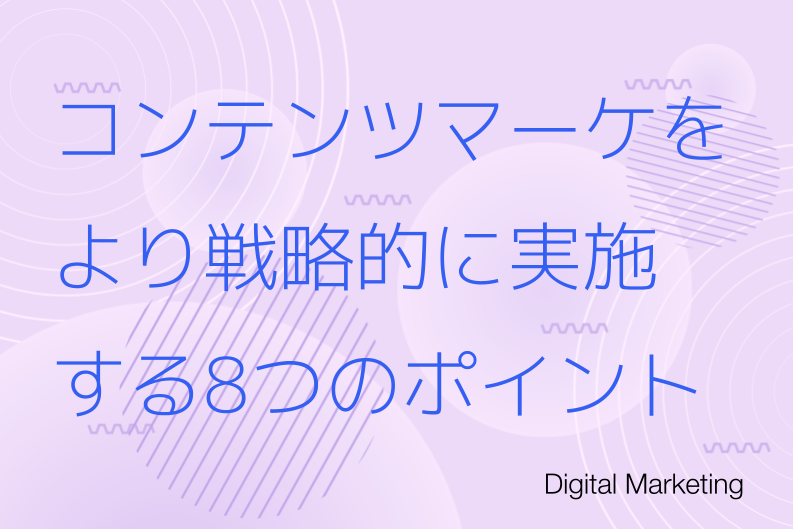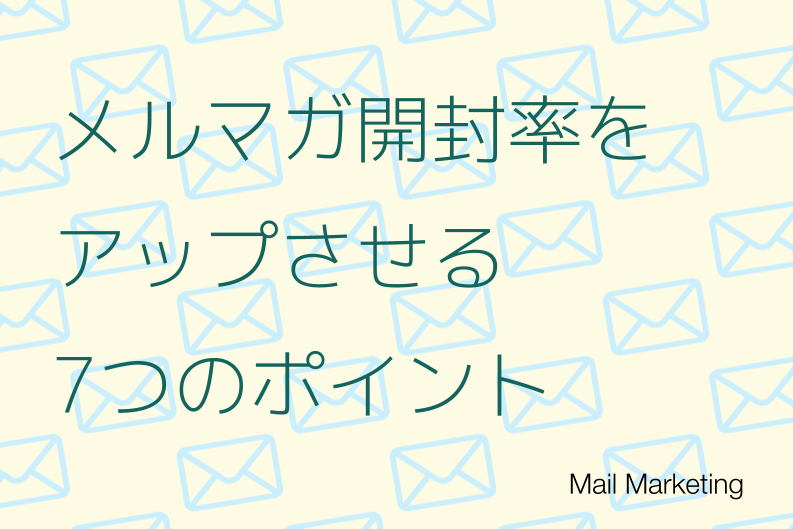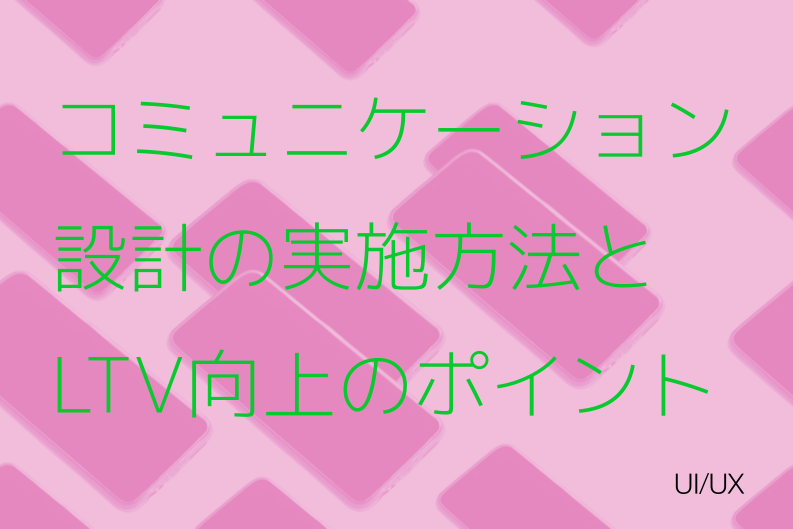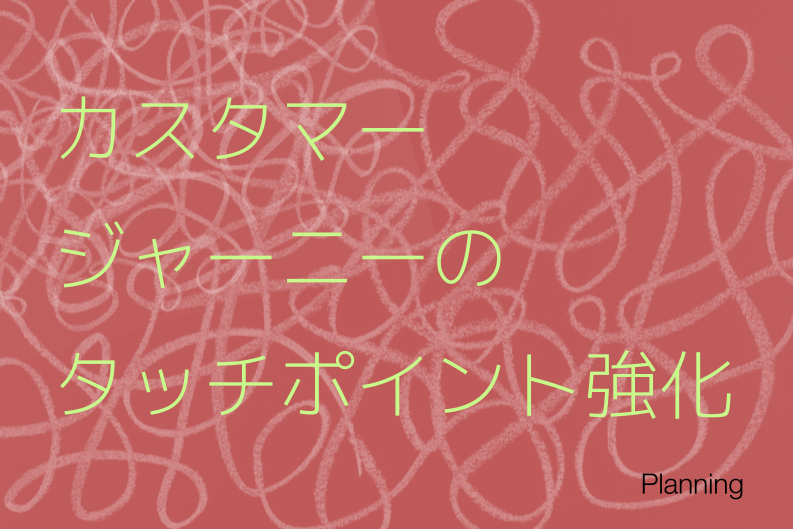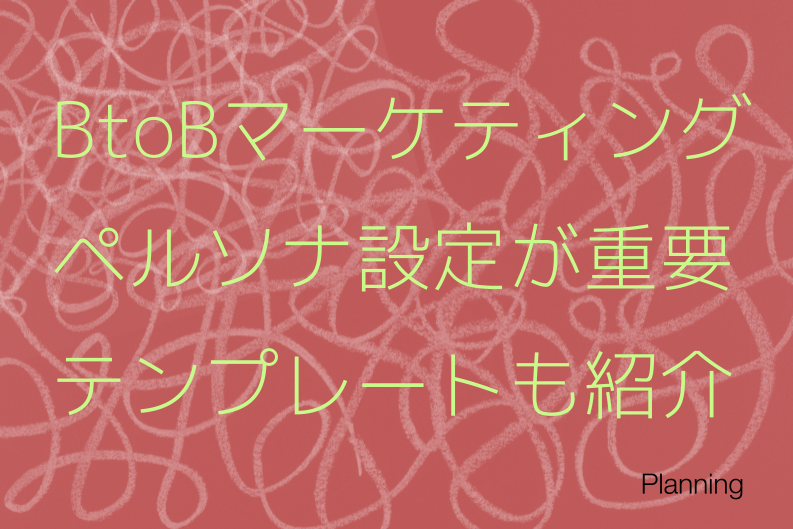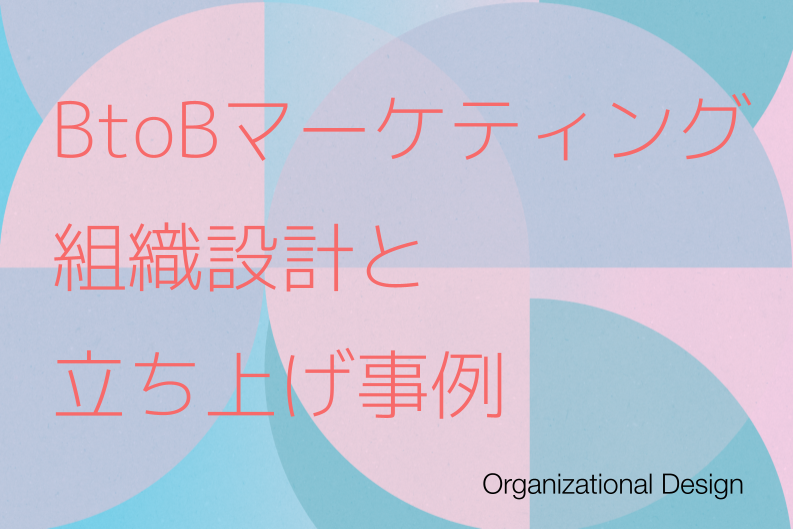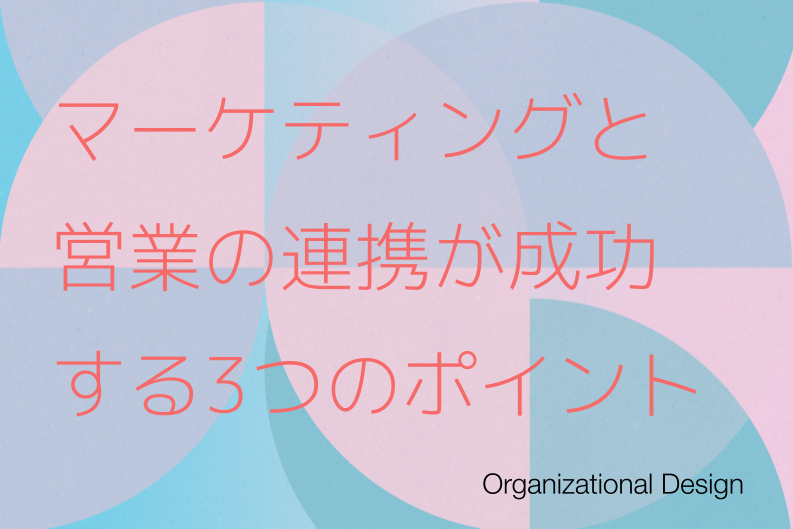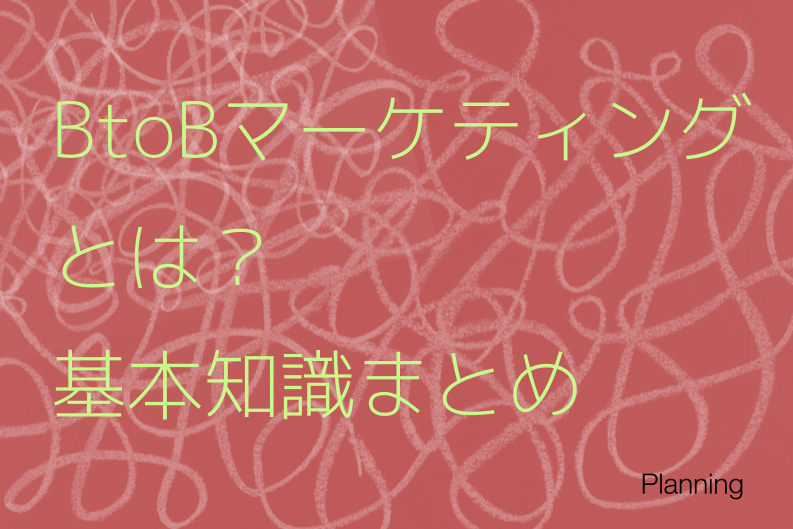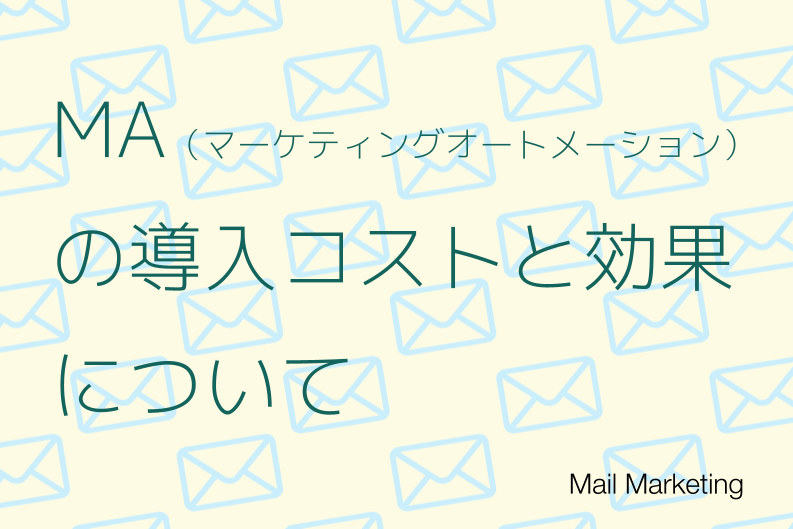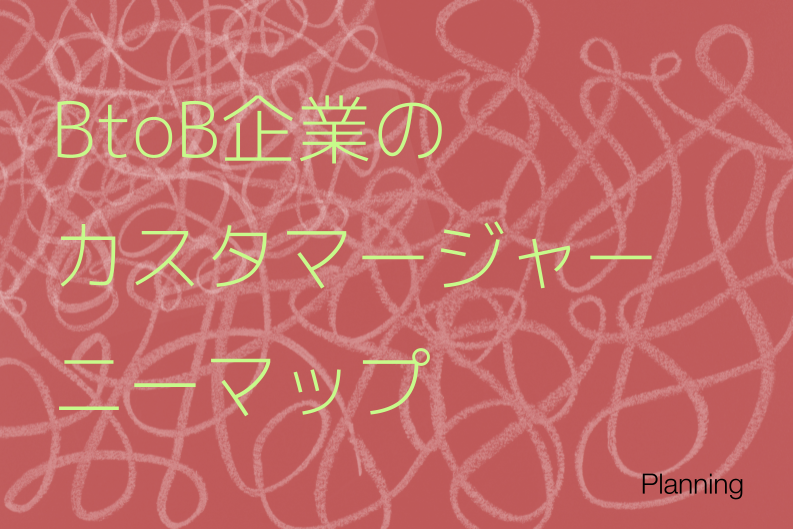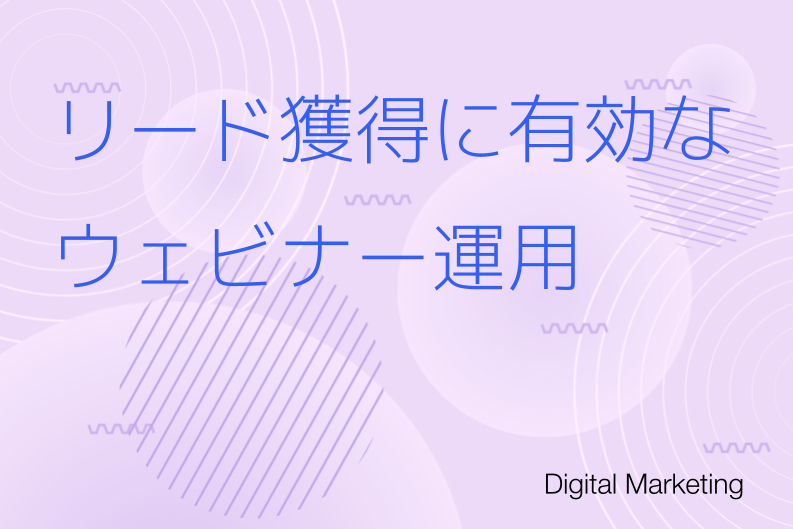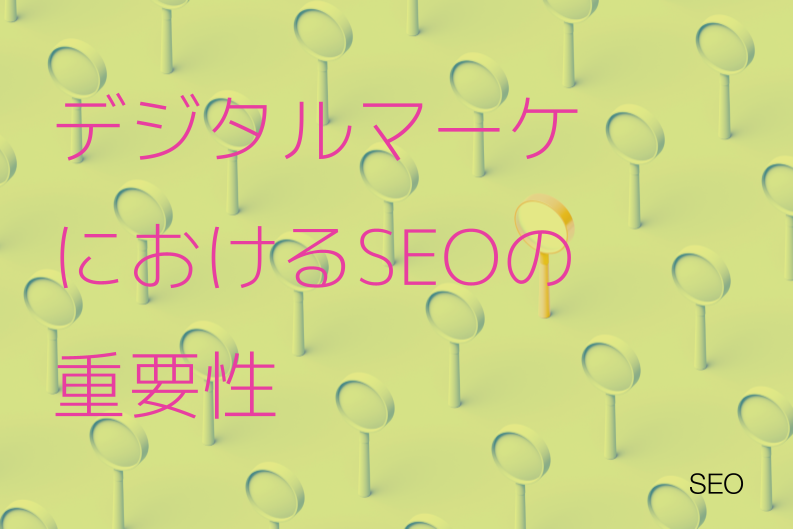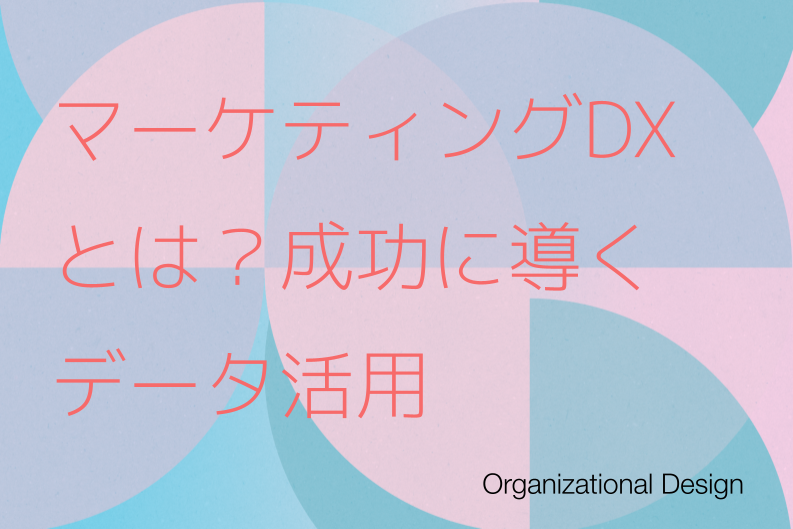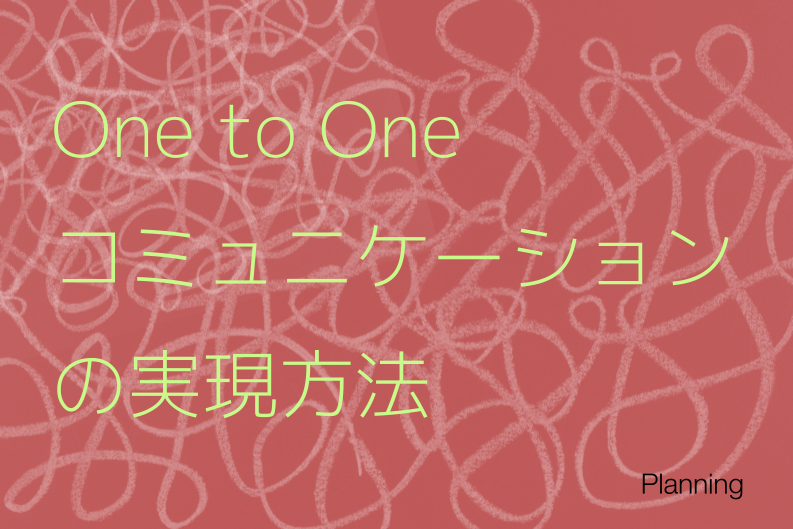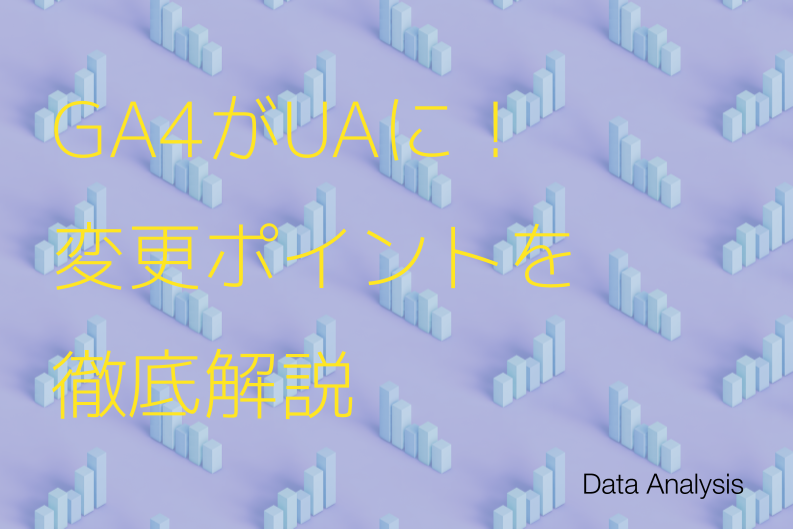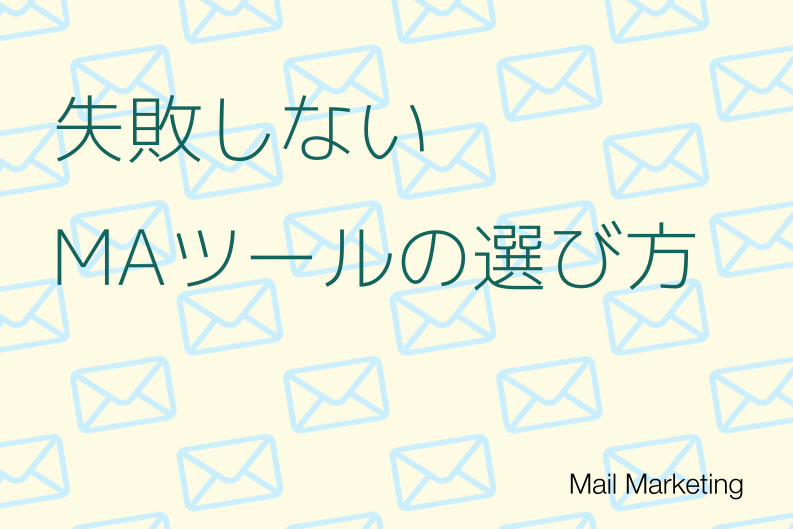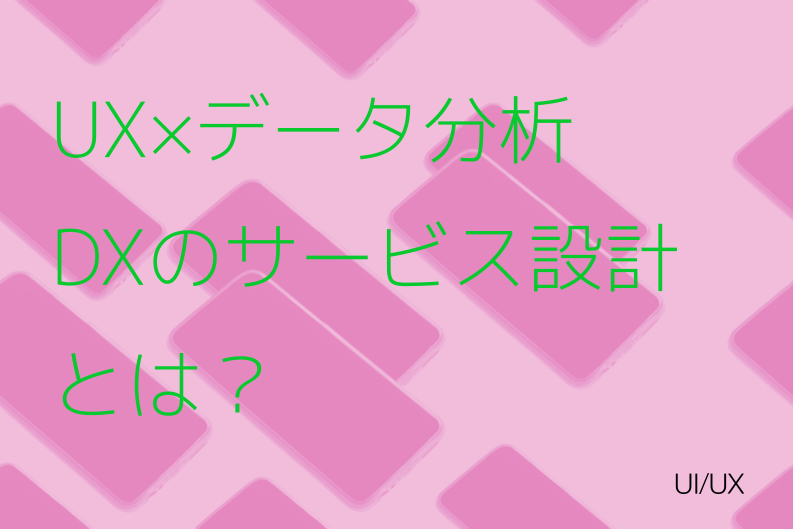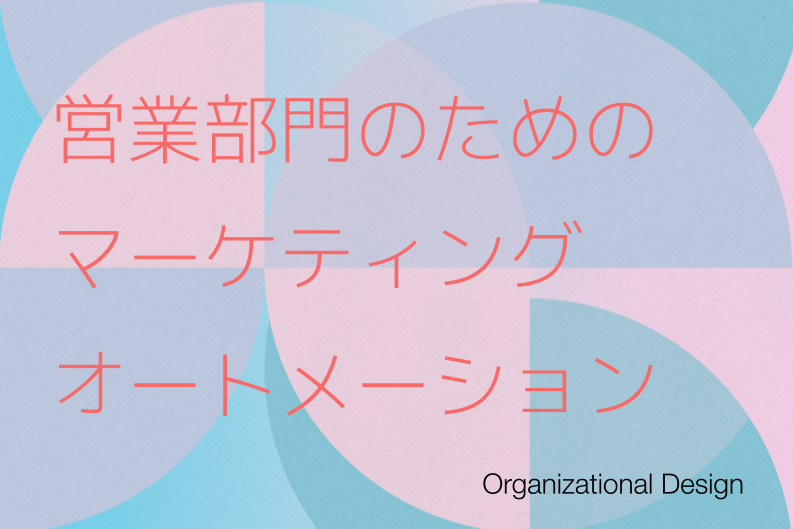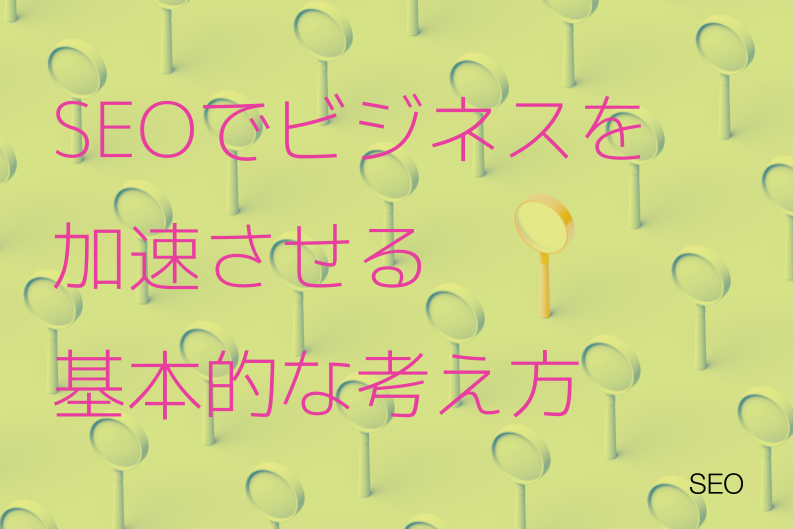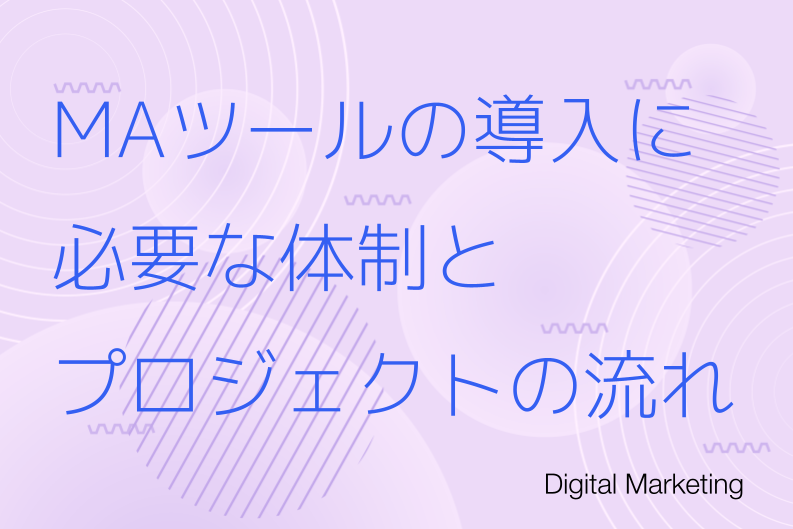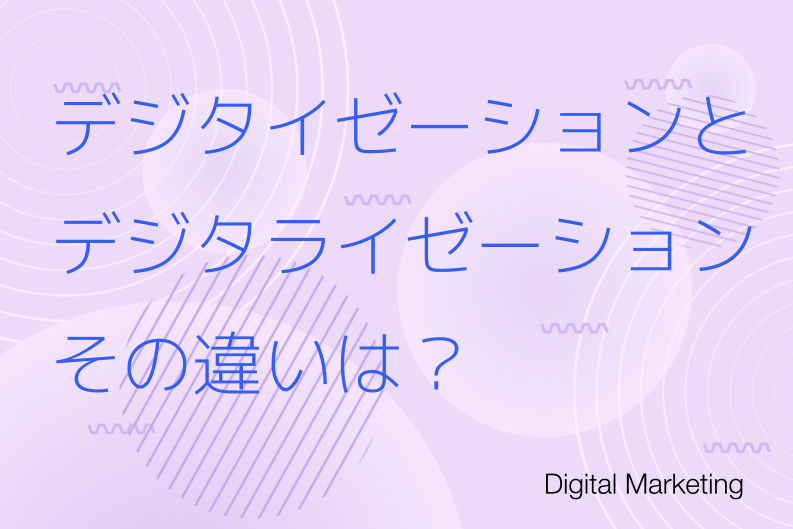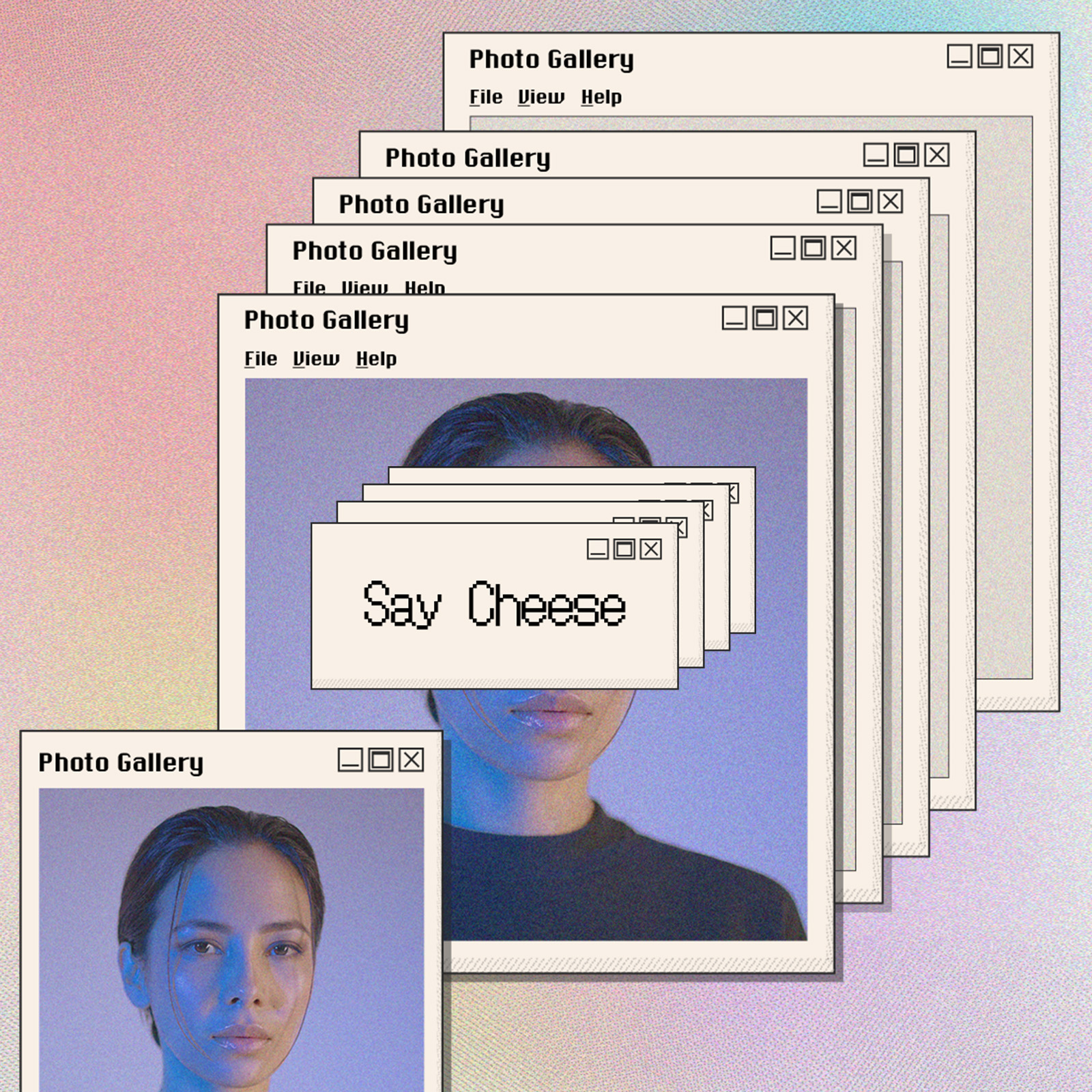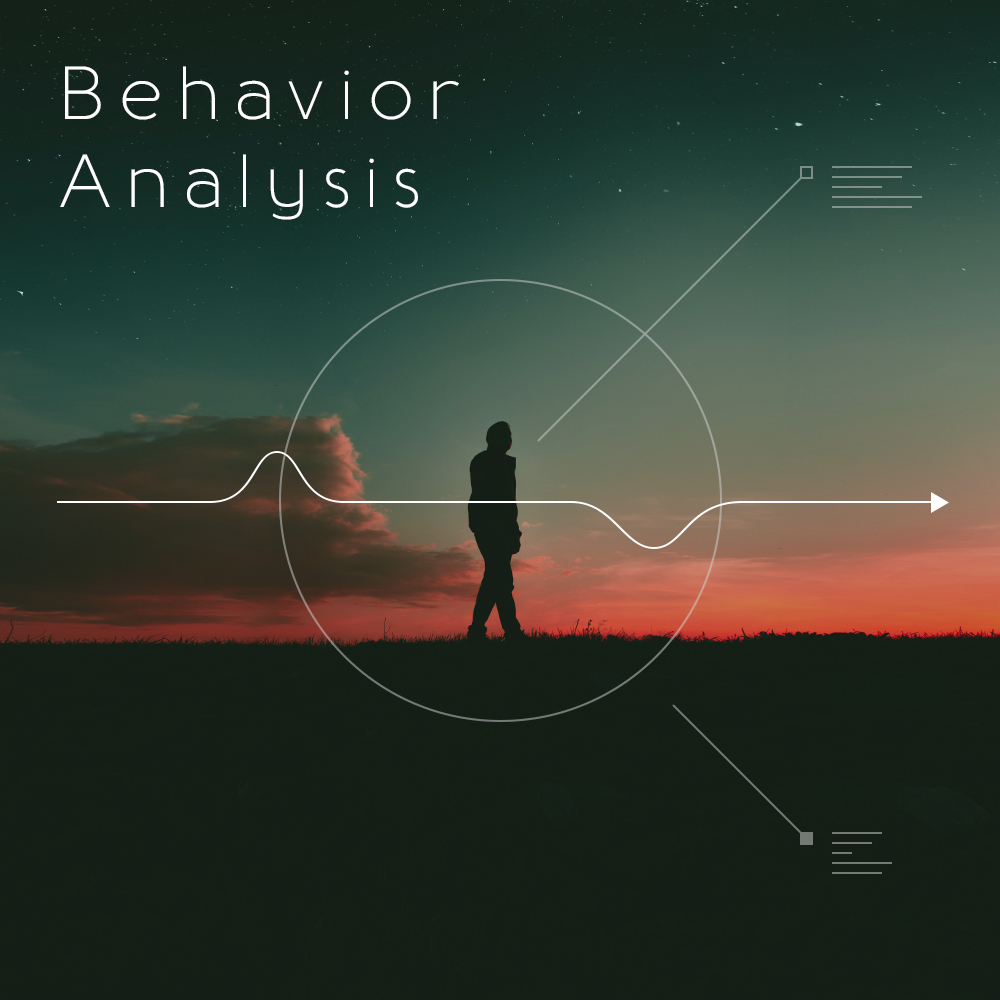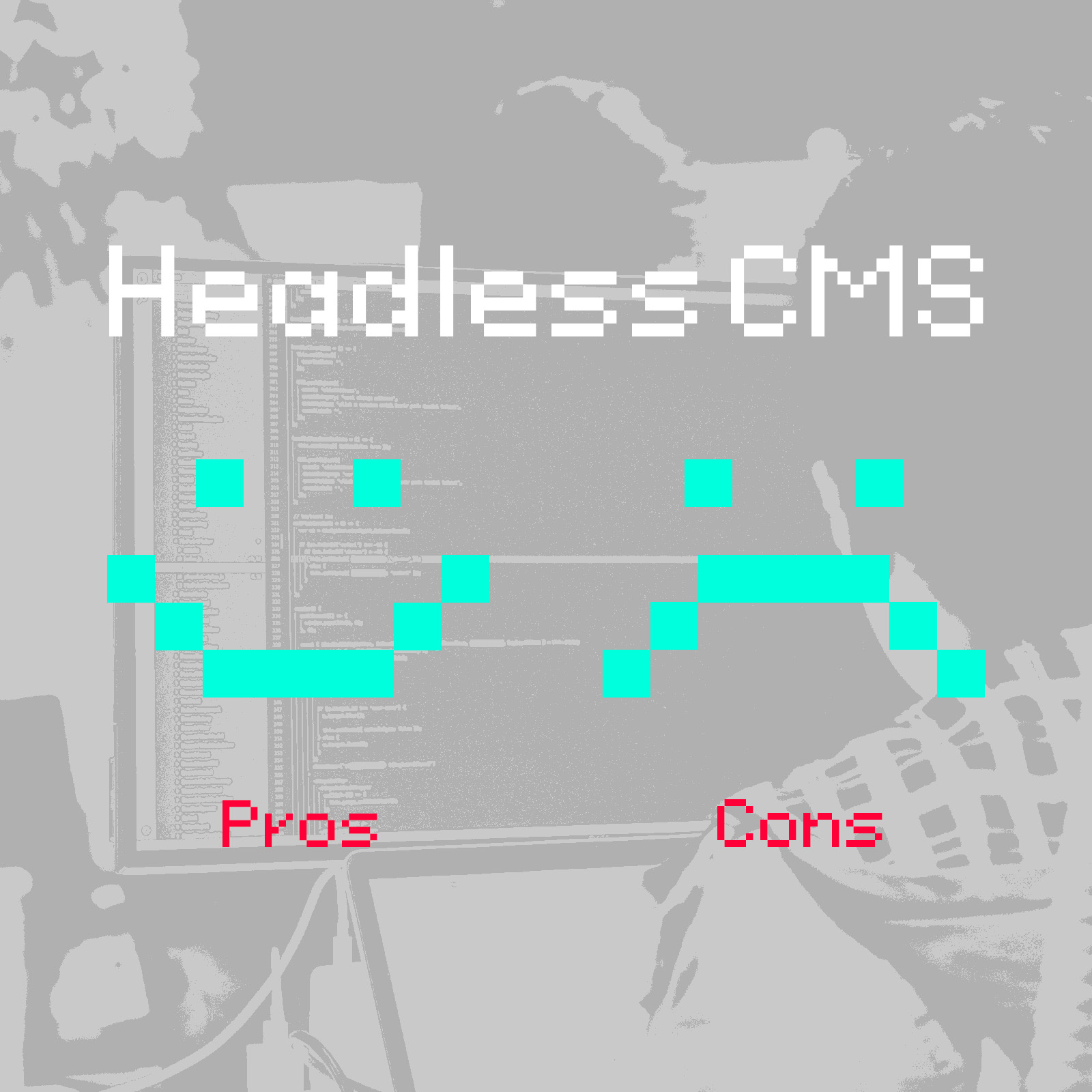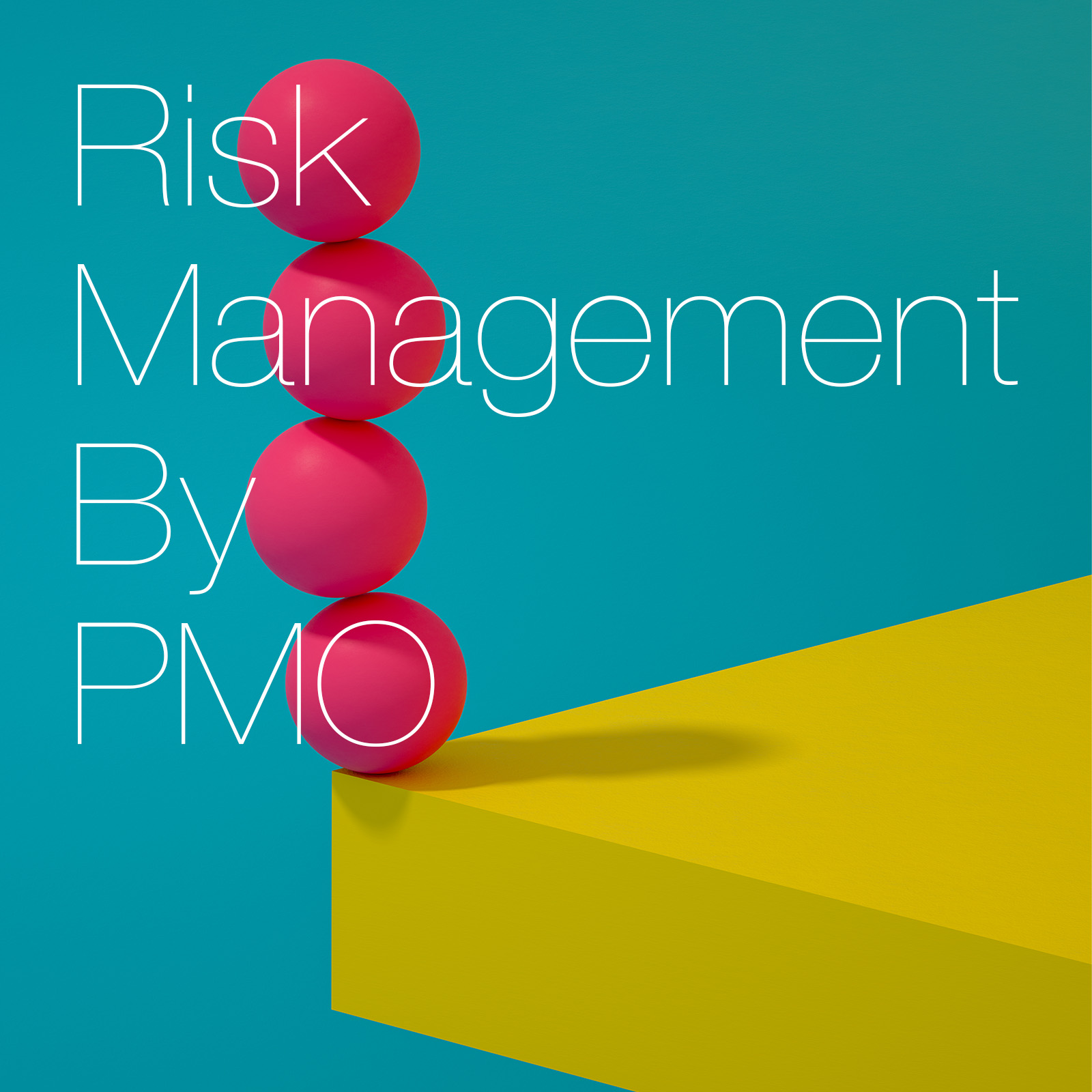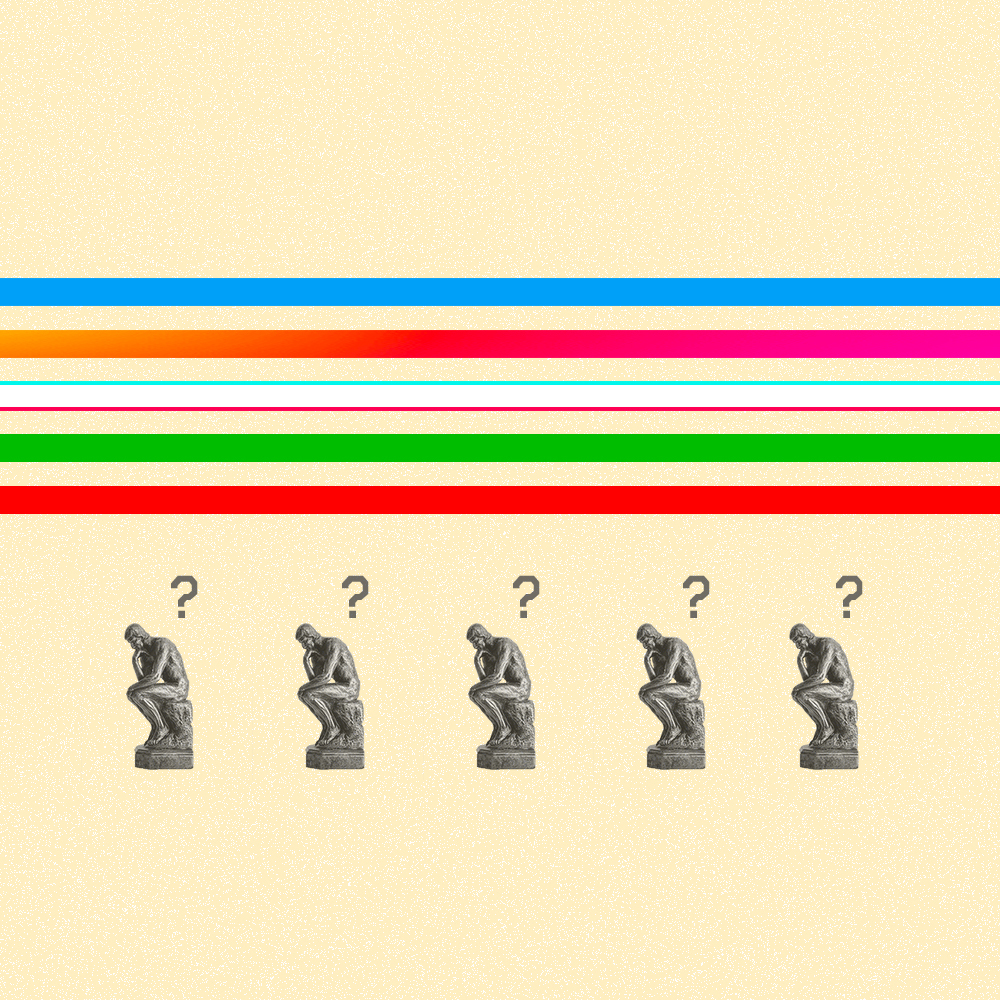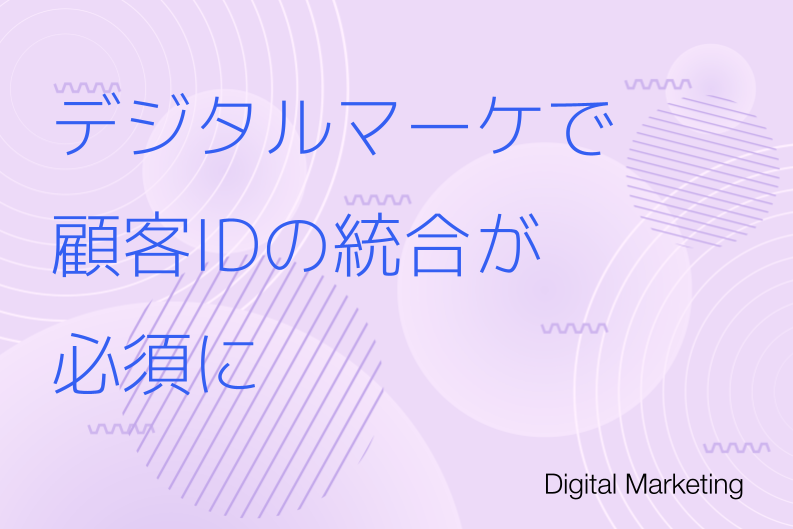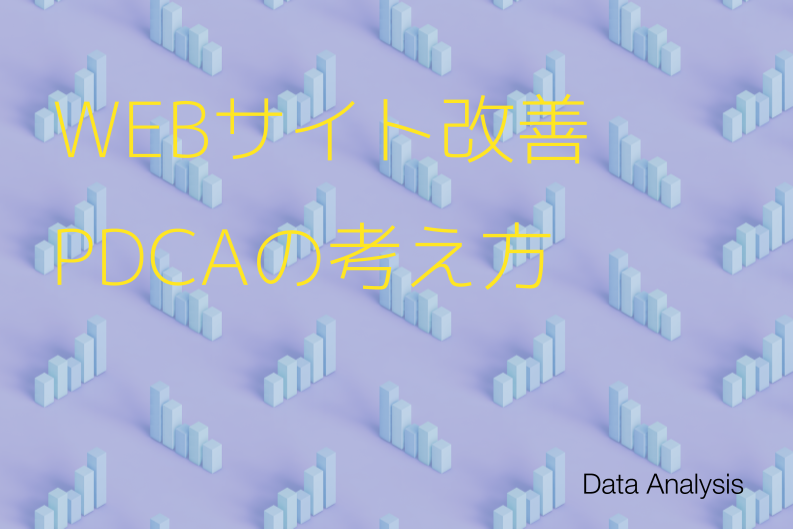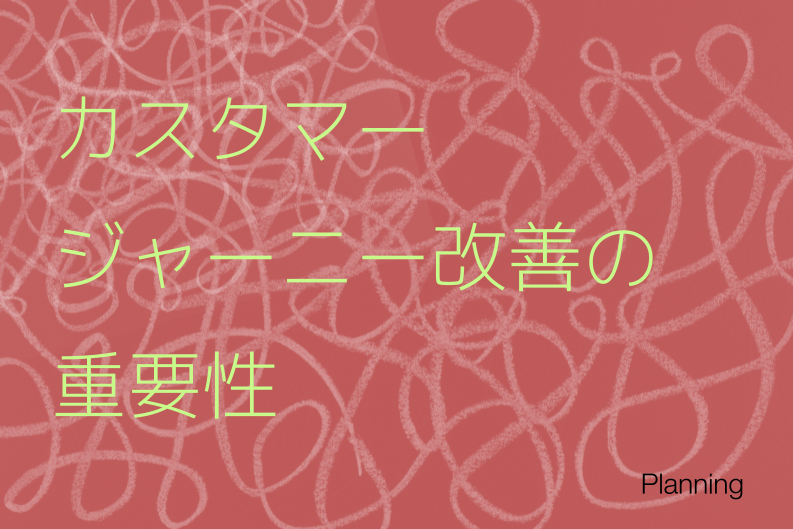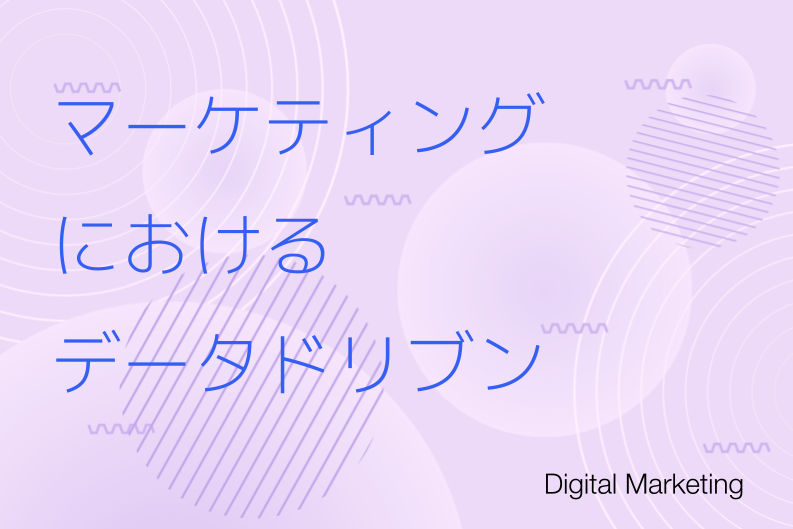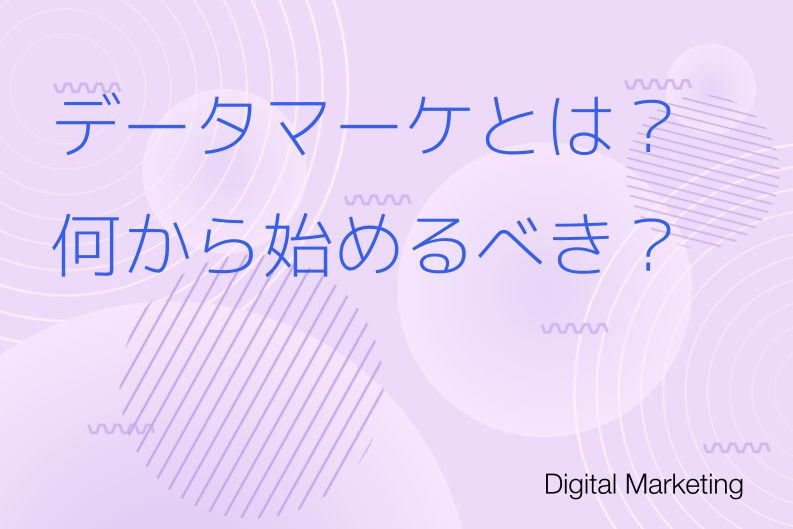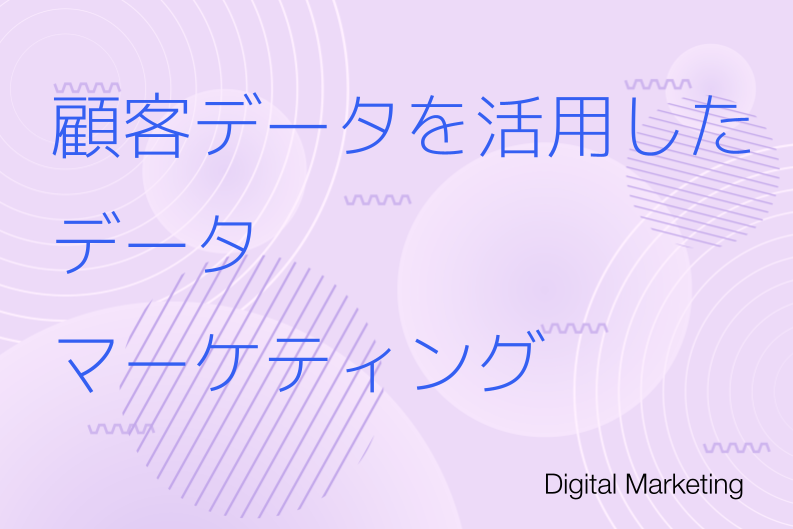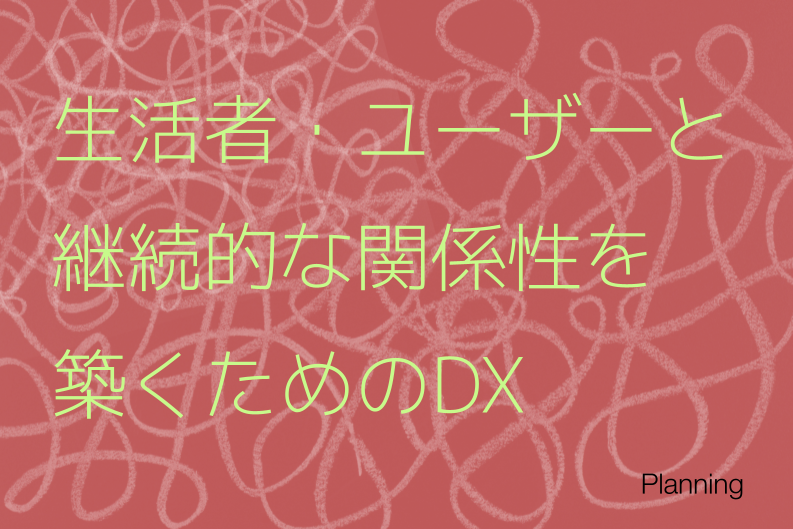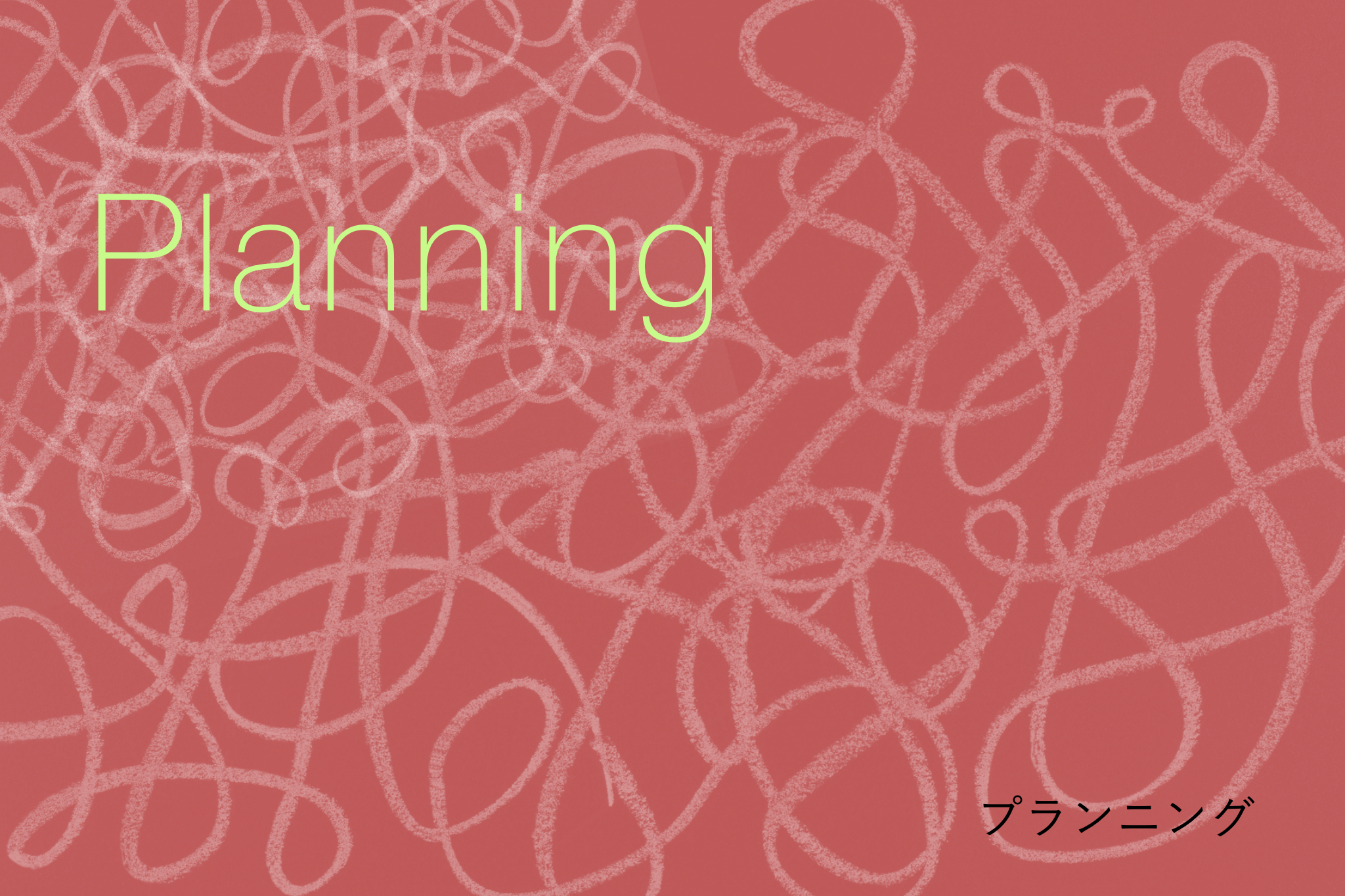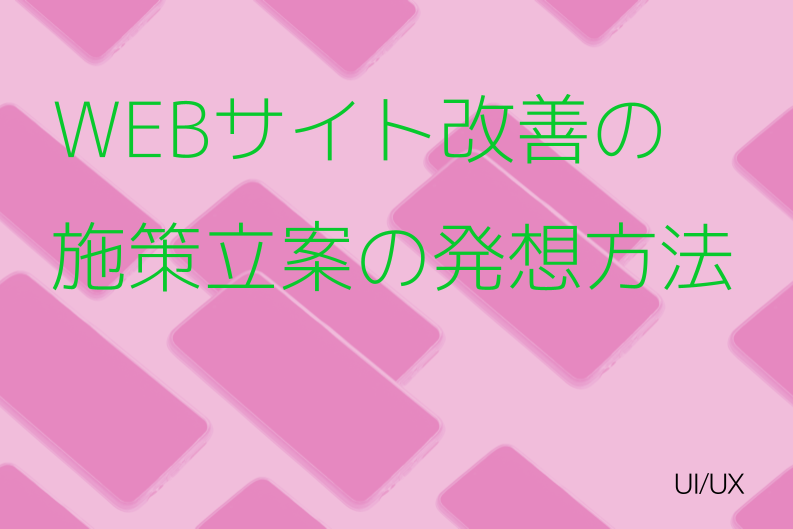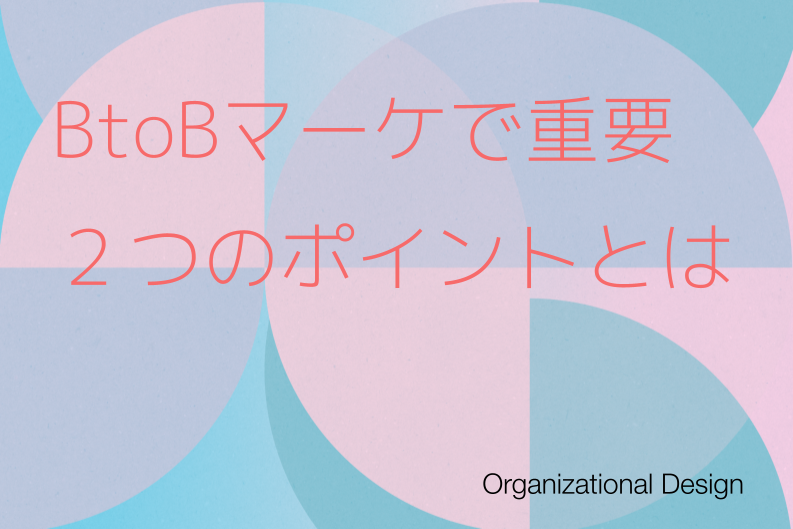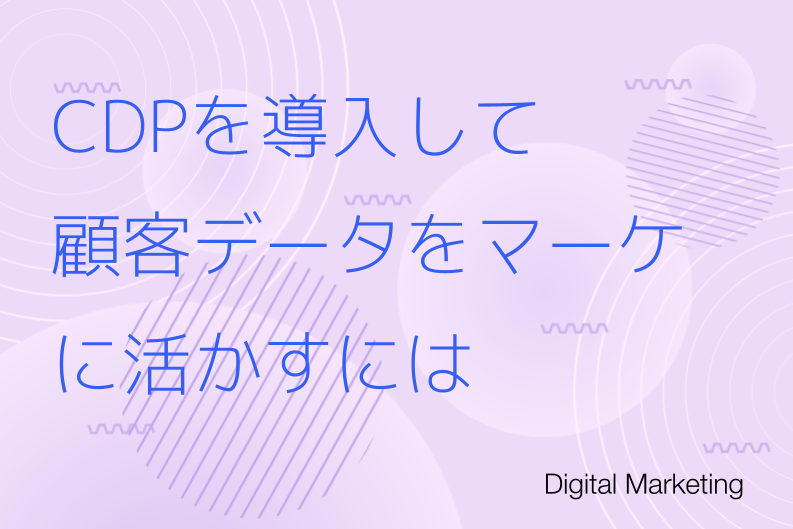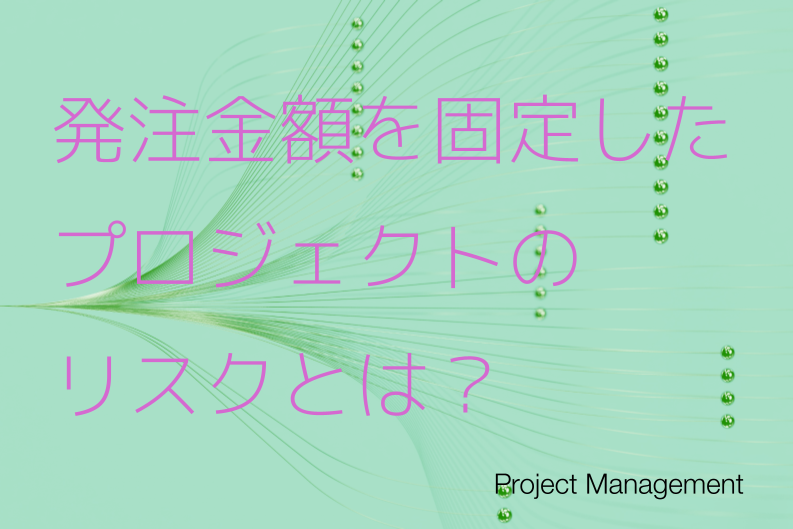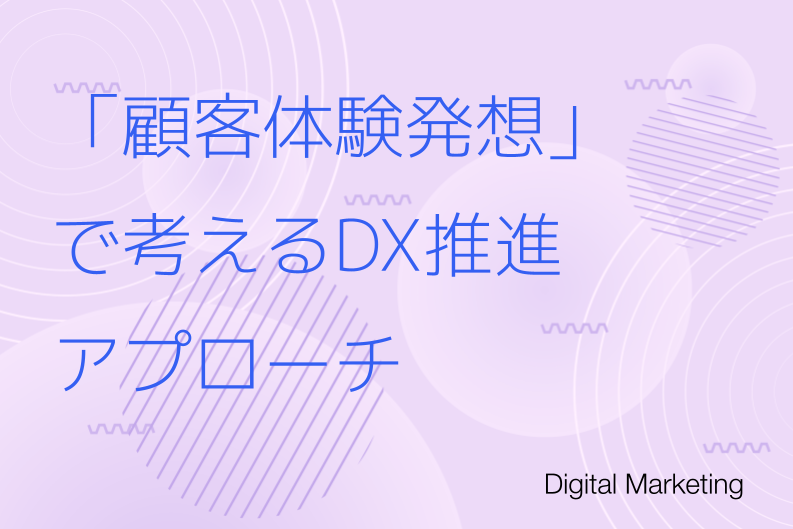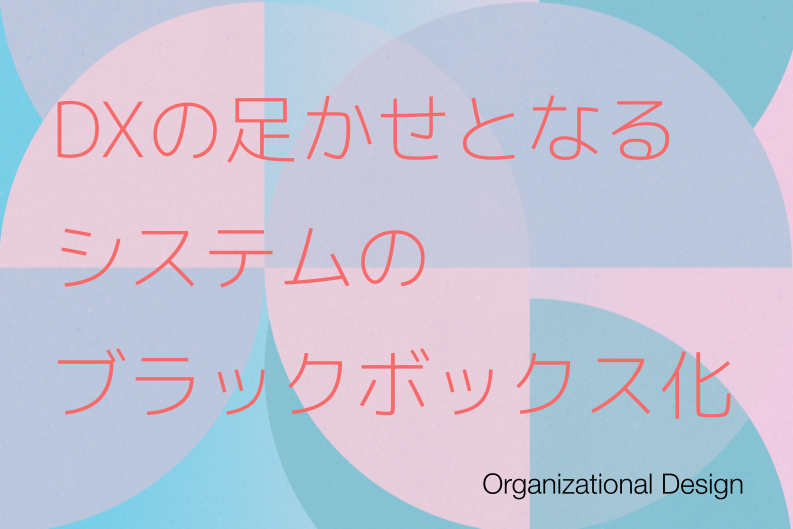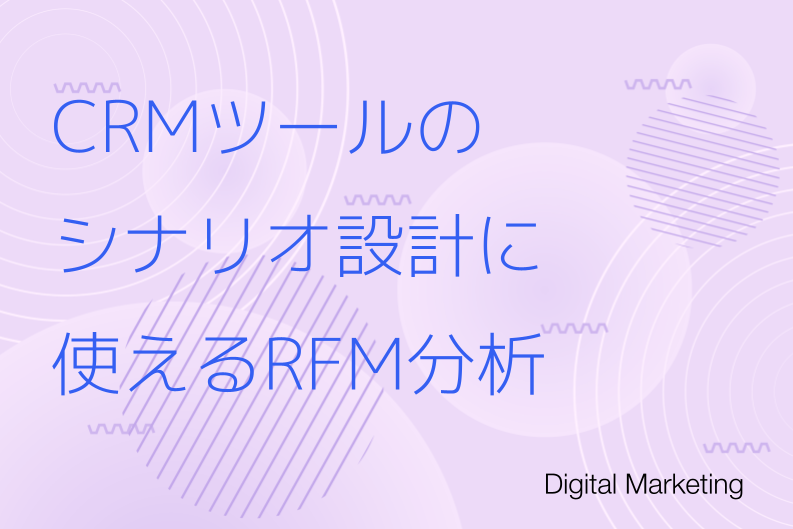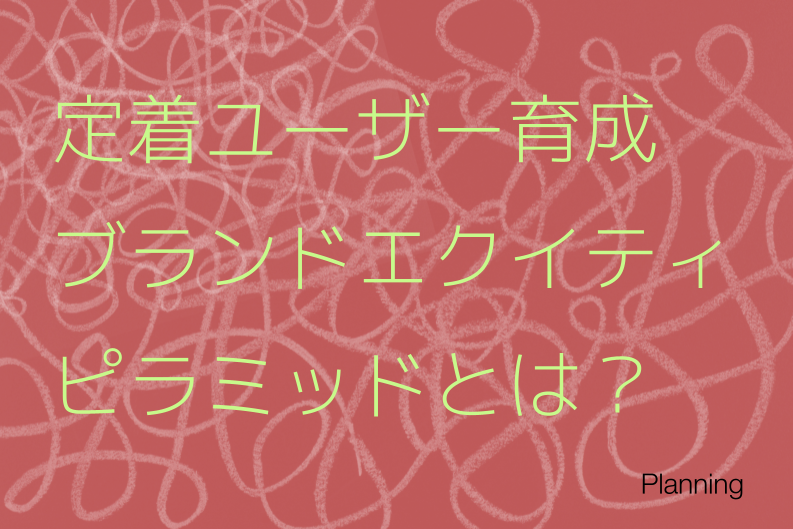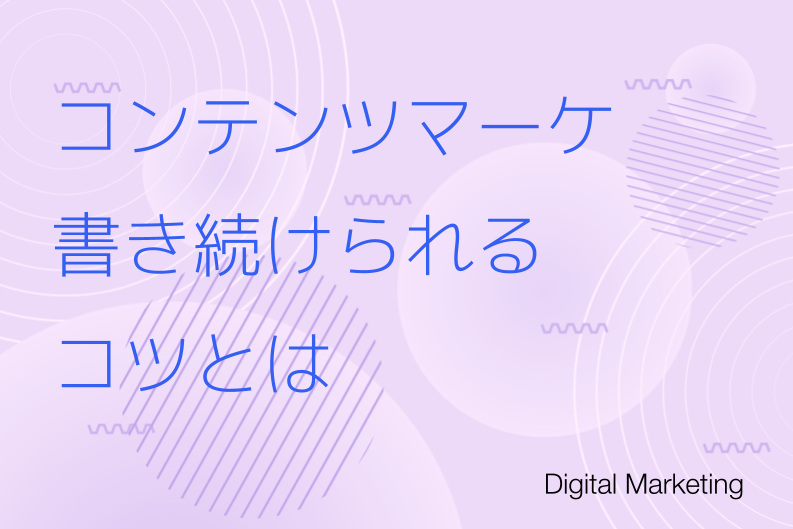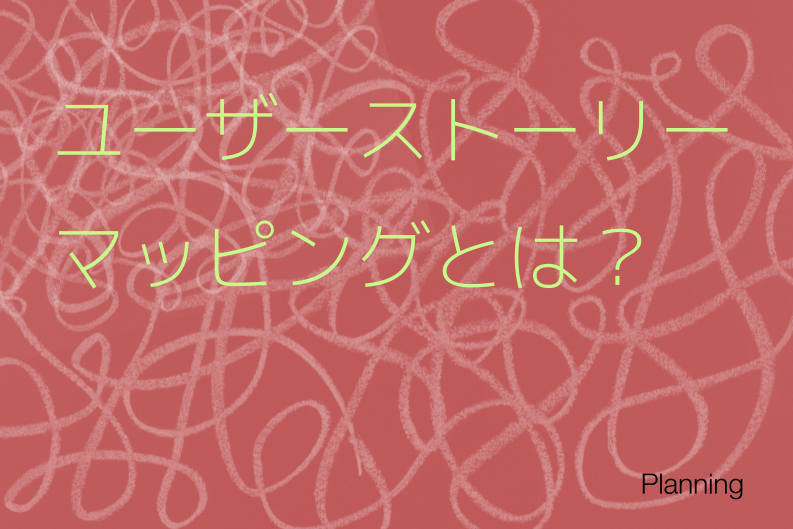「机上の空論にしない」UX/UI視点でパスをだす。

入社して7年と半年。今までどういったお仕事をしてきましたか?
「入社して4年目くらいまでは、主にWeb・アプリ・デジタルコンテンツなどの制作ディレクションを担当していました。業界でいうとエンタメから金融まで、幅広いですね。それから、国内外の様々なブランドのSNS戦略・企画運用、Z世代に向けたプロモーション施策など、ブランド全体のコミュニケーション戦略立案やプロデュースを行うようになってきました。最近では、新規のデジタルサービス立ち上げにあたってUX/UI設計なども担当しています。」
コンテンツ制作からサービス開発まで、領域を広げていった印象があります。仕事への向き合い方が変わったきっかけはありますか?
「入社2年目にディレクターとして携わったアプリ制作で、生活者視点での設計フェーズにおける考え方を徹底的に鍛えられたことですかね。Webのワイヤーフレームや構成書の設計はある程度できるようになってきた感覚があった中で、ニュース配信アプリの画面設計を担当したのですが、社内のアートディレクターから『本当に使いやすい情報設計や機能になっているか』とか『UIと見た目のデザインを混同していないか』とか、とにかく指摘をもらって。
そこで、これまでは高い視座を持った他のメンバーが自分の稚拙な設計や構成を汲み取って昇華してくれたおかげで、クライアントや生活者に届けられるレベルになっていただけだと気づいて。自分からバトンを渡すときに、もっと思考して、もっと意志をもって方針を示していかなければいけないと感じました。
元々、クリエイティブが好きでリスペクトがあるからこそ、意見やこだわり、見立てみたいなものはあったのですが、それを構成段階から考えて論理的にアウトプットに落とし込んでいくのはなかなか難しくて。様々な本を読み漁って勉強したりもしました。自分の設計をベースに質の高いディスカッションができるかを考えながら、必死に食らいつきましたね。その試行錯誤やアートディレクターとの協業を通して、自分の仕事の捉え方が少し変わったと思っています。」
そこから具体的にどういった視点を得ましたか?
「考え抜いた設計が机上の空論にならないよう、生活者視点で地に足ついたものになっているか。最終的な出目をできるだけ想像しながら、設計したものがその意図通りに体験してもらえるのかどうか。確認作業を挟むようになったのは大きな違いなのかなと。
例えば、ボタンひとつとっても、情報の順番や位置、形や色、合わせるテキストライティングなど...クライアントやブランド視点になりすぎず、あくまで生活者にとってのベストを考え抜く。それらの小さな最適解を積み重ねていくことが、自然な生活者体験を形作っていくんだということを、実感を伴って理解できたのは自分にとって大きな変化でした。
ただその一方で、そういった試行錯誤によって、プロジェクトとしての工数や出し戻しが増えてしまうことも気にしなければならず…。その工数を下げながらも最大限良いものをつくるために、まず最初のやり取りでプロジェクトの全体をしっかりと形作っていく必要がある。そこに気づけたことも、ひとつディレクターからプロデューサーへ視座が上がったポイントだったのかなと思っています。
例えば、クライアントの御用聞きをするのではなく、本来的な目的や優先して取り組むべきスコープをクライアントの理解を得ながら定めていくこと。それをクリエイティブチームに齟齬無く、かつ自分の意志をもって伝達すること。その心がけが、一番最初に出すパスの精度を上げ、結果としてアウトプットのレベルを底上げすることに繋がると思います。」
UX/UI視点を持ったアカウントとして、アウトプットのクオリティを上げていく動きを実践するようになったんですね。
「そうですね。プレーヤーとしての成長期に、そこにしっかりと向き合えたことは大きかったです。その後もアプリに限らず、大小様々、与件も異なるプロジェクトを担当させていただきましたが、難易度の高い仕事にも、時にはかなり泥臭く食らいついて、経験値を着実にためていくことができました。
すると段々と『UX/UIをちゃんと考えた制作ならアイスタに相談しよう』という周囲からの信頼が生まれて、仕事の引き合いも増えていきました。今ではアイスタでは職種問わずみんながその考えをもってやっていると思いますし、自分自身も、実感をもってUX/UIの提案ができるようになっています。」
ファン視点とアドリブ力で、クライアントのパートナーに。

ディレクターからプロデューサーというキャリアを歩む中で、印象的だったプロジェクトはありますか?
「初めてプロデューサー的な動きを任せてもらった「ポケモン情報局」という株式会社ポケモンの公式SNSアカウントの運用プロジェクトがありまして。
SNSの投稿クリエイティブを企画制作するところから依頼を受けたのですが、まず最初に思ったことは『”ポケモン”という圧倒的なブランドやキャラクターに対して、ファンの期待を決して裏切らないクオリティでなければならない』ということでした。企画の良さだけではなくて、投稿テキストやイメージなどのアウトプットがファンの琴線に響くかどうか。ターゲットの反応をシビアに捉えて、期待に応えるために、とにかくクリエイティブの表現やアイディアにはこだわりました。
『ファンならこういう投稿をしたら喜ぶはず』という視点で妥協せずに創り続けながら、プロジェクトを大きく安定したものにしていく。アウトプットだけではなく、プロジェクト運営のことも考えながら働くこと、そこにプロデューサーとしての楽しさを見出せたと思います。」
プロデュースをする上で大事にしていることはありますか?
「とにかくそのブランドやクライアントのファンになることです!ブランドについての情報をインプットするだけではなく、店舗で実際にそのブランドの商品を購入してみたり、サービスを体験したり、友だちに紹介してみたり...生活者としての日常をじっくりと体験してみること。その時間を通じて『愛着』を持つことを人一倍大事にしています。
そこから見えてきた魅力をクライアントに伝えたり、その体験をベースにした企画を提案したり、クライアントが向き合うターゲットと同じ目線をもってディスカッションできるように意識しています。ファンとしての体験を積み上げることで、提案するコンテンツや企画にもちゃんと自分の体重が乗るように感じます。そして、そのファンとしての体験を自分だけのものにせずに、クリエイティブチームへも共有し、チームみんなで愛着を持てるようにすることも、プロデューサーとして大切なことの1つだと思っています。」

愛着を持って向き合った結果、ポケモングッズで溢れる自宅に
クライアントとのコミュニケーションで意識していることはありますか?
「クライアントに対しては『お客様』というだけではなく、『パートナー』として同じ目線でお話しさせていただくことを大切にしています。前提として、ブランドについてはクライアントのほうが熟知していて知見もあるので、まずそこにリスペクトを持ちながらしっかりと耳を傾け、大切にしている想いや、生活者に伝えるべきポイントを抽出していきます。その上で、目的に対して最善だと思うことを“偽りなく”伝えるよう常に意識しています。
その時に、ファンとしての視点をもって発言をしていくと、お互いに納得しながらディスカッションを深められることが多いです。ファンであるからこそのシビアさやこだわり、説得力があると思っていて。『ファンはこう思う』というベースに『彼らに届けるコミュニケーションはこうあるべき』という提案をかけ合わせていくことで、より良い解を導くことができる。
また、柔軟な“アドリブ的提案”も心がけています。その場で反射的に思いついたアイデアや、会話する中で変わっていく考え方なども正直にお伝えすることで、クライアントからの信頼獲得へと繋がると思うので!アイスタにはデジタル領域であればどんなものでも形にできるスキルやノウハウがあります。だからこそ、パッと思いついたひらめきのような考えも臆せず口に出来るのかもしれません。」
デジタル上で削ぎ落とされてしまうユーザー体験。だからこそ頭を捻る。
プライベートでは劇団で役者や演出も行なっているそうですね。やはり表現することやものづくりは好きですか?
「好きですね。やっぱり昔からアートやデザインなど、自分で手を動かしてものを作れる人に対する憧れやリスペクトを持っていて。演劇は、社会人になってからは関わる時間も少なくなっているのですが、自分の身一つで役者として様々な表現をすることができるし、裏方として演出や演技指導で世界観をつくり込めるのが楽しい。人の心を動かす体験をつくるという点で、演劇も仕事も共通していると感じていて、仕事も自分が好きなことの延長として向き合っている感覚が強いです。」

所属する劇団の舞台上でのワンシーン
アートやデザインが仕事の刺激になった体験はありますか?
「刺激になったというよりも、改めて気をつけなきゃと思ったことはありますね。アートが好きで、日常的に美術館や芸術祭に行ったり、海外でも教会やカルチャーセンターなど様々な場所でアートに触れてきましたが、とにかく大きければ大きいほど作品にインパクトを感じたんです。すごく薄っぺらい感想みたいになるのですが(笑)
僕たちが仕事で取り組むデジタル領域においては、情報を媒介する物の質量や面積でいうと、スマホみたいにかなり小さいものもあったりして。それでどこまで感動を与えられるのか、人の心に残るのか...考えると、とても難しいことなのでは?と思います。どれだけ音質を良くしても、CDより生演奏の方がグッと来る、みたいな話とも近いですかね。デジタルではアナログのもつ“大きさ”に、敵わないんじゃないかと感じることもあって。
だからこそ、デジタルで人を動かしましょうとなったときに、すごく頭を捻らなきゃいけない。これから先、技術が発展し手段が増えれば増えるほど、そうだと思っていて。企画の幅は広がっても、デジタルだと削ぎ落とされてしまう感覚や体験に対して、意図的にギャップを埋めたり、新しい価値に変えたり、とにかく工夫が必要だと思っています。
直近では、自分自身のアバターを使った「じぶんランウェイ」というデジタルファッションショーサービスを手がける中で、新しい技術に触れるわくわく感と、実際に店舗で試着をする実感との狭間で、改めてデジタルというフィールドで感動を伴う体験を創る難しさと、楽しさを感じています。」
今後の展望、やってみたいことはなんですか?
「最近は、サービスのUX/UIを定義するプロジェクトを任せてもらうことが増えていて、そういった長期にわたって運用されていくサービスだったりプラットフォームだったり、基盤となるようなものを、パートナーと一緒に作りたいという気持ちがあります。
点での施策じゃなく、継続的に生活者に寄り添う形で、生活者へ良質な体験やサービスを提供し続けることに価値を感じていて。BtoBto“C”的に何か新しいサービスを作れたら良いなと思っています。“C”もただの生活者やお客さんではなく、共創するコミュニティメンバーとして捉えてみる。例えば…その地域に住んでいる人たちを巻き込んで、一緒にサービスを考えていくなんてことも面白いなと。
それがアートに関わることだったり、ステージ演出だったり、地方創生だったり、自分の興味がある分野でチャレンジできたら嬉しいです。」

取材・執筆:小宮 恵里花
撮影:小坂 夏未