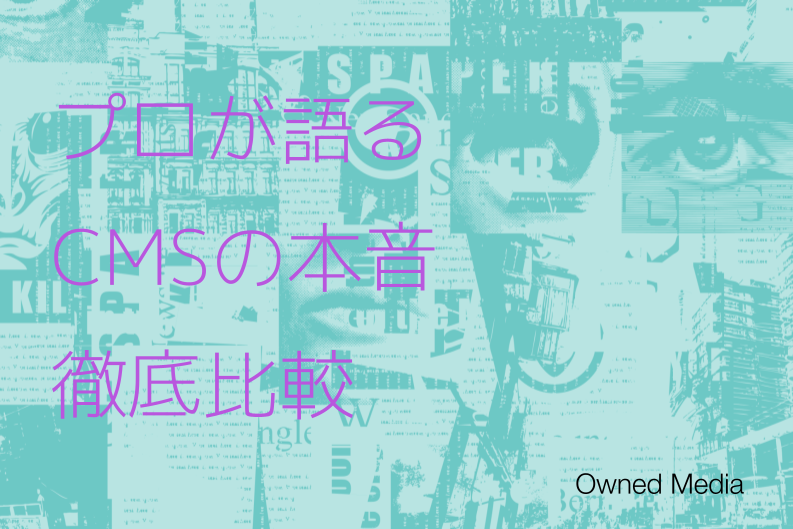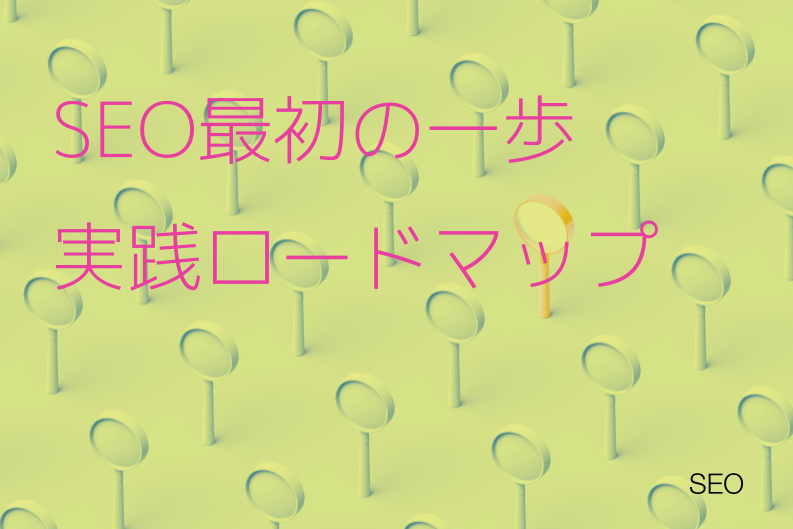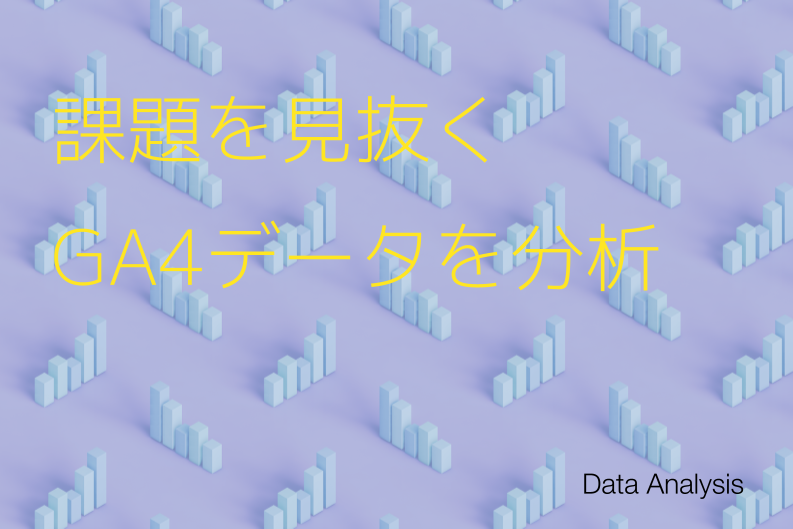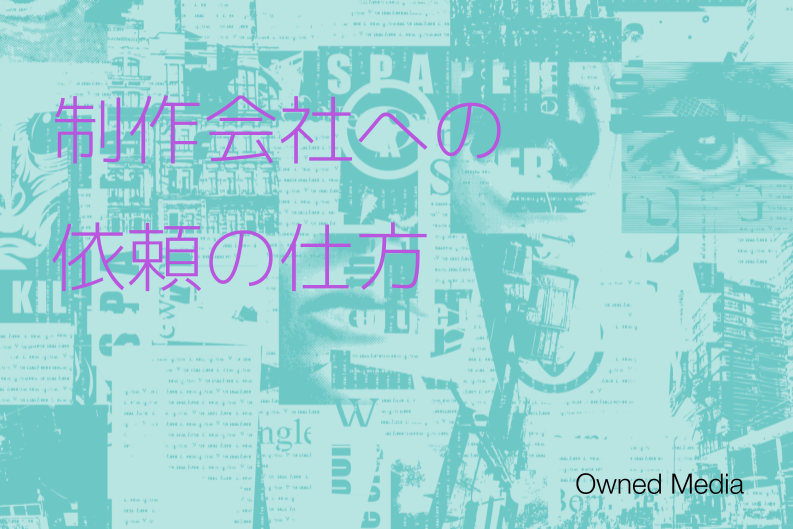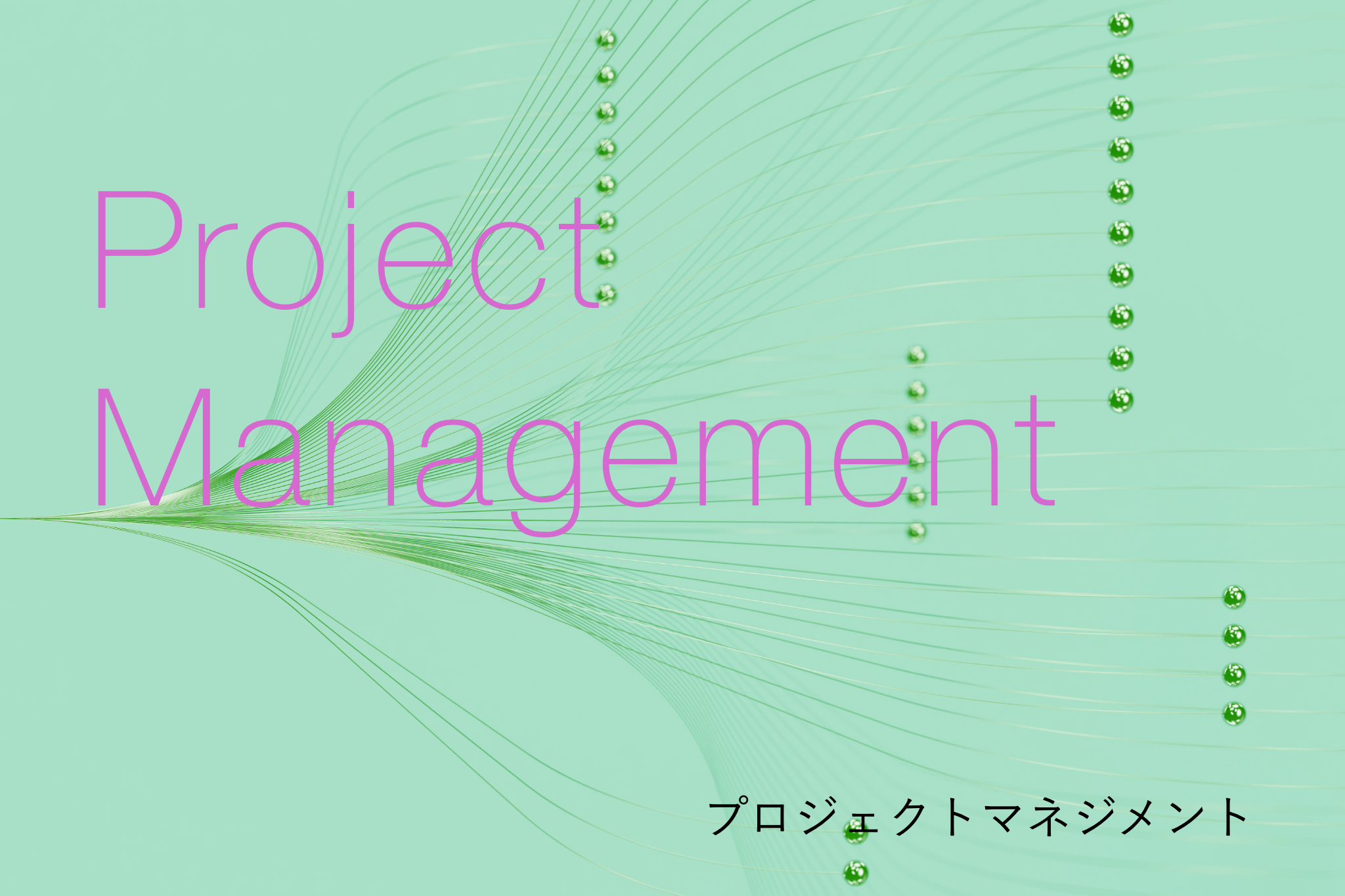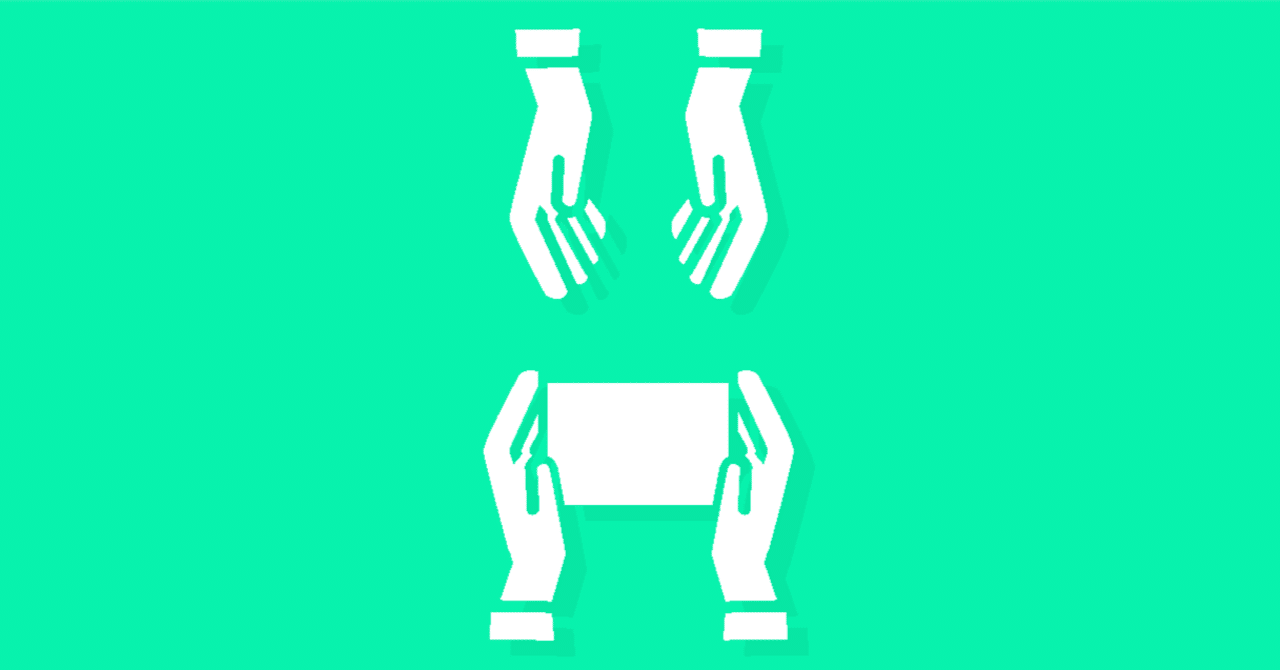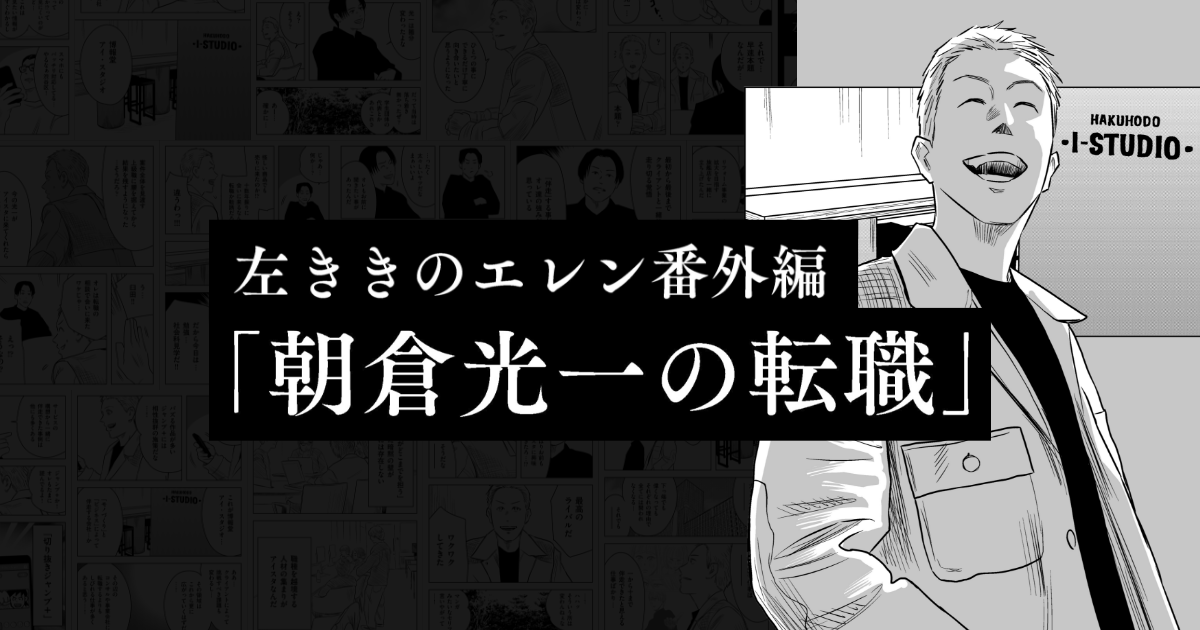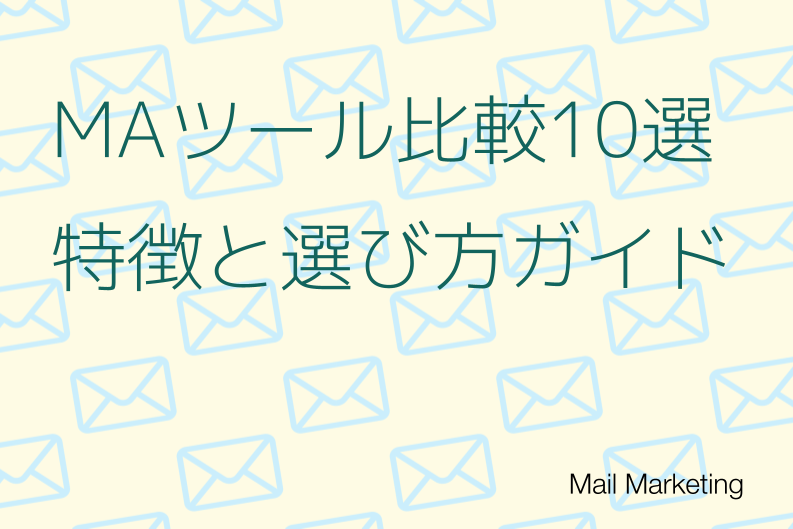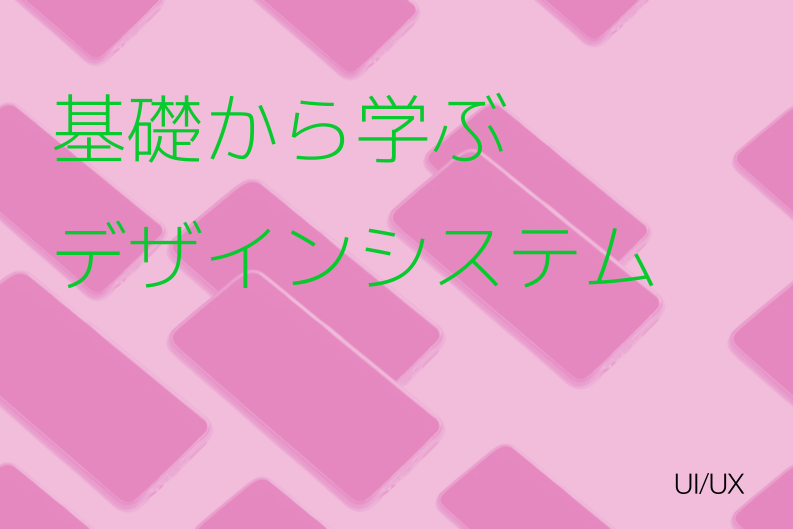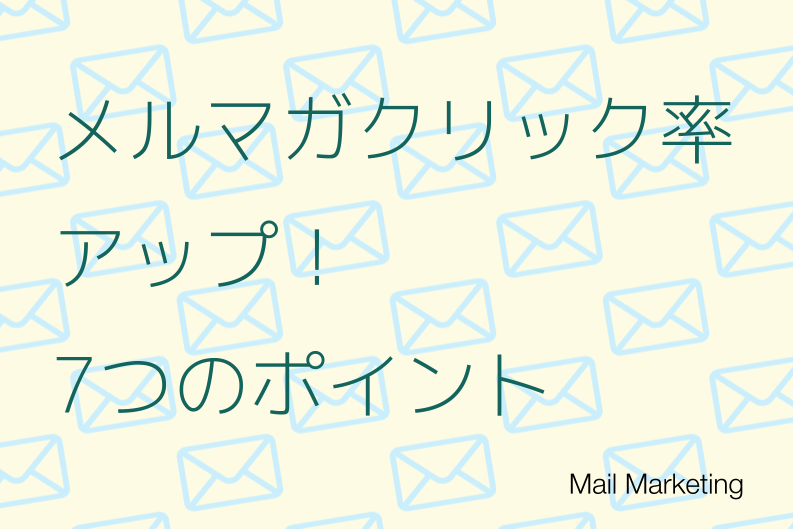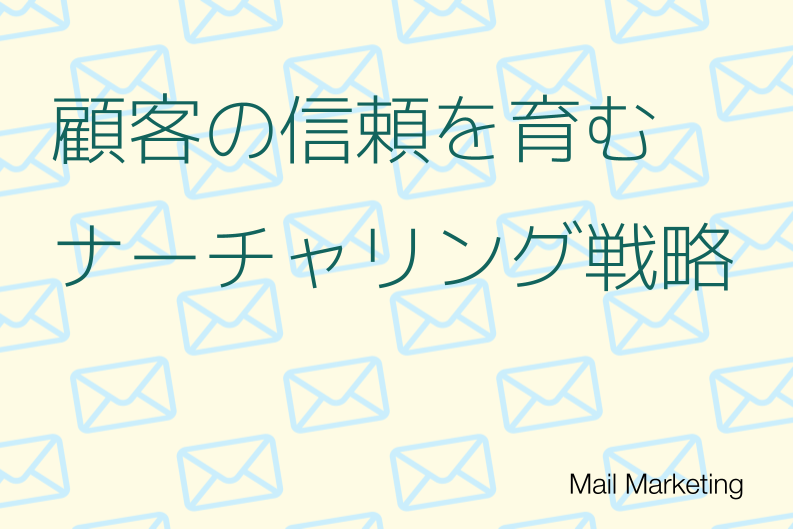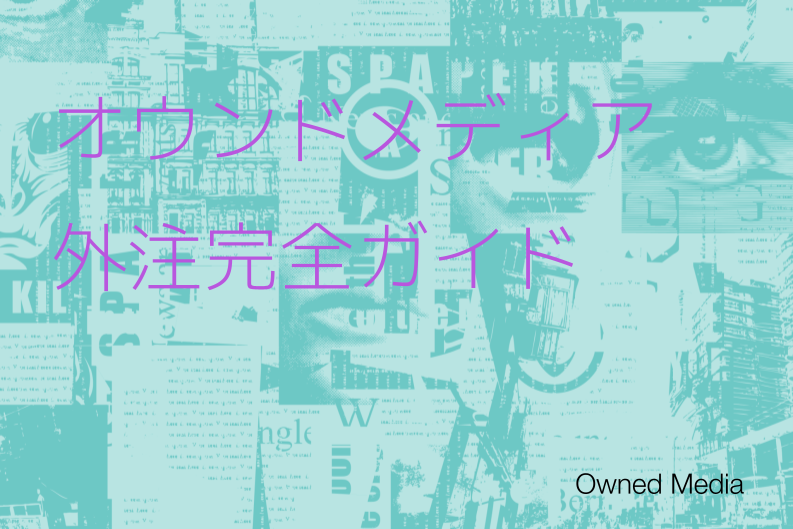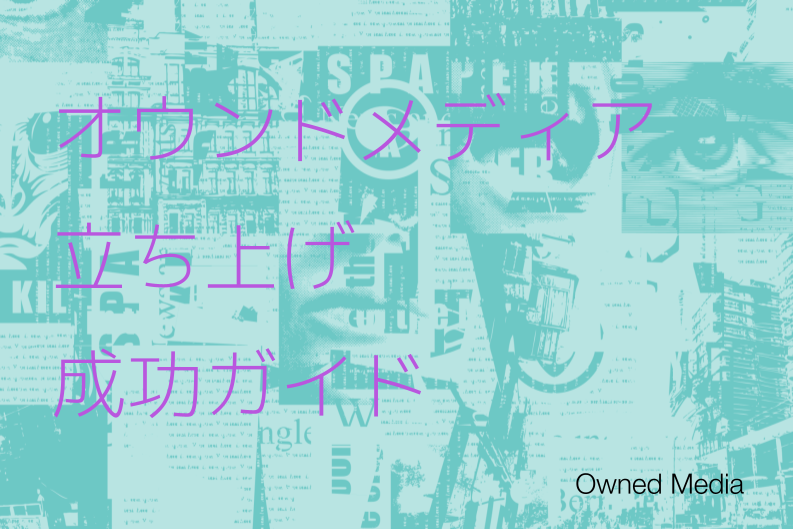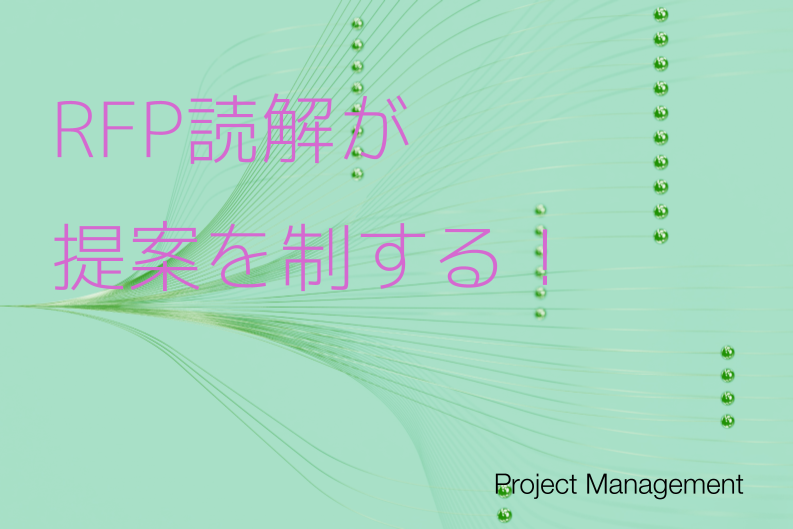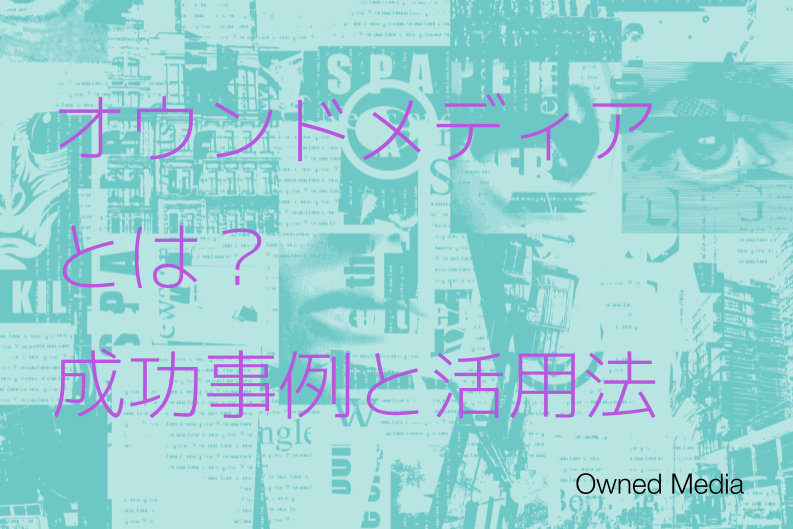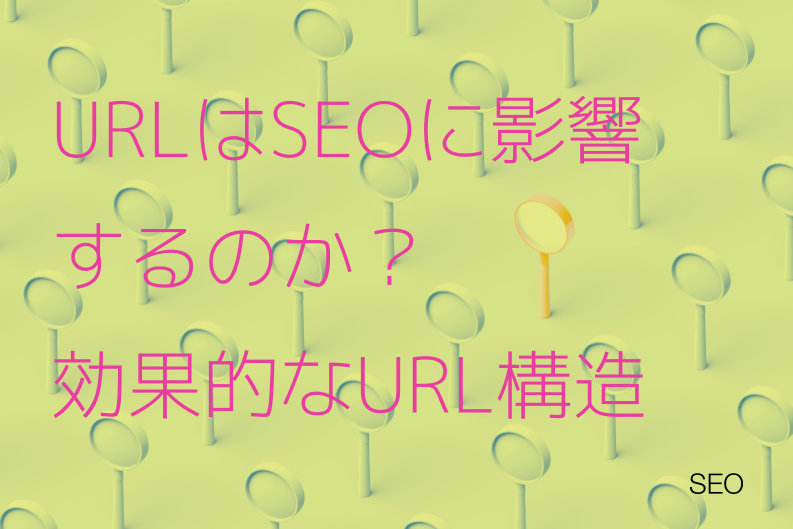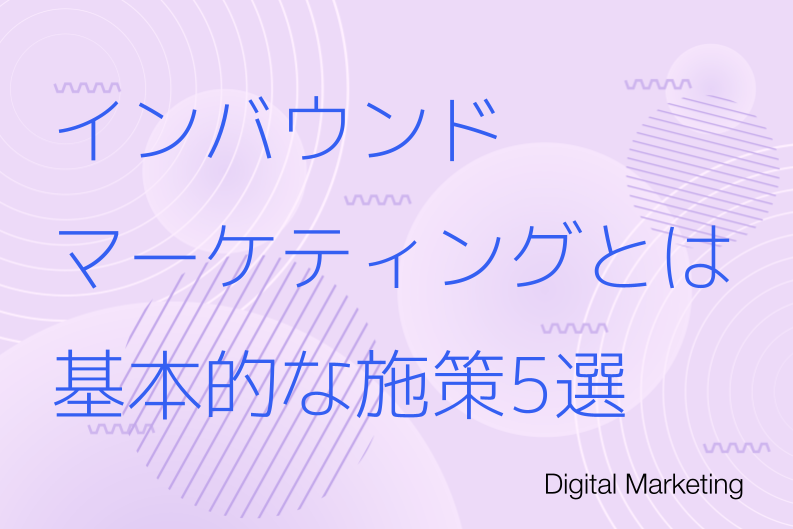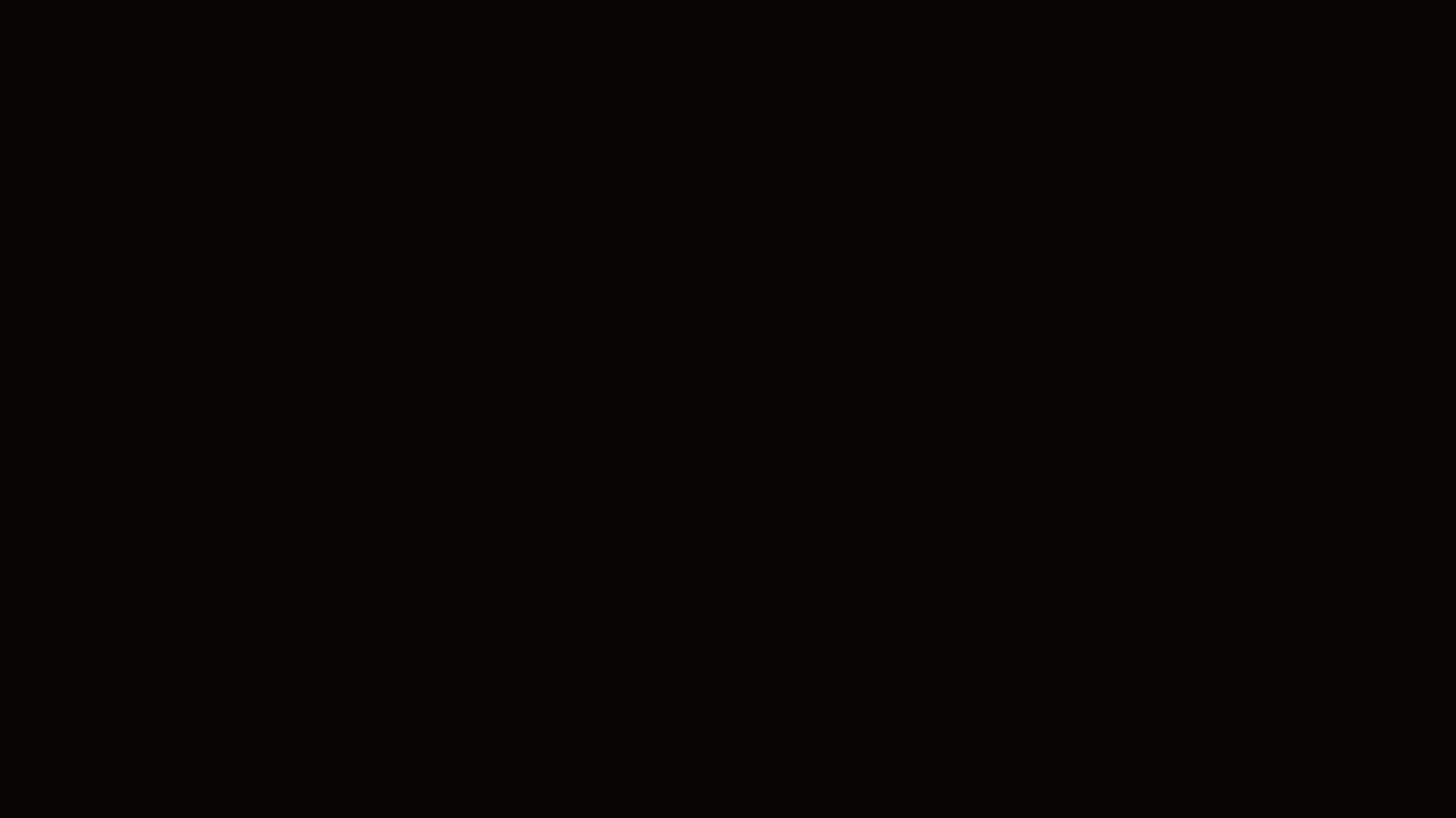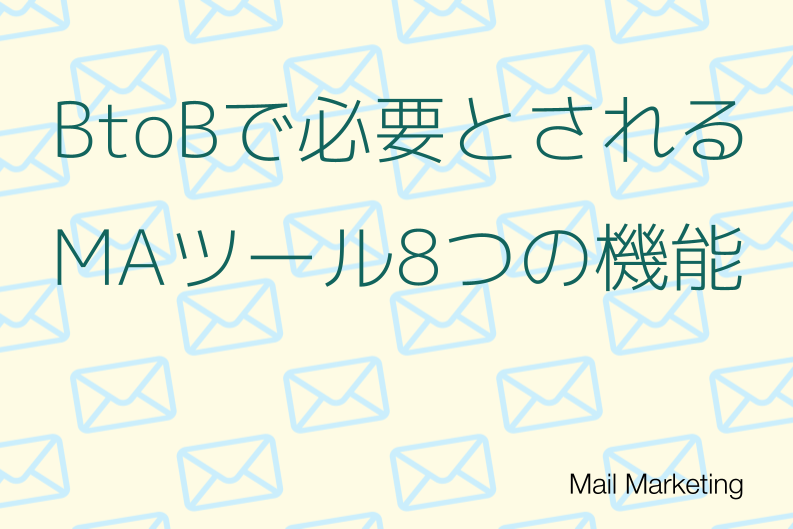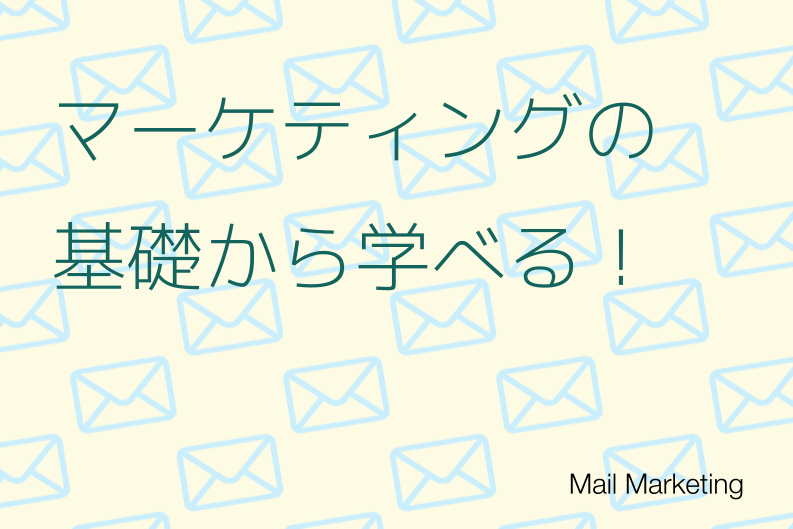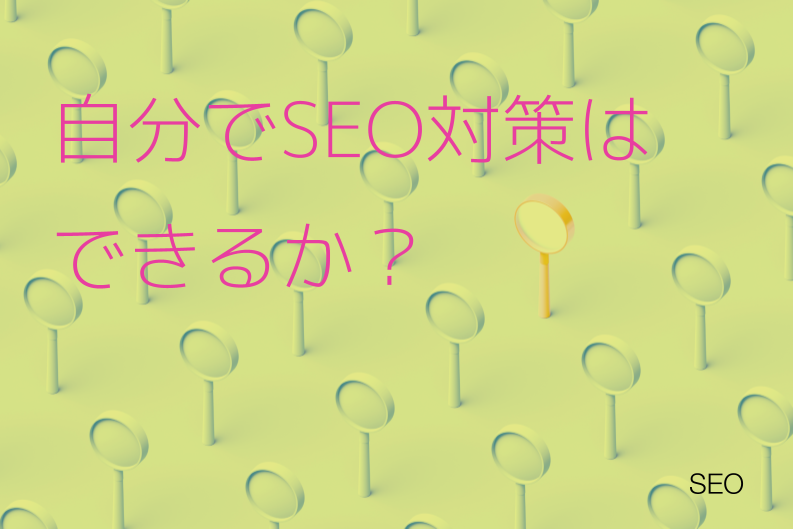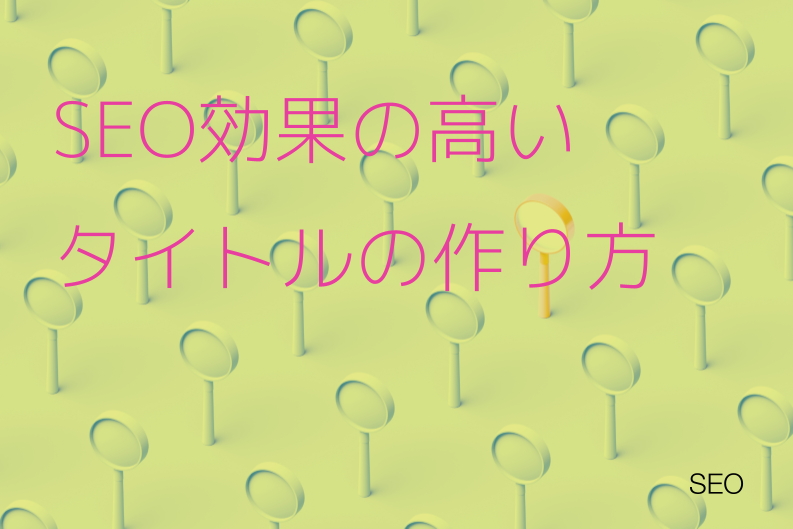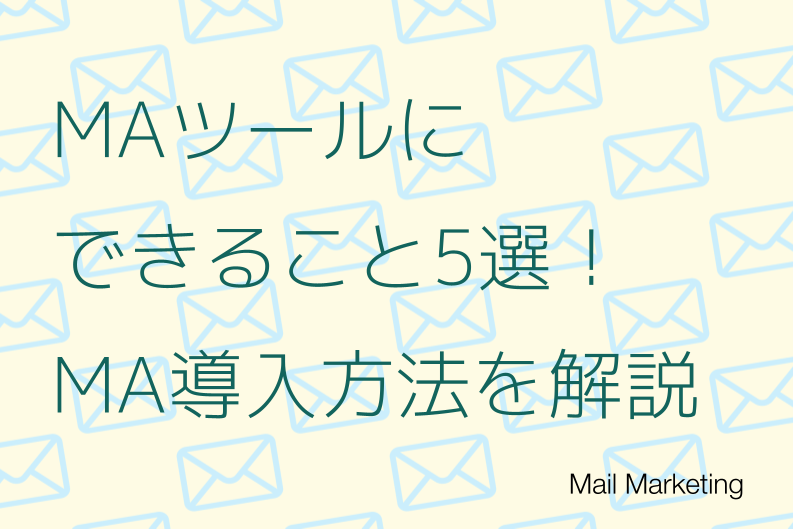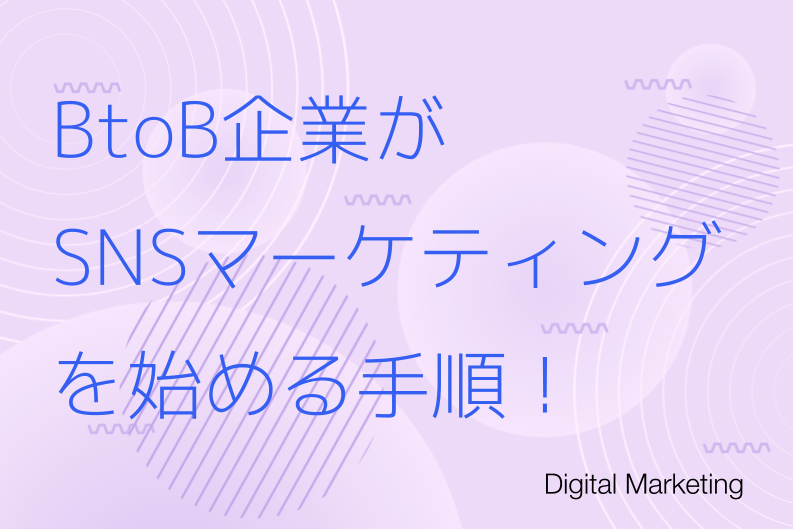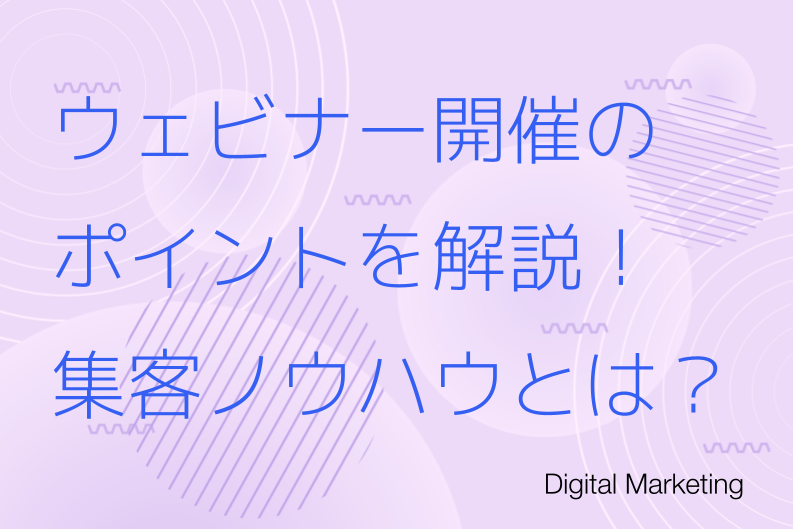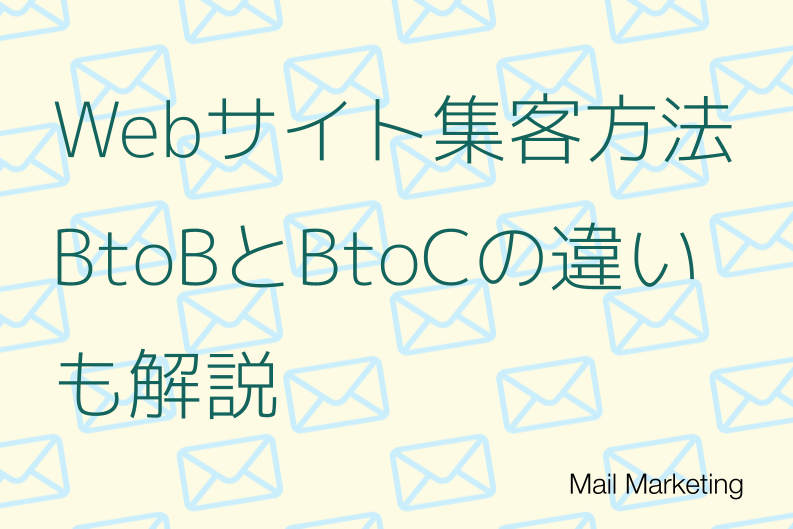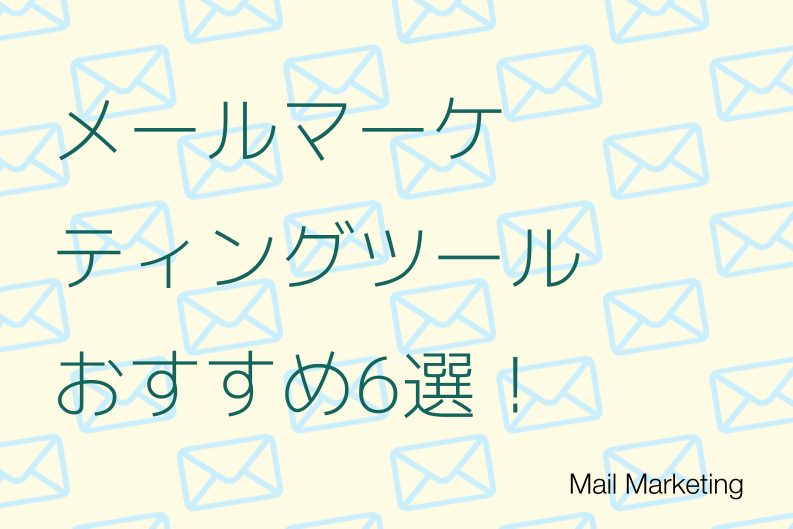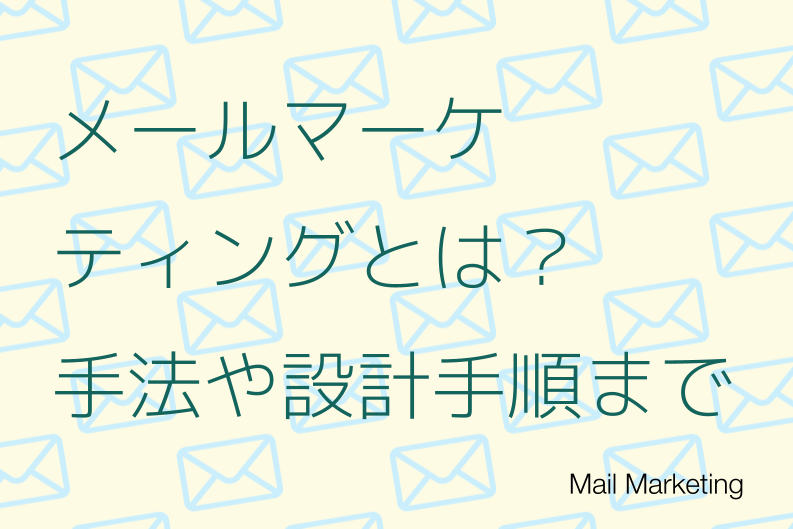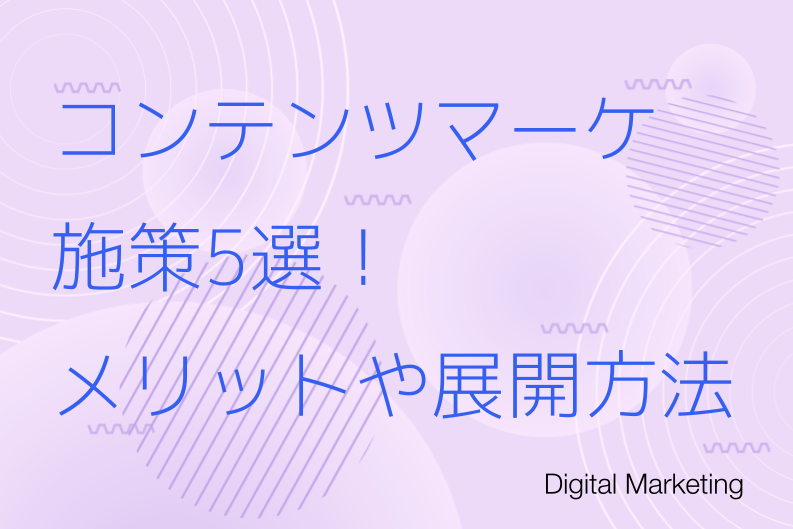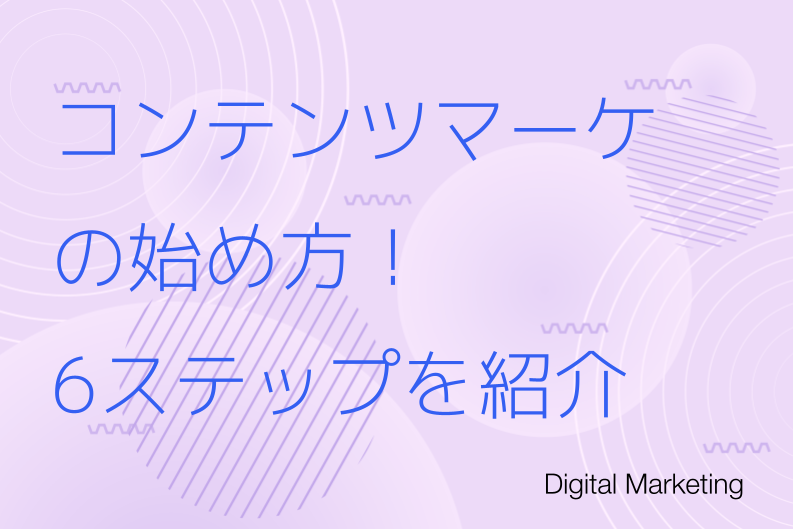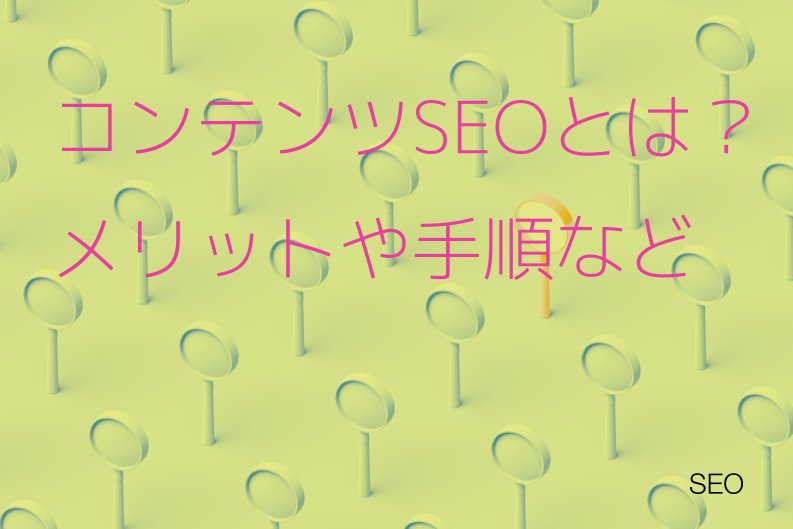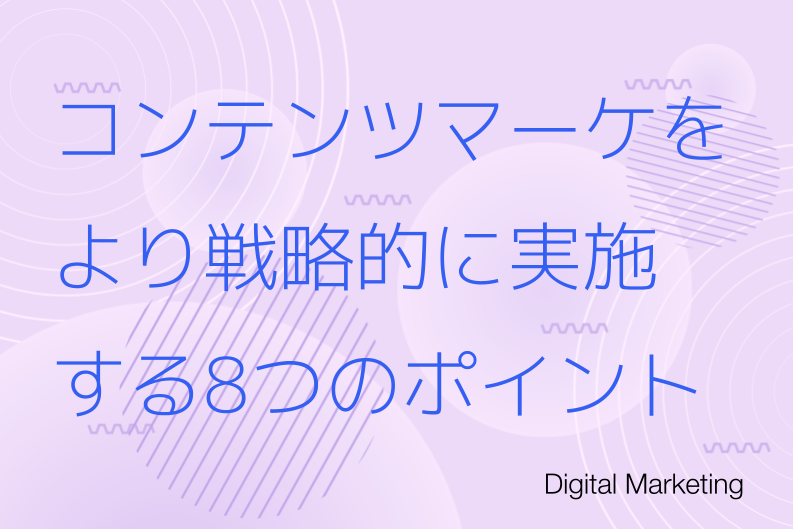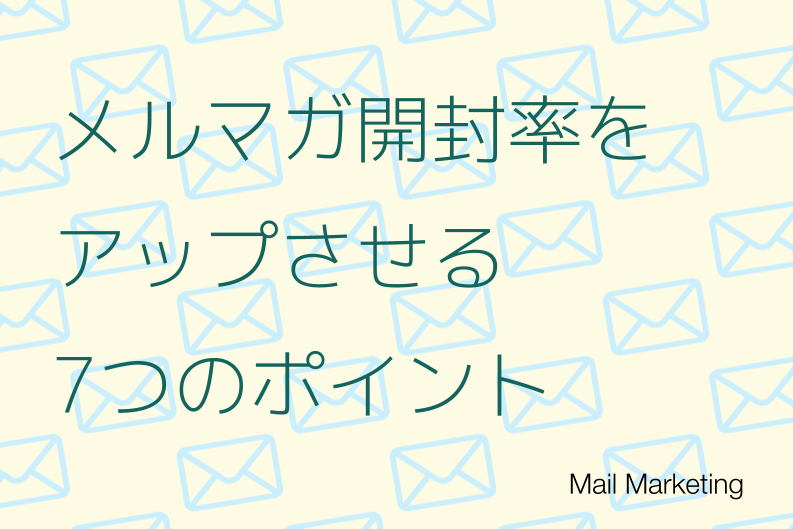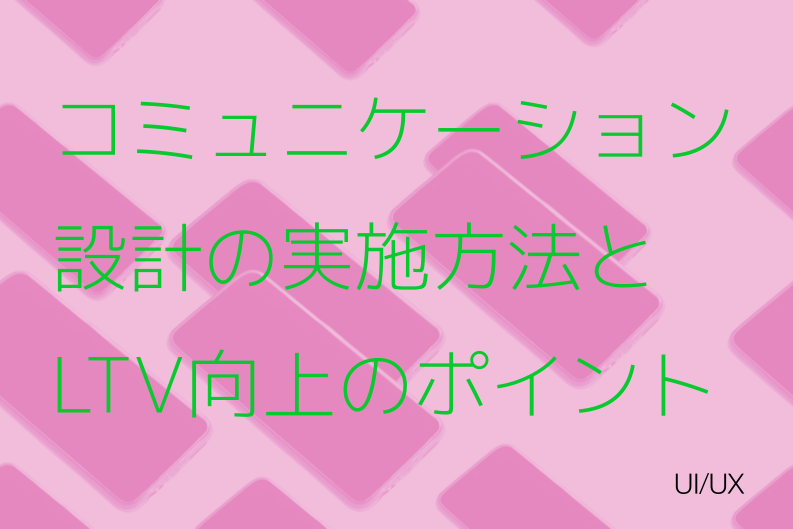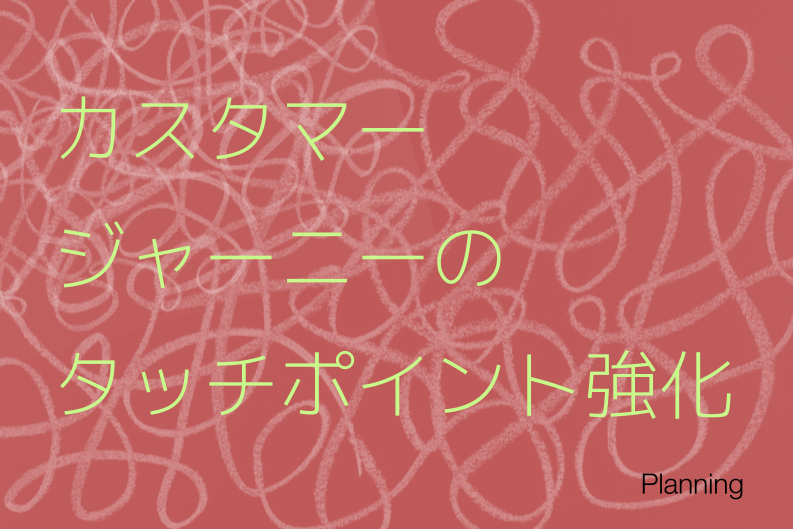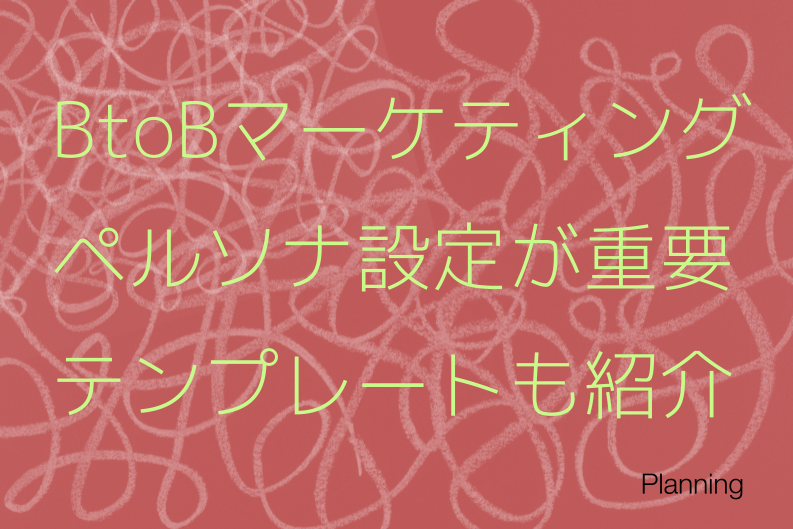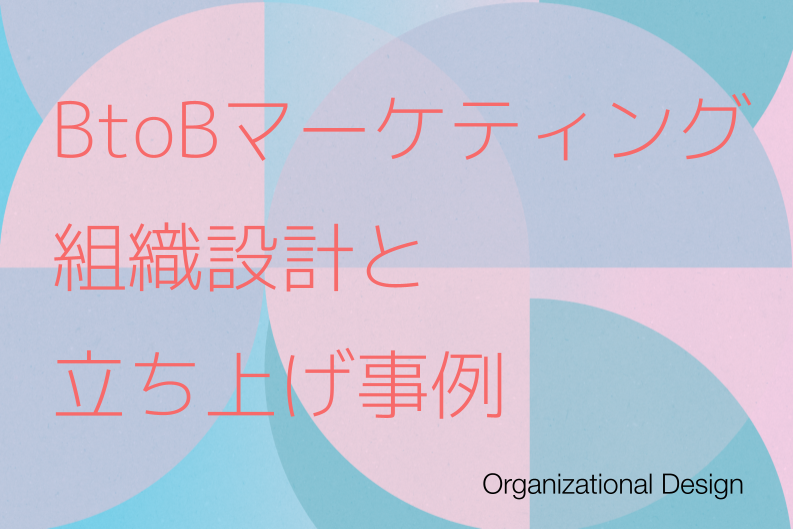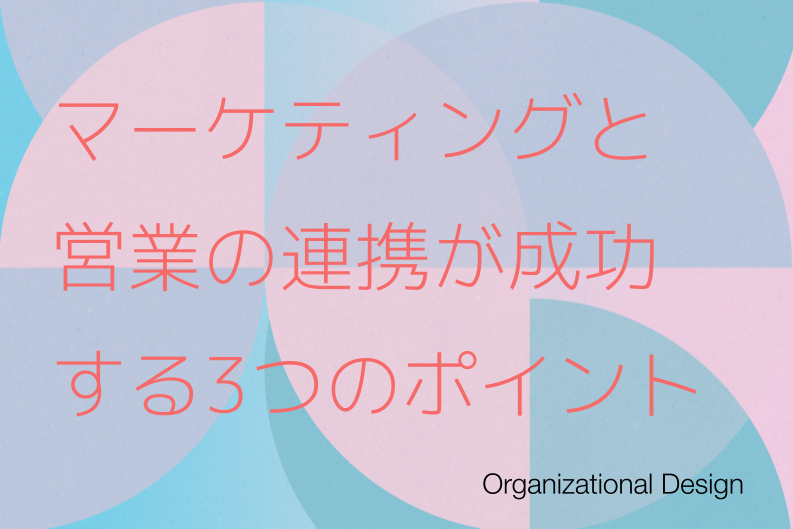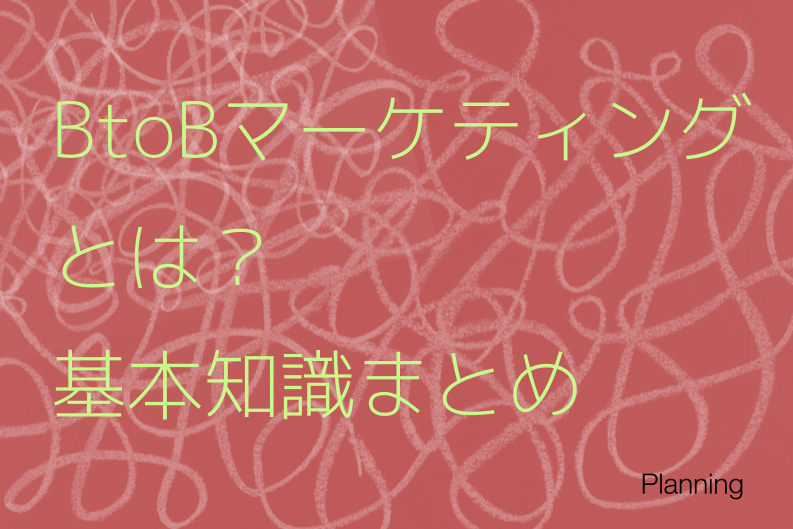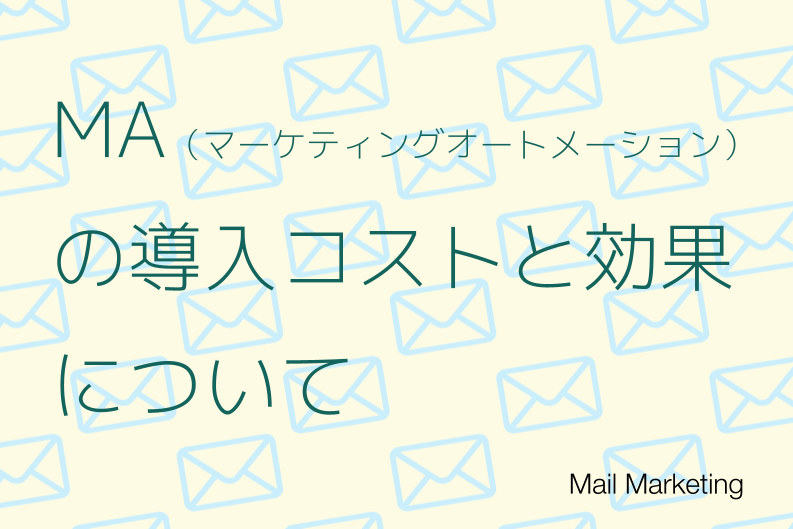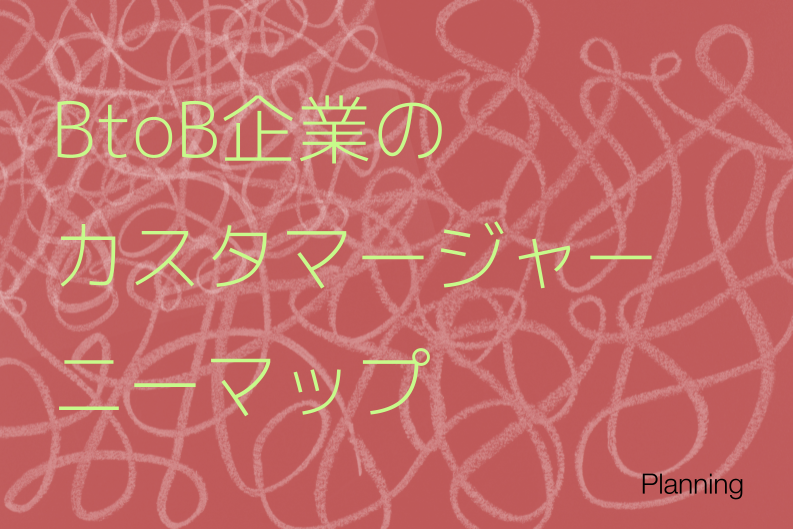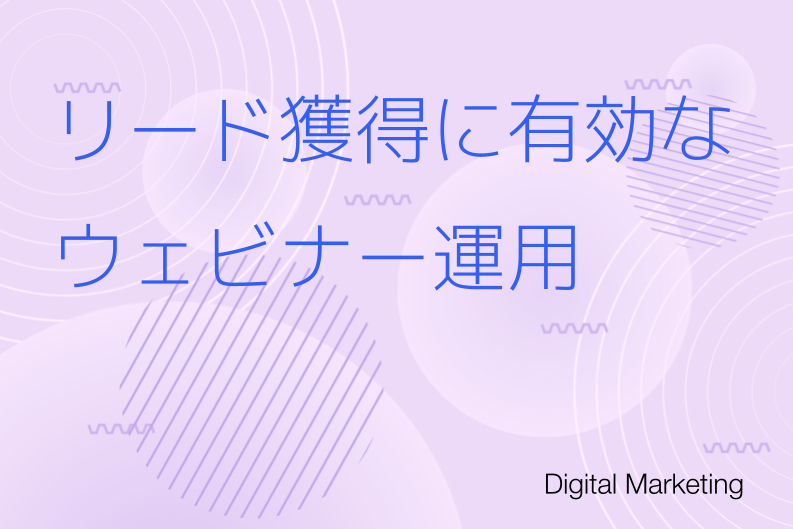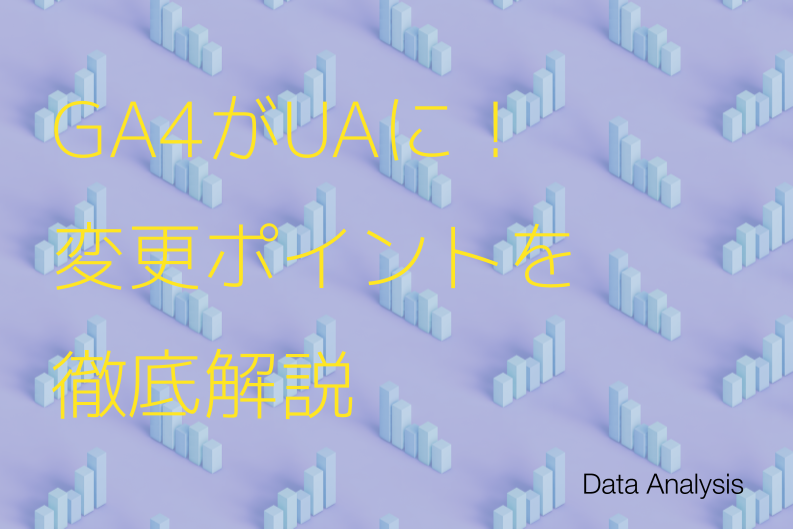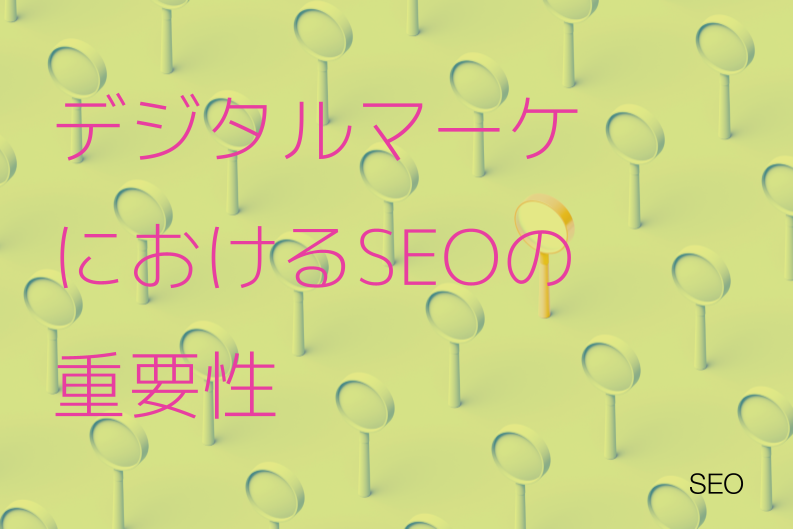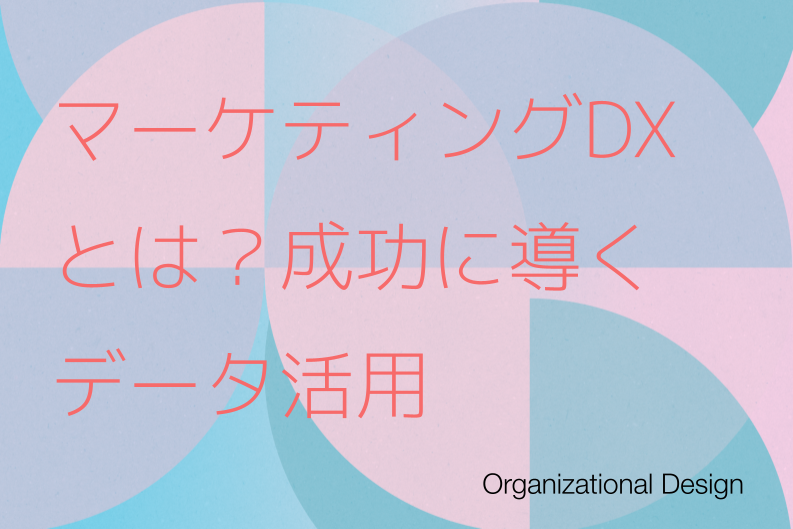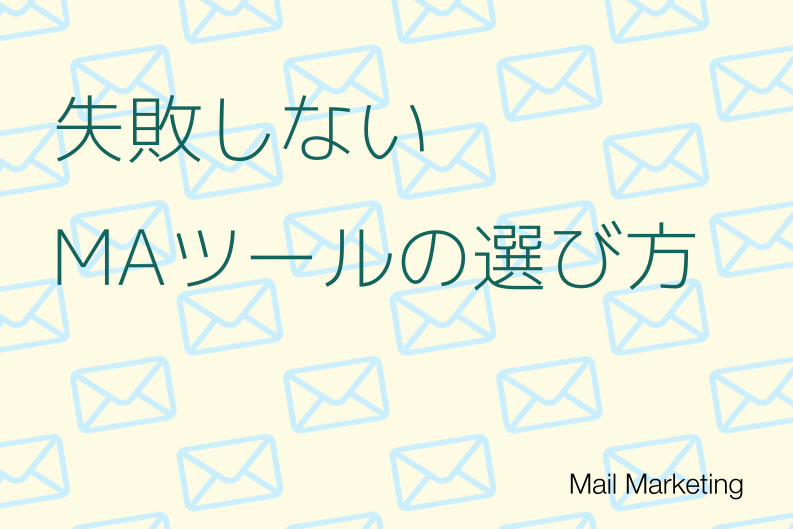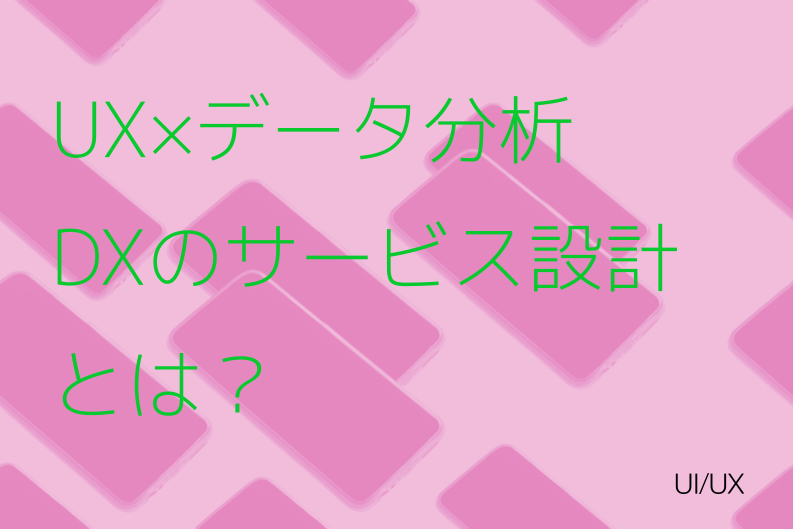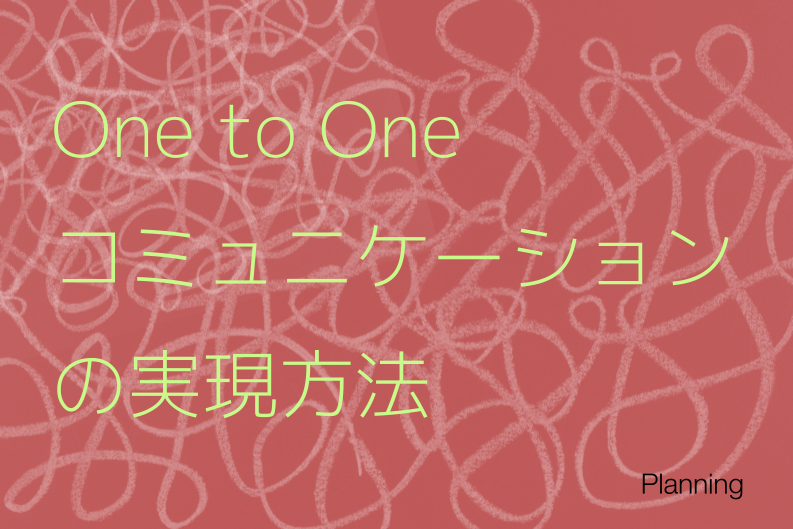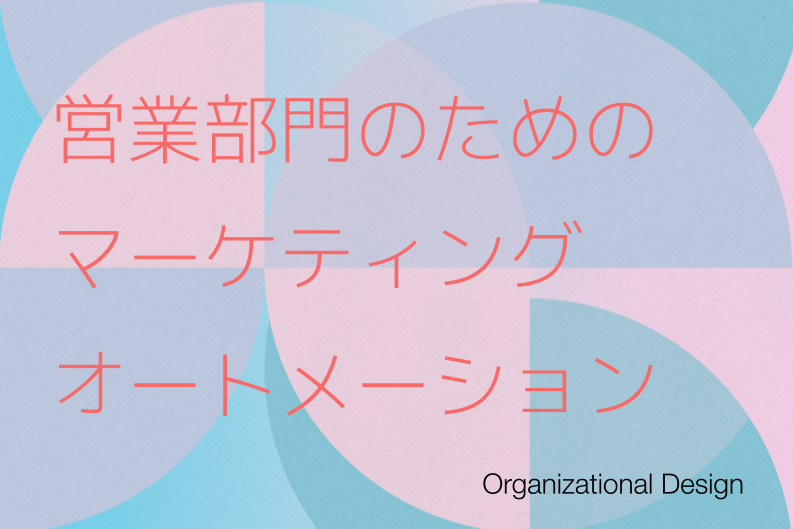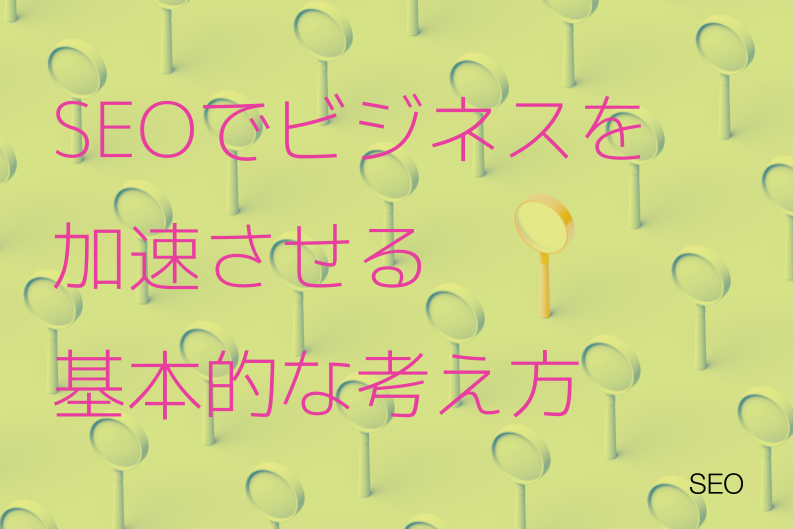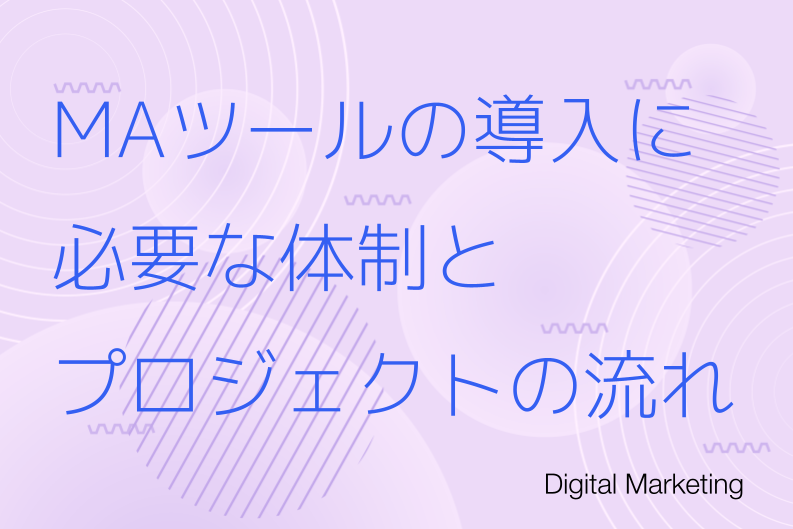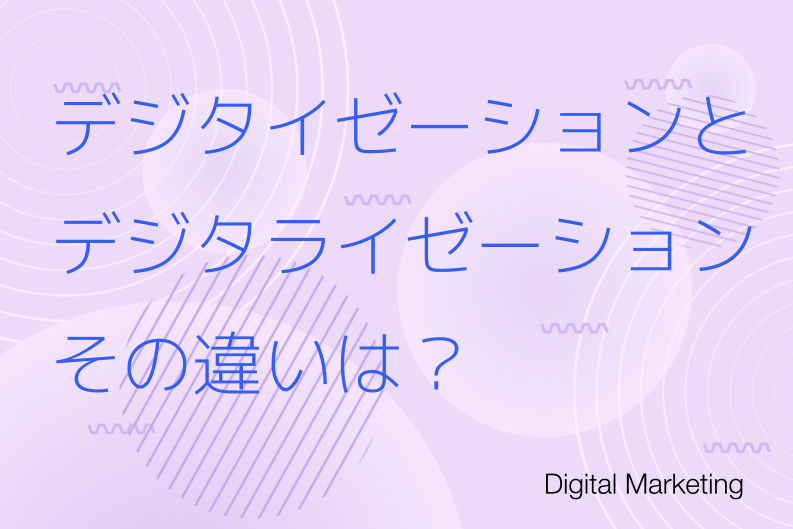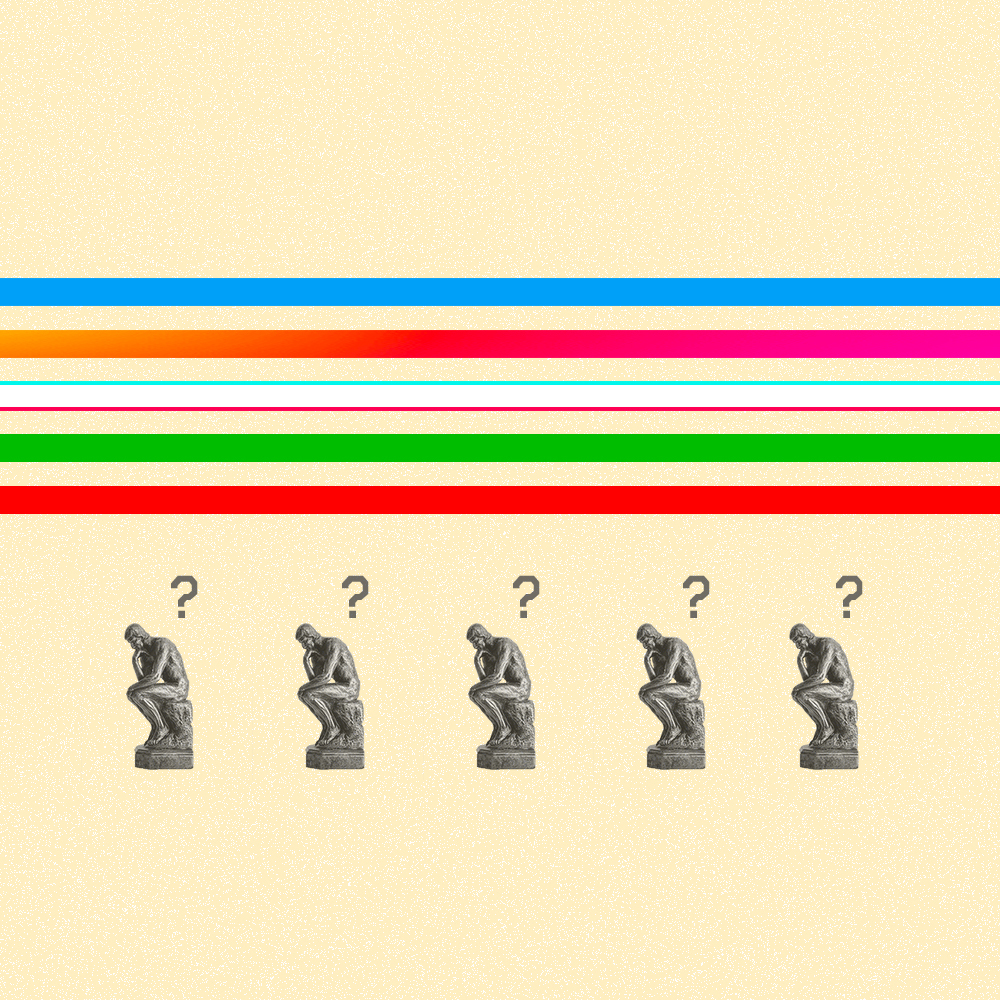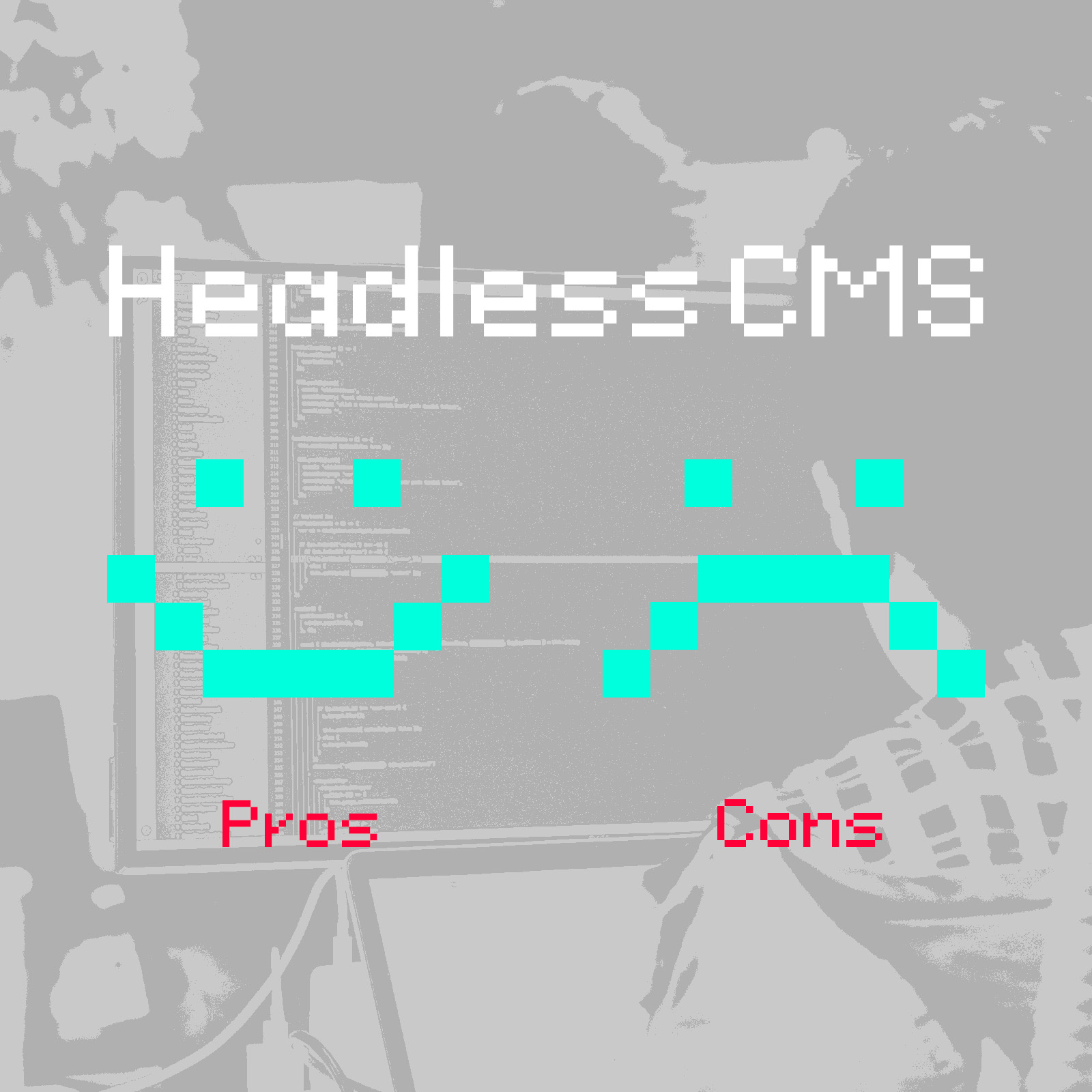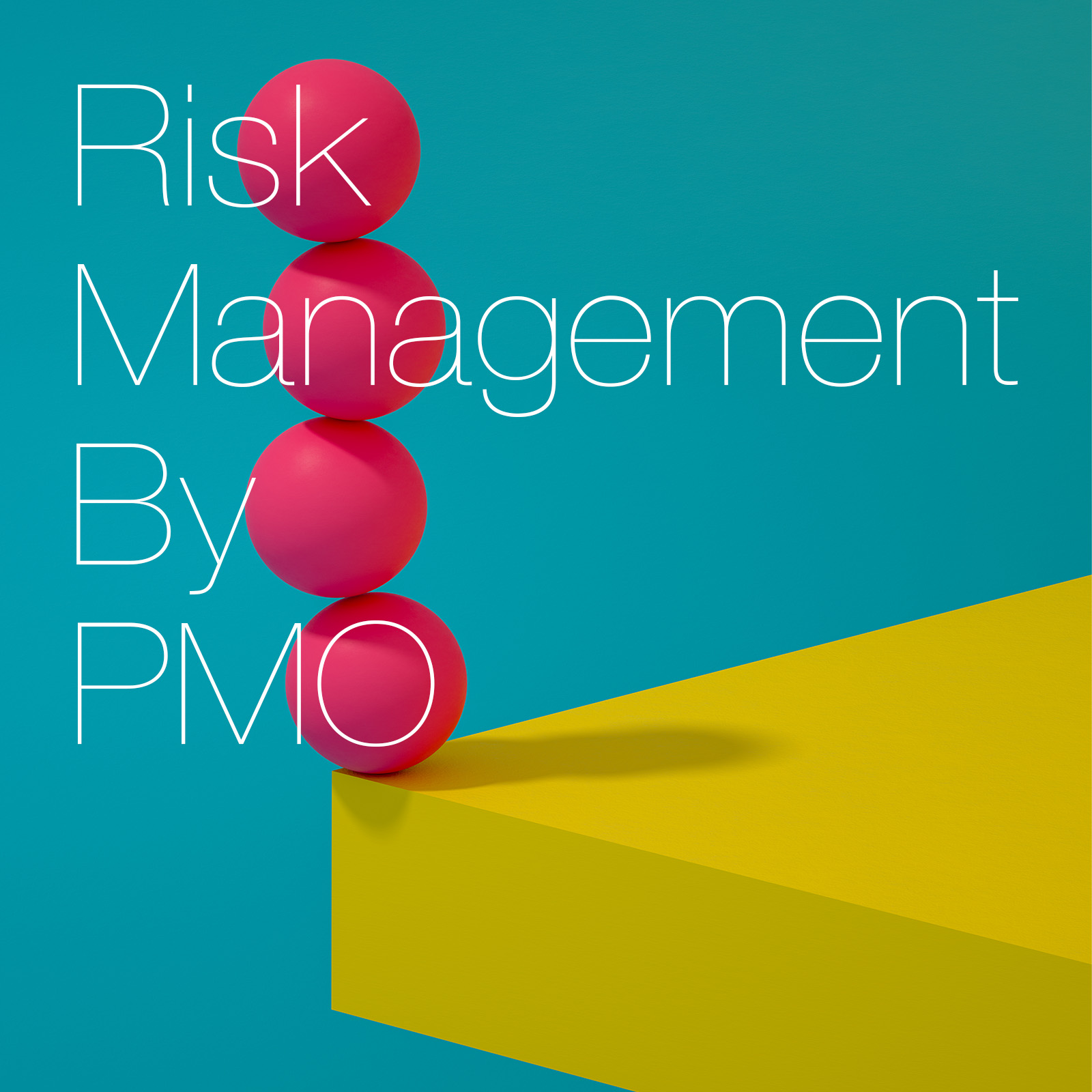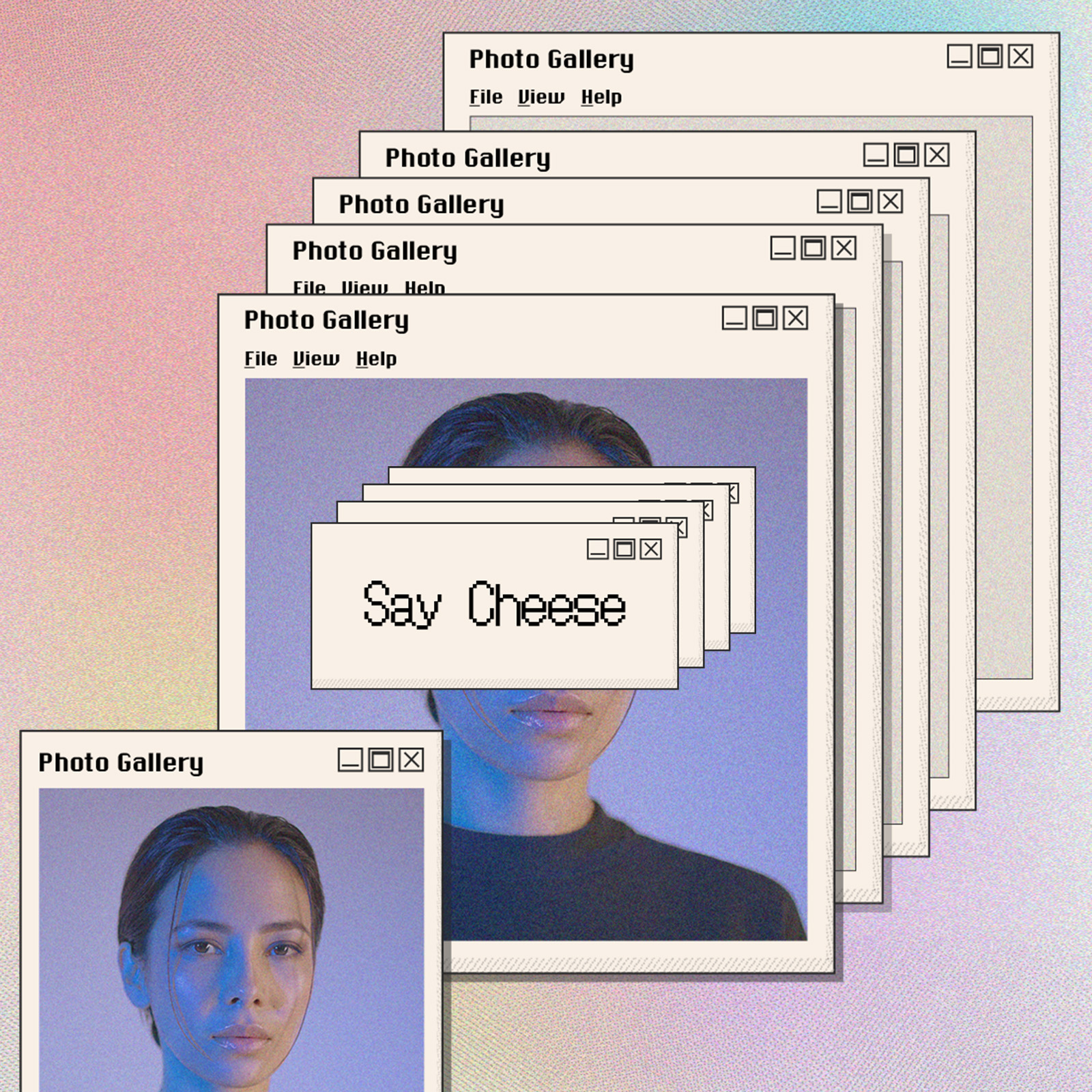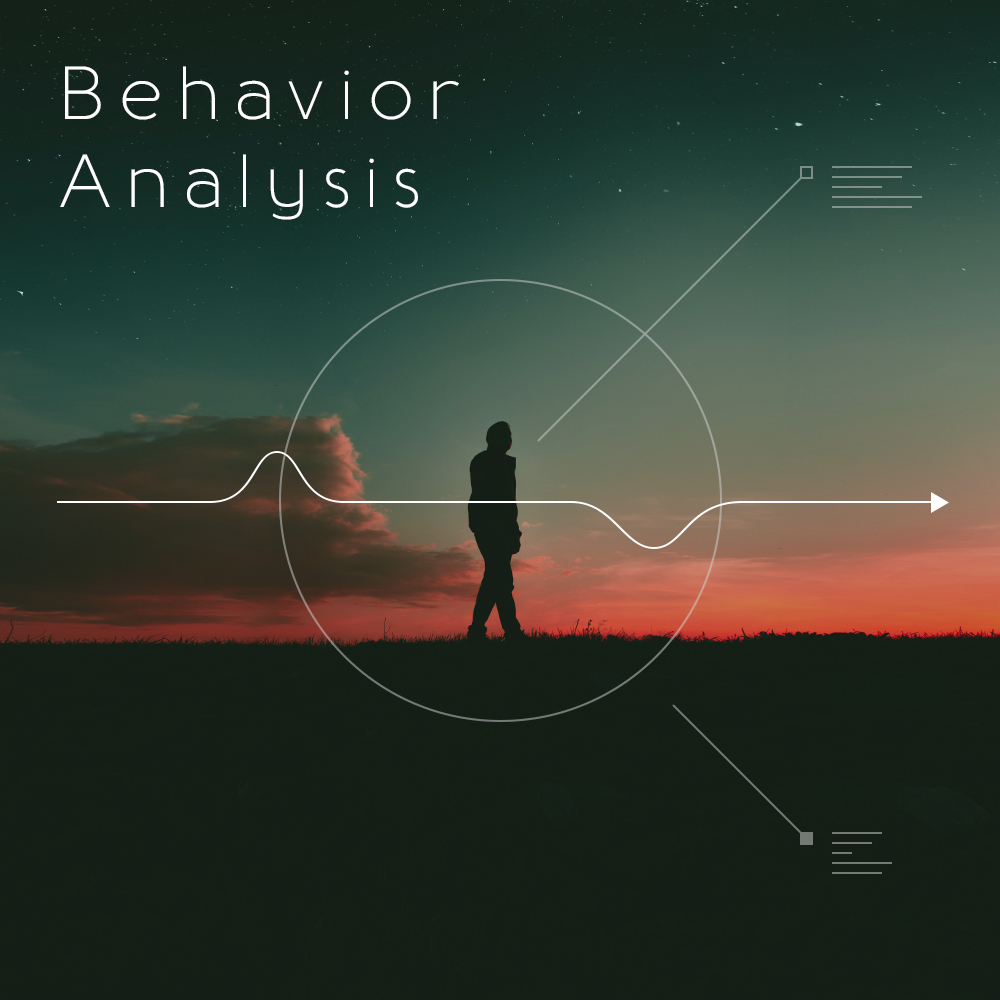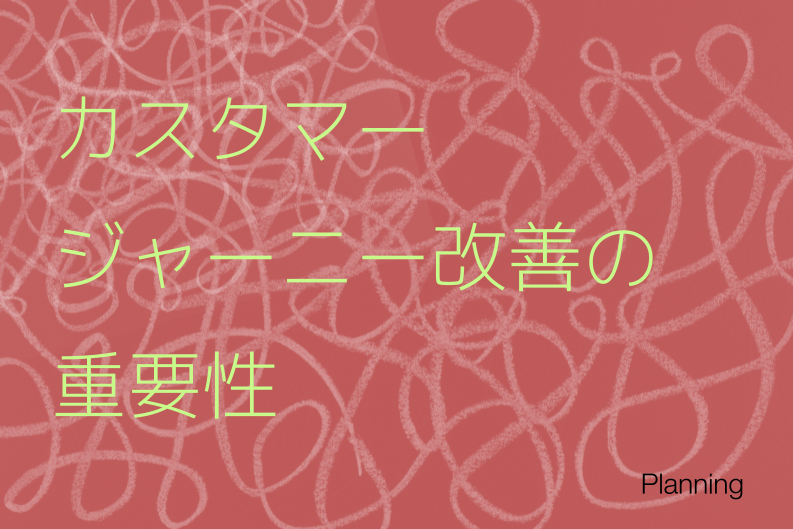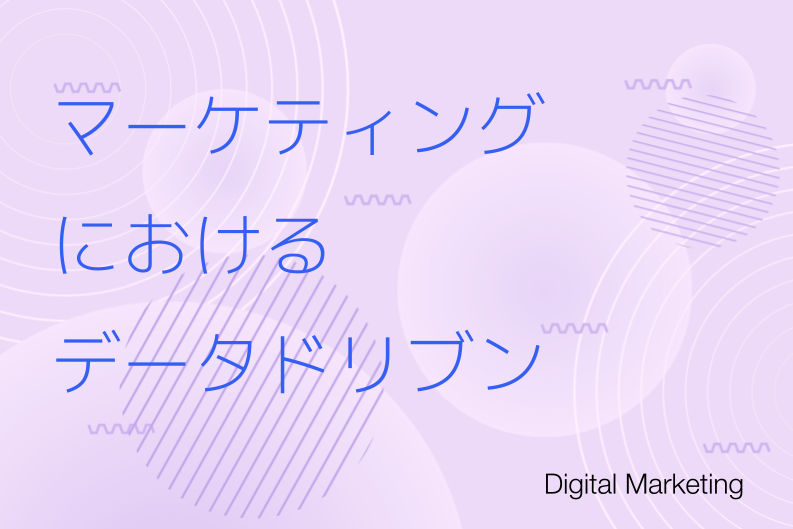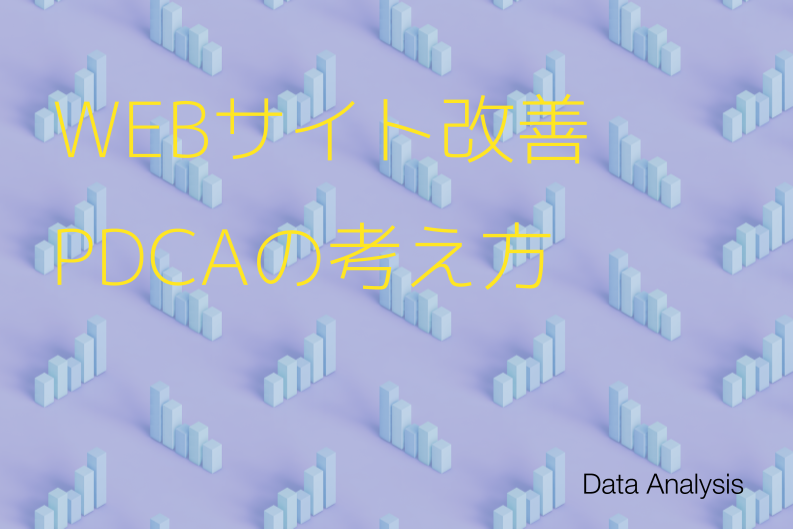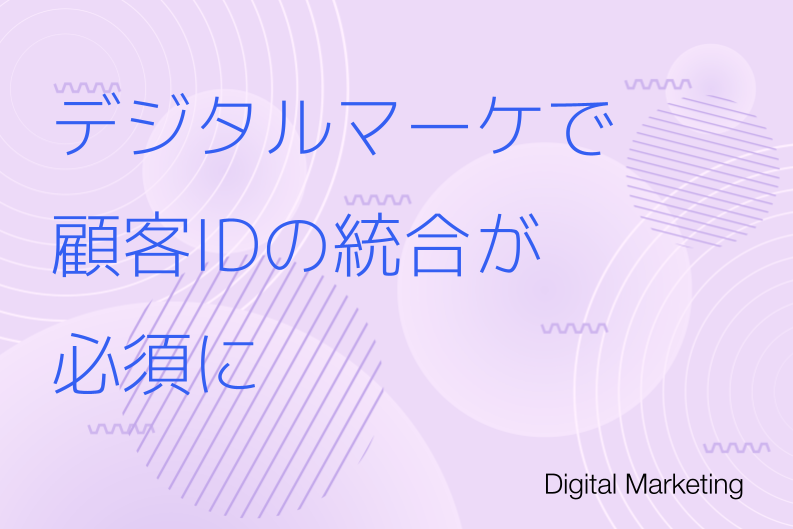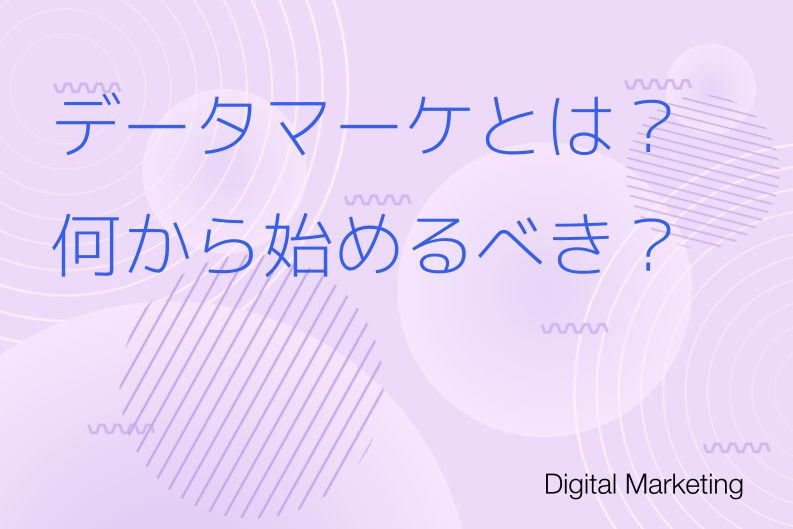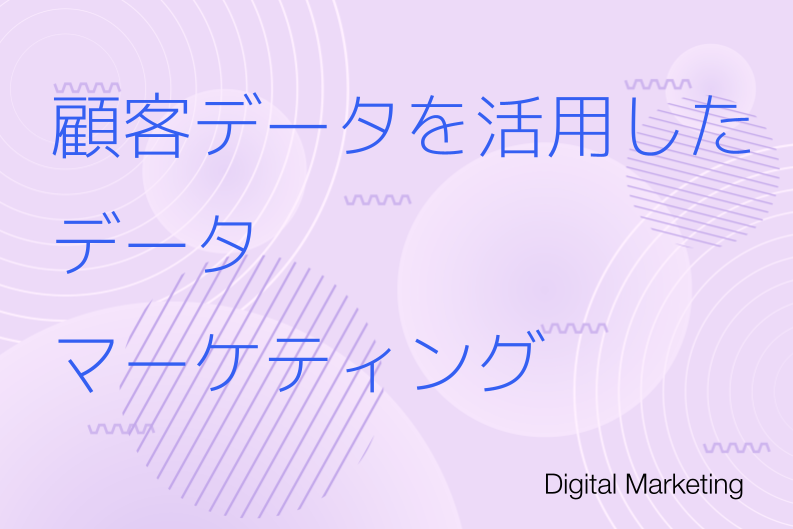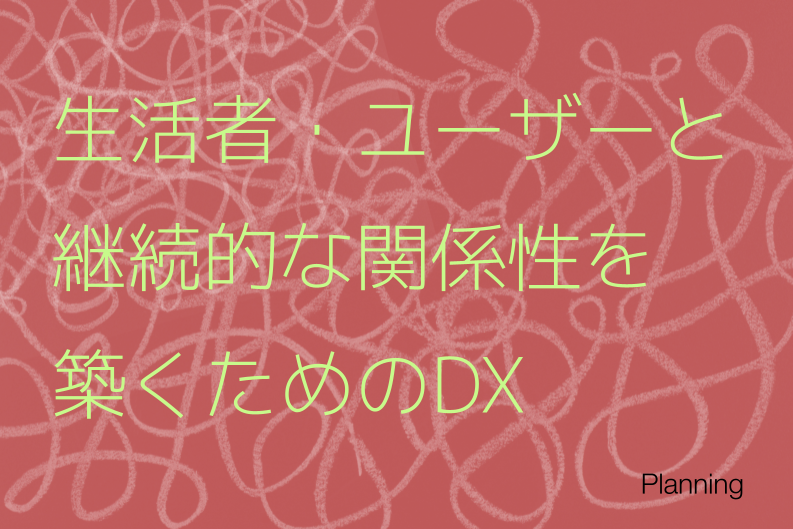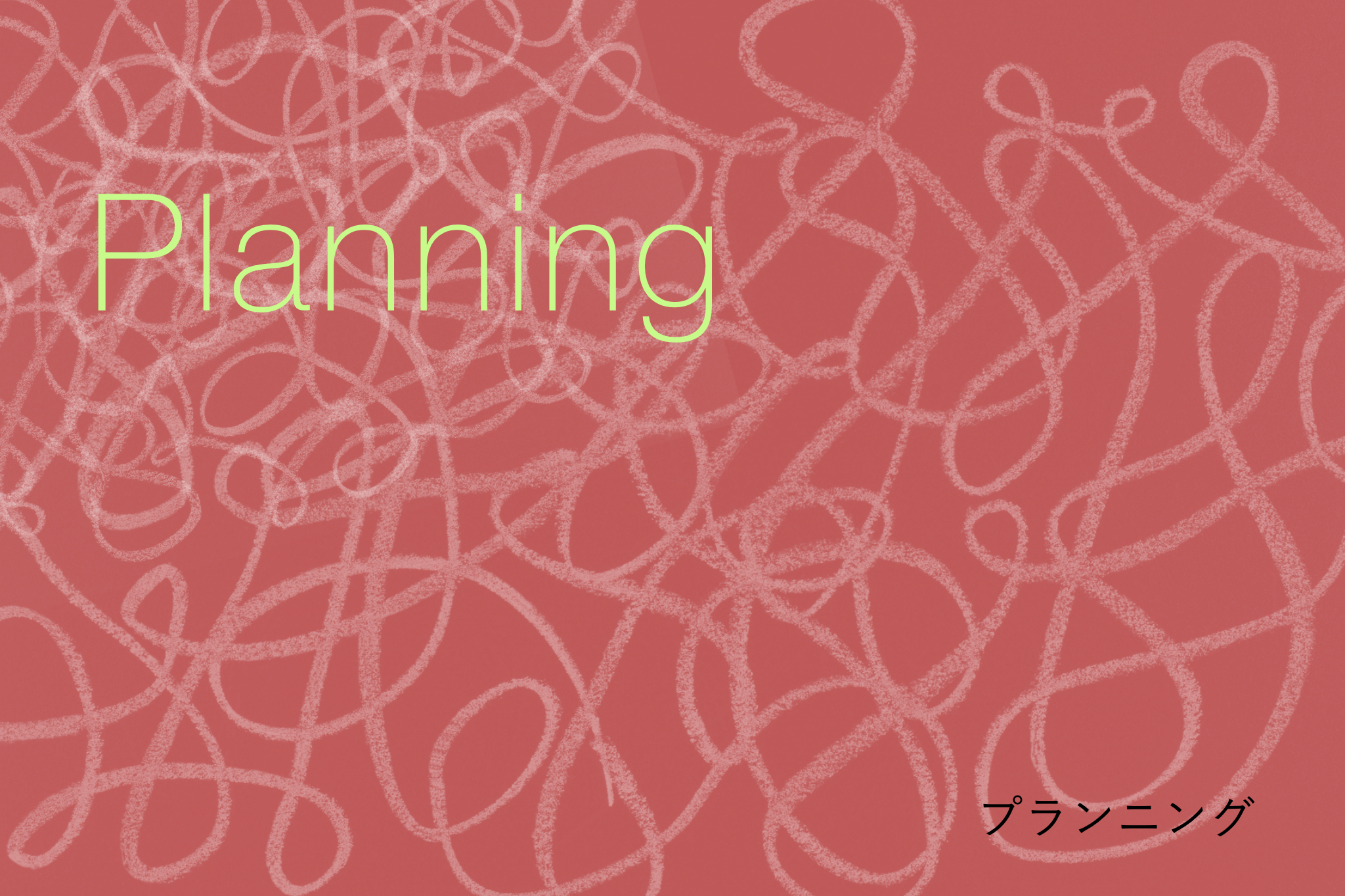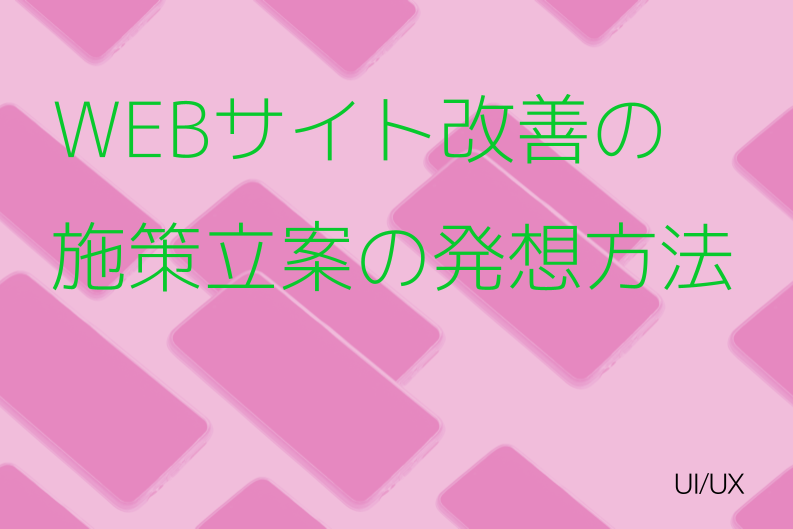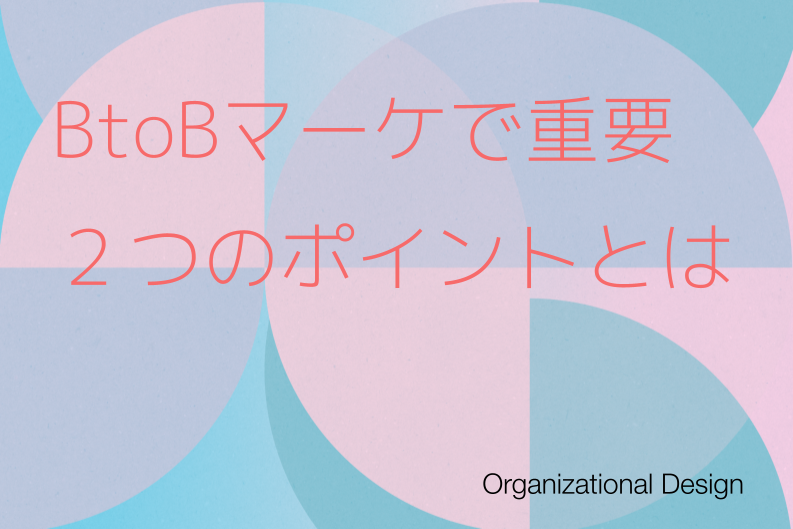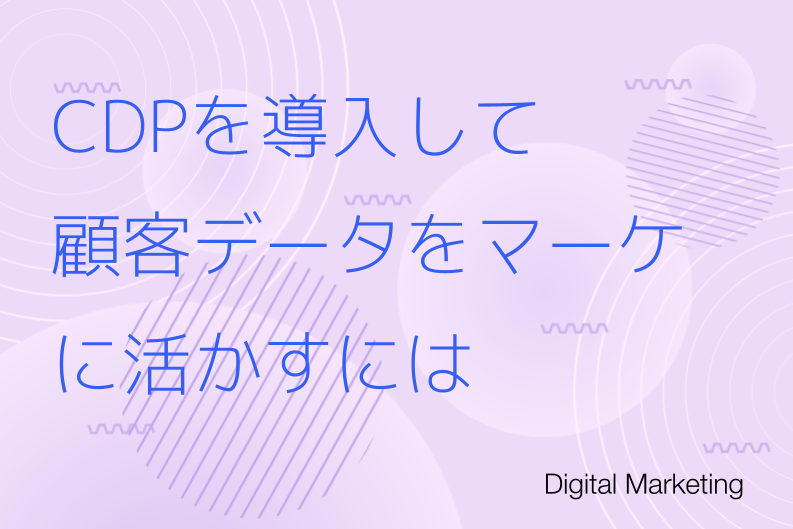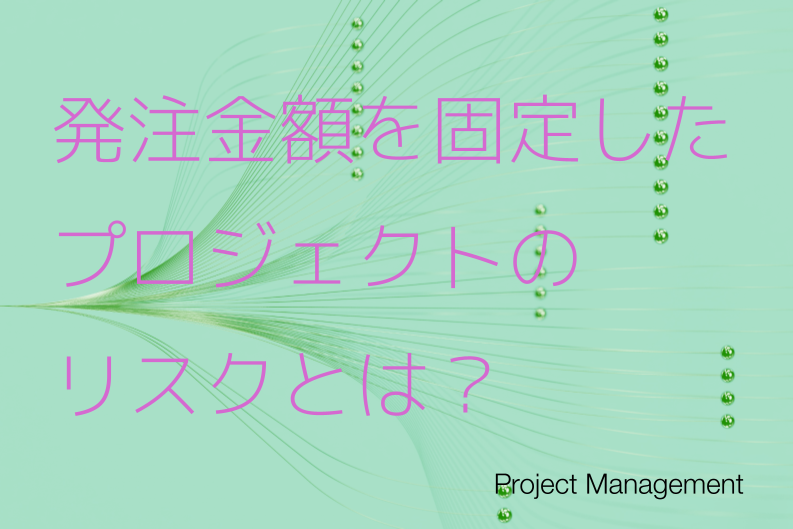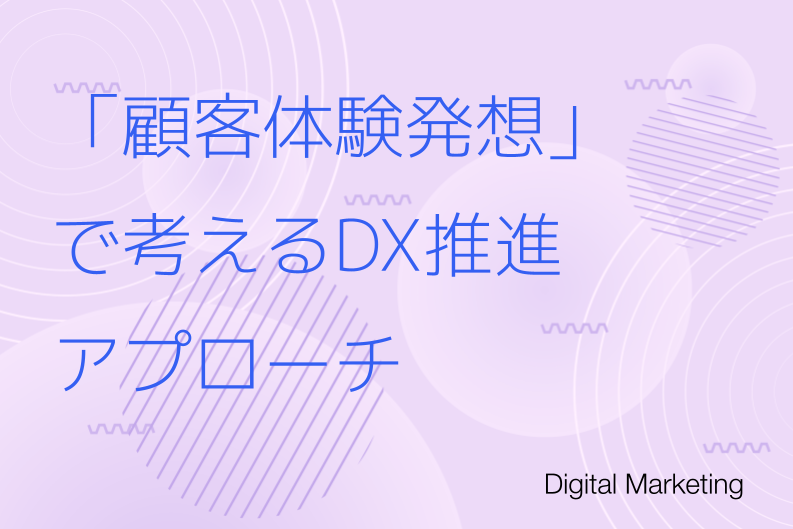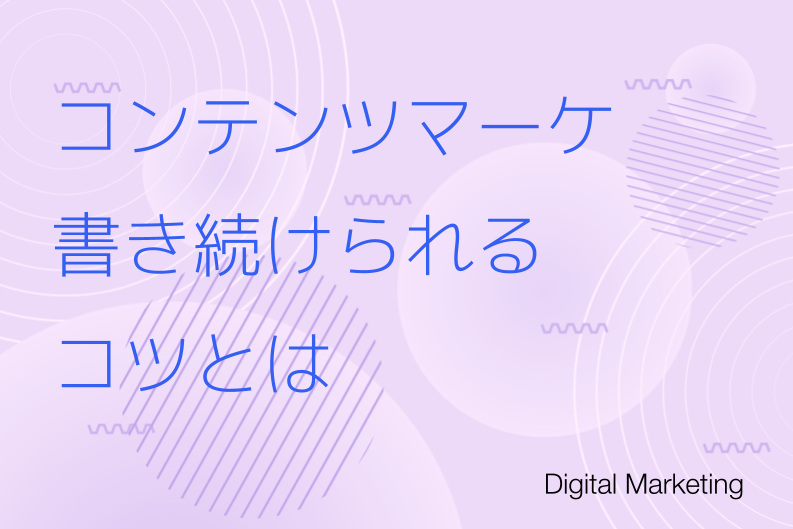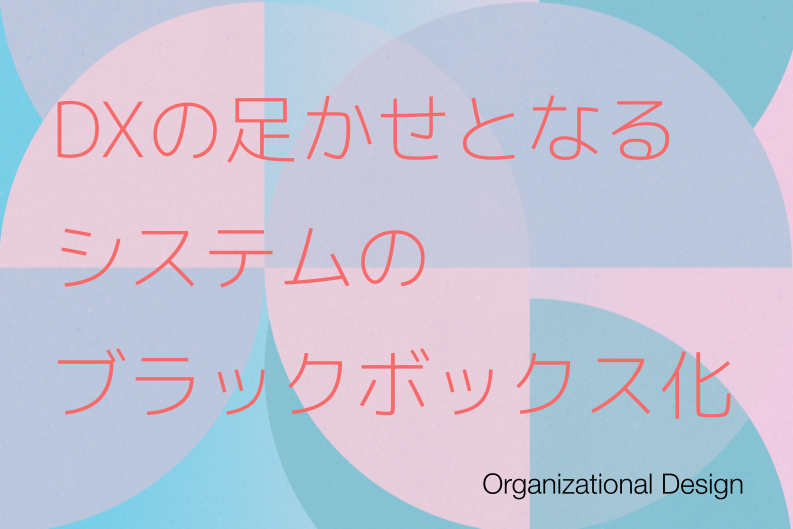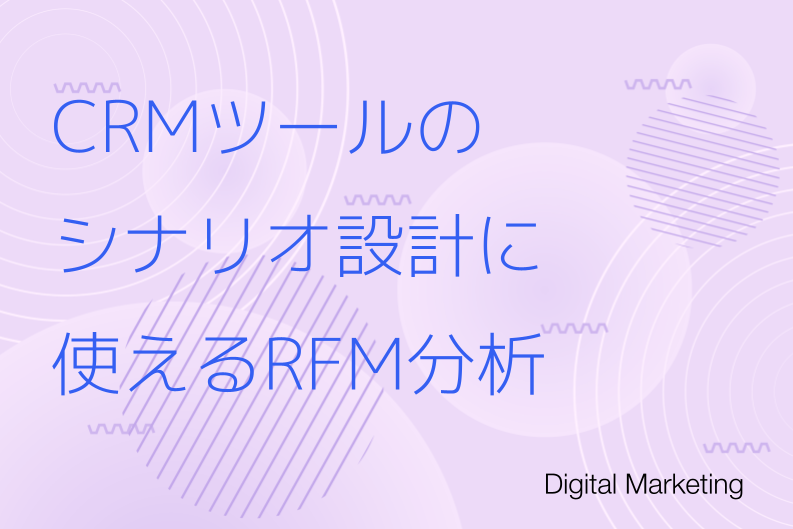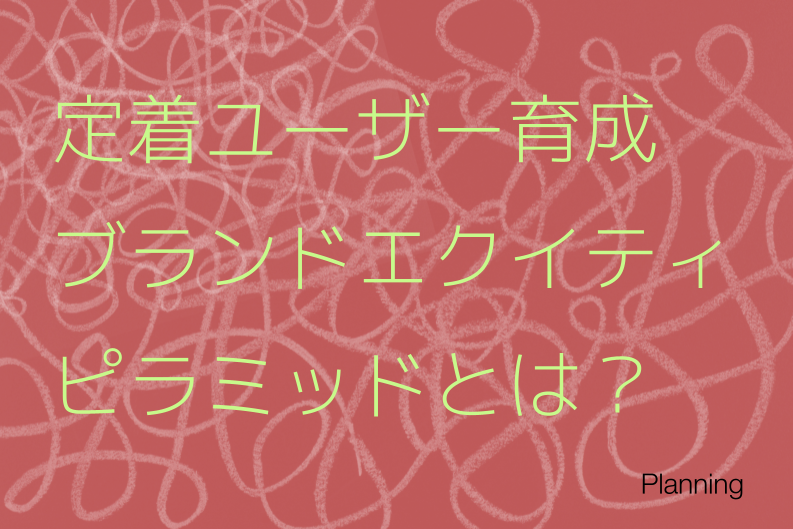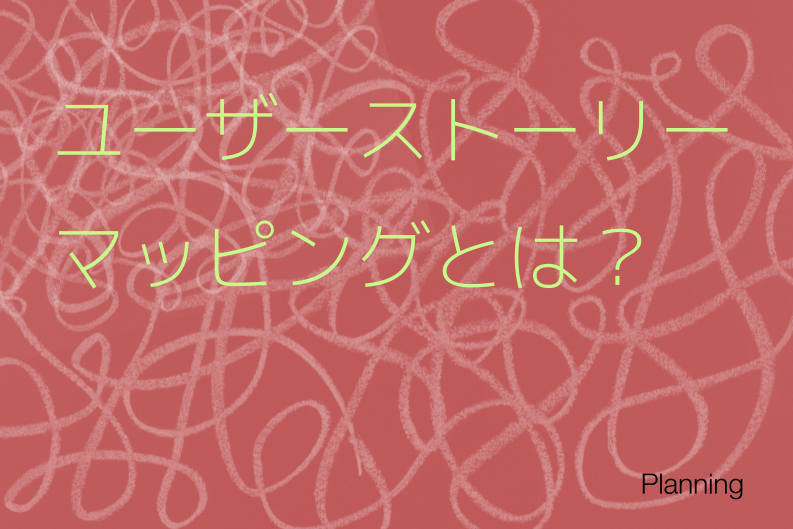教育学部でデザインにハマった、学生時代を経て

入社経緯を教えてください。
「もともと、美術の先生とか、学校の先生になれたらいいなと思って大学の教育学部に入って。興味ないことはやりたくなかったから、興味のあった美術コースを選択して、絵画・彫刻・美術史など、一通り勉強しました。イラストレーターとかフォトショップでチラシやロゴを作ったりしていく中で、だんだんとデザインにハマって。大学の中で教育実習に行ったりもしたけど、そっちより、デザインの仕事が面白そうだと思って就職活動を始めて。
それまでデザインを専門でやってたわけじゃないから、デザイン分野の会社を一通り調べていく中で、合同説明会みたいなところでアイスタのブースを見つけたんです。一応博報堂って会社は知ってたのと、そのグループ会社なのかなーくらい。作ってるものがかっこよかったら、受けてみようかな。って思って受けて入社しました。だから新卒のデザイナーで入社して、10年経って今11年目になりました。」
10年経過して、当時と今で変わったことは?
「興味の移り変わりは、あんまり変わってないですね。課題とかテーマとか、やりたいことに対して、表現するにあたってどういう中身がいいのか、デザインであったらいいのか。中身が面白くなっていくのかと考えて、作ることが続いています。
アートディレクターになっても、インタラクティブディレクターになっても、あんまり軸は変わっていなくて。サイト内の映像を作るとか、インタラクティブな表現を作る度に、エンジニアとか自分とは違う職業の方とコラボする意識で、今も取り組んでいます。」
国内外のデザイン賞などの受賞歴も多数ある竜沢さん。指名で仕事を受けることも多いと聞きます。ご自身の強みは何だと思いますか?
「ビジュアルアイデンディティを作ることと、今どきのデジタル体験というか。スマホしかり、ユーザーが情報に接触する状況の中に組み合わせるというところですかね。ユーザーのタイムラインというか、生活の中でどういうふうに使われるか、ビジュアルとUXを並列に扱って可視化することかなと。」
反射神経を磨く。突拍子もないことも、取り込む。

アートディレクションをする中で、大切にしていることは?
「いろいろなものを作ることを続けていると、個人で作ることって限界があるなと。物理的にも限界もあるし、体力的な限界も出てくる。だから、いろんな人との関わり合いの中で、自分で作るというよりかは、いつも誰かと作る感覚でいます。突拍子もないこともうまく取り込むということは、けっこう意識していて。自分が考えようが、誰が考えようが関係なくて。誰が考えたアイデアでも、いいなと思ったものを定着させることをやるようにしていますね。」
そのような考えに至ったきっかけは?
「新人のころは特に、分業で進行することが多いんです。最初にオリエンがあって、提案があって、プランがあって、構成があって、デザインするという流れの中でしか仕事をしていませんでした。当時、何も決まってないときにカンプを作ることになった時、それまで分業でしか仕事をやってこなかったから、全然うまくできなかったんです。
そんな時、先輩のアートディレクターに、プロジェクトの中で起きている問題やニュアンスを汲み取って、目指すべき構想を描くためのイメージを作っている人がいて。ああ、そういうやり方があるのかと。
分業で、効率的な仕事の進め方の正解はあると思うんです。ただ、それに慣れると何も決まってない状態からデザインすることが難しくなる。ある程度、理屈ではない部分でデザインして、そのアイデアがしっかり全体に機能していくのを横で見て、デザインはフェーズではなく、仮説づくりも担うんだと気付きました。」
その後プロジェクトをリードしていく立場になって、工夫してきたことはありますか?
「“健診戦”のサイトでも、“オオサカマニア”のサイトでもそうなんですけど、ある程度、関係者やプロジェクトがどんどん増えていくと、いろんなロジックや根拠意味づけはありつつも…最終的にどういうものになるのか? そこ次第でわかんないこととか、決まってないことでも、想像することが重要だと思います。どういうものになるのか、全く分からないことも完全な妄想や予想で手を動かしてきました。
まあ…自分の中では、勝手に「こうなるだろうデザイン」と「かもしれないデザイン」って呼んでて。何も決まってない状態でデザインすることをやると、自分の中でもジャンプできるし、反射神経が磨かれていく実感があります。なんだかんだ課題があっても、元々予想したかんじに勝手になっちゃうってことが結構あるからです。仮説立ててものづくりをすることが、最終的な良い成果につながるように感じています。」
デザインやものづくりに取り組みながら、マネージャー職にも取り組んでいるとか。
「基本的に現場もやるプレイングマネージャーなんで、そんなに仕事は変わってないとは思うんですけど、ものの見方は広がったように思います。教育学部にいたからか、比較的そういった仕事も自分ごととして受け入れてこれました。」
これから、チームのみんなで取り組みたいことはありますか?
「一般的によく言われることですが、生活している時、なんでこうなってるんだっけ?とそれぞれの人が思い、感じることを心がけたいですね。本読むとかかもしれないけど、批評的な目をしっかり持つことなのかな。聞いたもの、見たものを疑っていく、というのが今後大事なのかなと思います。」
ご自身の課題や、これからの目標があれば教えてください。
「批評的なことだけ意識するのも違うから、複数の視点を持っていたい。ラテラルな思考、ロジカルな見方、クリティカルな視点。それら3つの目でものづくりをしたい。生活したい。少し大袈裟に言うと、そんな風に生きていきたいです。」
今後のアイスタに期待することは?
「いわゆるデジタルプロダクションとして捉えると、クリエイティブは博報堂のDNAを元に20年で礎ができてきたんだと思います。だけど、これからはマーケティング視点が持てたらもっと生きるのかなと。広い視点で世の中をみて提案するとか。みんな言葉にはしないけど、実はこうなってるんじゃないかとか。このベクトルで進んでいくといいよ、って示唆があるものに向かっていかないといけないと思っています。
目に見えるもの、出目はどんなにこだわっても飽和状態になるんじゃないかなと思っている節があって。それはそれでありなんだけど、そもそもなぜそれをやるか?を突き詰めないと、同じ文脈でしか、仕事ができなくなってしまうんじゃないかと。
マーケティングを専門にしてる人って、頭もいいし、作る側と比べるとそこに対する時間の掛け方も違う。同じことをしてても勝てないわけだから、作る側の視点でそのような意識をすることが大事な気がします。どうしたらいいんでしょうね、でもみんなで意識するって決めるだけでも違うと思います。」
スニーカーと旅が好き。久しぶりの海外旅行はベトナムへ
プライベートの竜沢さんの暮らしぶりは?
「フリマアプリにハマって。着なくなってた服やもう見てない本など、いっぱい断捨離しました。おかげで、最近はどうすれば最安で郵送できるかとか、郵送方法にめちゃめちゃ詳しくなりました。でも、結局…気になるスニーカーをまた買っちゃったりして。もう運営側の思うツボですね。こうやってものを捨てさせずに、購買サイクルを作ってビジネスとして成立させてるのすごいなーって改めて思っていたところです。
あと、なるべく歩くようにしてて。深夜ラジオを聴きながら、週2〜3回くらい夜に散歩をすることが多いです。イヤホンつけて好きな芸人さんの話を聞きながらニヤニヤ笑っているので周りの人には気持ち悪く見えてるでしょうね。でも耐えられないくらいウケてます。自宅の前に干潟があって、野鳥がいて風景も綺麗なこともいい気分転換になってます。」
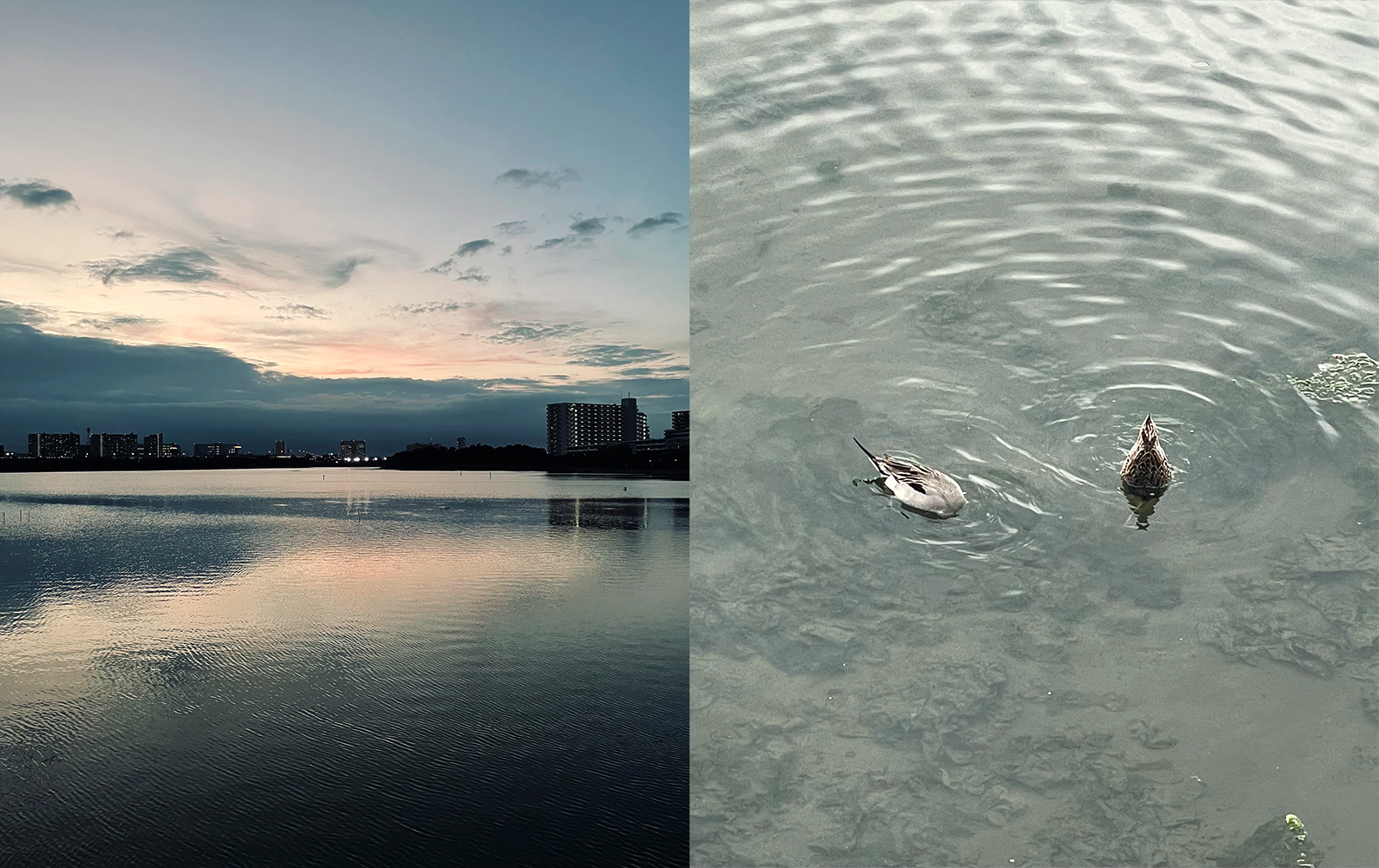
仕事とはうってかわって、自然派志向ですね。最近うれしかったことはありますか?
「フリバカ(*1)があれば国内外へ旅行に行きます。最近の休みは何年かぶりに海外旅行でベトナムに行きました!ごちゃごちゃした街中でご飯を食べたり、鉄道がないので配車アプリを活用しまくって移動していたりと、発展する国のエネルギーをダイレクトに感じられて、昔の日本もこんな感じだったのかなと想像しました。」
(*1)フリバカ=正式名称は「フリーバカンス制度」。半期に一度(年に2回)、年次有給休暇とは別に連続5営業日の休暇を取得できる休暇制度です。

「仕事でいうと、この“Whale”を作るのが面白いかな。ふだんから、個人で完結するよりも、他者との関わり合いの中でものづくりしたい方なので、チームのみんなで制作に取り組めるから、実は楽しみになっています。」

取材・執筆:田中 朝子
撮影:足守 新吾