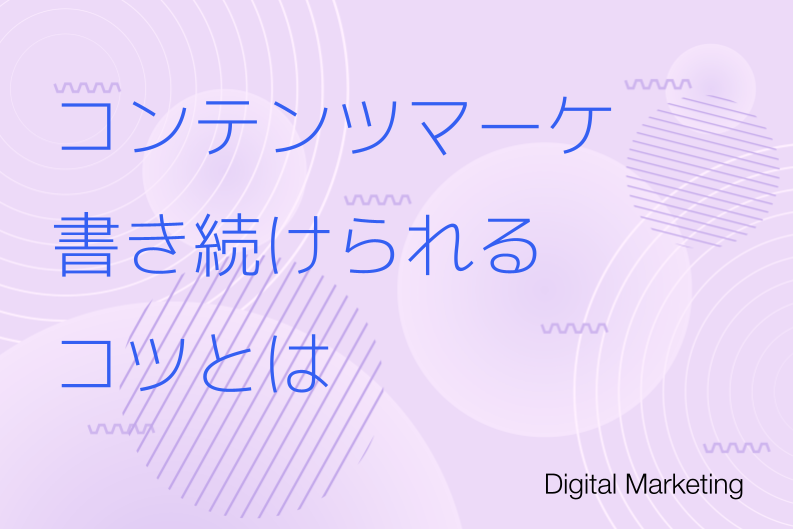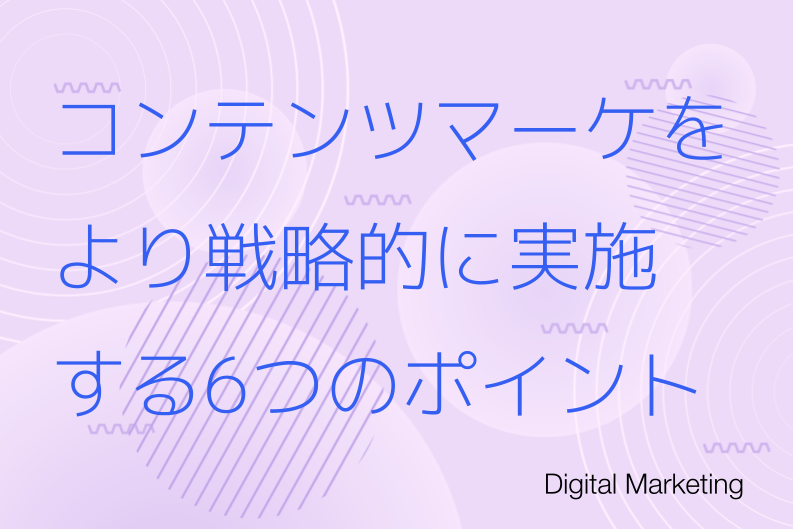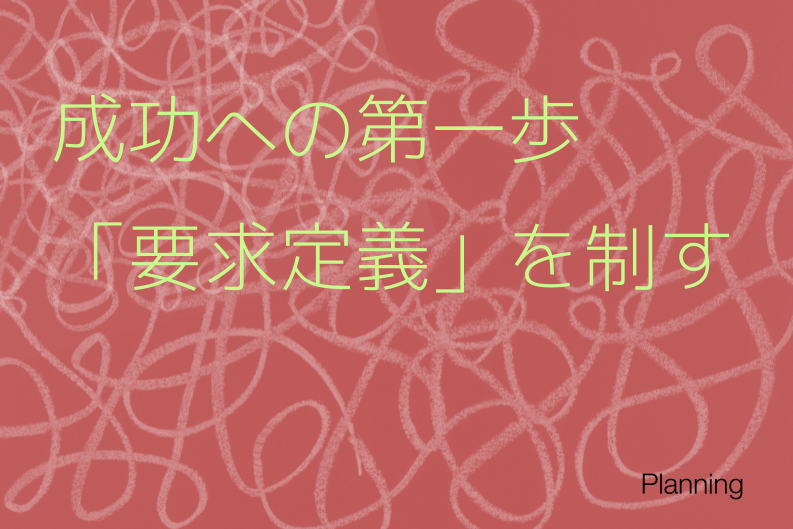顧客が自由にオンラインで情報収集するようになり、多くの企業がオウンドメディアやSNS、メールなどで顧客に向けて情報発信を行うようになりました。このように顧客にあわせた有益な情報をオンラインで発信することで、集客するマーケティング施策をコンテンツマーケティングと呼びます。
コンテンツマーケティングは低予算でも取り組むことができ、中長期的に成果を見込める施策ではありますが、日々コンテンツを作り続けることが極めて重要になってきます。なぜコンテンツが必要なのか、どのようにしてコンテンツを作り続けるのかコツをまとめます。 また、集客を目的とするコンテンツマーケティングは、マーケティングオートメーションと併せて利用することでより大きな効果を期待できます。
記事コンテンツのメリット
コンテンツといってもPDFや動画などさまざまな形式がありますが、中でも記事コンテンツは検索エンジンにヒットしやすいため非常に重要です。特にGoogleは常に質が高いコンテンツをインデックスしようとしており、質が高いコンテンツを多く網羅することでサーチエンジンから新規見込み客の流入を狙うことができます。
また、検索から集客した訪問者は目的意識を持って検索しているため、絞り込みやすい特徴があります。そのため、タイトル、記事内容によってターゲットを絞り訪問者に合わせたコンテンツを用意することで高いコンバージョンレートを狙えます。
有名企業や有名ブランドの多くは、外部のWebサイトからの被リンクが多かったり、古くからWebサイトが開設されていたり、指名検索が多いなどさまざまな要因で、検索結果ページの上位に掲載されやすい傾向にあります。しかし、それらの有名ブランドに対抗するポジションである場合は、サーチエンジンからの流入を増やすためには「質」だけでなく「量」も網羅することが重要になります。
このように情報収集を行っている見込み客を集めるための記事コンテンツをカテゴリで分類し、オウンドメディアを作ることでWebサイト訪問者の情報収集を助けることができます。
参考記事:コンテンツマーケティングをより戦略的に実施する8つのポイント
どのようなコンテンツを作ればよいの?
見込み客をWebサイトで集めるために記事コンテンツを作る場合、どのような記事を作る必要があるのでしょうか。特に記事コンテンツを作る上で意識しなくてはならない点についてまとめます。
コンテンツの計画を立てる
課題が顕在化している見込み客の多くは、検索エンジンで情報収集をします。どのような見込み客に記事を見てもらいたいか計画を立てる必要があります。
例えば私が「ダイエット食品ABC」を直販しているとします。まず初めに行うべきは「ダイエット食品ABC」を検索している生活者に対する情報提供でしょう。「ダイエット食品ABC」で検索している訪問者は、「ダイエット食品ABC」と競合商品を比較検討しているかもしれないし、「ダイエット食品ABC」を売ってるお店を探しているかもしれません。これらの生活者は目的のページを検索しても見つからなければ「ダイエット食品ABC 成分」や「ダイエット食品ABC 新宿」などとより細かいキーワードで検索を行います。これらの生活者に対してコンテンツを用意する必要があるのです。
しかし、残念ながら「ダイエット食品ABC」は世の中に知られておらず、それほど多く検索されていなかったとします。その場合、「ダイエット」で検索している検索者に「ダイエット食品ABC」を知ってもらう必要があります。「ダイエット」で検索している生活者数は非常に多くなりますが、中にはスポーツジムで体を動かすダイエットを検討している方や、食事制限などのダイエットのノウハウを探している生活者も多くいます。
このようなダイエット食品にまだ興味がない潜在顧客に対し、「ダイエット」のノウハウを提供しつつ、「ダイエット食品ABC」を知ってもらうコンテンツが必要になります。このようにして必要なコンテンツを洗い出します。
また、マーケティングオートメーションと組み合わせて利用することにより、Webサイト訪問者が資料請求などの個人情報を提供するまでの間にどのようなページを閲覧してきたのかなど、アクティビティをトラッキングすることができます。コンテンツを広く網羅する事で見込み客の興味関心を事前に知ることができるのです。そのため、顧客の興味を知る手掛かりとなるようコンテンツを作成することも大切です。
コンテンツSEO
しかし、実際にコンテンツを作ってみても、検索結果の上部に表示されません。コンテンツを用意したら何はともあれコンテンツを見つけてもらう必要があります。従って、SEOを考慮したコンテンツを作成する必要があります。サーチエンジンで見込み客にリーチさせるためのコンテンツ制作をコンテンツSEOといいます。 コンテンツSEOでは、一般的なSEO対策の中でも特にキーワード選定、タイトルや見出し、クローラビリティ、ページボリュームなどのポイントをおさえて作成する必要があります。
コンテンツマーケティング
コンテンツSEOによってWebサイト流入に成功しても、訪問者の多くが直帰してしまっては意味がありません。適切なWebサイト訪問者に有益な情報を提供することで、記事の目的を達成しなくてはなりません。 記事の目的は何か?目的を定めて記事を書くことが大切です。その目的を達成するために、記事を読む前と読んだ後でどのような変化を期待するのか、訪問者の知識や気持ちの変化などパーセプションチェンジを明確にしてコンテンツを作ると記事が書きやすくなります。
コンテンツSEOで対応が困難な記事
カスタマージャーニーマップに見込み客を落とし込むと漏れなく必要なコンテンツを洗い出すことができます。ここでコンテンツSEOを考える上で注意すべきことがあります。例えば、カスタマージャーニーマップを整理していくと、競合製品・サービスの比較検討のフェーズが出てくると思います。そこで競合との差別化・強みを訴求する記事コンテンツが必要になるのですが、比較検討に関する検索結果は比較するWebサイトが上位に優先的に表示される傾向があります。したがって、比較するWebサイトで自社の商品やサービスをお取扱いいただくように他社のWebサイトに対しても情報掲載・導線設計を検討することが有効な場合があります。
コンテンツ制作を継続することの重要性
有名ブランドなどのWebサイトの場合は、量が少なくても検索上位に表示される場合は多くありますが、狙うキーワードなどによっては、コンテンツの「質」だけでなく「量」も必要となる場合があります。 SEOで一定の効果が現れるためには3,000~4,000字程度の記事をまずは100記事程度を目標にします。例えば週に1本のペースであれば年間55本程度の記事をリリースすることができます。いくつかの記事コンテンツの制作ラインを作り記事コンテンツを定期的にリリースする計画を立てましょう。 オウンドメディアの初回立ち上げ時に50本+毎週1記事の連載であれば1年で100記事達成できるペースとなります。SEOは効果が現れるまでにどうしても時間がかかります。ターゲットとするキーワードなどにもよりますが、SEOに適切に対応した記事を書き始めて3か月程度は見たほうがよいようです。
コンテンツを連載し続ける為のコツ
記事を連載し続ける為にはオウンドメディア全体の設計・計画、記事を制作するリソースの確保や、ネタ、品質などが重要になってまいります。
コンテンツの種類は大きく2つ
Webサイトへの来訪を増やす為の記事は大きく2種類で「喜ばせるコンテンツ」「課題を解決するコンテンツ」となります。
「喜ばせるコンテンツ」とは、「〇〇〇を試してみた!」「〇〇〇ベスト5!」「●●●についてアンケート調査結果」といったものです。YoutubeやSNSなどでもよくみられるコンテンツでエンターテイメント系はとても重要なコンテンツになります。また、ニュースなどの時事などもコンテンツのヒントになります。潜在層にリーチしやすいコンテンツが作りやすいと思います。
「課題を解決するコンテンツ」は、主に課題を持つ生活者が求めるノウハウなどの提供になります。課題が明確であるため、顕在層を非常に集めやすいコンテンツと言えます。「Yahoo知恵袋」や「教えてGoo」などでどのようなことに悩んでいるかヒントを拾うことができます。
社内で執筆依頼
社員で分業することは極めて重要です。特にB2Bにおいては専門性が高まってくるため、個々の社員のノウハウや専門性を活かすことが大切です。この際マーケティング担当者が企画を行うようにし、現場担当者に記事を執筆してもらいます。そして、最後にマーケティング担当者が編集しリリースするようにします。また、忙しい現場担当者の負担を軽減するために下記の内容など予め整理して依頼しましょう。
記事の目的
キーワード
記事のタイトル
見出し
また、記事を読む見込み客をイメージしやすくするために、ペルソナシートなどを整理すると、よりイメージしやすくなるでしょう。
コンテンツのバリエーションを広げる
記事を連載し続けるとコンテンツのネタに困ることが出てくると思います。同じ事柄であっても、ターゲット別、シチュエーション別、業種別に書き換えることでより訪問者に寄り添った具体的な情報を提供することができます。その際、よりターゲットにあったキーワードを意識してコンテンツを作ることで、ニッチな層にリーチできるようにしましょう。
まとめ
以上、主に検索で集客するコンテンツマーケティングにフォーカスし、記事コンテンツを書き続けるポイントを整理いたしました。見込み客を集めて育てコンバージョンを得る上ではマーケティングオートメーションとの組み合わせて利用することが非常に効果的です。博報堂アイ・スタジオでは、マーケティングオートメーションの導入支援・運用支援を行っております。マーケティング部門を持たない企業様であっても、担当者様とご担当責任者様をアサインいただければ、導入・運用コンサルティングや運用支援を提供できます。